|
|
||
| 妙心寺 (京都市右京区) Myoshin-ji Temple |
||
| 妙心寺 | 妙心寺 | |
 |
 |
|
 南総門(重文)  南総門  南総門  南総門  南総門、石橋  南総門、空濠  勅使門(重文)  北総門(重文)  寺紋  放生池      伽藍は南北にほぼ一直線に建っている。   三門(山門、重文)      三門  三門、山廊   浴室(重文)  浴室  浴室内部   浴鐘楼  井戸  「四派の松」、三門と仏殿の間に植られている。  仏殿(重文)  仏殿、扁額「祈祷」  仏殿、本尊・釈迦如来坐像を安置する。  鐘楼  経蔵(重文)  経蔵、扁額「毘盧蔵(びるぞう)」、鎌倉時代、第92代・伏見天皇の宸筆(しんぴつ)という。  法堂(はっとう)(重文)  法堂、鏡天井に狩野探幽の「雲龍図」、説明板より  仏殿と法堂とつなぐ廊下     法堂と寝堂を結ぶ廊下  境内の石畳     法堂  法堂、鬼瓦は龍になっている。  法堂  雪江の松  鐘楼  梵鐘(国宝)の復原  鐘楼  梵鐘  寝堂(前方丈、礼間)(重文)   大庫裏(重文)、右下に韋駄天堂   大方丈(重文)唐門(真前唐門)  大方丈の玄関(重文)   大方丈(重文)  大方丈、扁額「方丈」  大方丈  東海庵(非公開)  東海庵   小方丈   小方丈   参道、境内内外に多くの塔頭が建ち並んでいる。   微妙殿 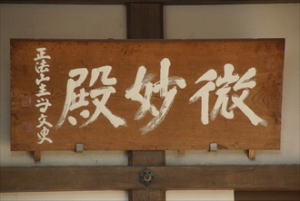 微妙殿  微妙殿     玉鳳院禅宮(左)、開山堂微笑庵。(非公開)   玉鳳院開山堂(微笑庵)(重文)、この地は、妙心寺発祥の地になっている。(非公開)  玉鳳院  玉鳳院  玉鳳院、「牛石」  放生池   宝蔵  玉鳳院開山堂(微笑庵)の唐門(重文)     玉鳳院開山堂(微笑庵)   涅槃堂  涅槃堂
 衡梅庵、四派四本庵の弟子たちの師・雪江宗深)の塔所。  衡梅庵、「本山四派渕源 雪江禅師塔所」の石標が立つ。  塔頭・龍泉庵(龍泉派)  塔頭・東海庵(東海派)  塔頭・聖澤院(聖澤派)   塔頭・霊雲院(霊雲派)  参道は石畳と松の並木が続いている。  境内から北に見える衣笠山   勅使門付近の空堀  境内の東に宇多川が流れている。 |
双ヶ丘の東、衣笠(きぬがさ)山の南に位置する妙心寺(みょうしん-じ)は、山号を正法山(しょうぼう-ざん)、法山ともいう。 豊かな自然環境のため、「西の御所」と呼ばれている。境内は10万坪(13万坪とも、33万㎡、東西500m、南北619m)の広大な敷地を有している。京童の囃子言葉では、「妙心寺の算盤面」といわれた。健全な禅は、安定した寺院経済を基礎にして成立するという伝統がある。 全国・世界に3400の末寺、在籍僧数7000人を数える。臨済宗妙心寺派の大本山であり、臨済宗14派の中でも最大の教団(全体の6割)を形成する。境内、境外には48の塔頭(子院)がある。このうち、山内塔頭は38院、境外塔頭は龍安寺を含めて10院ある。 臨済宗妙心寺派の大本山。本尊は釈迦如来像。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 鎌倉時代、かつてこの地には、花園上皇(第95代、1297-1348)の離宮「萩原殿(はぎわらどの)」「萩原御所」「仁和寺花園御所」)が営まれていた。 南北朝時代、1337年/1335年/1338年/少なくとも1342年以前、開基の花園法皇は、譲位後に落飾し、禅寺に改める。勅願により美濃山中より関山慧玄(かんざん-えげん)を招いて開山とした。(『正法山妙心禅寺記』『開山国師別伝』『妙心寺六百年史』『祖伝考彙』・『六祖伝別考』)。山号寺号の由来は、慧玄の師・大徳寺開山の宗峰妙超(大燈国師)の拈華微笑(ねんげみしょう)の逸話から「正法山妙心寺」と命名された。釈尊が嗣法の弟子・摩訶迦葉(まかかしょう)に向かって述べた「正法眼蔵涅槃妙心」より採られている。法皇は、玉鳳院を建て、慧玄に参禅した。当初は大徳寺末寺だったという。 1338年、 花園法皇は、玉鳳院を建て、慧玄に参禅した。 1342年、花園法皇は仁和寺花園御所(萩原殿)跡を禅苑とし、慧玄に管領させた。(「妙心寺文書」・「院宣」)。妙心寺が開創になる。 1347年、花園法皇は死の前年に、寺の造営を願う「往年の宸翰(しんかん、直筆文書)」をしたためる。(「玉鳳院文書」・「往年の宸翰」)。寺領紛争が起こる。 1348年、旧11月、 花園法皇が亡くなる。 1351年、旧8月、光厳上皇(北朝初代)の院宣により、慧玄が帰山する。(「妙心寺文書」・「光厳上皇院宣」) 1360年、旧12月、慧玄が亡くなり、開山堂(微笑庵)に祀られた。 1361年、 慧玄の弟子、授翁宗弼(じゅおう-そうひつ)が住持になる。 室町時代、1398年、室町幕府3代将軍・足利義満の祈願所になった。 1399年、義満への謀反「応永の乱(大内義弘の乱)」が起る。住持の6世・拙堂宗朴(せつどう-そうぼく)が、乱に関与した守護大名・大内義弘と師壇関係にあり、義満の怒りを買う。宗朴は、その後も義弘との関係を解消しなかった。このため、宗朴は青蓮院に幽閉の身になる。寺領・寺地は、青蓮院の義円、南禅寺の徳雲院・廷用宗器(ていよう-そうき)に移された。宗器は寺名を「龍雲寺」に改め、徳雲院付属とし妙心寺は中絶した。 室町時代、妙心寺は大徳寺とともに、在野の寺院、「林下(りんか)」の代表にされた。 1432年/永亨年間(1429-1441)、南禅寺・宗器より根外宗利に寺領が返還される。尾張犬山・瑞泉寺から入寺した後の7世・日峰宗舜は、管領・細川持之の外護により開山堂を再興し、中興の祖になった。方丈、開山堂の微笑堂を復興する。 文安年間(1444-1449)、8代将軍・足利義政により寺領が寄付されている。 1448年、細川持之は養源院(日峰塔所)を建立した。 1450年、細川勝元は龍安寺を建立する。 1462年、9世・雪江宗深(せっこう-そうしん)は、妙心寺、龍安寺の住持になる。宗深は、妙心寺の再中興開山になる。 1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)で多くの堂塔を焼失した。 文明年間(1469-1487)、中興事業がなり、大徳寺と対抗するまでに栄えた。 1476年、会計簿(米銭納下帳、日単簿)が作成され、財政の立て直しが行われる。 1477年、旧閏1月、宗深が第103代・後土御門天皇の綸旨を奉じて再興した。細川勝元・政元親子らの援助を得る。(「妙心寺文書」)。方丈が上棟される。宗深は中興の祖になった。 1480年、政元は衡梅院(雪江宗深塔所)を建立した。 1481年、政元は四派の一つ龍泉庵を建立する。 1484年、利貞尼(りていに)は境内地を寄進し、四派の一つ東海庵を建立した。 1486年、政元は妙心寺を再興する。 永正年間(1504-1521)、17世・鄧林宗棟(とうりん-そうとう)の時、大徳寺より独立している。(「妙心寺文書」・「正法山誌」) 1507年、宗棟は、勅許により、奉勅入寺式を挙行した。妙心寺の大徳寺からの独立を意味した。細川澄元の軍勢がこれを警護した。 1509年、第104代・後柏原天皇の綸旨により、独立本山とし、紫衣勅許の禅寺、大徳寺と同格の寺になる。宗棟が住し、奉勅入寺の制が始まるともいう。妙心寺と大徳寺は絶交する。 美濃加茂城主・斎藤利国の妻の利貞尼が、仁和寺真乗院領の土地を買い求め、妙心寺に寄進、境内は3倍に広がる。賦課金制度が始まる。(「妙心寺文書」) 1516年、大休が住した。 1523年、塔頭の龍泉庵、東海庵に加え、四派の一つ聖澤院が土岐氏により創建される。 1526年、四派の一つ霊雲院が創建された。これにより、「四派四本庵」による運営体制が確立した。 1528年、焼失している。その後、伽藍再興が続いた。大庫裏が建てられた。 1537年、開山堂が建てられる。 安土・桃山時代、1574年、滝川一益により瑞松院が創建される。 1575年、津川義近により衡陽院(後の太嶺院)が創建された。 1576年、金台院が創建される。 1578年、妙心寺壁書(法規)が制定された。南化、鉄山らが連署する。 1579年、通玄院が創建される。 1581年、滝川一益により長興院が創建された。 1583年、古仏殿、法堂が建立される。石河伊賀守光重により養徳院が創建される。牧村利貞により雑華院が創建された。 1584年、池田信輝により龍福院が創建される。 1586年、一柳直末により大通院が創建される。 1587年、浴室(明智風呂)が建立された。 1588年、法堂(兼仏殿)南北の廊下が建設される。 1590年、堀尾喜治により春光院が創建された。 1591年、豊臣秀吉の跡継ぎ・棄て丸(鶴松)の葬儀に際して、51世・直指宗諤が執り行う。初七日法要は、祥雲寺58世・南化玄興による。 1593年、池田輝政により盛嶽院が創建される。 1595年、石田三成により寿聖院が創建された。 1597年、稲葉貞通は智勝院を開創した。 1599年、三門が建立される。脇坂安治は麟華院を創建した。 江戸時代、隆盛し五山の外ながら幕府、諸侯の帰依篤く、勢力は臨済諸派最大になる。 1610年、勅使門が建立される。 1613年、幕府は大徳寺・妙心寺法度を制定する。 1614年、方広寺大仏殿の鐘銘事件により、105世・海山元珠(がいざん-げんしゅ、祥雲寺住持)ただ一人が豊臣家を弁護する。 1615年、旧7月、徳川家康の怒りを買った妙心寺は、幕府の厳しい規制の下に置かれ、「妙心寺法度」を押し付けられた。これに対して、単伝士印(たんでん-しいん)、東源慧等、同様の法度を出された大徳寺の澤庵宗彭(たくあん-そうほう)、玉室宗珀(ぎょくしつ-うはく)、江月宗玩(こうげつ-そうがん)らが抗議した。1632年まで続く。 1627年、幕府は抗議した4人の僧に対して、弾圧を加えた紫衣(しえ)事件が起きる。春日局の融和作はあったが、士印は陸奥国由利、慧等は津軽に流罪になる。第108代・後水尾天皇は譲位している。 その後、諸大名の帰依により、伽藍の再建、整備が進められた。 1628年、幕府は大徳寺・妙心寺の出世を禁じる。愚妙が住する。 1639年、春日局により浴鐘楼が建立された。 1640年、大徳寺・妙心寺の出世住山が許可される。 1653年、大庫裏が改造される。 1654年頃、大方丈、庫裏、寝堂など現在の伽藍が再建される。隠元隆琦(いんげん-りゅうき)が来日する。 1655年、妙心寺の龍渓性潜(りゅうけい-しょうせん)らによる黄檗宗の開祖・隠元隆琦の妙心寺住持就任要請は、山内が二派に分かれて大論争になる。愚堂東寔(ぐどう-とうしょく)、大愚宗築(たいぐ-そうちく)らにより成功しなかった。 1656年、玉鳳院を改築する。法堂、現在の浴室が完成する。唯一の門跡寺院の大和・円照寺が開創された。 1658年/1657年、愚堂の時、法堂が建立されたともいう。 1672年、盤珪が出世する。 1674年、経堂が建立される。 1789年、塔頭83、寮舎21、門前境内3庵15宇、末寺1417、孫末寺3205、曽孫末寺・玄孫末寺389があった。(「禅宗済家山城州正法山妙心寺派下寺院帳」) 1830年/1827年、現在の仏殿が建立される。 1859年、塔頭80余りがあった。(正法山妙心寺塔頭総図) 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により混乱する。幕末に100余りあった塔頭は半減した。 1872年、臨済宗、曹洞宗、黄檗宗が禅宗として統一される。その後、臨済宗、曹洞宗が分離する。 1876年、9月、文奕無学(ぶんえき-むがく)の時、臨済宗妙心寺派として独立する。 1878年、僧堂(天授院)が開かれる。 1885年、6月、「妙心寺派憲章」が政府の許可を得て成立する。 1886年、大教校(花園大学の前身)が開校した。 1931年、本坊の庭園は国の史跡に指定された。 現代、1962年、大衆禅堂を開く。浴鐘楼が焼失する。 1969年、国の史跡に指定された。 1981年、微妙殿が建立された。 ◆宗峰 妙超 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の僧・宗峰 妙超(しゅうほう-みょうちょう、1282-1338)。男性。俗姓は浦上、紀氏。諡号は興禅大灯国師、高照正灯国師、大慈雲匡真(だいじうんきょうしん)国師など。播磨(兵庫県)の生まれ。父・浦上一国、母・赤松則村の姉という。11歳で天台宗の書写山円教寺の戒信律師に学ぶ。鎌倉の万寿寺で夢窓疎石の師・高峰顕日(こうほう-けんにち)に禅を学ぶ。宋から帰国した南浦紹明(なんぽ-しょうみょう、大応国師)に師事し、26歳の時に印可を受けた。南浦の没後、1309年/1308年、東山の雲居庵で隠棲し、五条大橋の下で寝起きしたという。1315年頃、叔父・赤松則村が出資した洛北紫野の大徳庵(大徳寺とも)に住む。1325年、清涼殿での正中の宗論に兄弟子・通翁鏡円の侍者として参席し、玄恵(げんえ)ら諸宗派を論破している。1337年、病臥になる。第95代・花園天皇は離宮の「萩原殿」を寺に改め、妙超に住持の推挙、寺号の命名を求めた。法嗣・関山慧玄(かんざん-えげん)を推し、「正法山妙心寺」と名付けた。最期、妙超は重篤な病に伏しており、坐禅はできず、左膝を折り結跏趺坐し鮮血に衣を染めて逝ったという。著『大燈国師語録』、『夜話記』、『仮名法語』など。京都に没した。56歳。 臨済宗大徳寺派の始祖になる。第96代・後醍醐天皇、第95代・花園天皇が帰依し、それぞれより正燈高照国師(1333)、興禅大燈国師(1337)の号を贈られた。赤松則村が帰依した。唐様、鎌倉宋元風の書にも優れた。 門下に関山慧玄、徹翁義亨、海岸了義、虎渓道壬、後に一休、沢庵などが出た。女性の参禅者もあり、大徳寺近くに尼寺の妙覚寺を設けた。 ◆関山 慧玄 鎌倉時代中期-南北朝時代の臨済宗の僧・関山 慧玄(かんざん-えげん、1277-1360)。男性。俗姓は高梨、追諡は無相大師。信濃(長野県)の生まれ。1307年、鎌倉・建長寺の広厳庵で東伝士啓(とうでん-しけい)により受戒した。建長寺の南浦紹明(なんぽ-しょうみょう、大応国師)に師事し、慧眼という僧名を授けられた。1308年、南浦没後も鎌倉の物外可什、巨山志源などに参禅した。その後、信濃に帰る。1327年、建長寺開山の大覚禅師(蘭渓道隆)50年忌出席のため建長寺に行き、西来院での宿忌法要にのぞむ。宗峰妙超(大灯国師)を知り、門弟になり印可(許可)を得た。1330年、美濃国伊深に退き、草庵に隠棲する。「雲門の関字」の公案により悟りを開き、関山慧玄の名を与えられ宗峰の法を嗣いだ。1337年、病になった宗峰は、第95代・花園天皇の求めに応じ、後継に慧玄を推挙し、招かれて開山になった。寺名を正法山妙心寺とした。1360年、最期は、旅に出るといい、旅装束姿で風水泉近くの大樹にもたれた。弟子の授翁宗弼(じゅおう-そうひつ)に不立文字(ふりゅうもんじ)、教外(きょうげ)別伝の「応燈関一流」の禅の由来を諭し、行脚姿で立ったまま亡くなったという。著『関山和尚百則公案』1巻。84歳。 遺骸は艮(北東)隅に葬られ、微笑塔が建てられた。後に微笑庵と称し、開山堂になる。権力に接近することを嫌い、禅修業に徹した。この禅風はその後の妙心寺の伝統になった。 ◆花園 天皇 鎌倉時代後期-南北朝時代の第95代・花園 天皇(はなぞの-てんのう、1297-1348)。男性。名は富仁、法名は遍行。京都の生まれ。父・第92代・伏見天皇の皇子。第93代・後伏見天皇の異母弟。持明院統。大覚寺統の第94代・後二条天皇の後、12歳で即位した。だが、父・伏見上皇、続いて兄・後伏見上皇の院政下に置かれた。鎌倉幕府の大覚寺統と持明院統の迭立案(文保の和談)は不調になる。大覚寺統の尊治親王(第96代・後醍醐天皇)に譲位した。退位後は北朝初代・光厳天皇の養育を行う。信心深く、1335年、円観により出家、遍行と称した。1337年、宗峰妙超(しゅうほう-みょうちょう)に参禅し、印可される。1342年、離宮の花園御所「萩原殿(はぎわらどの)」を改めて禅寺とし、関山慧玄(かんざん-えげん)を招いて開山にした。上皇は寺内に玉鳳院を営み移り住み、日夜、慧玄について参禅したという。歌人として秀で、京極派の一人。京都に没した。自筆日記『花園天皇宸記』 (47巻) 。52歳。 ◆授翁 宗弼 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の僧・授翁 宗弼(じゅおう-そうひつ、1296-1380) 。男性。諡号は神光寂照(じんこうじゃくしょう)禅師、鑑国師。京都の生まれ。父・藤原宣房(ふじわら-の-のぶふさ)。第96代・南朝初代・後醍醐天皇に仕え、明極楚俊(みんき-そしゅん)、宗峰妙超(しゅうほう-みょうちょう)に参禅した。1334年、官を辞し洛北岩倉に隠栖し出家した。暦応年間(1338-1342)初め、妙心寺開山・関山慧玄(かんざん-えげん)に師事し、印可を得て法を嗣ぐ。1361年、関山の没後、妙心寺第2世になり、以後20年間住持した。近江国・三雲の妙感寺で隠棲した。85歳。 後醍醐天皇の討幕計画に参画した藤原(万里小路)藤房(1295-?)と、同一人物として妙心寺には伝えられている。法嗣に無因宗因がある。 塔所は妙心寺・天授庵であり、南朝の年号をとって付けられた。妙心寺における年号寺の初例になる。 ◆拙堂 宗朴 室町時代前期の臨済宗の僧・拙堂 宗朴(せつどう-そうぼく、?-? )。男性。河内の観音寺に住した。妙心寺6世住持になる。1399年、室町幕府3代将軍・足利義満に謀反を起こした応永の乱の大内義弘と師壇関係があったことから、義満の怒りを買う。宗朴は、その後も義弘との関係を解消しなかった。このため、宗朴は青蓮院に幽閉の身になり、寺領・寺地は、青蓮院の義円(後の6代将軍・足利義教)に与えられる。さらに、南禅寺の延用宗器(ていよう-そうき、義満の叔父)の手に移された。宗器は寺名も龍雲寺と改め、南禅寺塔頭徳雲院の末寺になり、以後、妙心寺は中絶した。 ◆廷用 宗器 室町時代前期の僧・廷用 宗器(ていよう-そうき、?-?)。男性。父・室町幕府の第2代将軍・足利義詮。第3代将軍・足利義満の弟。南禅寺、天竜寺の住持になった。1399年、応永の乱で妙心寺が大内義弘に加担し、義満は妙心寺を滅ぼした。寺領は青蓮院、竜雲寺・宗器に分与した。宗器は寺名も龍雲寺と改め、南禅寺塔頭徳雲院の末寺になる。以後、妙心寺は中絶した。1394年、義満没後、位牌の奉持者になった。 ◆大内 義弘 南北朝時代-室町時代前期の武将・大内 義弘(おおうち-よしひろ、1356-1400)。男性。幼名は孫太郎、大内介、法号は有繋、法名は秀山弘実。父・大内弘世。1371年、九州探題・今川貞世(了俊)に父と共に従い、安芸、豊前に出陣し九州平定した。豊前守護職に補される。1377年、懐良(かねよし)親王を奉ずる菊池武朝を破る。1380年、父より周防・長門守護職を継承した。弟・満弘と各地で戦い、1381年、内紛は収まる。1389年、3代将軍・足利義満の厳島参詣に際し防府で迎え、随行して上洛した。1391年、明徳の乱で義満に与し幕府方として山名氏清らを破る。その功により山名氏旧領国の和泉、紀伊を与えられ、周防、長門、石見、豊前の6ヵ国の守護職を与えられた。1392年、南北朝合体斡旋に尽力した。朝鮮に遣使し、室町幕府と朝鮮とを通交させ、倭寇取締、倭寇が連行した朝鮮人を送還した。朝鮮に大蔵経、土地を要求、朝鮮と交易した。1395年、少弐氏討伐のために九州に下向し、義満の命に背き上洛しなかった。1399年、義満と対立し、応永の乱を、鎌倉公方・足利満兼、山名時清らと謀る。和泉堺で幕府軍に敗死した。44歳。 官途は周防介、左京権大夫。当初は足利義満の忠実な家臣だった。義満は、北山第造営にあたり、諸大名に多額の費用と人数の供出を求めた。義弘だけは拒否し義満の怒りを買う。和歌、連歌に通じ、『新後拾遺和歌集』に入集している。 当初は堺・妙光寺に葬られた、後に、山口・菩提寺の香積寺(こうしゃくじ、現・瑠璃光寺)に移された。 ◆雪江 宗深 室町時代前期-後期の臨済宗の僧・雪江 宗深(せっこう-そうしん、1408-1486)。男性。俗姓は野間、諡号は仏日真照禅師。 摂津(兵庫県)の生まれ。建仁寺・五葉庵の文瑛に学ぶ。犬山・瑞泉寺の日峰宗舜(にっぽう-そうしゅん)に師事し、師と共に妙心寺に入る。日峰の弟子・義天玄詔(ぎてん-げんしょう)の法を嗣ぐ。妙心寺塔頭・養源院に住した。細川勝元の帰依を受け、龍安寺の住持になる。1462年、大徳寺41世として入寺し、義天の例に倣い3日間で退く。応仁・文明の乱(1467-1477)中、丹波八木の竜興寺に逃れ学徒指導した。乱後、妙心寺の再建を行う。1477年、第103代・後土御門天皇より、妙心寺再興の綸旨を得た。「正法山妙心禅寺米銭納下帳」(1486-1885)により、寺院経営を行い、経済基盤も確立した。晩年、妙心寺・衡梅院に退隠した。『開山行実記』『正法山妙心禅寺記』を選述した。79歳。 妙心寺中興の祖といわれる。外護者に細川勝元・政元を得る。法嗣の景川宗隆(けいせん-そうりゅう)、悟渓宗頓(ごけい-そうとん)、特芳禅傑(どくほう-ぜんけつ)、東陽英朝(とうよう-えいちょう)が4派4本庵による教団統括運営組織の基礎を築いた。 ◆景川 宗隆 室町時代前期-後期の臨済宗の僧・景川 宗隆(けいせん-そうりゅう、1425-1500)。男性。諡号は本如実性禅師、法名は別に紹隆。 伊勢(三重県)の生まれ。雲谷玄祥(うんこく-げんしょう)、義天玄詔(ぎてん-げんしょう)、伊勢・大樹寺の桃隠玄朔(とういん-げんさく)らに師事後、龍安寺で再び義天、さらに雪江宗深(せっこう-そうしん)の法を嗣ぐ。大徳寺、妙心寺、龍安寺の住持、大和・興雲寺、伊勢・瑞応寺、妙心寺・大心院の開山になる。犬山・瑞泉寺、丹波・竜興寺にも住した。大心院で亡くなる。76歳。 弟子に春江、柏亭、景堂など。 ◆悟渓 宗頓 室町時代前期-後期の臨済宗の僧・悟渓 宗頓(ごけい-そうとん、1416-1500)。男性。諡号は大興心宗禅師、仏徳広通国師。尾張国(愛知県)の生まれ。17、18歳で犬山・瑞泉寺の日峰の下で禅の修行、その後、妙心寺・日峰、汾陽寺・雲谷玄祥(うんこく-げんしょう)、愚渓寺・義天玄詔(ぎてん-げんしょう)、伊勢の大樹寺・桃隠玄朔(とういん-げんさく)に付く。1464年、龍安寺・雪江宗深(せっこう-そうしん)の法を嗣ぎ、悟渓の名を与えられる。1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)により帰郷する。瑞泉寺に臥龍庵を営む。1468年、守護代・斎藤妙椿(利藤)の帰依により、美濃に瑞龍寺を建立し開山(勧請開山は雪江)になる。1471年、大徳寺を経て、1481年、妙心寺11世住職になり復興の基礎を築く。草庵・東海庵を結び東海派の発祥になる。瑞龍寺に戻り、尾張余野の徳林寺開山になる。1497年、朝廷より生前の諡号・大興心宗禅師を受け、妙心寺初例になる。瑞龍寺・済北院で死去した。著『虎穴録』。85歳。 妙心寺東海派の祖。 ◆特芳 禅傑 室町時代前期-後期の臨済宗の僧・特芳 禅傑(どくほう-ぜんけつ、1419-1506)。男性。諡号は大寂常照禅師。尾張(愛知県)の生まれ。幼少で出家、東福寺、龍安寺の義天玄詔(ぎてん-げんしょう)、美濃・汾陽寺(ふんようじ)の雲谷玄祥、伊勢・大樹寺の桃隠に師事、1473年、妙心寺・雪江宗深(せっこう-そうしん)の法を嗣ぐ。龍安寺、丹波・竜興寺、摂津・海晴寺、妙心寺開堂、1478年、大徳寺住持になる。瑞泉寺、1488年、再興された龍安寺に帰り中興開山になる。1492年、丹波・竜潭寺(旧大梅寺)開山になった。1504年、龍安寺・西源寺で隠退する。西源寺より出された語録に『西源特芳和尚語録』。88歳。 詩文に秀でた。弟子に大休などがいる。 ◆東陽 英朝 室町時代前期-後期の臨済宗の僧・東陽 英朝(とうよう-えいちょう、1428-1504)。男性。諡号は大道真源禅師。父・土岐持頼とされる。幼くして玉岫により出家、龍安寺の義天、1478年、龍安寺の雪江宗深(せっこう-そうしん)の法を嗣ぐ。1479年、丹波・竜興寺、1480年、大徳寺、1481年、竜興寺、1484年、尾張・瑞泉寺、1489年、妙心寺の住持をつとめた。帰郷して美濃・不二庵、法雲山定慧寺、瑞泉寺を経て、少林寺の開山になり、没した。著『宗門正燈』。77歳。 詩文に優れた。 ◆日峰 宗舜 南北朝時代-室町時代中期の臨済宗の僧・日峰 宗舜(にっぽう-そうしゅん、1368-1448)。男性。俗姓は藤原、河嶋、諡号は禅源大済禅師。山城国(京都府)の生まれ。9歳で天竜寺・本源庵・岳雲周登に学び、諱を昌昕(しようきん)と称した。16歳で出家し、遠江(とおとうみ)奥山方広寺の開山・無文元選(むもん-げんせん)に参じ、摂津・海清寺の無因宗因(むいん-そういん)に師事する。その法を継ぎ宗舜と諱を改めた。1399年、応永の乱で没収された妙心寺の寺産を、将軍・足利義満に願い旧に復した。無因の没後、1410年、美濃、尾張などの寺で大蔵経を閲した。1415年、尾張犬山・瑞泉寺の開山になり、無因を勧請開山にした。1429年、荒廃した妙心寺を細川勝元の支援により中興再建する。養源院に住した。勝元の支援のもと、1447年、関山派として初めて大徳寺36世に住した。81歳。 妙心寺中興の祖とされる。 ◆鄧林 宗棟 室町時代後期の臨済宗の僧・鄧林 宗棟(とうりん-そうとう、?-1522)。男性。俗名は豊久。父・山名宗全、養父は管領・細川勝元。勝元に嫡子はなく、妻の父・山名宗全より豊久を養子として受けた。だが、1466年、勝元に実子・政元が生まれる。勝元は豊久を廃嫡したため、豊久は出家した。鄧林宗棟と称し、後に妙心寺17世住持になった。以後、宗全と勝元の対立は、応仁・文明の乱(1467-1477)の一因になったという。 ◆利貞尼 室町時代中期-後期の僧・利貞尼(りてい-に、1455?-1536/1537)。女性。細姫。父・関白・一条兼良/野間入道の娘(甘露寺親長の養女)とも。美濃の豪族・斉藤利国の妻になり、夫の戦死後、悟渓宗頓禅師の弟子につき尼になる。1509年、遺領を投げ打ち土地を妙心寺に寄進し、境内を3倍の広さに拡大する。山内に、大珠院、聖沢院、天授院、東海庵を寄進した。81歳?。 ◆海山 元珠 安土・桃山時代-江戸時代前期の僧・海山 元珠(かいざん-げんじゅ、1566-1642)。詳細不明。男性。南化玄興(なんか-げんこう)の弟子。祥雲禅寺の2世住持になった。1614年、方広寺梵鐘銘事件の際に、五山僧の中でただ一人、徳川家康の言い掛りに対し、「愚にもつかない誤り」と発言した。1615年、豊臣家滅亡後、家康による豊国社、祥雲寺の破却が行われる。海山は、師・南化玄興の木像を背負い、棄丸木像を胸に抱き、棄丸の遺品類も携えて妙心寺に戻った。自坊「亀仙庵(きせん-あん)」を祥雲寺の祥雲を逆さにして「雲祥院」と変えた。家康に無言の抵抗を続けたという。 弟子に鉄牛(1567-1615)がいる。 ◆海北 友松 室町時代後期-江戸時代前期の画家・海北 友松(かいほう-ゆうしょう、1533-1615)。男性。名は紹益、初名は友徳、別号に如切斎、有景斎。海北派の始祖。近江(滋賀県)に生まれる。父・浅井長政家臣・海北綱親の5男/3男。3歳で家が滅び、東福寺で出家、狩野永徳(元信とも)に絵を学ぶ。梁楷(りょうかい)など宋、元水墨画風に影響を受ける。減筆法を拓く。豊臣秀吉に認められた。40歳過ぎで還俗した。1582年、山崎の戦で敗れて処刑された友人の斎藤利三の処刑後、その妻子(子はのちに徳川家光の乳母春日局)の面倒をみた。1602年頃、八条宮智仁親王、第107代・後陽成天皇の御用を受ける。作品は建仁寺本坊方丈「山水図」、妙心寺「花弁図屏風」など。83歳。 ◆狩野 山楽 室町時代後期-江戸時代前期の画家・狩野 山楽(かのう-さんらく、1559-1635)。男性。姓は木村、名は光頼。近江(滋賀県)に生まれた。父・木村永光は浅井長政の家臣。当初は長政に仕え、後に豊臣秀吉の近侍になる。秀吉の推挙で狩野永徳の門人になり、養子になり狩野氏を許された。1590年、秀吉の命により、病に倒れた師・永徳を継ぎ、東福寺法堂「蟠竜図天井画」(1881年焼失)の修復を数日で完成させる。1594年、伏見城、1597年、再建の伏見城、1604年、大坂城の千畳敷大広間の障壁画にも参加した。1615年、豊臣家滅亡で大坂城を脱出し、男山八幡宮の社僧で山楽の弟子・松花堂昭乗のもとに身を隠した。於江与(崇徳院)らの取成しにより京都に帰る。2代将軍・徳川秀忠、3代将軍・家光に重用され、再建された四天王寺、大坂城本丸障壁画、妙心寺・天球院障壁画などにも加わる。代表作に正伝寺方丈、養源院の障壁画がある。 泉涌寺に葬られた。山楽、山雪の子孫は京都に住み京狩野と呼ばれた。77歳。 ◆狩野 探幽 江戸時代前期の画家・狩野 探幽(かのう-たんゆう、1602-1674)。男性。幼名は釆女、通称は守信、別号は白蓮子、生明。京都の生まれ。父・孝信の長男。幼少より絵を描き、1616年、江戸城家康霊廟天画の絵師、1617年、江戸幕府御用絵師になる。1623年、弟・安信に狩野宗家を譲る。1626年、二条城、1627年、大坂城の障壁画、1632年、徳川秀忠霊廟、1633年、名古屋城本丸障壁画などを手掛ける。1638年、法眼に叙される。1641年、「東照宮縁起絵巻」、1642年、大徳寺本坊方丈、1647年、江戸城の障壁画、1662年、法印に叙される。73歳。 ◆狩野 益信 江戸時代前期の画家・狩野 益信(かのう-ますのぶ、1625-1694)。男性。幼名は山三郎、名は益信、通称は采女、号は洞雲、宗深道人、松陰子(しょういんし)など。父・彫金家・後藤立乗。幼時より松花堂昭乗に書を学び、好んで画を描いた。1635年、狩野探幽の養子になる。1659年、江戸城本丸御殿障壁画制作に参加した。探幽の実子・狩野探信守政、探雪が各7歳、5歳になり、益信は35歳で別家し、駿河台家の祖になる。1665年、隠元隆埼(いんげん-りゅうき)より洞雲の号を与えられる。1667年、江戸屋敷を拝領した。1682年度の贈朝屏風を制作し、二十人扶持を拝領する。内裏造営の寛永度(1641-1642)、承応度(1654-1655)、寛文度(1662)、延宝度(1674-1675)に参加し、探幽、狩野安信とともに活躍した。1691年、徳川家光に好まれ法眼に叙される。代表作として、「獅子図・虎図・花島図襖絵」(妙心寺大方丈)、「琴棋書画・四愛図襖絵」(大徳寺玉林院)など。69歳。 駿河台狩野家の祖。探幽以後を担った主要画家だった。探幽、安信、常信らとの合作も多い。 ◆白隠 慧鶴 江戸時代前期-中期の臨済宗の僧・白隠 慧鶴(はくいん-えかく、1685-1768)。男性。号は鵠林。勅諡号は神機独妙禅師、正宗国師。駿河国(静岡県)の生まれ。幼い頃より、地獄、極楽の説法に魅せられたという。1700年、15歳で駿河・松蔭寺の単嶺祖伝のもとで出家、慧鶴と名付けられた。沼津・大聖寺息道に師事した。1703年、清水・禅叢寺で修行する。雲棲袾宏(うんせい-しゅこう)の『禅関策進』により開眼、諸国を巡り美濃・瑞雲寺の馬翁、松山・正宗寺の逸伝、1708年、越後高田・英巌寺の性徹などに参じ、信州飯山の道鏡慧端(どうきょう-えたん、正受老人)の法嗣になる。1710年、京都の白幽子に内観法を学ぶ。ただ、白幽子と会ったことについては創作説もある。1716年/1717年、松蔭寺に還る。1718年、妙心寺第一座になり白隠と号した。この時、法兄・透鱗の法嗣とした。1763年/1758年、三島・龍澤寺を中興開山、1768年、松蔭寺に戻り当寺で亡くなる。84歳。墓も松蔭寺(静岡県)にある。 臨済宗十四派の中興の祖。公案禅をすすめ、林(こうりん)派を形成した。漢詩文、法話、俚謡など多く著し、書画も遺した。弟子に東嶺円慈(とうれい-えんじ)など多い。以後、妙心寺は臨済宗の主流になった。 ◆文奕 無学 江戸時代後期-近代の臨済宗の僧・文奕 無学(ぶんえき-むがく、1819-1898)。男性。俗姓は山田、関、諱は文奕、号は無学、室号は樹王軒、美濃国(岐阜県)の生まれ。父・山田久兵衛の次男。8歳で得度、美濃・清泰寺の梅山和尚に師事し深源に学ぶ。1841年、江戸・佐藤一斉に儒教を学ぶ。のち蘇山玄喬(そざん-げんきょう)・羅山元磨(らさん-げんま)に参じ、羅山の寂後を受け、1866年、筑後・梅林寺に住する。1874年、妙心寺派管長、東京大教院の校長に就く。1876年、臨済宗妙心寺派として独立した。権大教正に補せられる。東京・済松寺に退く。1878年、再び妙心寺管長になり大教正に進む。1883年、辞し、1885年、管長に推薦せらた。1895年、管長の職に就く。妙心寺方丈で亡くなる。80歳。 ◆仏像・木像 ◈仏殿中央に須弥壇、左右に脇仏壇が作られている。 須弥壇に本尊「釈迦如来坐像」を安置する。右手を挙げた拈華(ねんげ)微笑、結跏趺坐、左手に蓮華の蕾、右手はそれを支える。猷通寺寄進による。 脇侍は「阿難」・「迦葉(かしょう)両尊者の像」を安置する。安土・桃山時代、1582年頃の造立による。雪牛和尚寄進による。 ◈三門二階の仏堂須弥壇に、本尊の「円通大士坐像(観音菩薩)」、脇侍は「善財童子」、「月蓋(げつがい)長者」、左右に「十六羅漢像」を安置する。 ◈開山堂に、没後造られた「関山慧玄木像」、肖像画が祀られている。 開山堂内、昭堂(鳳凰昭堂)には、法体姿の「花園法皇木像」が安置されている。 ◆建築 伽藍配置は、近世禅宗寺院の様式の遺例になる。南より、勅使門から、放生池の北に三門、仏殿、法堂(ほっとう)、寝堂、大方丈・小方丈、1大庫裏などの伽藍が、一直線に並ぶ禅宗大寺院の配置になる。さらにその周辺に、浴室、経堂など七堂伽藍が建ち並ぶ。仏殿、法堂が揃う。その周囲に塔頭が配置されている。 ◈「北総門」(重文)は、江戸時代前期、1610年に建立された。西(右手)に潜り通用門がある。大工・宗知、吉次作という。 3間、薬医門、切妻造、本瓦葺。 ◈「南総門(南門)」(重文)は、江戸時代前期、1610年に建立された。右脇小間に片開きの板扉の通用門がある。大工・宗知、吉次による。 3間、薬医門、切妻造、本瓦葺。 ◈「勅使門」(重文)は、江戸時代前期、1610年に総門として建立された。境内南、下立売通に面して建つ。かつては総門であり、南大門、南四足門と呼ばれた。板蟇股に彫刻が施されている。 四脚門、切妻造、檜皮葺。 ◈「三門(山門)」(重文)は、安土・桃山時代、1599年に建立された。棟梁は藤原家次による。京都では、東福寺三門、大徳寺山門に次ぐ古い山門建築という。この三門とは、空門、無相門、無作門の3種であり、三解脱門という。求道者が涅槃に至る3種の方法を示している。 建物は朱色に彩色(丹塗)されている。柱は礎盤に粽。階上に桟唐戸。縁に高欄、隅に逆蓮柱。扇垂木。二階欄干の擬宝珠は茶筅の様な形をしている。二階の仏堂は5間2間あり、須弥壇には、本尊の円通大士坐像(観音菩薩)と脇侍は善財童子、月蓋(げつがい)長者、左右に十六羅漢像を安置する。鏡天井に、龍図、迦陵頻伽(がりょうびんが)、天人、柱、紅梁などにも狩野権左衛門により波、雲、竜、鳳凰、飛天などが極彩色で描かれている。楼上より、東山、大文字、左大文字、仁和寺五重塔、愛宕山などが眺望できる。 5間3戸2階二重門、入母屋造、本瓦葺、高さ16m。階下左右に山廊が付く。山廊は、各2間2間、一重、切妻造、本瓦葺。 6月18日に二階上層で山門懺法会が行われ公開される。7月15日に階下で山門施餓鬼会が催される。 ◈「仏殿」(重文)は、安土・桃山時代、1583年/1584年に建立された。江戸時代、1827年/1830に改築された唐様建築になる。桟唐戸、花頭窓、板壁、貫を通す柱、扇垂木。4本の大梁の2本は仁和寺、1本は江州、1本は宇治より運ばれたという。裳階に海老虹梁、化粧屋根、敷瓦の四半敷になる。棟梁は神森若狭藤原勝信による。須弥檀には本尊の釈迦如来像(拈華 [ねんげ]の釈迦像)、脇侍は後に加えられた迦葉、阿難を安置する。須弥檀の背後に祖師堂、土地堂、祠堂がある。 3間3間、四周1間通、一重裳階付(上屋根に裳階が載る)、入母屋造、本瓦葺の禅宗様。 勤行は毎日行われている。1日、15日に祝聖、釈尊降誕会、成道会、涅槃会、般若、祠堂斎が催される。 ◈仏殿と法堂とつなぐ「廊下」は、江戸時代の建立による。 5間1間、一重、唐破風造。 ◈「法堂(はっとう)」(重文)は、江戸時代前期、1657年/1656年に建立された。山内最大の建物になる。内部身屋は5間4間。中央に須弥壇、天蓋、後屏風、四半瓦敷の床。材は富士山麓の欅、小屋根の大梁は日向国、淀の松による。仏殿より一層大きく禅宗様(唐様)に徹した造りになっている。住職が法要儀式、法を説くところで、上堂といい須弥壇だけを設ける。鏡天井に狩野探幽筆「八方にらみの龍」が描かれている。 5間4間(裳階部分を含むと7間6間)、四周1間通、一重裳階付、入母屋造、本瓦葺、禅宗様(唐様)。 御所、南東を向いた側の法堂などの鬼瓦は、鬼ではなく、龍になっている。火伏せの意味もある。 年朝上堂(1月1日)、入制上堂(4月15日)、解制上堂(7月15日)、四節上堂、そのほか新住持の入寺開堂式、法要の際には、その都度それぞれの仏祖が祀られる。法会としては開山忌、花園法皇忌、達磨忌などで使用される。吉田兼好が『徒然草』のなかで、その鐘の音は「黄鐘(おうじき)調」と形容した国宝「黄鐘調の鐘」が保管されている。1973年まで、外の鐘楼に下げられ朝夕に鳴らされていたが、鐘の破損の恐れがあるため中止された。 ◈大方丈の「玄関」(重文)は、江戸時代前期、1654年に建立された。 5間1間。一重、唐破風造、桧皮葺。 ◈大方丈の「唐門(真前唐門)」は、江戸時代前期、1654年に建立され、江戸時代後期、1806年改造された。向唐門様式。 ◈「大方丈」(重文)は、安土・桃山時代、1592年に建てられた前方丈を、江戸時代前期、1654年/1653年に改築した。6室あり、北に裏の間。北中の間に仏間がある。近代、石清水八幡宮の奥の院から、阿弥陀如来、観音菩薩、勢至菩薩が勧請された。表側3室に狩野探幽らの障壁画がある。扁額「方丈」は宋の張即之(1186-1266)の書による。正面、両横に大広縁、落縁を廻す。 桁行29.5m、梁行21.7m。一重、入母屋造、檜皮葺/杮葺。 ◈「小方丈」(重文)は、江戸時代前期、1603年に建立される。1656年に玉鳳院を移築、改築された。花園法皇は、離宮にあった「麒麟閣(きりんかく)」に開山・関山慧玄を迎えたことから「麒麟閣(麟徳殿)」とも呼ばれている。南縁西の板戸に麒麟が描かれている。住持が常住した。室中、仏間がない。 桁行15.9m、梁行10m。一重、入母屋造、杮葺。 ◈開山堂「微笑庵」(重文)は、花園天皇により建立された禅堂をいう。妙心寺発祥の地になっている。天皇の離宮は禅宮御殿になっていた。室町時代初期に建てられたもので、室町時代後期、1537年/天文年間(1532-1555)に東福寺より移築された。1538年に造立されたといい、山内最古の建物になる。室町時代作の開山・関山慧玄(無相大師尊像)の像が安置される。 3間4間、入母屋造、本瓦葺、一重禅宗様。花狭間唐戸、床は四半敷。 堂前の二基の石灯籠は、妙心寺型といわれ、竿が太く膨らんでいる。(非公開) ◈開山堂内、「昭堂(鳳凰昭堂)」には、法体姿の花園法皇の木像が安置されている。 東の開山堂と西の玉鳳院は渡り廊下でつながっている。 ◈「玉鳳院(鳳凰禅宮)」(重文)の現在の方丈は、江戸時代前期、1656年に再建された。三方に広縁外の落縁に高欄、東面に階段が付いている。 桁行18.7m、梁行10.8m。一重、入母屋造、檜皮葺。 ◈「経蔵」(重文)は、江戸時代前期、1673年に上棟された。1674年に竣工した。大坂の淀屋辰五郎の寄進による。回転式輪蔵は八角形回転式で、本体の八角の堂型の柱間に一切蔵経6527巻の経巻が納められている。12人の学僧が8年の歳月をかけ写経したという。四手先の組物で支えられた縁が本体を囲み、各柱が立つ。上に三手先の組物に扇垂木、八角の輪蔵下に円い縁が付き、上の八天の彫像は「八天推輪の像」が置かれる。これは、輪蔵を廻す持国・増長・広目・多聞の四天王、さらに梵天・帝釈天、密迹(みっしゃく)・金剛の二力士が描かれている。輪蔵を考案した中国南北朝時代、南梁の僧・傳大士(ふだいし)木像が安置されている。その姿は、道教の冠、儒衣、仏教の袈裟を身に着けている。傳大氏(497-569)は名を傳翕(ふきゅう)、双林大士、東陽大士とも呼ばれた。武帝と仏法を論じ、回転式の書架を考案し、字の読めない者、その時間がない者のために、輪蔵の扉を押して回すだけで読経と同じ功徳があるとした。扁額「毘盧蔵(びるぞう)」は、鎌倉時代、第92代・伏見天皇の宸筆(しんぴつ)という。 鏡天井、床瓦敷、1間1間(外観は重層、3間3間)、四周1間通、一重裳階付、宝形造、本瓦葺、八角輪蔵付。 ◈「鐘楼」は、江戸時代、1696年に建立された。 1間1間、袴腰付、切妻造、本瓦葺。 ◈「浴鐘楼」は、江戸時代前期、1639年、春日局が寄進したものが焼失後、局の菩提寺である塔頭・麟祥院より移築された。角の斗栱(ときょう)枡組は白漆で塗られ美しい。 3間2間、入母屋造、袴腰付。 ◈「大庫裏」(重文)は、室町時代後期、1528年に建立され、江戸時代前期、1653年に上棟(改築ともいう)、1654年に竣工された。江戸時代後期、1808年に杮葺より瓦葺に代えられる。白壁に垂直、水平の木組みが格子模様になっている。屋根上に排気用の櫓煙出し(吸口 [すいぐち])がある。唐破風屋根の迫り出した部分の韋駄天堂には、守護神・韋駄天が祀られている。内部は入口土間、板敷広間、大庫裏、小庫裏、食堂(30畳)には定朝作の地蔵菩薩像を安置している。ほかに、貯蔵庫からなる。土間には6つの大竈がある。行事に際して雲水は数百人分の斎(とき、食事)を調える。 妻壁に虹梁大瓶束、海老虹梁。 桁行25.8m、梁行18m、一重、切妻造、妻入、東面・西面・北面庇付、北面・東面下屋附属、総杮/葺桟瓦葺。 ◈「寝堂(前方丈、礼間)」(重文)は、江戸時代前期、1656年に建立された。かつては、住持の接客場、後に法堂の控室になる。土壁白土仕上。鏡天井に床は四半瓦敷。南に戸口、東南端に戸口。花頭窓。 3間3間、一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈「浴室(明智風呂)」(重文)は、江戸時代前期、1656年/1587年に建立された。明智光秀(1528-1582)の叔父、密宗和尚(塔頭・大嶺院開山、その後廃寺)が光秀の追善菩提のために建立したとされ、「明智風呂」とも呼ばれている。内部は蒸風呂と洗い場になっている。床の板間より蒸気が上る蒸し風呂で、現在でも使用できるという。 正面に唐破風屋根がある。蟇股、桟唐戸。花頭窓。桁行5間、梁行正面5間、背面3間。一重、切妻造、妻入、本瓦葺。 なお寺伝によれば、安土・桃山時代、1582年の本能寺の変後、光秀は妙心寺に逃げ込み、自害しようとした。その時、密宗和尚に諭され思いとどまったという。 ◈境内の「石畳」は、近代、1895年に、花園法皇550年遠諱(おんき)に当たり、匡道慧潭(きょうどう-えたん、1808-1895)が私財を投じて境内縦横の参道に石板を敷いた。一部は自ら工事を行った。以後、雨が降っても泥濘で汚れることが無くなったという。 ◆庭園 本坊庭園は、大方丈前庭、大方丈庭園、小方丈庭園の3つに大別される。近代、1931年に国の史跡に指定された。 ◈「大方丈前庭」は、江戸時代初期に作庭された。対照形方形の庭園になる。勅使門と山門の間に石橋が架かる。左右相対の方形の放生池がある。泮(はん)池といわれる。池には反りのある桁行形式の石橋が架かる。俗世から聖地に入る境界を意味する。松の疏林が植えられ、山門北の四派の松と呼応する。 ◈「大方丈庭園」は、江戸時代、1654年に再建された大方丈の南庭になる。全面白砂敷の平庭になる。3本の老松がある。正面に唐門があり、方丈正面には2つの盛り砂がある。 ◈「小方丈庭園」は枯山水式庭園(史跡・名勝)になっている。江戸時代末期に作庭された。苔地に、三尊石の石組を中心に、わずかな石、木が配されている。樹齢200年の馬酔木が植えられている。 ◈塔頭・玉鳳院内南側に白砂と切石の延段のみの庭がある。 ◈玉鳳院内北側に「蓬莱式枯山水の庭園」と井戸「風水泉」(史跡・名勝)(130坪)がある。苔地に、安土・桃山時時代初期の豪快な石組、滝組、蓬莱石の石組、飛石、低い植栽が見られる。江戸時代前期、1656年に一部改修されている。鶏足嶺は、江戸時代の作庭による。長方形の築山に景石群を配した。インドの仏蹟鶏足山に因む。鷄足嶺の麓に、織田信長・信忠、武田信玄(1521-1573)・勝頼(1546-1582)・信勝(1623-1650)・信豊(1549-1582 )の石塔6基が立つ。井戸「風水泉」は、開山・無相大師が傍らで立ったまま入寂したという逸話がある。据えられている手水鉢の基礎は蓮葉になっている。北東に棄丸の御霊屋(棄君堂)が建てられている。(非公開)。 ◈小方丈には「枯山水式」(史跡・名勝)の庭園がある。江戸時代末期に作庭された。樹齢200年の馬酔木が植えられている。 ◈塔頭・東海庵には3つの庭がある。書院院西庭の枯山水式の「東海一連の庭」は江戸時代後期、1814年に東睦和尚により作庭された。三尊石(不動石、日天石、月天石)、築山(方丈、蓬莱、瀛州 [えいしゅう])の三神仙島、亀石・鶴石、水分石、礼拝石などが配されている据。北(右)手前に一文字型手水鉢、南に春日型の六角燈籠、橋柱の手水鉢が据えられている。植栽は木斛(もっこく)、山茶花(さざんか)、梔子(くちなし)、躑躅(つつじ)、皐月、南天、松、槇などがある。 方丈南庭には、白砂敷きで砂紋のみが引かれている。左手前に大棗形手水鉢が据えられている。 坪庭がある。書院南の枯山水式庭園「中坪の庭」は7坪の白砂に、7つの石が直線上に置かれている。中央の石を軸にして砂紋が同心円に広がっている。石は7石しかないが七五三石組のひとつ。また、一石は隠し石になっている。(非公開) ◆妙心寺 山号、寺号について釈迦の逸話が関係している。 釈迦が霊鷲山(りょうじゅせん)で弟子達に仏法を説いた。釈迦は、黙って大梵天王から受けた金波羅華(こんぱらげ、金色の蓮花)を捻り弟子たちに見せた。摩訶迦葉(まかかしょう)のみがその意味を悟り微笑んだという。そこで、釈迦は彼だけに仏法の心理を授けた。これを「拈華微笑(ねんげみしょう)」という。「花を捻りて微笑する」、言葉を使わずに互いが理解しあう。心から心へ伝わる微妙な境地、感覚、以心伝心をいう。 釈迦は「吾に正法眼蔵、涅槃妙心あり。摩訶迦葉に附嘱す」と続けた。正法眼蔵、涅槃妙心とは、仏法そのものを表し、法が摩訶迦葉に伝わったことを意味した。 宗峰妙超は、花園法皇の求めに応じ、山号をこの正法眼蔵より正法山、寺号を涅槃妙心により妙心寺とした。また、花園法皇は大梵天王に、宗峰妙超自身は釈迦、関山慧玄は摩訶迦葉、そして花園離宮を金波羅華に喩えたという。 ◆応燈関の法脈 花園上皇は、宗峰妙超(大燈国師)に帰依した。上皇が宗峰に妙心寺開山の推薦を願い、関山慧玄が選ばれた。宗峰の師は南浦紹明(大応国師)であることから、中世の臨済禅の三人の名から「応燈関の法脈」と呼んだ。 ◆禅 前5世紀、現在のネパールの釈迦は、菩提樹の下での坐禅により悟りを得た。6世紀前半、南インドの達磨大師は、これを中国に伝える。平安時代、宋より栄西は臨済宗と看話禅(公案を重視し、研究理解することで大悟に至る)を日本に伝えた。鎌倉時代、道元は曹洞宗と黙照禅(座禅を重視し、無念無想となることにより悟りを得る)を伝えた。 臨済宗の公案禅は、師家が弟子に公案といわれる問題を出題し、坐禅の中でその答えを見出すことにより悟りを得ようとした。江戸時代、臨済宗中興の祖・白隠は、公案の体系化を行っている。 ◆林下 五山は、鎌倉時代、中国寺院の統制制度を導入した官寺制度をいう。妙心寺は「林下(りんか)」といわれ、これらの制度から外れていた。林下は山隣派といわれる幕府の庇護は受けず、朝廷と関わり深かった妙心寺、大徳寺と、地方で勢力伸長させた曹洞宗・永平寺の二つがあった。 五山は十方住持制という住持就任の際に、門流に固定せず幅広く人材を採用した。これらの寺院を「十方住持刹」といった。林下は「一流相承制(徒弟院)」という門流による寺院相続を採った。だが、次第にすべての寺院が一流相了承制になった。 室町時代、京都の禅宗のうち、幕府の庇護と統制下にあった一派(禅林、叢林)と、それとは一線を画す格下、在野の寺院(林下)があり、妙心寺は大徳寺とともに、修行を重んじる厳しい禅風を特色とした林下の代表的寺院とされた。 ◆四派四本庵 雪江宗深の法嗣から四派、10世・景川宗隆(けいせん-そうりゅう、龍泉派)、11世・悟渓宗頓(ごけい-そうとん、東海派)、12世・特芳禅傑(とくほう-ぜんけつ、霊雲派)、13世・東陽英朝(とうよう-えいちょう、聖澤派)が出た。 室町時代、それぞれに四本庵が付与された。龍泉庵(1481)、東海庵(1484)に加え、聖澤院(1523)、霊雲院(1526)が創建され四派の拠点になる。これにより、「四派四本庵(しは-しほんあん)」による運営体制が確立する。この四派により、一山の全権が掌握され、住持も決定された。 師・雪江は4人を評し、「禅は景川、徳(福)は悟渓、寿(頌)は特芳、才は東陽」と讃えている。 なお、この4院に如是院、退蔵院、衡梅院などの3院を加え「六祖道場」とも呼ばれた。 ◆紫衣事件 江戸時代、紫衣(しえ)事件が起こる。 江戸時代前期、1613年旧6月、徳川家康は「勅許紫衣之法度」発布により、大徳寺、妙心寺など7寺の住持に関して、勅許の前に幕府に予告することを定めた。だが、妙心寺、大徳寺は応じなかった。引き続き1615年、住持についての法度「諸宗本山諸法度(元和の法度)」が出される。 1626年、第108代・後水尾天皇は幕府に報告なく、妙心寺、大徳寺などの僧に紫衣着用を許可したため、幕府はそれを無効とした。1627年の「諸宗法度」により、幕府は法度の厳守を求める。 1628年、大徳寺の澤庵宗彭が起草し、玉室宗珀、江月宗玩、妙心寺の単伝士印が署名した抗弁書が京都所司代・板倉重宗に提出された。1629年、三氏は幕府により江戸に呼び出され、藤堂高虎、以心祟伝、天海らの評議を受けた。 1629年旧7月、それでも抵抗した澤庵は出羽上山藩、玉室は陸奥棚倉藩、単伝士印は出羽本庄藩、東源慧等は陸奥弘前藩に流罪になる。また、1615年以来、幕府の許可なく着した紫衣を剝奪された。 この「紫衣(しえ)事件」は、旧来は高僧が着る法衣の紫衣の勅許は朝廷の権限であったものを、幕府に事前に知らせることにした。幕府による寺院統制を行う意図があった。関わった僧は流罪にされ、後水尾天皇は譲位し、これに抗したといわれている。 ◆四派の松 三門と仏殿の間に「四派の松」といわれる4本の松が植えられている。室町時代、妙心寺の運営体制を確立した妙心寺四派の、龍泉派・東海派・霊雲派・聖澤派をそれぞれ表しているという。 また法堂東に、その師・雪江宗深に因む「雪江の松」があった。近代、1929年の風水害により倒木し、その後実生した松が育っている。 ◆女性建立の塔頭 境内には女性が建立、庇護した塔頭が10ほどある。 斎藤利国妻・利貞尼は妙心寺に土地を寄進し、大珠院、聖沢院、天授院、東海庵を寄進した。備前岡山藩主・池田光政伯母は、天球院を建立した。信濃松代藩主・真田信之孫・長姫は大法院を、徳川家光乳母・春日局は麟祥院を建立している。 ◆文化財 ◈鎌倉時代、1329年、紙本墨書「宗峰妙超(大灯国師)墨蹟 関山号」(66.7×72.7㎝)は、妙超が弟子・慧玄に与えた道号。かつて巻物だったが、掛幅に改装された。 ◈鎌倉時代後期、1330年紙本墨書「宗峰妙超(大灯国師)墨跡 無相大師への印可状」(国宝)は門外不出とされた。 ◈鎌倉時代後期、1329年の紙本墨書「宗峰妙超 関山字号」(国宝)。鎌倉時代、1330年「宗峰妙超頂相 自賛」(重文)。鎌倉時代「南浦紹明頂相」、南宋時代、1258年「虚堂智愚頂相 自賛」(重文)。室町時代、「花園法皇御影 後花園上皇追賛」(重文)。南北朝時代、1347年「花園天皇遺詔 往年の宸翰」(重文)。 鎌倉時代「六祖師像」(重文)。室町時代、相阿弥筆という「山水図」(重文)。室町時代、狩野元信筆「瀟湘八景」(重文、東海庵蔵)。 ◈安土・桃山時代、17世紀初頭、海北友松筆の屏風、17世紀の紙本金地着色「花卉図」(重文)(各178.1×361.4㎝)では、咲き誇る牡丹の花弁が扁平に歪められ、線、面ともに強調されている。 ◈「寒山捨得図・三酸図」・「琴棋書画図」、17世紀の狩野山楽筆、紙本金地着色「文王呂尚・商山四皓図」六曲一双(重文)(167.4×364.3㎝)は、かつて海北友松筆とされていた。左隻には釣り糸を垂れる呂尚(太公望)を周の文王が訪ねている。右隻には乱世を逃れ隠棲する4人の老高士が描かれる。いずれも金雲に人物像が強調されている。 ◈安土・桃山時代、17世紀の狩野山楽筆、紙本金地着色「龍虎図」(重文)六曲一双は、右隻の雲間の龍と左隻の牙をむく雄虎が頭を右に振り龍を威嚇する。牝虎(豹)が脇に描かれている。 ◈「巌子陵図」・「虎渓三笑図」(重文)。 ◈南宋時代、李確筆「豊干図」(重文)・「布袋図」(重文)。南宋時代、滅翁文礼賛「達磨図」(重文)。元時代、馬麟筆という「普賢菩薩像」(重文)。梵鐘(国宝)は最古の銘を持つ。 ◈3歳で夭逝した豊臣秀吉長子・棄丸の「豊臣棄丸坐像・玩具船」(重文)(隣華院所蔵)。「色々絲縅胴丸」(重文)。鎌倉時代の「倶利迦羅龍合口剣」(重文)。「白綸子包胴丸」「漆箔兜」「黒漆塗菊文蔵」。 ◈山門天井画は狩野派による。天女を描いた筆遣いが角ばった線で構成されており、視覚的な効果を生む。 ◈法堂に国宝「黄鐘調の鐘」が保管されている。吉田兼好が『徒然草』のなかで、その鐘の音は「黄鐘(おうじき)調」と形容した。現代、1973年まで、外の鐘楼に下げられ朝夕に鳴らされていたが、鐘の破損の恐れがあるため中止された。 ◆障壁画 ◈大方丈の表側3室に、江戸時代前期、1655年の狩野探幽筆76面、裏側3室に狩野洞雲(采女、益信、1625-1694)筆)筆52面の障壁画がある。「四季山水」、「花鳥山水」、「獅子」、「竹虎」などが描かれている。 ◈小方丈に「山水花鳥図」があり、片山尚景筆という。 ◆狩野探幽・龍図 法堂内部の鏡天井に狩野探幽(1602-1674)筆の「雲龍図」(重文)がある。江戸時代前期、1656年作による。8年の歳月をかけて描いたもので、円相の直径は12mある。現在まで、修復されておらず、描かれた当時の状態が保たれている。 龍は、寺側の注文通りに、鏡天井に貼られた板に直接描かれている。絵は地上で描かれ後に天井まで吊り上げらている。円相の外に霊雲、内側の渦巻く黒雲を背景として、頭を円の中央に置いた龍が蜷局を巻いている。 「八方睨みの龍」といわれ、どの方向から見上げても、常にそちらの方向を睨んでいるように見える。場所によっては、天から降りるようにも昇るようにも見える。探幽は、龍の眼を描く際には牛を、爪は鷹というように実在の動物を参考にしたという。 この龍図には逸話が残されている。最後に、探幽が龍の眼に筆を入れた時、風雨が起きるほどの出来栄えだったという。また、探幽は、寺が用意した画料と酒樽も受け取らずに立ち去ったという。 探幽は、狩野孝信の長男として京都に生まれた。江戸幕府の御用絵師になり、江戸城、二条城、寺院などに多くの障壁画を残した。「余白の美」で知られている。写生画は、尾形光琳も模写した。 天龍図は、龍が水を司る神であることから、仏法を守護し、修行僧に法雨、仏法の教えを降し、寺を火災から守るという意味もあった。室町時代、東福寺法堂に、画僧・兆殿司(明兆、1352-1431)が蟠龍図を描いたのが日本の初例といわれている。 ◆妙心寺版 妙心寺版として、平安時代後期、1125年に成立した宋の圜悟克勤(えんご-こくごん)著の仏教書『碧巌録(へきがんろく)』10巻が開版され、再度復刻された。安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長・元和年間(1596-1624)にも、古活字版の印行が行われた。 ◆黄鐘調の鐘 法堂(はっとう)内に「黄鐘調(おうじきちょう/おうしきぢょう)の鐘」といわれる「梵鐘」(国宝)がある。雅楽の六調子の一つ、黄鐘を基音とする調子に美しい音色が合うとされ、この名が付けられた。 飛鳥時代、698年に鋳造された。紀年銘文のある鐘としては日本最古とされる。鐘の内部に「戊戌年四月十三日壬寅収 筑前糠屋評造春米連広国鋳鐘」と刻まれている。筑前糠屋評(郡)の糠屋評造(郡領)で糠屋屯倉の後身であり、発願の春米連は屯倉に置かれた春米部を統轄する伴造の後裔になるという。鋳工・舂米連広国とすれば、鋳工名を知る最も古い記録になる。 太宰府・観世音寺の梵鐘と同型の鋳造によるとみられる。同時期、同工房で製作されたという。『徒然草』220段に記されている「黄鐘調」という。 古式の特徴として、口径が小さく丈長く細身になる。胴張が少なく、上下帯に唐草文、撞座(つきざ)の位置も高く12弁の蓮華座になっている。鐘の音は、低周波の複合音から成り、この鐘は理想とされる129ヘルツという。西洋音階での「ラ」を基準音としている。上部にある突起状の「乳(ちち)」の一部が欠如している。民間信仰により、乳の出がよくなるとされ、引き剥がされたためともいう。口径86㎝、総高151cm/150.5㎝、青銅製。 伝承として厩戸王(うまやどのおう、聖徳太子、574-622)が大坂・四天王寺六時堂前での聖霊会の際に、楽律調整に用いた鐘ともいう。後、花園・法金剛院に移された。また、浄金剛院(壇林寺後身)にあったともいう。妙心寺門前で、開山は鐘を運ぶ農民に出遭う。尋ねると、農民は廃寺の鐘を売り、農具と取り替える途中だと述べた。開山は妙心寺に梵鐘がなかったことから、馬目一貫目で求めたという。 現在、鐘楼に吊るされている梵鐘は、現代、1974年に復元された。音色も再現されており、儀式、時の鐘として撞かれている。 ◆不思議 本山、塔頭に不思議といわれる伝承がある。 「四派の松」は、仏殿、山門の間に植えられている。四派を表し、竜泉(東北)、東海(西北)、霊雲(東南)、聖沢(西南)になる。別項詳細。/「涅槃像」は涅槃堂にある。鋳工・吉岡豊前守藤原重次の作という。地下は檀家納骨所になる。黄銅製、3.9m。/「黄鐘調の鐘」は別項詳細。/「懸魚に四葉」は、南正面の門にある。懸魚は四葉に樽の口になる。普通は六葉という。 「南蛮渡来の鐘」は塔頭・春光院にある。南蛮寺にあった風鈴の一つという。/「さざれ石」は、塔頭・春光院の庭にある。/「日暮門」は、塔頭・蟠桃院にある。左甚五郎作という。/「開山足洗い石」は、塔頭・大龍院の後庭の小高い所に石二つがあり、開山が足を洗う姿が刻まれている。近代、1892年に立てられた。 ◆石橋 総門前に架かる石橋の銅製の擬宝珠に、江戸時代前期、1610年に対馬守・藤原国久が総門橋として造ったとの銘がある。 ◆映画 時代劇映画「丹下左膳 百万両の壺」(監督・山中貞雄、1935年、日活京都)の撮影が境内大庫裏付近で行われた。山中作品の現存する貴重な3作品の一つになる。 ◆アニメ ◈アニメーション『けいおん!(第1期)』『 けいおん!!(第2期)』(原作・かきふらい 、制作・京都アニメーション、第1期2009年4-6月、第2期2010年4月-9月、第1期全14話、第2期全27話)の舞台になった。2期4話「修学旅行!」で、花園会館に宿泊した設定になっている。妙心寺前交差点付近も登場する。 ◆宿坊・修行体験 坐禅会・大衆禅堂(妙心寺派教化センター)では、宿泊し、坐禅、提唱(講話)、作務(掃除)が体験できる。毎土曜日17:30-翌日曜日9:00、1・8・12月は休会。 宿坊「花園(はなぞの)会館」に宿泊できる。 妙心寺禅道会(毎月6-8日、6:00-7:30、大方丈、坐禅、提唱、講座、最終日に茶話会)。 ◆年間行事 修正会・祝聖・諸堂諷経・改旦上堂・仏殿般若(1月1日)、仏殿諷経・般若(1月2日)、仏殿諷経・般若満散(1月3日)、仏殿般若(1月16日)、方丈懺法(1月18日)、開山大師降誕会(2月7日)、涅槃会(2月15日)、彼岸会・祠堂斎(3月彼岸中日)、恒例法要・釈尊降誕会(花祭り)(4月8-12日)、巡塔諷経(4月14日)、入制上堂・楞厳会(りょうごんえ)(4月15日)、仏殿般若(5月16日)、方丈懺法(5月18日)、山門懺法(6月18日)、巡塔諷経(7月14日)、解制上堂・楞厳会満散・山門施餓鬼(7月15日)、経蔵虫払い(7月24日-25日)、祠堂斎(8月3日)、お精霊迎え(8月9日)、お精霊迎え(8月10日)、お精霊送り(法要、お焚き上げ)(8月16日)、青空市場(京野菜など)(8月9日・10日・16日)、夏期講座(8月下旬頃)、仏殿般若(9月16日)、方丈懺法(9月18日)、祠堂斎(9月彼岸中日)、達磨忌宿忌(10月4日)、達磨忌半斎(10月5日)、曝凉展(11月3日-4日)、法皇忌宿忌(11月10日)、法皇忌献粥・法皇忌献茶式・法皇忌半斎(11月11日)、成道会(12月8日)、開山忌宿忌(12月11日)、最も重要な法要の開山忌献粥・開山忌半斎(12月12日)、冬夜巡塔諷経(12月14日)、歳末般若(12月25日)、巡塔諷経(12月31日)。 坐禅会・大衆禅堂(妙心寺派教化センター)(毎日曜日17:30-翌日曜日9:00、休会あり、1・8・12月)。祝聖(毎月1日、15日)。 *南総門から北へ向かって案内しています。普段は非公開の建物があります。多くの塔頭は非公開です。建物内部、庭園などの写真撮影禁止の場所があります。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *「上皇」は皇位を退いた天皇の尊称。「法皇」は出家した上皇。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『妙心寺 650年の歩み』、『古寺巡礼 京都 31 妙心寺』、『旧版 古寺巡礼 京都 10 妙心寺』、『妙心寺史』、『妙心寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『日本の古寺大巡礼』、『京都古社寺辞典』、『近世に於ける妙心寺教団と大悲寺』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都府の歴史散歩 上』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『第47回京の冬の旅 非公開文化財特別公開ガイドブック』、『事典 日本の名僧』、『京都・美のこころ』、『よくわかる妙心寺 禅のこころ』、『京都の寺社505を歩く 下』、『秀吉の京をゆく』、『京都絵になる風景』、『京の怪談と七不思議』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、『週刊 日本庭園をゆく 16 京都洛西の名庭 2 妙心寺』、『週刊 仏教新発見 28 大徳寺妙心寺』、『週刊 古寺を巡る 23 妙心寺』、『週刊 日本の美をめぐる 室町5 38 狩野派の流れ 元信 永徳 探幽』、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「妙心寺」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「静岡県立博物館デジタルアーカイブ」、ウェブサイト「コトバンク」  |
|
 |
 |
|