|
|
|
| 海福院 〔妙心寺〕 (京都市右京区) Kaifuku-in Temple |
|
| 海福院 | 海福院 |
 |
 |
 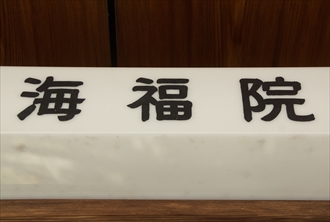      庫裏  方丈(本堂)   庭  庭、半月の手水鉢、円山応挙の作という。  庭  福島政則の墓、五輪塔 |
妙心寺境内、本坊の東北にある海福院(かいふく-いん)は、妙心寺塔頭の一つになる。 臨済宗妙心寺派。東海派。本尊は釈迦如来坐像を安置する。 ◆歴史年表 江戸時代、1616年、武将・福島正則が、夬室智文(かいしつ-ちもん)を開祖として建立した。院名は法華経普門品「福寿海無量」の一説に因むともいう。また、正則法号「海福院殿月翁正印大居士」によるともいう。 夬室と正則の子・福島忠勝は、豊臣秀吉に仕えていた父・正則が、関ヶ原の戦いで徳川方に属したことを家康に示すために、また、正則が秀頼とも親交あり、大坂夏の陣後の家康の報復を恐れ、その改心を示すために建立したともいう。以後、福島家の菩提寺になる。 年代不詳、2世・斯経慧梁(しぎょう えりょう、1722-1787)により公家・町尻家が帰依し、以後、香火(こうか)寺になる。 1811年、本堂が等持院に移されている。 ◆夬室 智文 江戸時代後期の臨済宗の僧・夬室 智文(かいしつ-ちもん、?-1787)。詳細不明。男性。妙心寺79世・一宙東黙(いっちゅう-とうもく)下八哲の一人という。妙心寺・海福院の開山になる。妙心寺135世。 ◆斯経 慧梁 江戸時代中期-後期の臨済宗の僧・斯経 慧梁(しぎょう-えりょう、1722-1787)。詳細不明。男性。姫路(兵庫県)の生まれ。寒巌壊灰の弟子、白隠慧鶴(はくいん-えかく)の法嗣。当院6代住持になる。町尻家の帰依を受けた。遠羅天(おらて)流茶道の始祖。『答客難』を撰した。65歳。 ◆福島 正則 室町時代後期-江戸時代前期の武将・福島 正則(ふくしま-まさのり、1561-1624)。男性。幼名は市松、通称は左衛門大夫、号は高斎、法号は海福寺月翁正印大居士。尾張(愛知県)の生まれ。父・福島市兵衛正信、母・豊臣秀吉の伯母・木下氏の長男。1578年、秀吉に仕える。初陣で播磨三木城を攻め、兜首(大将格)2つを討ち取る。1583年、秀吉と柴田勝家が戦った賤ヶ岳の戦では、一番槍・一番首で「賤ヶ岳の七本槍」筆頭になる。1585年、伊予今治に移り、島津征伐、小田原の役、朝鮮出兵にも従う。1595年、尾張清洲城に移る。1598年、秀吉没後、大大名になる。1600年、会津征討で徳川家康下、豊臣武将とともに従軍したが、石田三成の挙兵後は家康の味方になる。関ヶ原の戦で先鋒第一番手の戦功をあげる。家康は懐柔のため広島城に任じ、知行を倍増させ、安芸・備後の2国を与えた。1614年-1615年、大坂の陣では、家康に江戸屋敷に留めおかれた。1619年、居城・広島城の無断修築により幕府に咎められ、福島家は改易された。幕閣・本多正純の謀略だったとされている。出家する。その後、領地没収になり、越後・信州に転封になる。信州高井村に蟄居、病没した。64歳。 茶人としても知られた。家臣が火葬し、遺骨は妙心寺・海福院(右京区)、建仁寺・正伝永源院(東山区)に分葬したという。墓はそのほか各所にある。 ◆福島 忠勝 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名・福島 忠勝(ふくしま-ただかつ、1599-1620)。男性。幼名は市松、初名は正勝。尾張(愛知県)の生まれ。父・福島正則、母・照雲院(津田長義の娘)の次男。従兄弟の義兄・正之の没後、嫡男になる。1614年、大坂冬の陣で出陣した。1615年、夏の陣では道・堤の修復を行う。1619年、父が改易され、将軍秀忠の上洛に随行、その後、父と共に信濃高井野に移り家督を譲られた。22歳。 墓所は大乗寺(須坂市)、海福院(右京区)にもある。 ◆狩野 探幽 安土・桃山時代-江戸時代前期の画家・狩野 探幽(かのう-たんゆう、1602-1674)。男性。名は守信、別号は白蓮子。山城国(京都府)の生まれ。父・狩野孝信の長男。4歳で筆をとる。1617年、幕府御用絵師になる。1623年、弟・安信に宗家を譲る。1626年、二条城、1627年、大坂城の障壁画、1632年、徳川秀忠霊廟、1636年、名古屋城本丸障壁画などを手掛ける。1639年、法眼に叙される。1641年、大徳寺本坊方丈、1647年、江戸城障壁画を制作した。1650年、加賀支藩大聖寺藩主前田利治の江戸屋敷に俵屋宗雪と共に「金碧草花図」を描く。1662年、法印に叙される。1666年、後水尾法皇(第108代)寿像を描き「筆峯大居士」の印を贈られる。江戸で没した。江戸狩野派様式を創始した。73歳。 ◆白隠 慧鶴 江戸時代前期-中期の臨済宗の僧・白隠 慧鶴(はくいん-えかく、1685-1768)。男性。諡は神機独妙禅師、正宗国師。駿河国(静岡県)の生まれ。幼い頃より、地獄、極楽の説法に魅せられたという。1700年、15歳で駿河・松蔭寺の単嶺祖伝(たんれい-そでん)のもとで出家、慧鶴と名付けられた。沼津・大聖寺息道に師事した。1703年、清水・禅叢寺で修行する。雲棲袾宏(うんせい-しゅこう)の『禅関策進』により開眼、諸国を巡り美濃・瑞雲寺の馬翁、松山・正宗寺の逸伝、1708年、越後高田・英巌寺の性徹などに参じ、信州飯山の道鏡慧端(どうきょう-えたん、正受老人)の法嗣になる。1710年、京都の白幽子に内観法を学ぶ。ただ、白幽子と会ったことについては創作説もある。1716年/1717年、松蔭寺に還る。1718年、妙心寺第一座になり白隠と号した。この時、法兄・透鱗の法嗣とした。1763年/1758年、三島・龍澤寺を中興開山、1768年、松蔭寺に戻り当寺で亡くなる。84歳。 臨済宗十四派の中興の祖。漢詩文、法話、俚謡など多く著し、書画も遺した。墓は松蔭寺にある。弟子に東嶺円慈(とうれい-えんじ)など多い。 ◆秋里 籬島 江戸時代後期の読本作者・秋里 籬島(あきさと-りとう、?-1830頃)。男性。名は舜福、字は湘夕、通称は仁左衛門。京都の生まれ。1780年、『都名所図会』を出版する。以後、『大和名所図会』『東海道名所図会』などを出し、挿絵のある旅案内の先駆になる。『源平盛衰記図会』(1800)、俳書、辞書、作庭の書なども出版した。 ◆曾我 蕭白 江戸時代中期の絵師・曾我 蕭白(そが-しょうはく、1730-1781)。男性。姓は三浦、名は暉雄(てるお)、暉一、暉鷹、字は師龍、通称は左近二郎、別号は蛇足軒、鬼神斎、如鬼、虎道、鬼神斎、鸞山(らんざん)など多い。京都の生まれ。父・商家・吉右衛門、母・ヨツの次男。家は紺屋「丹波屋(丹後屋)」という。10代で両親、兄を亡くす。絵は高田敬輔、望月玉蟾に師事したともいう。雲谷等顔(うんこく-とうがん) に学ぶ。室町時代の画家・曾我蛇足に私淑し蛇足軒、10代蛇足を称した。曾我直庵にも学んだという。江戸時代中期の白隠の影響を受けたともいう。20代後半で画業で生計をたて、曾我蕭白を名乗る。1758年、伊勢旅行、1764年、再び伊勢に行く。伊勢・久居の米屋で奉公していたという。1767年、播州を旅する。播磨、1772年頃から京都に戻る。池大雅と親しくした。1775年、『平安人物志』載る。 山水、人物、花鳥、故事など奇怪な画風で評判を呼び、細密な描写、構図、鮮やかな彩色などで「異端」の画家と位置付けられた。骨法用筆による荒々しい筆法を用いた。興聖寺に、代表作「寒山拾得図」が残る。ほかに「群仙図屏風」など。奇行の逸話が残る。51/52歳。 墓は興聖寺(北区)にある。 ◆町尻 説久 江戸時代中期の公卿・町尻 説久(まちじり-ときひさ、1715-1783)。男性。初名は兼久、法名は如水。父・町尻兼量(かねかず)の次男。竹内式部について垂加神道、儒学を学ぶ。第116代・桃園天皇に仕え、1758年、正三位。尊王論者が幕府に処罰された宝暦事件に連座し、罰せられた。海福院の斯経慧梁(しぎょう-えりょう)に帰依し、1760年、出家した。69歳。 墓は妙心寺・海福院(右京区)に一族の墓とともにある。 ◆町尻家 公家の町尻家は藤原北家水無瀬流、羽林家(うりんけ、摂家、清華家、大臣家につぐ家格)になる。江戸時代初期、権中納言・水無瀬兼俊の次男・町尻具英(1623-1671)を始祖として創立された。3代・町尻兼重の娘・町尻量子は中御門天皇女御の母、豊岡家から養子に入った9代目当主・町尻量衡(1828-1907)は、後に子爵になった。妙心寺・海福院に一族の墓がある。 ◆本尊 本尊の観世音は、建仁寺末・永源寺より遷したという。 ◆建築 ◈ かつての「本堂」は、江戸時代後期、1811年に等持院(北区)に移築されている。欄間中央に豊臣家の桐紋が浮き彫りになっている。 ◈「庫裡」は、桂春院の西向かいにあった、安土・桃山時代、1598年に創建の塔頭・韶陽院の庫裏を現在地に移築し、増改築している。 方丈・書院として使われた。1間の広縁があり、近世前期の禅宗寺院の庫裏の特徴という。4部屋ある。8畳間の室中の奥に6畳の仏間がある。室中西の6畳間は「蘆雁の間」と呼ばれている。名は、障壁画に描かれた蘆と雁に由来する。かつては、茶堂だったとみられている。 かつては杮(こけら)葺、現在は本瓦葺になっている。虹梁大瓶束に湾曲した海老虹梁が見られる。切妻造。 ◆茶室 室中西の6畳間「蘆雁の間」の西の襖には、江戸時代の岸岱(がんたい、1782-1865)の絵(1852)が描かれている。襖の奥には「押入仕込茶室」が隠される。押し入れ内に点茶、水屋など一切が仕込まれている。これは、妙心寺では茶の湯を公けに嗜むことは慎まれたためという。 仕込み茶室の中心に面皮柱(めんかわばしら、柱の四隅に皮を削り残す)が立ち、南寄り(庭側)に間口1間の空間が作られている。左手手前にさらに面皮柱1本が建つ。格子窓が開き、障子が掛けられる。上方に上下二重の袋棚、その下に釣竹の一重の棚がしつらえてある。下の板敷に丸炉(36㎝)を切り、茶釜を据える。 北寄りには袋棚と、その下に板戸の引き戸があり、背面からの出し入れできる配膳棚になっている。 北の壁に掛けられた軸は、臨済宗中興の祖・白隠慧鶴(はくいん-えかく、1686-1768)愛用の茶釜・遠羅天釜(おらてがま)を描く。その前に、裏千家8代・一燈宗室(又玄斎、1719-1771)の位牌が祀られる。 「押入仕込茶室」は、草庵が作られる以前の点茶の形を残しているという。 ◆庭園 庭園は、江戸時代後期、秋里籬島(? -1830頃)の作庭といわれる。書院式露地、蹲踞の形式を残している。苔地に中木の植栽と石組、飛石、延段などがある。 本堂の前に据えられた半月の手水鉢は、江戸時代の絵師・円山応挙(1733-1795)の作という。 ◆文化財 ◈賤ヶ岳の戦いで一番槍として戦功をあげた福島正則の長槍(3m)は、本堂長押に掛けられている。 ◈曾我蕭白が描いたという江戸時代作、衣冠姿の紙本墨画「福島正則像」は、斯経慧梁(しきょう -えりょう)の賛があり、正則家臣・上月卜庵が描かせた嶺南崇六(れいなん -すうろく)賛の画を受けたという。また、嶺南崇六の賛を斯経慧梁が清書したともいう。 ◈「夬室禅師像」「斯経禅師像」。 ◈血痕が残る陣中杯は貝殻の杯で、戦に倒れた者の血を注ぎ供養のために飲んだという。福島正則の書状などのゆかりの遺品がある。 ◈狩野探幽(1602-1674)筆「唐人猿回し図」は、探幽が酒に酔って描いたという。 ◈円山応挙(1733-1795)筆「斯経慧梁肖像画」 ◆障壁画 ◈曾我蕭白筆の襖絵、探幽の養子・狩野益信(1625-1694)筆「山水図」。 ◈岸派の岸岱(1782-1865)筆襖絵など。 ◆猿回し図 江戸時代の狩野探幽(1602 - 1674)は、妙心寺法堂の「雲龍図」製作のために、海福院に滞在した。ある時、酒に酔い悪戯に、方丈の新調されたばかりの金箔唐紙の襖に、唐人猿回しの絵「猿曳」を描いたという。無断だったため、帰宅した院主に叱られた。筆力は確かであり、後に知られるようになった。(『都林泉名勝図会』巻4) その時の絵とされるものがいまも残されている。絵は、江戸時代、1616年の桐紋唐紙に描かれている。この桐紋の配置、図柄は桂離宮・古書院で使われている唐紙桐紋と同じとされ、古書院の建立年代が裏付けされた。 ◆墓 ◈福島正則の墓という五輪塔と、次男・福島忠勝の五輪塔が並んで立つ。忠勝孫・福島正勝(1664-1696)、福島家家臣などの墓石もある。 ◈福島家姻戚の公卿・町尻説久(霊知院殿、1715-1783)、説望(鏡海院殿、1738-1789)、量原(玉淵院殿、1741-1799)など町尻家の墓もある。 *普段は非公開大部分の建物、室内は撮影禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『妙心寺』、『妙心寺 六百五十年の歩み』、『京都・山城寺院神社大事典』、『事典 日本の名僧』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都大事典』、『京都戦国武将の寺をゆく』、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |
| |
|