|
|
|
| 退蔵院 〔妙心寺〕 (京都市右京区) Taizo-in Temple |
|
| 退蔵院 | 退蔵院 |
 |
 |
  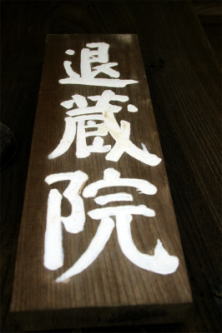      延段        庫裏 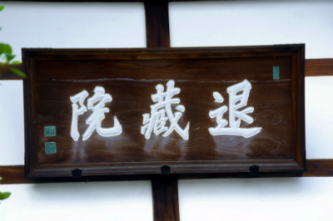    聖観世音菩薩  方丈の大玄関(重文)    南側にある大玄関  方丈   方丈  杉戸絵  「瓢鮎図」の一部、説明板より   杉戸絵  「元信の庭」、絵画的な手法が取り入れられているという。    「元信の庭」、手水鉢  水子地蔵尊    薬医門   薬医門   余香苑、枝垂桜  余香苑  余香苑、陽の庭、白川砂を用いている。  余香苑、陰の庭、  余香苑、陰の庭、黒色の安曇川の砂を用いている。       ミヤマキリシマ   ツツジ  蹲、水琴窟     余香苑    余香苑、東西に広がりのある石組、池泉の配置となっている。      フジ  大休庵  無余苑  大休庵、枝垂桜   大休庵  ミツバツツジ  中興の祖、亀年塔  開山・光澤塔 |
退蔵院(たいぞう-いん)は、妙心寺の塔頭の一つになる。山内塔頭で天授院に次いで古く、「屈指の古刹」といわれている。室町時代作庭の庭と、新たに作庭された現代の庭で知られている。 臨済宗妙心寺派。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 2つ星観光地(庭園も2つ星)」(改訂第4版)に選ばれている。余香苑は、アメリカ合衆国の日本庭園専門誌"Sukiya Living Magazine, The Journal of Japanese Gardening"の「しおさいプロジェクト」「日本庭園ランキング(数寄屋生活空間)」に、2017年に第17位に選ばれている。「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 室町時代、1395年、妙心寺3世・無因宗因(むいん-そういん)は、越前の豪族・波多野出雲守屋敷内(下京区、千本松原)に退蔵院を建立したという。(「寺院明細帳」) また、1404年、波多野出雲守重通が、無因を開山として、同家下屋敷に創建したともいう。(寺伝)。同年、妙心寺7世・日峰宗舜(にっぽう-そうしゅん)は、霊雲院の東に移転したともいう。(「退蔵院文書」) 1459年まで/長禄年間(1457-1460)/15世紀(1401-1500)前半、日峰宗舜が妙心寺塔頭・霊雲院の東に移した。「臥雲日件録」には「花園退蔵院」の名がある。後に、さらに妙心寺塔頭・東林院の東に移される。 応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失した。 永正年間(1504-1521)/1509年以降、中興の祖・妙心寺34世・亀年禅愉(きねん-ぜんゆ、照鑑祖鑑)により現在地に移されたという。 1509年、利貞尼の妙心寺拡張に伴い、現在地に移るともいう。境内は、現在の退蔵院境内南すべてを含むものだったという。(『妙心寺史』) 1522年頃、亀年禅愉が山内東林院の東に無明院を創建する。千本大宮より庵を移し退蔵院としたともいう。 その後、霊雲院が現在地に創建され、無明院が合併される。その所領も有する。利貞尼(1455?-1536/1537)により現在地が寄進された。退蔵院を移転し、その後、亀年禅愉によって中興された。この頃、「元信の庭」も作庭される。 近世初頭(安土・桃山時代)、檀越の豪商・比喜多宗味、その子で5世・千山玄松(せんざん-げんしょう)により整備される。玄松は大岩庵(だいがんあん)、艮庵(ごんあん)を併合する。以後、比喜多家の菩提寺になる。 1602年、現在の方丈が建立される。 近代、1931年、庭園「元信の庭」は、国の名勝・史跡に指定された。 現代、1966年、中根金作により庭園「余香苑」が作庭される。 2011年、「方丈襖絵プロジェクト」が始まる。 ◆無因 宗因 鎌倉時代後期-室町時代前期の僧・無因 宗因(むいん-そういん、1326-1401)。男性。興文圓慧。尾張(愛知県)の平氏、荒尾一族の生まれ。9歳で建仁寺塔頭・可翁宗然(かおう-そうねん)の室に入り、出家した。1361年、妙心寺2世・授翁宗粥(じゅおう-そうひつ)の室に入り、1371年、印可を受ける。1381年、妙心寺3世になる。1395年、千本松原の波多野出雲守屋敷内に退蔵院を建立した。大徳寺への誘いを断り、1396年、西宮・天海清寺を創建する。同寺・光澤庵に住し没した。75歳。 同寺と退蔵院(北区)の光沢塔にも分骨された。 ◆波多野重通 室町時代の武将・波多野重通(はたの-しげみち、?-?)。詳細不明。男性。道元の外護者である波多野義重の一族。退蔵院の外護者だった。 ◆日峰 宗舜 南北朝時代-室町時代前期の臨済宗の僧・日峰 宗舜(にっぽう-そうしゅん、1368-1448)。男性。俗姓は藤原、諡号は禅源大済禅師、霊鑵慈光、後に河嶋。山城(京都府)の生まれ。1376年、9歳で天竜寺・本源庵の岳雲周登の弟子になり、諱は昌昕(しようきん)と称した。1387年、伊勢・光讃寺で修行する。1388年、遠州・方広寺・無文元選(むもん-げんせん)、1391年、美濃・大円寺・南山勲(なんざんくん)、1398年、摂津(兵庫県)・海清寺・無因宗因(むいん-そういん)のもとで修行した。無因の歴住に同行し、1406年、無因より印可を得て宗舜に改める。1411年、美濃の無著庵、1412年、伊勢の金剛証寺、尾張・八葉蓮台寺で修行する。1415年、犬山・青竜山瑞泉寺を開き無因を勧請開山にした。1429年、妙心寺に住し、細川勝元の支援により応永の乱で没収後の寺産を復して再建した。1432年、妙心寺中興のために養源院を建てる。1447年、関山派として初めて大徳寺に入寺した。養源院で亡くなる。81歳。 妙心寺の中興開山になる。 ◆亀年 禅愉 室町時代後期の臨済宗の僧・亀年 禅愉(きねん-ぜんゆ、1486-1561/1562)。男性。俗姓は遠山。山城(京都府)の生まれ。1502年、16歳で龍安寺の特芳禅傑(とくほう-ぜんけつ)の下で出家した。建仁寺・月舟寿桂、雪嶺永瑾(せつれい-えいきん)に学ぶ。後、霊雲院・大休宗休(だいきゅう-そうきゅう)の室に入り、印証を密付された。1522年、妙心寺山内に無明院を創建する。妙心寺34世になり、住持10余年の間に、梵鐘「黄鐘調」を嵯峨浄金剛院より求める。第105代・後奈良天皇の帰依を受け、照天祖鑑国師の号をおくられた。著『法語集』。75/76歳。 ◆如拙 室町時代前期の画僧・如拙(じょせつ/にょせつ、?-?)。詳細不明。男性。大巧如拙(たいこう-じょせつ)。相国寺の僧とみられ、周文の師という。号の如拙は、絶海中津から与えられ「大巧(たいこう)は拙なるが如し」の意になる。応永年間(1394-1428)、足利将軍家の側近として活躍した。1414年-1425年、相国寺の開山・夢窓疎石の碑建立のため、石材を求めて四国に出向いた。1410年/1415年前後、4代将軍・足利義持の命で、座頭屏風として描いた代表作「瓢鮎図」(妙心寺・退蔵院蔵)がある。ほかに、「三教図」 (建仁寺・両足院) 、「王羲之書扇図」(京都国立博物館蔵)など少ない。 南宋院体画、梁楷の影響を受けた。初期水墨画の基本になり、周文、雪舟にも影響を与えた。 ◆狩野 元信 室町時代後期の画家・狩野 元信(かのう-もとのぶ、1476?-1559)。男性。幼名は四郎二郎、号は永仙、玉川、のちに古法眼。山城国(京都府)の生まれ。父・狩野派始祖・正信の長男/次男。孫に永徳。父の跡を受けて幕府の御用絵師になった。1513年、「鞍馬寺縁起」、同年、大徳寺・大仙院客殿障壁画を一門と相阿弥とともに制作した。1535年、内裏に水墨の屏風を納めた。1539年-1553年、石山本願寺(大坂本願寺)障壁画、1543年、妙心寺・霊雲院の旧方丈障壁画、内裏小御所、1546年、内裏記録所の障子絵を描く。将軍義政・義澄に仕えて大炊助、越前守、法眼に叙せられる。84歳。 代表作に清凉寺「清凉寺縁起絵巻」(1515?)、大徳寺・大仙院「四季花鳥図」(1513)、妙心寺・霊雲院「山水花鳥図」(1543)など。宋・元・明画、漢画、阿弥派、土佐家(土佐派)のやまと絵の技法も取り入れ、狩野派の基礎を築いた。一門による工房の分業による制作を確立する。障壁画、屏風、絵巻、絵馬なども手掛け、武家、宮廷、寺院、堺町衆まで支持された。「本朝三傑(ほかに土佐光信、雪舟)」の一人。 ◆千山 玄松 江戸時代前期の僧・千山 玄松(せんざん-げんしょう、?-?)。男性。京都の生まれ。父・豪商・大文字屋比喜田宗味居士(雪岩)の二男。霊雲派の亀年禅愉(きねん-ぜんゆ)の法孫になる。妙心寺178世、妙心寺・退蔵院5世になる。1656年、妙心寺・龍華院の勧請開祖になった。 ◆渡辺 了慶 安土・桃山時代-江戸時代前期の画家・渡辺 了慶(わたなべ-りょうけい、?-1645)。男性。氏は渡辺、のち狩野姓を許された。了桂、了敬、量慶。出羽国(山形・秋田県)の生まれ。藩に仕えた。その後、京都・狩野派の狩野光信の門人になり、高弟の一人とされる。1606年/1605年、光信、興以と高台寺の障壁画を制作した。1612年以後、西本願寺復興に際し、その中心になり対面所、白書院に障壁画を描いたという。元和・寛永年間(1615-1645)、狩野派の有力者だったという。晩年は、平戸松浦藩の御用絵師になったという。 主な作品は「源氏絵屏風」 (福田寺) 、「禅宗祖師図屏風」 (建仁寺・両足院) 、妙心寺・退蔵院、東福寺・普門院などでも障壁画を描いたとされる。 墓は江戸・種徳寺にある。 ◆中根 金作 近現代の作庭家・中根 金作(なかね-きんさく、1917-1995)。男性。静岡県の生まれ。静岡県立浜松工業学校、一時は企業に就職した。東京高等造園学校(現、東京農業大学造園科学科)卒業後、1943年、京都府園芸技師に任用された。文化財保護課課長補佐などを歴任した。後、裏千家学園茶道専門学校講師などを務める。1966年、中根庭園研究所設立した。大阪芸術大学学長、浪速短期大学学長などを歴任した。78歳。 足立美術館庭園、大仙公園日本庭園、城南宮楽水苑、退蔵院余香苑、ボストン美術館天心園など、国内外300近い庭園を作庭した。1982年、第7回日本公園緑地協会北村賞など受賞多数。「昭和の小堀遠州」といわれた。 ◆村林 由貴 現代の日本画家・村林 由貴(むらばやし-ゆき、1986-) 。女性。兵庫県の生まれ。京都造形芸術大学情報デザイン学科卒業後に、同大学大学院芸術研究科を修了した。2011年、妙心寺・退蔵院と同大が共同で進める「退蔵院方丈襖絵プロジェクト」の絵師に選出された。寺院での1年間の修行を行う。2012年より、退蔵院で生活し「現代のお抱え絵師」として、水墨画の襖絵64面の制作を始める。2013年、妙心寺・寿聖院の書院、本堂の襖絵を完成させた。2016年、一度筆を置き、2017年より再開した。 ◆退蔵 退蔵院の「退」とは、陰徳とされる。人知れない隠れた善行を「蔵」のように積重ねるの意味になる。 退蔵院とは、退蔵を目指した行の場としてある。 ◆木像 「開山像」は、江戸時代中期、1757年に新造立された。 ◆建築 近世、檀越の大文字屋比喜田宗味居士により大玄関、茶室、廊下などが寄進された。千山玄松の頃、桂昌院(盛岳院、その後廃寺)と退蔵院の間に大岩庵があり、霊雲院北隅に艮庵(ごんあん、種徳庵)、属院の鳳台院があった。 ◈現在の「方丈」(重文)は、安土・桃山時代-江戸時代の慶長年間(1596-1615)に建立されている。化粧裏板の釘書により、安土・桃山時代、1602年の建立ともいう。伝承として、室町時代後期、1569年、織田信長が足利義昭のために建立した将軍邸を移築したともいう。 西の鞘の間は、江戸時代中期に改造された。庭園鑑賞のためという。古式を残しており、正面室中央に桟唐戸を設けず、仏間背面には長5畳眠蔵がある。 やゝ小型の方丈形式本堂の代表例になる。六間取型方丈様式、桁行16.9m、梁行10.9m。室中は2間四方。一重、入母屋造、杮(こけら)葺。 ◈方丈の「大玄関」(重文)は、江戸時代初期の富豪・比喜多宗味居士より寄進された。唐破風造りの変容で珍しい様式になる。袴腰造と呼ばれている。破風の曲線が直線的で、袴の腰のように見えることから名付けられた。法要儀式、貴人々の出入り以外は使用されなかった。前後唐破風造。 ◈「薬医門」は、江戸時代中期に建立された。親柱2本、控え柱2本により、当時、高貴な薬医にしか与えられなかった御屋敷門の様式をとる。 ◆庭園 「元信(もとのぶ)の庭」と「余香苑(よごうえん)」の新旧二つの庭がある。 ◈庭園「元信の庭」(名勝・史跡)は、観賞式枯山水庭園であり、方丈西から南にかけてある。室町時代の絵師・狩野元信(1476-1559)の作庭とされている。元信が70歳近くで関わり遺作になった。 「生きた襖絵」として絵画的な手法が見られる。立体的な水墨山水画と枯山水式に、池庭を取り入れた表現になる。同期の中国的な大仙院庭園と並び、退蔵院は日本的趣向になっている。庭は、江戸時代、『都林泉名勝図会』(1799)にも、「画聖古法眼元信の作なり。他にこのたぐい少し」と紹介されている。 50坪(80坪とも)ほどの広さがあり、方丈の西、鞘の間、檀那の間から鑑賞した。石組と小石、白砂、小さく丸く刈り込まれたツツジなどの植栽、鶴島の羽石を利用したといわれる蹲踞などにより構成されている。 蓬莱神仙思想を表している。また、水が滝から大海に流れ込むまでの様子を白砂によって表現している。造庭当時は、双ヶ丘を借景にしたという。中央(北西)奥の滝組・蓬莱石、蓬莱連山を中心に、巨石により曲線を主流にした。低い「枯滝」が組まれ真黒石の平らな小石が敷かれている。これは、滝水の飛散を表し、室町時代-安土・桃山時代の移行期にみられる。正面奥に大きく山型の蓬莱石があり、左奥(南西)に石橋が架かる。枯流れは庭面の南西隅へ向かう。一段低い枯池の手前中央に「亀島(南に亀頭石、亀手石)」がある。亀島より枯池の右奥(北西)に、青石自然石の石橋が架かる。亀島右手(北)にも、石橋が架かる。左手手前(南東)に鶴石組の「鶴出島」がある。 背景には、ヤブ椿、松、槇、モッコク、カナメモチ、椎、樫、青木などの常緑樹が植えられている。 ◈「余香苑」は現代の造園家・作庭家・中根金作(1917-1995)の作庭による。現代、1961年の作で「昭和の名園」といわれる。800坪(2664.6㎡)の回遊式山水庭園は、東から西へ水の流れがある。庭面は長方形であり、大小の刈込と滝の石組、北に楓、東屋などの植栽が見られる。石は紀州石、小豆島石、但馬石もある。西付近は一番低く造られ、池泉があり、東側の空全体を借景として取り入れている。 ◈枯山水式の庭園、「陽の庭」と「陰の庭」は、薬医門の中門の北と南にある。対照的な独特の曲線を描く低い垣内の庭面に、砂紋とわずかな石、苔地だけで構成されている。それぞれ砂に白川砂(南、左手)と、黒色(北、右手)の安曇川の砂を用いており、白と黒が対比されている。両庭の中央に枝垂桜が植えられており、春には趣向を見せる。 ◈大休庵の「前庭」には、枝垂桜と楓が植栽されており、季節ごとの変化を愉しむことができる。 ◆茶室 非公開の茶室「囲いの席」がある。外からは見えないため「かくれ茶室」といわれている。 妙心寺では、かつて修行の妨げになるとして茶の道が禁じられていた。だが、第6世・千山玄松和尚は、密かに茶席を建て、茶の湯を嗜んだという。 ◆水琴窟 水琴窟がある。蹲踞の落ちる水滴を利用して、金属音のような微かな高い音がする。素焼きで、江戸時代中期より書院中庭にあったものを、現代、1975年頃に現在地に移した。 土中には、底に穴を開けた甕が逆さに埋めてあり、水滴が落ちる際にその音が甕内に反響する仕組みになっている。 ◆瓢鮎図 紙本墨画淡彩「瓢鮎図(ひょうねんず)」(国宝)(京都国立博物館寄託)は、室町時代前期、1410年/1415年前後の作とみられる。本格的な山水を取入れた日本最初期の水墨画になる。 水墨画の祖といわれた絵師・如拙(じょせつ、?-?)作という。絵は、室町幕府4代将軍・足利義持(1386-1428)(大相公)の命を受けて描かれた。南宋院体画の影響がある。111.5×75.8cm。 禅の悟りの契機を描いた禅機画、詩画軸になる。義持(義満とも)は、京都五山の禅僧31人に題詩を書かせた。上半分には、大岳周崇(たいがく-しゅうすう、全愚周崇)の「序」があり、玉畹梵芳(ぎょくえん-ぼんぽう)ら五山文学の禅僧による画賛がある。 瓢箪で鯰を押さえるという禅の公案(試験問題)を師家(しけ)が与えた。図の下半分に水の中を泳ぐ鯰と、それを瓢箪で捕らえようとする髭面の人物が描かれている。問いは「円くすべすべした瓢箪で、ぬるぬるした鮎をおさえるには如何」といものだった。 南宋宮廷画院画家の梁楷、馬遠などの技法に倣ったとみられている。これらは、院体画(いんたいが)と呼ばれ、余白を大きくとった辺角景(へんかくけい)構図法、減筆の手法などが用いられている。 かつて屏風として作られ、表に絵が裏に賛があった。その後、掛幅に改装され、上下につなぎ合わせて一面に表装されている。この「新様」について、当時輸入されていた梁楷、馬遠などの中国南宋院体画の様式に倣ったと見られている。 江戸時代初期の剣豪・宮本武蔵(1584-1645は、愚堂禅師を訪ねて参禅したという。武蔵は、この瓢鮎図を前に自問自答した。武蔵自作の刀の鍔にも、瓢鮎の意匠があったという。 なお、「瓢鮎図」の「鮎」は「あゆ」ではなく、「なまず」の意味になる。「鮎」「鯰」の漢字の混乱があり、「鮎」は、本来の漢字で「なまず」の意になるる。日本では「鮎」は訓読みで「あゆ」と読む。日本で作られた漢字・国字には、「鯰」があり「なまず」と読む。ちなみに漢字では「あゆ」を「香魚」と書く。 ◆障壁画 ◈方丈の檀那の間に「剡渓訪戴図(えんけいほうたいず)」がある。安土・桃山時代後期の狩野光信の高弟・狩野(渡辺)了慶の筆による。「世説新語」の故事に因んでいる。 雪の夜、王子猷(おうしゆう、王徽之)が、曹娥江上流の剡渓に戴逵(たいき)を訪ねる。だが、門前で引き返してしまう。人にその理由を尋ねられると、興が尽きたので引き返したと答えたという。「楼閣山水図」も飾られ、狩野(渡辺)了慶の筆による。 ◈方丈室中に狩野(渡辺)了慶筆「西湖図」12面、礼の間に「真山水図」8面がある。 ◈現代、2011年より、「方丈襖絵プロジェクト」が始まる。現代の絵師・村林由貴が方丈の襖絵を描いている。 ◆文化財 周徳筆「竹雀図」、室町時代、1398年の無因自賛像「無因禅師画像」、「亀年禅師像」、亀年禅師筆「偈頌」、愚堂東寔(ぐどう-とうしょく)筆「法話」、龍華道忠が庭園をうたった無著道忠(むじゃく-どうちゅう)筆「題退蔵院假山水偈」。 「花園天皇宸翰消息」(重文)、「後奈良天皇宸翰徽号」(重文)。 ◆花暦 季節の花木60種が咲き誇る花の寺でもある。春の枝垂れ桜(4月)に始まり、皐月(5月)、蓮(6月-8月)、秋には楓(200本)が庭を彩る。 ◆精進料理 精進料理が供される。 *方丈内から庭園を鑑賞することはできません。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『妙心寺』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、『京都・山城寺院神社大事典』、『妙心寺 650年の歩み』、『古寺巡礼 京都 31 妙心寺』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都大事典』、『禅僧とめぐる京都の名庭』、『京都で日本美術をみる』、『京都 古都の庭をめぐる』 、『週刊 日本庭園をゆく 16 京都洛西の名庭 2 妙心寺』、『週刊 日本の美をめぐる 34 竜安寺石庭と禅の文化』、「こころのおみやげ」 、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |