|
|
|
| * | |
| 鴨川河畔を歩いてみましょう 四条大橋から御薗橋まで Kamogawa River Walking 鴨川散策・散歩 ウォーキング |
|
| 鴨川河畔を歩いてみましょう | 鴨川河畔を歩いてみましょう |
 |
 |
 賀茂大橋下流右岸  北大路橋上流右岸、桜並木は対岸の「半木の道」  上賀茂橋上流左岸 |
鴨川散策・散歩を楽しみませんか。ウォーキング、フットパスとしても最適なコースです。 鴨川は四季折々の美しさに満ち、それぞれの魅力があります。鴨川の流れをさかのぼって、鴨川の清流、東山の景観、木々の緑、草花、水鳥などの生き物と触れ合ってみませんか。歩くにつれて、季節の変化で移り変わる景色を眺めながら、木陰のベンチで一休みすることもできます。ランチを楽しむこともできます。飛び石のあるところでは、川遊びもできるでしょう。鴨川の河川敷の大半は土の道で、足に優しいのです。車の騒音や信号機に煩わされることもなく、排気ガスのストレスもほとんど感じません。 コースとしては、たとえば四条大橋→賀茂大橋(下鴨神社周辺)は、直線距離で約2.9km、所要時間は約50分。四条大橋→北大路橋(府立植物園周辺)は、約4.6km、77分。四条大橋→御薗橋(上賀茂神社方周辺)までは約6.8km、113分となります。 また、三条大橋→賀茂大橋、賀茂大橋→北大路橋、北大路橋→御薗橋などの短いコースを、自由に組み合わせることもできます。鴨川を往復し、帰りは対岸を歩いてみるのもいいでしょう。散策の間に、周辺の社寺観光を挟んでみてはいかがですか。川沿いには、川面を眺めながら食事がとれる素敵なレストランやカフェなども増えてきました。こうしたところで、気が向けば一息入れることもできます。 コースはすべて市街地の、よく手入れされた鴨川公園内です。ほぼ直線のコースのため、道に迷う心配もほとんどなく、だれでも安心して散策できます。歩くのに少し疲れたら、途中や帰りは公共交通機関を利用するなど、無理のない散策も考えられます。鴨川の西を平行して南北に走る加茂街道には、市バスなどが通っており、途中で挫折してもこれらをいつでも利用できます。また、自転車・レンタサイクルを利用する方法もあるでしょう。 時間は、60m/sを一応の目安としました。歩く早さには個人差があります。また、当然のことですが、鴨川を上流へさかのぼる道は、緩やかな上り坂が続きます。個々人の体力、休憩なども考えると、時間はゆとりを持って計画しましょう。 |
| 一例として、四条大橋から、鴨川公園(葵公園)、下鴨神社、河合神社、府立植物園(半木神社)を経て、上賀茂神社へ向かいます。全行程8.9㎞、高低差49m、時間は寄り分、個人差もありますが徒歩で2時間程度としておきます。 | |
 |
|
| |
最寄りの駅 |
 七条大橋  スタート地点のスロープ  遊歩道、この付近は少し狭くなっている。  川端通にある句碑  春には東岸の石垣の上の花の回廊が、見事な桜並木となる。 |
では、七条大橋から鴨川の散策に出かけましょう。鴨川の流れを遡って北へ向かいます。七条大橋の上からは、鴨川の東北に比叡山、東に東山などの山々を見ることができます。 鴨川東岸にタイル張りの遊歩道があります。河川敷に降りるには、橋の東詰南に石段があります。また、川端通を少し南へ下がったところに、スロープが設けられています。このスロープの降り口、七条大橋の東南は公園が設けられています。公園には、クスノキ、桜のヘイアンシダレ、橋のたもとにシダレヤナギの大木、そのほか、ヒイラギ、ジンチョウゲ、サザンカ、ヒラドツツジなどが植えられています。 では、遊歩道から出発しましょう。この付近の道は少し狭いので、ほかの歩行者や、自転車、ランナーなどの通行の際にはご注意ください。 石橋の美しい形をご覧ください。橋は、鴨川に架けられている橋の中で最も古い建造です。 橋の東には、三十三間堂などがあります。橋の西詰南に隣接して、小社、松明殿稲荷神社があります。 この付近では、鴨川の流れを間近に感じることができます。川幅も広く、川の中には、水草が揺れています。魚や、野鳥、冬には、ユリカモメなども見ることができます。 右手の石垣の上の川端通には、遊歩道と鴨川の間に、「花の回廊」が設けられています。四季折々の草木が植えられ、楽しむことができます。シダレザクラの並木が続いており、春には見事な花を咲かせます。また、シダレヤナギ、イロハモミジ、サルスベリ、ケヤキ、エノキ、そのほかアベリア、レンギョウ、ヤマブキ、ジンチョウゲなども植えられています。 七条大橋と正面橋の中間あたり、川端通の植込みの間に、鴨川を題材にした句碑が置かれています。「凛とした白さぎの様 京の川 八木紗和子」、川端通には、このほかにもいくつもの句碑が設けられていますので、それらもご案内していきましょう。 鴨川の対岸には、家並が見えています。やがて、正面橋が見えてきました。 |
| |
|
 正面橋   橋の東詰から少し上がった川端通の西にある「元和キリシタン殉教地」  川端通にある句碑 |
正面橋に通じている正面通は、平安京の七条坊門小路の位置に当たります。豊臣秀吉による方広寺大仏殿造営に伴い、大仏殿の正面に当たることから、正面通と呼ばれるようになりました。橋の東には、方広寺、豊国神社などがあります。西には、渉成園があります。橋の上からは、東に、比叡山、東山の連なる山容を見ることができます。 橋の東詰、川端通を少し北へ上がったところに、「元和キリシタン殉教地」という石碑が立てられています。 遊歩道に沿って、鴨川のゆるやかな流れが続いています。鴨川の流れが間近に見られます。野鳥や魚の姿も見ることができます。 右手には石垣が続いています。石垣の上には、シダレザクラ、シダレヤナギ、イロハモミジなどの並木が続いています。 鴨川の遊歩道は、中ほどより少し広くなりました。 五条大橋と正面橋の中間あたり、川端通の植込みに句碑が立てられています。石段から北へ少し上がったところです。「ひとひらの 花をみながら たたずめば 賀茂の河原に みやこどり舞ふ 村上静代」 対岸には、町家の家並が続いています。 |
| |
|
 五条大橋   五条大橋西詰北の「牛若ひろば」にある弁慶と牛若丸の石像。  五条大橋の石の橋脚、五条大橋西詰北  大田垣蓮月の句碑、五条大橋西詰北  五条大橋近く川端通の西にある、「友愛」の碑  川端通、五条大橋近くにある、石の橋脚、おそらく五条大橋に使われていた石材だろう。  川端通、五条大橋と松原橋の間にあるもうひとつの石の橋脚  句碑、川端通、五条大橋と松原橋の中央付近  桜の頃  秋の紅葉の頃  広場には石の椅子が置かれ、市民がくつろいでる。  五条大橋西詰北、みそそぎ川の終点、右の鴨川に注いでいる。  料理旅館「鶴清」 |
現在、国道一号線が通っている五条大橋は、すでに平安時代に架けられていたといいます。豊臣秀吉の方広寺大仏殿を造営にともない架け替えられ、五条大橋と名を変えました。それまでの五条大橋は、現在の松原橋の位置に架けられていました。 五条大橋の上から北を見ると、北山、比叡山、東山の雄大な山並みを望むことができます。川の西岸を鴨川に並行して流れている川が、みそそぎ川です。川は、橋の少し上流で鴨川に合流しています。 五条大橋西詰北にある「牛若ひろば」には、牛若丸と弁慶の決闘をあらわした石像があります。また、かつて石橋に使われていた石の橋脚が置かれています。大田垣蓮月の句碑「あすも来て見んと 思へば 家づとに 手折るもをしき 山さくら花」も立てられています。 遊歩道に戻りましょう。右手には、花街の宮川町があります。 遊歩道に沿って、さまざまな樹木が植えられています。シダレザクラ、サトザクラ、イロハモミジ、シダレヤナギ、キョウチクトウなどの大木があります。そのほか、ハギ、ヤマブキ、コクチナシ、テイカカズラ、レンギョウ、サンゴジユなどが植えられています。この付近では、春の桜、夏の新緑、秋の紅葉を楽しむことができます。遊歩道の中ほどには、公園が設けられ、石のベンチなども置かれています。川のせせらぎを聞きながら、小休止しましょう。 五条大橋と松原橋の中間あたり、川端通の植込みの中に、句碑が立てられています。「鴨川に 立ちて比叡の 峰あかり 蛯名正人」。 |
| |
|
 松原橋   鴨川の西側を流れているみそそぎ川  町家の景観  秋、石垣の上にシダレザクラの紅葉が見られる。  句碑、川端通 |
かつては五条大橋と呼ばれていた松原橋です。橋の上からは北に、北山、比叡山、大文字山、東山などの山並みを見ることができます。また、鴨川の西には、みそそぎ川が流れています。 この付近には、シダレザクラ、イロハモミジの大木、シダレヤナギ、川端通にはイチョウの並木が続いています。そのほか、ユキヤナギ、テイカカズラ、ヤマブキ、ハギ、セイヨウイワナンテンアキシラリスなどが植えら、春には見事な花の共演となります。秋には、紅葉を楽しむことができます。 松原橋と団栗橋の間、松原橋よりの川端通の植込みの中に、句碑が立てられています。「身障の 妻の手をとりて 川小径 ゆりかもめ舞う 空と川面に 岩城清一」 鴨川の対岸には、ビル群に囲まれるようにして、まだ町家の美しい家並が残されています。 |
| |
|
 団栗橋  団栗橋の南  団栗橋の北  句碑、川端通  釣り人 |
団栗(どんぐり)橋は、京都の歴史上最大の大火といわれる「天明の大火」と関わりがあり、鴨川の東岸の民家より火の手が上がり、大きな被害をもたらしました。橋の東には建仁寺があります。 付近では、普段でも、魚釣り、投網する人の姿を目にすることができます。 遊歩道に沿って、シダレザクラ、イロハモミジ、サルスベリなどが植えられています。 団栗橋東詰北に句碑が立てられています。「鴨川の 水べり刻む 青春譜 森永浩樹」。 四条大橋が見えてきました。このまま、東岸を北上し、散策し続けることができます。今回は、橋の手前にある階段を上って、一度、四条大橋を渡り、橋の西詰北の階段から、鴨川西岸の遊歩道を北上することにしましょう。 |
| |
|
    四条大橋東詰北にある「鴨川」の碑  出雲御国像、四条大橋東詰北  四条大橋からの眺め、三条大橋と北山  「花の回廊」碑、四条大橋東詰南  句碑、四条大橋東詰南  句碑、四条大橋東詰南  四条大橋から見える鴨川越しの南座  みそそぎ川の納涼床  納涼床  対岸の白川の流入口です。時間にゆとりがあれば、ぜひ寄り道を。  橋に立つ僧侶  対岸の南座  みそそぎ川、サクラの頃  対岸のサクラ並木  花の回廊   先斗町歌舞練場 |
それでは、四条大橋から鴨川の散策に出発しましょう。これから、鴨川上流へ向けて北上し続けることになります。 まずは、四条大橋の上から鴨川上流の北山を望みましょう。天気がよければ、北山の峰がはっきりと見えるはずです。今日はどうでしょうか。 また、橋に立つ修行僧は見つかりましたか。三条大橋にも立たれていることがあります。 歴史に興味のある方は、橋の周辺にも出雲の阿国などの史蹟がいろいろと残されています。ゆっくりと散策されてみてはいかがでしょうか。詳しくは下のリンクへ。 さて、橋の西詰北側に、鴨川へ降りる階段があります。少し急な勾配なので気をつけて、鴨川河川敷西岸に降りてみましょう。 左に小さな水路が流れています。鴨川の分流である「みそそぎ川」といいます。夏には、この川の上に先斗町のお店によって納涼床が造られます。これからずっと、「みそそぎ川」が上流へと導いてくれるでしょう。 それでは、鴨川上流に向けて歩き始めましょう。足元が石畳で少し歩きにくくなっています。気をつけてください。 右手後ろには、歌舞伎発祥の舞台となった南座を見ることができます。鴨川越しに正面で見る場合には、一度四条大橋の橋脚下を南へ抜けて、ゆっくりとご覧ください。 このあたりは、カップルが等間隔で座ることで知られています。その研究書『心理学研究法入門』(伊藤正人)という本も出ています。 さて、右手対岸に川が注いでいるのが見えましたか。あれが、白川の注ぎ口です。時間があれば、サクラの頃、白川沿いに祇園白川の散策もお薦めします。 対岸を走っている道路は、川端通です。かつては、河岸を京阪電車が通っていました。今は、地下化されました。春の頃には、「花の回廊」のシダレザクラ並木が満開になります。また、サクラ、ムク、イロハモミジなどの巨木があり、紅葉の頃も楽しむことが出来ます。 冬場、この付近で水鳥に出遭うことができます。「冬の使者」といわれ、カムチャッカから3000kmの旅をしてくるユリカモメ(都鳥)、鴨川お馴染みのいろいろなカモ類などは見つかりましたか。 やがて、左に大きな建物、歌舞練場が見えてきました。不思議なことに、いまや鴨川の風景に溶け込み、あまり違和感を感じません。「鴨川をどり」の会場として使われ、普段は芸妓・舞妓さんの踊りなどの練習場となっています。 |
| |
|
 三条大橋  三条大橋西岸、橋の手前にある眉毛のある地蔵  三条大橋から北の眺め、御池大橋と北山   川端通、三条大橋近くにある石の橋脚 |
純和風の三条大橋は、鴨川とよく馴染み、絵になります。橋脚は石柱、欄干などは木製となっています。豊臣秀吉が造らせたこの橋は、擬宝珠欄干の刀疵などさまざまな歴史の刻まれた橋です。橋の周辺にもいろいろな史蹟もありますので、歴史に興味のある方はゆっくりとどうぞ。詳しくは下のリンクへ。 今日は橋の中ほどに、お坊さんが立っているのが見えたでしょうか。 左手、橋のたもとに、眉毛の書かれた愛嬌のある地蔵があります。見つかりましたか。 このあたりで見ると、鴨川の水量もかなりあるように感じます。 対岸には、サクラ、クス、エノキ、トウカエデも植えられています。 三条京阪の駅が見えてきました。 左には、「みそそぎ川」が続いています。 右には、ビルの合間に東山の山影が見え始めます。これからしだいに、東山三十六峰の景観が目に入ってきます。鴨川をさかのぼるにつれ、変化していく川の流れと稜線の景色をお楽しみください。新緑の頃、夏の深い緑、秋の紅葉、冬の雪景色と四季折々の変化も楽しめます。 |
| |
|
 御池大橋      鴨東運河の鴨川への流入口、山は大文字山  みそそぎ川  みそそぎ川から高瀬川(左)の分岐点  高瀬川への分流点  大文字山  みそそぎ川と納涼床  雪化粧した比叡山 |
文学に興味のある方は、できれば御池大橋西詰南に上がってみましょう。作家・夏目漱石の歌碑が見つかります。漱石の京都を舞台とした作品もいくつかあります。碑の歌は、祇園白川のお茶屋の名物女将に宛てたものです。詳しくは下のリンクへ。 さて、鴨川へ戻りましょう。右に、琵琶湖疏水から流れる鴨東運河の鴨川への流入口があります。普段は水が鴨川に注いでいません。大雨のときになどは、水が溢れていることもあります。このあたりは、サーフボードの"メッカ"となっています。 対岸には、サクラ、イロハモミジなどの並木が続いています。 右に、大文字山、それに比叡山も見え出します。山容がずいぶん、大きく見えるようになってきました。 左には、まだ「みそそぎ川」が続いています。 左に、高瀬川の説明版がありました。ここから、「みそそぎ川」は高瀬川へも分流し注いでいます。「みそそぎ川」も高瀬川も、鴨川の分流になります。高瀬川は、江戸時代に角倉父子が造った運河で、高瀬船という専用の船が行き来しました。これにより、二条、伏見、大阪間が結ばれ、近代まで300年も利用されました。 ここで、高瀬川周辺に寄り道もできます。幕末の史蹟もたくさん残されています。歴史に興味がなくても、美しい高瀬川のせせらぎと景観、サクラ並木なども楽しめますので、お急ぎでない方はぜひどうぞ。詳しくは下のリンクへ。 |
| |
|
 二条大橋  みそそぎ川、サクラの頃  ザ・リッツ・カールトン京都  左はみそそぎ川、右は鴨川、この付近は見晴らしがいいところです。四季折々に、川沿いにはいろいろな花が咲き乱れています。  飛び石、船とチドリ、川遊びができます。周辺の景色も楽しんでください。  みそそぎ川に架かる木の小橋への階段  木の小橋からの眺め、みそそぎ川と右は鴨川  琵琶湖疏水の流入口  鴨川へ降りる親水のための階段  センダン 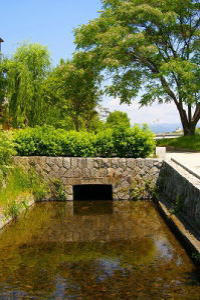 みそそぎ川地表への出口部分、みそそぎ川にはホタルが生息しています。  比叡山と大文字山   比叡山  丸太町橋近くには、ポプラの巨木、ヤナギなどの大木。  洋館、旧京都中央電話局上分局、レトロな建物。  紅葉の頃 |
左にはザ・リッツ・カールトン京都が見えます。 左に、木の小橋があります。上ってみましょう。この橋からは、「みそそぎ川」の流れを見わたすことができます。右には鴨川も見えます。このように、鴨川と「みそそぎ川」は平行して北から南へ流れています。みそそぎ川の西岸にはサクラ並木があります。川沿いの並木、鴨川、東山の山並みも見渡すことができます。 再び鴨川の河川敷へ戻りましょう。ヤマブキの長い生垣に沿って進みます。道は土に変わりました。土の感触が足に心地よく感じます。コンクリートブロックより歩きやすくなりました。春の頃、この辺りには紐が川面に張られています。これは、放流されたアユの稚魚をカワウから守るためのものです。 右に東山がよく見えてきました。対岸には、サクラ(ソメイヨシノ、ヤマザクラ)、ケヤキ、シダレヤナギの並木が続いています。 飛び石があります。ここでは、千鳥と船(高瀬舟)の形をした石があります。もともとは川床の安定のための石です。少し遊んでみましょうか。石の間の間隔が少し離れているのでご注意ください。川の中からの、北山の景色が楽しめます。今から目指す、糺の森(ただすのもり)は見えましたか。 再び、出発しましょう。右に琵琶湖疏水の流入口があります。今日は、鴨川に水が合流しているでしょうか。その奥には、大文字山が見えます。でも、まだこの辺りでは、少し斜めの「大」の字です。 「みそそぎ川」は、ここで地中に潜り、見えなくなります。鴨川に降りられる階段があります。急がなければ、気をつけて鴨川の川床へ近づいてみましょうか。堰の造りがよくわかります。川音と低い視点での景色も楽しめます。 センダンの大木があります。この木には、冬場に、木の実を求めてヒヨドリなどの野鳥が集まってきます。また、この付近には、トンビもゆっくりと空を旋回しています。今日はどうでしょうか。なお、野鳥への餌やりはお薦めしません。また、トンビは、その鋭い爪で怪我した人がいますので、食べ物を持った人などはご注意ください。 対岸には、サクラの並木が続いています。 東山の山並みと、大文字山がよく見えるようになりました。 左には、ヤナギの大木があります。かつては、鴨川沿いに多くのヤナギが植えられていました。これは堤防の強化をするという防災の意味もあったようです。また、平安京の朱雀大路には道の両側にヤナギが植えられていたそうです。 左に見える大きな洋館は、かつて旧京都中央電話局上分局でした。一番高い屋根の部分は、受話器の形をしています。この近代建物も、鴨川の風景と違和感がありません。先を急がなければ、対岸からの建物の景色をお楽しみください。夜、建物に明かりの灯った光景も、鴨川に光が映ってなかなかすばらしいものがあります。 |
| |
|
 丸太町橋  丸太町橋から北の眺め  橋の西詰北にある丸太町橋の説明版  山紫水明処、予約がないと見学できません。   左の比叡山と大文字山  対岸のサクラ並木  木の陰に比叡山がかすかに見えます。  荒神橋近くの車石の跡  荒神橋近く西岸にある二体の地蔵  荒神橋近く、川中に残るかつての橋脚?  冠雪した比叡山 |
丸太町橋の中ほどにある少し出っ張っているバルコニーからは、北山が見晴らせます。ちょっと行ってみましょうか。 ここで、丸太町橋から西へ行けば、広大な自然公園でもある京都御所に寄り道もできます。詳しくは下のリンクへ。 鴨川に戻りましょう。左に、茅葺の小さな建物が見えましたか。これが有名な、幕末の頃の学者・頼山陽の山紫水明処です。最近になって屋根などが修復されました。鴨川と東山の景色をとても愛した人でした。この庵から「山紫水明」の言葉が普及したといわれています。なお、予約がないと見られませんので、今日は外観を見るだけにしておきましょう。 広い公園があります。鴨川公園です。なお、鴨川全体が公園となっており、あちこちに鴨川公園があることになります。ベンチもありますので、一休みしていきましょうか。 ふたたび、歩き始めましょう。左には、ところどころにまだ低い町家が残っています。昔は、もっと東山などが見張らせたはずです。京都市では景観条例(2007)などで、鴨川からの五山送り火などを見渡せるよう、景観保護を進めるようになりました。 この付近は、建物の高さが比較的抑えられており、比叡山、東山、大文字山もよく見えます。 右に、京都大学などの建物群が見えてきました。なんとか、景観と調和するように工夫されているのがわかります。建物や樹木の間に、霊峰・比叡山も見え隠れしています。対岸にはサクラ(ソメイヨシノ、ヤマザクラ)とシダレヤナギ、ケヤキ、クスノキなどの並木が続いています。 荒神橋が近づいてきました。左手足元に注意してみましょう。かつて荒神橋にあった車石の跡が再現されています。わかりましたか。石に刻まレールのようなものです。このレールの上を荷を積んだ牛車が行き来しました。荷車は橋を痛めるので渡れず、鴨川の河原に入っていました。 |
| |
|
 荒神橋  この付近には緑も多く、東山などの見晴らしもききます。  飛び石、亀形  鴨川公園、比叡山  付近にはセンダン、5月頃白い花をつけるハリセンジュなどの大木の森があります。  緑も多く、比叡山などの見晴らしもよいところです。  みそそぎ川の取り入れ口へ降りる階段  みそそぎ川の鴨川からの取り入れ口  様々な形のベンチが置かれています。  |
大文字山がよく見えます。大文字の五山送り火の正面については、御所、この荒神橋辺りともいわれています。確かに、形のいい「大」の字となってきました。 ここにも広い鴨川公園が広がっています。大木もあります。ベンチもあります。また、一休みしていきますか。 荒神橋から西へ行けば、ここからも京都御所へ寄り道することができます。 ふたたび飛び石が見えてきました。ここでは亀の形をしています。飛び石から北山を眺めてみましょうか。広大な別の鴨川の姿が見えてきます。鴨川と高野川の合流した賀茂大橋以南のこの付近が、鴨川の川幅が一番広くなっています。 このまま鴨川を渡って、東岸を歩いてみるのもいいでしょう。サクラ、ヤナギの並木があります。今回は、このまま西岸を歩きましょうか。 この付近は、見晴らしがきいて気持ちよく散策できます。また、ケヤキ、センダン、エノキ、ハリセンジュなどの大木が植えられており、緑も多いので森林浴も楽しめます。近くに自動道もありませんので、空気もきれいです。 左には巨大な府立医大、付属病院などの建物群があります。センダンなどの大木が生えており、河川敷も広いので開放感があります。対岸は京都大学などの建物が続きます。東山はあまり見えません。建物の間に、ときどき、比叡山が見え隠れしています。 しばらく行くと、ふたたび比叡山、大文字山が仲良く見えるようになりました。 エノキの巨木もあります。対岸にはサクラ(ソメイヨシノ、ヤマザクラ)とシダレヤナギ、ケヤキ、クスノキなどの並木がまだ続いています。 鴨川へ降りる階段があります。これが鴨川からの「みそそぎ川」への取り入れ口となっています。少し危ないので、自信のない方はここまでにしておきましょう。 |
| |
|
 賀茂大橋と比叡山  賀茂大橋と比叡山、サクラ   賀茂大橋からの北の眺め、三角州、糺の森、左が賀茂川(鴨川)、右が高野川。ぜひとも橋の上に立って、360度の景色をお楽しみください。   飛び石、亀とチドリ、こどもたちがよく水遊びをしています。  比叡山、鴨川公園  三角州にある葵公園(鴨川公園)、糺の森、週末にはコンサートなどのさまざな催しが行われています。  鴨川公園内の泉、小さな子どもの水遊びの場。  ポンプ式の井戸。水が出ます。  雪の朝の白い大文字  大文字山と光虹 |
右前方に、比叡山、右に大文字山が見えます。 ぜひ、賀茂大橋の上に立ちましょう。左から鴨川、右から高野川がこの地点で合流しています。この橋から上流を「賀茂川」、下流を「鴨川」と使い分ける人もいます。ただ、「加茂川」もあります。歴史的に見ても名称が逆転していた時期もあり、それほど厳密なものではありません。なお現在、公的にはすべての川を「鴨川」として統一しています。このページでは、鴨川をなるべく使うことにします。興味のある方は、下記リンクの「鴨川の基礎知識」へどうぞ。 三角州には鴨川公園(葵公園)があります。三角州は、その形から「剣先」とも呼ばれています。確かに、鋭く尖っているのがわかります。三角州の奥に広がる深い森は、糺(ただす)の森と呼ばれています。ここに下鴨神社があります。 左手の鴨川(賀茂川)の方に目をやると、北山の山並みが見わたせます。右のほうに目を移すと、高野川の方角に、五山送り火の大黒天山(東山)の「法」の字は見えたでしょうか。「妙」のある松ヶ崎の万灯龍山(西山)はこの西(左)にありますが、残念ながらここからは見えません。 その右の、ひときわ高い山が霊峰・比叡山です。さらに、東山の峰、右の方、橋の右手正面には大文字山が望めます。横断歩道から橋の南側へ渡ると、いままで歩いてきた鴨川下流の景色が見晴らせます。この360度の眺望を、ゆっくりとお楽しみください。 ここでは、一帯の松林になっている鴨川公園(葵公園)でぜひ休憩しましょう。千鳥の飛び石で、中州、高野川へも渡ってみましょうか。鴨川より川幅は狭いのですが、高野川を散策するのもいいでしょう。こちらの河岸にもサクラ(ソメイヨシノ)、シダレヤナギなどの並木が続いています。春には、見事なサクラの帯が続きます。また、河川敷には菜の花も咲き乱れ、桜色と黄色の二つの花色を楽しむことができます。 飛び石から見る、賀茂大橋もなかなか趣があります。橋の欄干には、夕方になると淡い光が灯され、これもなかなかの風情があります。 この後、鴨川とゆかりの深い下鴨神社、河合神社へ参拝してみてはいかがでしょうか。糺の森を散策し、森の巨木、野鳥たち、森を流れるいくつかの川など、都市に残された貴重な山城原生の自然をゆっくりとお楽しみください。また、ここからも御所へも寄り道できます。詳しくは下のリンクへ。 なお、出町橋の西詰北に、公衆トイレがあります。 さらに健脚の方は上流を目指しましょうか。次へどうぞ。 |
| |
|
 出町橋、葵祭の祭列が通る。   出町橋と大文字山  糺の森、森の中に下鴨神社、河合神社があります。寄り道をぜひ。  サクラの花咲く頃  紅葉の頃 |
いよいよ、ここから鴨川から賀茂川への旅が始まります。鴨川の上流部となります。 右後方に、大文字山がよく見えます。ここで見ると「大」の字が形よく見えます。 右に松林の糺の森が見えます。森の中に河合神社、下鴨神社があります。「糺す」ということで、偶然か故意か、簡易裁判所の建物もあります。 わかりにくいかもしれませんが、右に、泉川の鴨川への小さな注ぎ口があります。糺の森を流れている川の一つです。 左には、サクラ(ソメイヨシノ)の大木があり、この付近も春の花見客でとても賑わいます。 冬場は、このあたりでは、カモ類などさまざまな野鳥に出遭うことができます。 なお、葵橋から右へ折れて、ここからも下鴨神社へ行くことができます。 |
| |
|
 葵橋  アキニレの大木、木陰で一休みできます。この付近はすばらしい景観です。  葵橋の説明板、木陰にある木のベンチ  説明板  比叡山と大文字山  美しい比叡山を望むことができます。  対岸のしはん桜、春には見事な桜並木となります。  対岸、サクラの咲く頃の風景  出雲路橋近くにある広場、この付近も比叡山、大文字山の眺望がすばらしいところです。  この付近の鴨川から見た五山の送り火、大文字    雪景色 |
少しだけですが、鴨川の勾配を感じませんか。当然ですが、鴨川の遊歩道は、ゆるい坂道となっています。堰を落ちる鴨川の瀬音が一段と大きくなってきました。 左に、アキニレ、サクラ、クロマツの巨木が続いています。左の、鴨川に沿っている道路は加茂街道です。 また、緑陰で一休みしていきましょう。アキニレの大木の下にベンチがあります。ここには、古い葵橋についての説明板があります。 対岸には、かつて師範学校関係者によって植樹されたソメイヨシノの並木が続いています。春には、鴨川沿いに見事なサクラ並木となり、ここも京都のサクラの名所になっています。 この付近は、建物の高さが抑えられていて、右には比叡山が大きくよく見えるようになってきました。前方の北山もかなり迫ってきました。大文字山もきれいな山の形が望めます。 鴨川公園の芝生も広く、よく手入れされています。芝生ではピクニックなどを楽しむことができます。また、このあたりの鴨川では釣り人の姿も見かけることができます。 なお、出雲路橋の手前、西詰南に公衆トイレがあります。前の広場からは、比叡山、東山、大文字山、そして鴨川の清流を一望することができます。 |
| |
|
 出雲路橋   出雲路橋からの北の眺め、サクラの頃  比叡山がよく見えます。   北大路橋近くのケヤキの並木  サクラ並木  紅葉の頃、この付近にはエノキなどの大木があります。 |
北山が随分間近になりました。雄大な比叡山も真横に見え出します。大文字山は、しだいに後退していきます。 さらに進むと、北山、比叡山と大文字山のすべての景観を見わたすことができます。 河川敷が広がり、加茂街道の車の騒音も少し遠くなりました。鴨川の流れと、せせらぎの音、空の高さをお楽しみください。 コートでは、さまざまなスポーツを楽しむ人たちがいます。冬には、このあたりで凧揚げの光景も見ることができます。この付近には、釣り人もよくいます。少し眺めてみましょうか。アユ、フナ、コイなど、今日の釣果はどうでしょうか。 さまざまな水鳥も間近に見られます。 左には、サクラ(ソメイヨシノ)、クロマツの大木が続いています。それにケヤキの巨木。春の新緑、夏の木陰、秋の紅葉、そして冬の立ち姿、四季を通じてケヤキの並木は見事です。 右の対岸には、サクラの並木がまだ続いています。大きなサクラの木が多く、春にはこの付近でも花見ができます。四月初旬には、サクラが満開となります。その季節には、ぜひ、東岸へ渡り、散策してみましょう。 ずいぶん川を上ってきました。少し疲れていませんか。北大路橋から、植物園に寄り道をする手もあります。今回の散策をここで終わるのもいいでしょう。左へ向かえば、市営地下鉄の北大路駅もあるので便利です。 なお、北大路橋の下をくぐった橋の西詰北に、公衆トイレがあります。 散策を続ける方はさらに次へどうぞ。 |
| |
|
 北大路橋、葵祭の祭列が通る。  北大路橋からの北の眺め、北山、右は植物園、時間があれば植物園にもぜひ。  鴨川と半木の道、気持ちのいい散策路です。  サクラの咲く頃の半木の道、見事なシダレザクラの並木道となります。  半木の道、対岸からの光景  植物園入り口にあるモニュメントと比叡山  鴨川で見かける鳥たちの看板  飛び石、野鳥が間近で見られます。 飛び石から眺める景色も素晴らしい所です。  対岸のケヤキの大木があり壮観です。  紅葉の頃  |
このまま西岸を歩いてもいいのですが、加茂街道の車の騒音と排気ガスを避けて、一度北大路橋を渡り、今度は東岸を散策してみましょう。北大路橋の下を一旦くぐって、左手の階段から北大路へ上がりましょう。 北大路橋から、北山方向を眺めてみましょう。北山が、かなり大きく見えています。山は鴨川を屏風のように塞いでいます。右には、比叡山があります。これもかなり近く見えるようになりました。植物園の樹木は大きな森となっています。 植物園のケヤキ並木へ寄り道してみましょう。気持ちのいい並木です。新緑と紅葉も素晴らしいです。ここで植物園に立ち寄って、散策を終わることもできます。園の中に、半木(なからぎ)の森という、かつての山城の森が残されています。 美術に興味のある方は、さらに足を伸ばして「陶板名画の庭」はいかがでしょうか。詳しくは下のリンクへ。 健脚の方はさらにどうぞ。ふたたび鴨川へ戻りましょうか。「半木(なからぎ)の道」が鴨川に沿ってあります。ベニシダレザクラの名所で、春には大変な見物客で賑わいます。この道には、日本初の太陽エネルギー灯が点りました。 左前方に見える山は、送り火で有名な船山です。正確には、西賀茂舟山(妙見山)の「船形万燈籠」といいます。これから、鴨川をさかのぼるにつれて次第に近づいてきます。 なお、北大路橋の方へ少し戻ると、鴨川に集まる水鳥の詳しい解説板があります。鳥に興味のある方はぜひどうぞ。 「半木の道」、鴨川の河川敷のどちらでも、気に入った方を歩きましょう。右には、植物園のクロマツの巨木、竹、さまざまな木々の並木が続いています。対岸には、ケヤキ、サクラなどの巨木が続いています。秋の頃、このあたりのケヤキの紅葉、春の頃のサクラも見事です。 やがて、飛び石があります。対岸に渡ってみるのもいいでしょう。ここでは、眼の高さで、鴨川の堰と北山の山並みを見られます。間近で水鳥が見えるかもしれません。気をつけて、ぜひどうぞ。石が小さいので、向こうから人が来たら、三角の少し大きな石でしばらく待ちましょう。なお、南方向の景色もお忘れなく。 そのまま、飛び石を渡って、西岸を歩いてもいいでしょう。あまり見晴らしはききませんが、東にわずかに比叡山、南に大文字山を見ることができます。 |
| |
|
 北山橋  前方は五山送り火の船形。    この付近の鴨川から見た五山の送り火、船形。  紅葉の頃  雪景色 |
今回は、東岸の散歩を続けましょう。鴨川は案外急流で、この北山通と東寺五重塔・九輪の塔先端(57m)がほぼ同じ高さとなっていいます。随分鴨川の上流に上ってきました。空気が澄んで、少し気温も下がってきたと感じませんか。 前方には美しい船山が見えます。右にサクラ(ソメイヨシノ)並木、対岸にはケヤキの大木が見え出します。この地点からは、とても美しい夕日を見ることができます。そして、もちろん五山の送り火の際には、火の灯された船形を見ることができます。 この付近では、冬場、水鳥にも出遭えます。今日は、トンビが空高くを旋回していませんか。 なお、北山橋を右に折れて、ここからも植物園に寄り道することができます。 |
| |
|
 上賀茂橋  上賀茂橋からの北の眺め、正面は船形。  しだいに道幅も狭くなってきます。空気も澄んできます。船形も見えます。  対岸の加茂街道の巨木並木、ここは葵祭の祭列が進む道筋です。   御薗橋、葵祭の祭列が渡ります。  御土居、鴨川西岸の御薗橋を下った加茂街道沿い、加茂川中学の北側。   雪景色 |
いよいよ鴨川散策も終わりが近づいてきました。 川幅はしだいに狭くなってきました。歩道も狭くなってきました。まだ大きくはないのですが、サクラ(ソメイヨシノ)並木が続いています。これから、立派なサクラの並木に育っていくでしょう。対岸には、ケヤキ、エノキなどの並木が見えます。これらの木々は、春の新緑も、秋の紅葉も楽しませてくれます。 船山、北山もかなり近づき、大きく見えるようになってきました。 いよいよ終点の御薗(みその)橋です。御薗橋は、葵祭の際に行列が、上賀茂神社に向かうときに渡る橋として知られています。 なお、御薗(みその)橋を渡った対岸には、少し下ると豊臣秀吉の築造させた御土居(おどい)の跡を見ることができます。鴨川に面した数少ない遺跡の一つですので、歴史、鴨川の治水に興味がある方はぜひどうぞ。 お疲れ様でした。今回は、鴨川の魅力についてわかっていただけたことと思います。また、いつかお越しください。鴨川には四季それぞれの美しさがあります。 ここまでくれば折角ですから、鴨川とゆかりの深い上賀茂神社にぜひご参拝ください。ここにもいくつかの鴨川の支流となる川が流れています。できれば、明神川と社家の町並み、季節の頃なら、カキツバタの大田神社もお薦めします。 では、また、鴨川でお会いしましょう。またのお越しをお待ちしています。 |
| |
|
 |
 |