|
|
|
| * | |
| 松原橋・旧五条大橋 (京都市下京区-東山区) Matsubara-bashi Bridge |
|
| 松原橋 | 松原橋 |
 |
 |
    北方向の景色   下流  下流  上流、料理旅館「鮒鶴」  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風 上杉本」に描かれた五条大橋、上の建物が大黒堂、鴨川二条大橋の説明板より  【参照】上記「上杉本洛中洛外図屏風 上杉本」中で五条大橋下流で魚捕る人々、鴨川二条大橋の説明板より 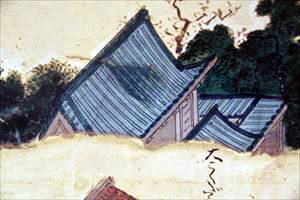 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた大黒堂、鴨川二条大橋の説明板より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた大黒堂、鴨川二条大橋の説明板より 【参照】安土・桃山時代の「洛中洛外図屏風」右隻に描かれた大仏殿、下に旧五条大橋(松原橋)、鴨川、京都国立博物館の屋外展示物説明板より  【参照】物吉村、室町時代、「洛中洛外図屏風(上杉本)」、京都アスニー陶板壁画より  【参照】松原通りの表示板 |
鴨川に架かる松原橋(まつばら-ばし)は、現在の五条大橋の一つ上流に架かる。安土・桃山時代まではこの橋が「五条大橋(五条橋)」と呼ばれていた。橋は、「清水橋」「清水寺橋」、僧侶による勧進(募金)により賄われ「勧進橋」とも呼ばれた。道の両側に松並木があり「五条松原橋」とも称されていた。 牛若丸と弁慶が出会った場所との伝承がある。橋は、清水寺への参詣道に当たり、鳥辺野に至る葬送地への入り口、此岸と彼岸の境界だった。河原は、死者の葬地にもなっていた。橋は、苦集滅路(くずめじ、滑谷 [しるたに越] 、渋谷越)に至る玄関口にもあたっていた。 ◆歴史年表 平安時代、809年-823年、第52代・嵯峨天皇(810-824)の勅命により橋が架けられたともいう。(「京都府百年の年表」)。すでに「五条大橋」と呼ばれた。 1080年、10月8日条、清水寺橋(五条橋)が架けられていたという。清水橋の橋下鴨河原で迎講が修された。(『水佐記』『京の橋ものがたり』) 1139年、旧6月、清水橋(五条橋)架橋の記録がある。覚誉上人が供養した。長さ64間(116m)、幅4間8寸(7.5m)あった。(『濫觴抄』『百錬抄記』)。かつての五条橋は、現在の松原橋付近に架けられていた。清水寺参拝道であり、鴨川氾濫のたびに流出したことから、参拝者の喜捨(寄付)により寺が架橋する勧進橋だった。 1159年、平治の乱で、六条河原では初の源平合戦が繰り広げられる。六波羅邸より平清盛が西行し、東行してきた源義朝の20騎に、平氏方に寝返った源頼政も北行して加わる。義朝は敗れ東国へ逃れる途中、尾張国で自害する。平家の軍勢は橋板を壊し、楯として防戦した。(『平治物語』) 1188年、大勧進沙弥印蔵は法然の説話を聞き、五条橋の造営勧進の願主になり、架橋した。清水寺阿弥陀堂の常行念仏も開く。 平安時代末、石橋が架けられていたという。(『梁塵秘抄』) 鎌倉時代、五条橋下には流灌頂(ながれかんじょう)を行う、乞食僧の「いたか」が住していたという。 鎌倉時代前期、「清水橋」、「清水寺橋」と呼ばれた。(『明月記』『東大寺要録』)。 1202年、建仁寺寄進により架橋された。 1228年、風雨洪水により、五条大橋・四条大橋・末橋などが流される。(『百錬抄』) 1233年、囚人を預かる大番衆が召人を逃した罰として、五条橋の修造が課せられた。 1235年、旧1月、幕府は京都大番役を怠った西国御家人に、清水寺橋の修理を命じる。(「鎌倉幕府法、追加法第69条」「中世法制史料集) 1245年、五条橋の修造費は幕府が一部負担した。(「即成敗式目追加法」) 1263年、清水橋(五条橋)、鴨川川防用途を近国御家人に賦課する。(鎌倉遺文8970) 1383年、加茂川洪水により、五条橋・四条橋が切落ちた。新たに五条大橋を供養した。 室町時代、1408年、浄財の寄付により修架されている。 1409年、京都の住人・慈恩が浄財200万文を集め、僧・慈鉄が設計し、長さ86丈余(260m)?、幅24尺余(7.3m)の長大な橋を架ける。(『本朝高僧伝』『京都御役所向大概覚書』『仲方和尚語録』) 1427年、洪水により五条橋・四条橋が落ち、河原在家といわれる庶民の家100余戸が流された。 1441年、洪水により五条橋は四条橋とともに落ちる。 1448年、旧5月、洪水により五条橋は落ちた。(「文正年代記東寺過去帖」) 1461年、「寛正の大飢饉(山城大飢饉)」の際に、飢饉と疫病、戦乱により、8万2000人の餓死者が出ている。時宗の僧・勧進聖の願阿弥は、四条橋の河原、五条橋の河原、油小路の空地で多くの餓死者を葬り塚を作った。(『碧山日録』『大乗院寺社雑事記』『臥雲日件録』)。鴨川には遺体が溢れ、川の流れを塞いだという。この後、五条橋で万寿寺の僧による施餓鬼が行なわれる。 1486年、旧5月、勧進聖・願阿弥は、五条橋中島の堂で病没したという。(『大乗院寺社雑事記』) 1488年、五条の河原の夏禹廟(燕丹之社、燕丹の廟)について記されている。かつて、四条橋に悪党がおり、綴法師と呼ばれていた。六波羅の命により捕らえられ、五条河原で斬首された。祟るのを畏れて祀ったという。(『相国寺蔭凉軒主亀泉集証』) 1525年-1536年/1525年頃、五条橋中島を挟み2本の板橋が描かれている。(『洛中洛外図屏風』町田本) 1544年、大風、洪水により五条大橋・四条大橋が落ちる。京中でも被害がある。(『言継卿記』) 1547年頃/1550年-1560年、五条大橋が描かれ、中島を挟み2本の橋が描かれている。(『洛中洛外図屏風』上杉本) 1566年、中島の法城寺について記されている。文献初見という。(『花洛名勝図絵』中『水月集』よりの引用) 1573年、五条橋が甚だ古く頽廃しているとの記述がある。(『耶蘇会(士)日本通信』) 安土・桃山時代、1579年、旧7月、建仁寺・東福寺僧による勧進で五条橋・四条橋が復興した。(『緑紅叢書』) 1585年、旧7月、洪水により、五条橋・四条橋が落ちた。(『緑紅叢書』) 1590年/1589年、豊臣秀吉は奈良・東大寺大仏殿を模し、方広寺大仏殿を造営した。その際に、五条坊門通-六条坊門小路にあたる現在の五条大橋の位置に、増田長盛、前田玄以により橋を架け替えさせ、「五条大橋」と改めた。長さ74間(135m)、幅4間1寸(7.3m)あり、「いかなる洪水にも滞る事なし」とされた。(『緑紅叢書』『都のにぎはひ』)。「旧五条大橋」は現在の松原橋になる。 1591年、豊臣秀吉はお土居を築造している。 江戸時代、元和年間(1615-1624)、新しく架橋された大仏橋が「五条橋」と称されたという。通り名も六条坊門小路から「五条橋通(近年になって五条通)」に変わる。旧五条通は「松原通」に変えられた。 1645年、大仏橋(現在の五条橋)が石橋に架け替えられ、新たに「五条石橋」と呼ばれるようになったともいう。 1669年-1670年、鴨川新堤(車坂-五条橋)の工事が始まる。 近代、1935年、6月、松原橋は「鴨川大洪水」により流出する。 現代、1959年、松原橋は修築される。 ◆願阿 室町時代中期-後期の時宗の僧・願阿(がんあ、? -1486)。男性。願阿弥。越中国(富山県)の生まれ。時宗の勧進聖になり、流出した五条大橋の架け替え、南禅寺仏殿の再興も行う。1459年、長谷寺の本尊開帳に際して、勅許の綸旨を興福寺へ持参した。1460年-1461年、8万人の餓死者が出た寛正の大飢饉では、8代将軍・足利義政は、願阿に飢民への施食を命じ、100貫文を与えた。願阿自らも勧進し、六角堂の南に小屋を建て、飢民に粟粥を施した。だが、飢民の数が多く、資金難から1カ月程で中止した。願阿は興福寺により清水寺の勧進僧の役を与えられる。応仁・文明の乱(1467-1477)後、諸国を勧進し、1478年、清水寺の鐘を鋳造する。1479年、清水寺本願職に補任された。1481年、奈良・元興寺極楽坊曼荼羅堂の千部経勧進を行い供養する。1482年、清水寺本堂を上棟している。その後、その功により「成就院願阿」と呼ばれた。五条橋中島の堂で亡くなったともいう。 ◆禹 中国古代の伝説上の帝王・禹(う、?-?)。詳細不明。禹王。姓は姒(じ)、別名は文命。西方の異民族の出身ともいう。父・鯀(こん)。尭帝の時代に黄河の大洪水が起こり、父・鯀が治水にあたり失敗する。その後、舜帝は禹に治水を命じた。禹は部下の益(えき)・后稷(こうしよく)とともに刻苦13年で成功した。水を導き、農業・産業を整備した。その功により舜帝から天子の位を譲られ、夏王朝を創始したという。 治水に当たり、自らは衣食を粗末にし、身を粉にして働いたとされ伝説化した。尭・舜と並び太古の聖王とされる。禹の死後、子・啓が諸侯から推されて天子になり、中国の世襲王朝の始まりになったという。 ◆増田 長盛 室町時代後期-江戸時代前期の武将・増田 長盛(ました-ながもり、1545-1615)。男性。通称は仁右衛門(にえもん)、右衛門尉と称した。尾張国(愛知県)/近江国(滋賀県)の生まれともいう。少年時代から秀吉に仕え、1584年、小牧・長久手の戦の戦功で加増された。1585年、従五位下・右衛門尉に叙任された。1589年、方広寺大仏殿造営に際し、大仏橋(五条橋)の造営奉行になる。1590年、小田原役に従い、京都鴨川に三条橋を架橋した。1591年、長束正家らと近江を検地する。1592年、文禄の役で、朝鮮に渡り、文吏派大名として兵站にあたり和議を進めた。1594年、伏見城の工事を分担する。1595年、行賞として、豊臣(羽柴)秀保の没後、居城・大和郡山城を与えられた。従四位下・侍従に叙任された。1598年、石田三成らと共に五奉行になり、秀吉没後に秀頼補佐を担う。1600年、関ヶ原の戦で西軍に属し、兵3000で大坂城の留守居を務めた。家臣・高田小左衛門に兵をつけて送る。他方、東軍・徳川家康に大坂城内の味方情報を送る。戦後、家康は許さず、領地没収・科料金の処分を受け、高野山に追放された。後に、武蔵岩槻城主・高力清長に預けられる。1615年、大坂夏の陣で、子・盛次が大坂方にあり、連座により自刃させられた。71歳。 民政に重用され、近江、安房(あわ)などの検地奉行として太閤検地に尽力した。 ◆前田 玄以 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・前田 玄以(まえだ-げんい、1539-1602)。男性。名は宗向、孫十郎基勝、号は半夢斎、策勝軒。美濃(岐阜県)の生まれ。父・前田基光。孫十郎基勝と称し、比叡山で出家、尾張・小松寺の住職僧ともいう。織田信長臣下になり、1579年、信長の命で嫡子・信忠の家臣になる。1582年、本能寺の変で信忠が自害し、その嫡男・三法師(さんぼうし、秀信)とともに岐阜に逃れ保護した。三法師を擁して清須に赴いた。この功により、1583年、信忠の弟・信雄より京都奉行に任じられる。以後、17年間在職した。禁裡御用地、門跡領、寺社領管理などを行う。1584年、豊臣秀吉に仕え、右筆(ゆうひつ)ともいう。その信厚く、1585年、丹波亀山を領された。1588年、第107代・後陽成天皇の聚楽第行幸で奉行し、寺社奉行で当初はキリシタンを弾圧した。1595年、豊臣秀次の問責に当たり、妻妾を亀山に預った。1598年、豊臣政権下五奉行の1人に任じられた。秀吉没後、徳川家康と石田三成の対立では三成方に属した。1600年、家康を討つよう長束正家、増田長盛らと諸大名に命じた。関ヶ原の戦は西軍に与し、大坂城の留守居として参戦しなかった。東軍・徳川方に通じ、戦後、金剛寺(河内長野)に謹慎になり、家康に許され丹波亀山の本領安堵、初代藩主になる。故事、典例、故実に通じ、千利休に茶を学んだ。64歳。 墓は妙心寺・蟠桃院、専念寺にある。法名は「徳善院殿天涼以公大居士」。 ◆松原橋 松原橋の架設年は、現代、1959年になる。 橋種は3径間連続鋼プレートガーター、橋長は83.55m、幅員は6m(6.7mとも)になる。鉄筋コンクリート製。 ◆晴明塚 平安時代の陰陽師・安倍晴明(921?-1005)が葬られたのは、五条大橋(松原橋)の東北の中州(現在の橋の東詰付近)だったという。 かつて鴨川の中州に、法城寺(ほうじょうじ、大黒堂)という寺が建てられ、晴明を祀る塚もあったという。(『洛中洛外図屏風』『雍州府志』)。寺の名は、「法」は「水去りて」、「城」は「土と成る」という意味になる。寺は、鴨川の洪水を防ぐために晴明本人が建てたともいう。晴明の墓は晴明塚といわれ、松が植えられていた。その後、晴明祠が建てられ、木像が祀られた。 寺を民間陰陽師が支えたとも、清水坂の犬神人によるともいう。少なくとも室町時代には存在した。付近は、「大黒信仰」の中心地になり、下級芸能者の拠点にもなった。 なお、安土・桃山時代、1593年、1594年、豊臣秀吉(1537-1598)の命により、畿内の多くの陰陽師(声聞師)が、尾張国の治水工事、荒地開墾の名目で移住させられた。京都からは109人が動員される。京都町奉行・前田玄以(1539-1602)が関与した。陰陽師狩りであり、勢力を削ぐという意図もあった見られている。 江戸時代前期、1607年、寺と塚は洪水被害により三条橋の東へ移転し、心光寺と寺号を改めた。また、度重なる鴨川の氾濫、安土・桃山時代の秀吉による新しい五条大橋替え工事、秀吉による弾圧により消えたともいう。 江戸時代前期、1654年まで、塚は中州に存在していた。(『新版平安城東西南北并洛外之図』)。その後、現在の松原橋の東、下京の物吉村(東山区八坂通大和大路付近とも)に遷された。塚を守護するために清圓(円)寺(せいえん-じ)、その隣に晴明社が祀られたという。(『京雀跡追』)。 近代、1868年、清圓寺、晴明社は廃絶し、中堂寺村の善徳寺に晴明像なども遷された。近代、1877年、像は長仙院(中京区裏寺町)に遷されたという。現在、長仙院は晴明像、神像などを所蔵している。 法城寺の名は、法城山晴明堂心光寺(三条大橋東)の山号寺名に残されている。心光寺は法城寺の後身とされ、かつては境内に晴明塚があったという。 近代、1885年以降、廃絶した清圓寺、晴明社の跡地に、松田儀兵衛により荒龍(あらたつ)神社が再建された。(「京都日出新聞」)。後に稲荷社に代わり、いまもその子孫の邸内に祀られているという。 ◆夏禹王廟 鎌倉時代には、橋下中州に夏禹王廟(かう-おうびょう)があったという。(『蔭涼軒日録』)。禹王(うおう)は、古代中国の夏王朝の最初の王で、黄河の治水に力を注ぎ、中国の道教では、治水や土木工事の神として崇められた。 夏禹王廟と法城寺との関連も指摘されている。また、仲源寺が後身ともわれている。 ◆いたか 鎌倉時代に、五条橋下には流灌頂(ながれかんじょう)を行う、乞食僧の「いたか」が住していたという。 川畔の四方に竹、板塔婆を立て、布をつり広げ、柄杓で通行人に水を注いでもらう。おもに難産死した女性の供養をしていた。 ◆寛正の大飢饉 室町時代前期、1420年、京都に大地震が起き、大干ばつ、飢饉が続いた。洛中には、飢餓者や疫病者があふれた。翌年、幕府によって五条河原に仮小屋が建てられ、大施餓鬼が執り行われた。 「寛正の大飢饉」(山城大飢饉)(1461)の際、飢饉と疫病、戦乱により、8万2000人もの餓死者が出た。時宗の僧・勧進聖の願阿弥(?-1486)は、四条橋、五条橋、油小路において多くの餓死者を葬っている。それでも鴨川には、遺体が溢れ、流れを塞いだという。この後、両橋などで、五山の僧による施餓鬼も相次いで行なわれた。願阿弥は、五条大橋での勧進による造営を行なっている。 ◆六波羅 松原橋は、鴨川を越えた平安京の「洛外」にあり、此岸(しがん、現世)から彼岸(ひがん、あの世)へと繋ぐ橋でもあった。橋を渡り東へ進むと、六道の辻を経て葬所地の鳥辺野(とりべの)の入り口に至る。清水坂から南西に向かうと観音霊場の清水寺に至った。 鴨川の東岸、五条-七条にかけては六波羅と呼ばれた。都人が亡くなると棺桶に遺骸を収めて鴨川を渡った。寺の僧侶は引導を渡し野辺に送る。鳥辺野とは、五条坂-今熊野にかけての阿弥陀ヶ峰の南麓一帯をいう。行基(668-749)が開いたとも伝えられ、山麓に阿弥陀堂があったことからこの名がついた。 なお、中世以降、清水坂では穢れを清める「清目」「坂者」とも呼ばれた職掌集団が、葬送、埋葬に関する特権を有していた。 橋向こうは、冥界への入り口、あの世とこの世の分岐点と考えられ、六道珍皇寺、六波羅蜜寺、念仏寺などのお堂が点在していた。六道の辻(六道の辻地蔵尊)にも通じた。六道とは、衆生が生前の業因よって赴くとされる地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上の六界を指し、何れかに行って、やがてこの世に転生すると考えられた。また、かつて呼ばれていた髑髏原(どくろがはら)から六道、六原、麓原、六波羅に転じたともいわれている。 ◆牛若丸 このかつての五条大橋は、武蔵坊弁慶(?-1189)と牛若丸(源義経、1159-1189)の対決の伝承でも知られている。 ◆お伽草子 お伽草子『和泉式部』では、和泉式部(978頃-?)の産んだ子どもが、五条大橋のたもとに捨てられる。子は、やがて比叡山の道命阿闍梨(974-1020)という僧になる。後に、宮中の法華八講で見初めた相手とは、和泉式部その人だった。 ◆阿国 安土・桃山時代の出雲阿国(いずも-の-おくに、1572 ?-?)は、四条河原ではなく、五条河原(松原の河原)でややこ踊りを演じ、北野社でかぶき踊りを披露したともいう。 ◆鮒鶴 松原橋上流西岸に、料理旅館の「鮒鶴(ふなつる)」がある。創業は、近代、1870年になる。 本館(旧館)(登録有形文化財)は、1927年に建てられた。入母屋造に唐破風を付けた楼閣と、唐破風寄棟造の折衷による。大広間を3段重ねた3階建と、鴨川の護岸に面し地下階を設けた箱状の大規模木造建築になっている。 本屋町通側には洋館(新館)(登録有形文化財)があり、近代、1933年に増築された。旧館の南側に建てられている。設計は東京帝国大学出身の建築家・柴田四郎(?-?)による。ライト風意匠を取り入れた。鉄骨造4階建であり、3階と4階の間に中3階を挟み、実質は5階建になる。 増改築を重ね、1・2階は北から南まで鴨川沿いに縁側が連なり、12畳-40畳半の座敷が並んだ。3階は、北側99畳、南側83畳あり、大床を構える折上格天井の大広間になっている。南北合わせて182畳という巨大な座敷を有し、大規模な宴会を催せた。最上階の座敷は東山・鴨川の眺望に優れていた。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の鴨川と橋 その歴史と生活』、『京の橋ものがたり』、『鴨川・まちと川のあゆみ』、『増補 洛中洛外の群像』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『史跡探訪 京の七口』、『京都まちかど遺産めぐり』、『あなたの知らない京都の歴史』、『京都の治水と昭和大洪水』、 『京都水ものがたり 平安京一二〇〇年を歩く』、『京都大事典』、『京 no.55』、『京都の災害をめぐる』、『京都・鴨川と別子銅山を歩く』、京都国立博物館、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)、ウェブサイト「鮒鶴」、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |
| |
|