|
|
|
| 拾翠亭 (京都市上京区) Shusui-tei |
|
| 拾翠亭 | 拾翠亭 |
 |
 |
        玄関  露地、飛石  露地、蹲踞  露地、ツワブキ  玄関  飛石   拾翠亭  拾翠亭、鯱、九条家家紋の鬼瓦。      勾玉池(九条池)  庭園、石橋  高倉橋、庭園の苔地  露地庭  勾玉池(九条池)の滝組  控えの間  控えの間  控えの間、石垣貼り    広間  広間より見た勾玉池(九条池)  広間、釘隠し    広縁、左の板敷、右の榑縁  広縁の天井、左の鏡天井、右の化粧屋根裏天井    広縁下の石組  広縁先の汀  蹲踞  蹲踞  蹲踞  露地     小間  小間  小間  水屋   二階座敷  二階座敷、床  二階座敷  二階座敷、丁字七宝  障子の石垣貼  二階座敷  二階座敷、縁高欄 二階座敷、縁高欄     四阿  四阿、明り窓  四阿の屋根上の獅子像  庭園、ホトトギス  庭園、井戸  庭園、石橋  庭園  庭園、スギゴケ  庭園、高倉橋  勾玉池(九条池)    高倉橋からみた建礼門  九条池   九条池 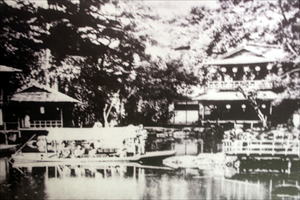 【参照】近代、明治期(1868-1912)初期の拾翠亭 、閑院宮邸跡収納展示館の展示より  【参照】拾翠亭 庭園模型、中央に高倉橋、閑院宮邸跡収納展示館の展示より |
京都御苑内に九条(九條)家の遺構「拾翠亭(しゅうすい-てい)」が建てられている。かつてこの地には、五摂家の一つ、九条家の屋敷があり、別荘として使用されていた。 現在は、拾翠亭と池だけが残されている。九条家の現存唯一、また、現存する貴族の茶室として数少ない遺構とされている。 アメリカ合衆国の日本庭園専門誌"Sukiya Living Magazine, The Journal of Japanese Gardening"の「しおさいプロジェクト」「日本庭園ランキング(数寄屋生活空間)」に、2007年に第23位に選ばれている。 ◆歴史年表 江戸時代、1778年頃、庭園が作庭されたという。 寛政年間(1789-1801)、建物が造立された。 幕末、米総領事・ハリスの通商条約締結要請に対し、開国派の関白・九条尚忠は、その向かい東隣の屋敷にあった攘夷論の太政大臣・鷹司政通と対立した。幕府と朝廷の交渉は尚忠邸で行われた。 1864年、禁門の変では焼失しなかった。 近代、1869年、第122代・明治天皇、最後の藤原氏長者・左大臣・九条道孝は東京に移った。 1878年、勾玉池(九条池)に仮橋が架けられる。 1882年、池に現在の高倉橋が架かる。 ◆九条 兼実 平安時代後期-鎌倉時代前期の政治家・九条 兼実(くじょう-よしみち、1149-1207)。男性。父・摂関家・藤原忠通、母・女房加賀(藤原仲光の娘)。1166年、右大臣になる。1156年、異母姉の皇嘉門院の猶子、1158年、兄・基実の猶子として元服、左近衛権中将、権中納言、左近衛権中将、権大納言・右近衛大将、内大臣を経て、1166年、右大臣に進み、1174年従一位に昇る。1179年、平清盛の権力奪取後、1185年、頼朝内覧の宣旨により、1186年、摂政・藤原氏長者になる。1187年、記録所を設ける。1189年、太政大臣、1190年、娘・任子を入内させ、第82代・後鳥羽天皇中宮になる。1192年、後白河法皇(第77代)没後、頼朝に征夷大将軍を宣下する。だが、1196年、政変により失脚した。弟の天台座主・慈円の後見になり仏教界に影響を及ぼす。息子、妻を亡くし法然へ帰依した。1202年、出家、円証と号した。後法性寺殿、月輪殿と称された。59歳。 和歌に親しみ、藤原俊成・定家らの庇護者になる。40年間の日記『玉葉(ぎょくよう)』がある。 九条家を興した兼実は法性寺に葬られ、墓は東福寺(東山区)内にある。 ◆九条 尚忠 江戸時代後期-近代の公家・九条 尚忠(くじょう-ひさただ、1795-1871)。男性。父・二条治孝、母・信子。九条輔嗣の嗣子。1858年、日米修好通商条約の締結により、1856年、関白として幕府との協調路線をとる。将軍継嗣問題では徳川慶福(家茂)擁立を図る南紀派につく。第121代・孝明天皇、廷臣の不信により、内覧を辞職しのち復職した。1862年、実現した和宮降嫁を進め公武合体に尽力した。攘夷派の糾弾により、1862年、関白・内覧を辞し、岩倉具視らと落飾・重慎に処せられ九条村に閉居した。1867年、免除され還俗を許される。74歳。 ◆九条家 九条家(くじょうけ)は、藤原氏北家の嫡流、五摂家の一つになる。家号は始祖・九条兼実(1149-1207)の九条殿に因む。兼実は関白・藤原忠通(1097-1164)の3男になる。九条の坊名に因み陶化(とうか)ともいう。これは、京都の南東部の九条陶化坊に領地を有していたことによる。 平安時代後期、摂政・関白・氏長者の地位は、藤原道長の子孫・御堂流の嫡流だった。鎌倉幕府を開いた源頼朝(1147-1199)は、兼実を摂政・氏長者に推挙した。以後、九条家は兄・基実(1143-1166)の近衛家と対立し、摂関家は二分される。孫・道家の子・良実(1216-1270)、実経(1223-1284)が、それぞれ五摂家の二条家、一条家を立てた。 安土・桃山時代、豊臣秀吉は、御所南に九条家の領地を移させた。九条家は最盛期に敷地は1万7000坪、建物も3800坪を有したという。 幕末、関白・尚忠(1798-1871)は佐幕派、道孝(1839-1906)は、官軍奥州鎮撫総督に任じられた。近代以降、九条家は公爵になった。道孝四女は、第123代・大正天皇の貞明皇后(九条節子、1884-1951)になっている。 ◆拾翠 「拾翠亭」の「拾翠(しゅうすい)」とは、「緑の草花を拾い集める」の意味があるという。 平安時代、春まだ浅い頃、貴族は待ちきれずに野辺に出て、若菜、草花を摘んだという。その慣わしに因むという。 また「翠」には、鳥のカワセミを意味する。碧い羽を持つカワセミは、「翡翠(翡翆)鳥」「翡翠(翡翆、ひすい)」とも呼ばれた。古くは「翠鳥(そにどり)」などとも称された。かつて勾玉池(九条池)に、カワセミが数多く飛翔していたことから「拾翠」と名付けられたともいう。現在は、マガモ、アオサギなども飛来する。 ◆建築 拾翠亭は、40坪(130㎡)の広さがある。かつて、茶会、歌会などに使用された。 門より飛石を伝い、左に折れる。西面して「玄関」、その東の「控えの間」、北に「広間」、北端に「小間」がある。広間の東と北に池に面して広縁が付く。二階には「座敷」がある。数奇屋風の書院造、二階建。 ◈控えの間 「控えの間」(7畳半)は、玄関の東、広間の南にある。南、東は庭に面しており、二方向に窓が開いている。広間での茶席の際には、控えの間として使われた。北の襖を外すと、広間と一体として使うことができた。 ◈広間 一階の主室「広間」(10畳)は、寝殿造の様式を残した書院造になる。西側北寄りに床(1間)があり、床柱は皮付丸太、炉は四畳半切(点前畳に接した外側の畳に切る出炉のうち、点前畳が丸畳で、点前畳の長辺を二等分した位置から下座側に炉が切られている)で茶室にもなる。床脇の襖は太鼓襖(襖縁を設けない)であり、かつて墨絵の鳥の図が描かれていた。天井は竿縁天井(天井板を竿という部材で押さえて天井を張る)になる。 北と東を池に面しており、広縁が廻されている。広縁は、巾広板敷、榑縁に分かれる。天井もそれぞれ鏡天井、化粧屋根裏になっている。屋根は入母屋造、瓦葺、一部に杮(こけら)葺、頂に一対の鯱が載る。その下に九条家家紋の鬼瓦がある。 ◈小間 「小間」は茶席であり、三畳中板の席という。手前座(1畳)、客座(2畳)、その間に板(1尺5寸)に炉を切る。客座中央に床、床脇の給仕口は引違の太鼓襖、床柱は百日紅の曲木、相手柱に杉の磨丸太、床框に黒柿、落掛にヘゴシダが用いられている。広間に隣接し、二つの茶席として利用されていた。 ◈障子貼り 障子は「石垣貼り」という貼り方になる。一枚の紙を用いず、継目のついた紙を桟割に合わせて2分の1ずつずらして貼る。熟練が必要とされる。障子、欄間、茶室の明かり窓もこの貼り方で統一されている。 ◈二階座敷 階段より「二階座敷」(2間半)に上る。南西隅に踏込床(床框を用いず、畳面と同一平面に床板を設けた)、床柱は皮付丸太、落掛は湾曲した雑木、床脇に天袋を吊り、下に書院風の中敷居窓を開けている。北、東、南に縁高欄が廻されている。 ◆茶室 茶室は、亭の北にある。三畳中板、台目切、床柱にサルスベリの古木、へ後ヘゴの茎を用いている。 ◆庭園 勾玉池(九条池)を中心とした池泉回遊式庭園になる。建物の南、東、北に池は広がる。江戸時代後期、1778年頃に作庭されたという。面積は7200㎡(東西90m、南北60m)ある。 拾翠亭からの東の眺めを前提として造られたといわれ、東山の稜線を借景としていた。かつては二階より東に、大文字山を望むことができた。現在は樹木が繁茂し、当初の借景は隠されている。 池は、勾玉(まがたま)形の勾玉池(九条池)といわれる。東南隅に滝組があり、かつては鴨川の水が引かれていた。池中に岬があり、交互に突き出している。 池の中央、南北方向に高倉橋が架かけられ、現在では景色の一つになっている。池には野鳥が訪れる。 拾翠亭の南、西、北に露地庭があり、苔、飛石、蹲踞などで構成されている。庭内にツバキ、コムラサキ、サルスベリなどの植栽がある。 池の西よりの中島には九条家の鎮守社・厳島神社が祀られている。 ◆高倉橋 九条池に架かる高倉橋(たかくらばし)は、近代、1878年に仮橋が架けられた。1882年、現在の橋が架かる。かつて、御所の建礼門から南へ、丸太町通に出るために一直線の御幸道の計画があった。そのために架橋された。だが、計画は中止になる。現在、道は丸太町通直前で途絶し、東西への細い沿道しかない。 橋脚は、旧三条大橋、五条大橋の橋脚を再利用している。かつて三条小橋の擬宝珠を載せていた。現在は、新調したものを使う。長さ43m、幅3.3m。 ◆一般公開日 一般公開日は、毎週金曜日と土曜日。京都御所一般公開日、葵祭(5月15日)、時代祭(10月22日)。参観休止(12月28日-2月末日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 「拾翠亭パンフレット」、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都大事典』、『秘密の京都』、『京都事典』 、閑院宮邸跡収納展示館、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |