|
|
|
| 園城寺 (三井寺) (滋賀県大津市) Onjo-ji (Mii-dera) Temple |
|
| 園城寺 (三井寺) | 園城寺 (三井寺) |
 |
 |
  外周は石垣、堀が築かれている。     大門(仁王門)(重文)     総門   釈迦堂(食堂、じきどう)(重文)  弁才天社  手水舎   教待堂  宝篋印塔   智證大師円珍像    鐘楼(三井の晩鐘)(重文)  梵鐘(三井の晩鐘)   金堂(本堂)(国宝)  金堂、天台系内陣  金堂、手挟に雲、菊、蓮、迦陵頻迦などの彫刻がある。  金堂、二手先、軒天井、支輪、尾垂木もないのが特徴という。  金堂、金堂前灯籠(園城寺金堂無名指灯籠)  金堂北の石段  閼伽井屋  閼伽井屋内部、いまも岩間より湧水が続いている。  閼伽井屋、覆屋正面上部にある江戸時代の彫り物  閼伽井石庭、閼伽井の北隣にある。  熊野権現社、金堂の西にある。  天狗杉、金堂の向かいに立っている。  長等山(左)、境内の西に見える。  参道、左端に天狗杉   「三井寺の 門をたたけばけふの月」、芭蕉  霊堂   霊堂、弁慶の引き摺り鐘  霊堂、弁慶汁鍋  霊堂、絵馬   光浄院客殿(国宝)  一切経蔵への石段  一切経蔵、八角輪蔵(重文)  一切経蔵、波形連子の欄間、蟇股  一切経蔵、八角輪蔵  一切経蔵、明り取りの窓  一切経蔵、鏡天井、極彩色の天井画   孔雀舎、境内で飼われている孔雀  唐院  唐院、四脚門(重文)  唐院  唐院、大師堂(重文)  唐院、潅頂堂(重文)  唐院、潅頂堂、正面から唐破風  唐院、長日護摩堂(県指定文化財)  唐院、三重塔、塔婆(重文)   村雲橋、勧学院の石垣の築地堀の手前にある。  勧学院  勧学院客殿  勧学院、自然石を積み上げた穴太(あのう)衆による穴太積みの石垣。  三尾明神の影向石、勧学院の西にある。  宝寿院  微妙寺 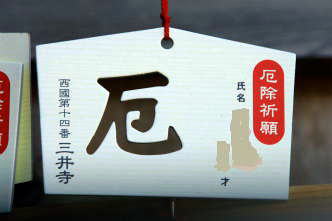 微妙寺、絵馬  天台大師像  天台大師像、智顗(ちぎ)  観音堂への参道  衆宝観音、三十三観音の一つ。  ねずみの宮(十八明神)  毘沙門堂(重文)  毘沙門堂  観音堂への参道  観音堂(県指定文化財)   水子地蔵尊  観音堂百体堂(県指定文化財)  観音堂、百体堂、大津絵の「鬼の寒念仏」の絵馬  観音堂、観月舞台(県指定文化財)  観音堂からの琵琶湖の景色  鐘楼(県指定文化財)  鐘楼内梵鐘、かつて「童子因縁之鐘」と呼ばれる鐘が鐘楼内に吊られていた。  絵馬堂(市指定文化財)  観音堂境内、遠景は琵琶湖   手水舎(市指定文化財)  大津そろばん顕彰碑  地蔵堂(市指定文化財)  宝篋印塔   水観寺(県指定文化財)   行者堂  行者堂  神変行者堂  行者堂、弁天堂  行者堂、神変大菩薩(役小角)像  行者堂  護法善神堂前の石橋(重要美術館)  護法善神堂前の門  三井寺南別所、護法善神堂  護法善神堂・千団子社(市指定文化財)」  財林坊  財林坊、本地堂  南別所・両願寺  収蔵庫  【参照】新羅善神堂  【参照】法明院  【参照】弘文天皇(大友皇子)長等山前陵 |
大津市の園城寺(おんじょう-じ)は、長等山(ながらさん、354m)中腹に35万坪(157 025㎡)の広大な境内を有している。東に琵琶湖を見下ろす境内は、古都保存法に基づき、「園城寺歴史的風土特別保存地区」に指定されている。 「三井寺(みいでら)」、「御井寺」ともいう。延暦寺を「山門」「山」というのに対し、「寺門」「寺」ともいう。正式には、長等山園城寺(ながらさん-おんじょうじ)という。 平安時代に智証大師円珍が園城寺を天台別院として中興後、「本朝四箇大寺(ほんちょう-しかたいじ)」(園城寺、東大寺、興福寺、延暦寺)の一つに数えられ、南都北嶺の一翼を担った。 現在、観音堂を中心とした南院、唐院・金堂などの中院、新羅善神堂・法明院などの北院の三院で構成されている。 天台寺門宗総本山。本堂(金堂)には、永久秘仏の本尊、弥勒菩薩が安置されている。 金堂の秘仏・弥勒菩薩像は法然上人(圓光大師)二十五霊場第番札所。 観音堂・秘仏の如意輪観音坐像は、西国三十三所観音霊場巡礼第14番礼所、近江西国観音霊場第5番札所、数珠巡礼札所、びわ湖百八霊場(湖西二十七名刹)札所。 微妙寺・十一面観音立像は湖国十一面観音霊場第1番札所、水観寺・薬師如来・二十八部衆は西国薬師霊場第48番札所。「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。 飛鳥時代、667年、大津京遷都に伴い、第38代・天智天皇長子・大友皇子は、長等山東麓(現在の園城寺の地)に邸宅を構えたという。この頃、天智天皇は夢告により、渡来の金銅の弥勒菩薩像を安置するために、長等山麓に寺院建立を発願したという。 670年条、「山御井」と記されている。(『古事記』) 672年、壬申の乱が起り、大友皇子と大海人皇子が皇位継承を巡り争う。敗れた大友皇子は、境内の「長等山崎」で自害したとされる。皇子・大友村主与多王(与多麻呂)は、天智天皇の霊と戦没兵を弔うために、田園城邑(じょうゆう、屋敷)を寄進し、第40代・天武天皇に園城寺建立を奏上する。(寺伝) 白鳳時代(673-710) 、大友村主(すぐり)氏の氏寺として創建されたともいう。(近代の古瓦出土による) 673年、園城寺の工事が始まる。(寺伝)。天智天皇が建立した祟福寺の堂舎を移したともいう。 686年、創建されたという。伽藍の工事が終わる。大友皇子の発願により、その子・大友与多麿(与多王)が父の菩提を弔うため、自らの田園城邑(じょうゆう)を投げ打ち寺を創建したともいう。(『扶桑略記』)。第40代・天武天皇より「園城寺」の勅願を贈られた。第38代・天智天皇、第39代・弘文天皇(大友皇子)、天武天皇の勅願寺になる。(寺伝)。弥勒菩薩を本尊にした。後に豪族・大友氏の氏寺になる。 奈良時代末、大友村主氏の氏寺として創建されたともいう。 平安時代、829年、円珍は叡山に上がり、座主・義真の門に入る。(『珍伝』) 833年、円珍は菩薩戒を受く。(『珍伝』) 838年、円珍は黄不動尊の示現に会い、空光に描かせる。(『珍伝』『智年譜』) 844年、円珍は一期棲山を満じる。(『智年譜』) 859年、円珍は園城寺長吏になり、再興を試みる。(『園長』、866年とも)。檀越・大友都堵牟麿、住僧・教侍の付属を受けた。天台別院とし伽藍を再興し、天台座主・円仁が導師として修造供養を行う。この頃より「三井寺」と呼ばれる。第56代・清和天皇より仁寿殿を賜り、密教修学の道場・唐院を建て円珍将来の経籍を移す。(『智寺撮』) 860年、円珍、円敏、増命、康済らにより新羅神社が建立される。(『寺撮』) 862年、宗叡らに阿闍梨灌頂を授け、唐ノ坊灌頂の初例になる。 863年、円珍は当寺で宗叡に両部大法を伝授した。 864年、仁寿殿に大悲胎蔵灌頂壇を設けた。 866年、太政官牒により、真言・止観両宗弘伝の公修を贈られ、円、密、禅、戒の四宗、さらに修験の教法が認められた。旧5月、園城寺を延暦寺別院にした。(『座主記』)。円珍は三井寺別当職に任じられる。以後、別当は円珍の血脈より挙用することに定まる。(『智年譜』)。俗大別当に大友夜須麿を任命する。 旧10月、延暦寺は牒を下し、園城寺の別当三綱を補任する(『座主記』) 868年、旧6月、5世天台座主に円珍が就き、密教色が強まる。(『智年譜』『座主記』)。寄進も相次ぎ伽藍も整い、儀式も整備された。円珍に園城寺が贈られ、伝法潅頂道場になり、唐より請来の経籍を唐坊に納める。(『智年譜』) 875年、円珍は鎮守の諸社、新羅明神社を修造し、講堂、大塔を建立する。(『寺撮』)。以後、智証(円珍)門徒が別当を継承する。 888年、円珍は、円仁の学積顕彰のため前唐院を創建する。円珍は門弟に対して三ヵ条の制誡文を示す。(『座主記』) 891年、円珍は遺告を書き増命に与え、円仁門徒との親交を諭す。円珍は比叡山山王院で亡くなる。(『珍伝』)。惟首が2代・園城寺長吏になる。(『園長』) 892年、円珍の死骨は木像胎内(御骨大師像)に納められる。惟首が天台座主になる。 899年、増命が4代・園城寺長吏になる。 906年、増命が天台座主になる。 927年、円珍に智証大師の諡号が追贈られる。勢祐は、9代・園城寺長吏になる。 971年、余慶の奏により、新羅明神に正四位上の神階が授けられる。 979年、余慶は、15代・園城寺長吏になる。 980年、岩倉山観音院を円融天皇の御願寺とし、勝算はその阿闍梨になる。 981年、致平親王(法名悟円)が出家し園城寺に入る。余慶が法性寺座主になるが、慈覚門徒は改補を奏請強訴し、円仁・円珍門徒間が不和になり、互いの確執が始まる。以後500年間にわたる寺門、山門の抗争が続いた。 982年、余慶は法性寺座主を辞する。慈覚・智証両門徒は不和により、余慶・門人は岩倉大雲寺観音寺に、穆算・門人は一乗寺に、勝算・門人は修学院に、勧修・門人は岩倉・解脱寺に移る。山僧126人は円珍の経蔵を守護する。 989年、余慶が天台座主になるが、慈覚門徒が拒んだため辞する。 993年、慈覚門徒が円珍ゆかりの比叡山の千手院(山王院)など40坊舎を壊した。智証門徒1000人は比叡山を下る。以後、延暦寺(円仁派・山門派)、園城寺(円珍派・寺門派)として対立、分裂した。慶祚(けいそ)、賀延、忠増、門徒は、千手院の智証大師像(中尊大師像)を園城寺唐坊に移す。慶祚は八所明神を園城寺に勧請する。 995年、智証門徒が園城寺に集まる。 1017年、智証大師遠忌に当たり、藤原道長・頼通らが園城寺に来寺して法華十講を修し、初めて碩学竪義を置く。 1031年、 永円が28代・長吏(園長)になる。以後、親王摂関子孫が任じらる。 1038年、寺門派・明尊の天台座主の補任を慈覚門徒が拒み、寺門、山門が対立する。 1039年、明尊は園城寺に戒壇を建てることを請う。山徒3000人が関白・藤原頼道第に強訴した。 1040年、園城寺の戒壇院問題により、寺門、山門双方の僧兵が衝突する。明尊は水観寺を建てる。 1041年、朝廷は、園城寺戒壇設立の可否を諸宗に問う。延暦寺のみが反対する。以後、長く寺門、山門は戒壇問題により対立する。 1048年、明尊は、天台座主に任じられる。だが、山徒が拒み在職3日で辞した。以後、寺門からの7度の座主補任は数日で辞任に追い込まれる。 1051年、源頼義は、前九年の役出陣に際して園城寺に詣で、新羅明神に戦勝祈願する。子・三郎義光を氏人として奉じた。 1063年、頼義は前九年の役を平定し、子・快誉を寺門学侶とした。 1070年、園城寺戒壇建立の可否を諸宗に問う。 1072年、聖願寺(現在の正法寺)が建つ。 1074年、踏歌の節会に端を発し、日吉祭が新宮に移された。その後の祭りも園城寺により妨害され、延暦寺と園城寺の間で僧徒が武力対立した。山門派は園城寺を焼討ちし、園城寺が報復、さらに園城寺を焼いた。 1075年、園城寺衆徒、延暦寺山徒は、戒壇の事で抗争する。 1080年、白河上皇(第72代)は羅惹院を建立し御願寺にする。 1081年、大津浦神人の帰属をめぐり日吉社、園城寺が対立する。日吉祭で延暦寺山徒、園城寺門徒が争乱する。6月、延暦寺山徒が園城寺を焼く。9月、園城寺僧徒が延暦寺を攻め、八王子山に籠る。朝廷は前陸奥守・源頼俊に追補させた。山徒は再び園城寺を焼討ちし灰燼に帰した。源義家は園城寺を討つ。(1度目の大抗争) 1084年、金堂が建立される。 院政期(1086-1192)、円満院、聖護院、実相院の三門跡があった。北院、中院、南院、五別所の寺域があった。 1087年、白河上皇の護持僧・増誉は、上皇の熊野御幸の先達になる。 1090年、 増誉は熊野三山検校に任じられる。以後、智証門流より熊野三山検校職が任じられる。 1096年、白河上皇の崇敬厚く、長吏・隆明を護持僧として沙弥戒を受ける。 1104年以降、延暦寺では、園城寺との争いにより強訴も行われる。 1105年、延暦寺山徒は祇園の神輿を奉じ、園城寺・証観の探題を訴える。 1108年、尊勝寺灌頂阿闍梨問題では、園城寺、延暦寺が対立を超えて協力する。 1116年、行尊は熊野三山検校に任じられる。園城寺僧徒が法勝寺の事で強訴しようとし、検非違使が制止する。 1120年、領地所有をめぐり、寺門派僧侶による山門派僧侶の殺傷があり、山門派は、園城寺を焼討ちする。院宣により園城寺、延暦寺の僧徒の乱行を禁じた。(2度目の大抗争) 1121年、園城寺僧徒による延暦寺修行僧の殺害を発端として、延暦寺山徒が園城寺の塔堂を焼き、廃墟と化す。観音院、一乗寺も焼く。 1123年、延暦寺、園城寺の僧徒が争う。 1134年、金堂供養。鳥羽上皇(第74代)により御造営供養が執り行われる。閼伽井屋が創立される。 1138年、園城寺僧徒は別当禅仁の房舎を焼く。覚猷は天台座主になり、在職3日で辞した。 1140年、旧4月、延暦寺山徒は、園城寺の塹坑を埋めようとして園城寺衆徒と争う。旧7月、園城寺を焼討ちした。この年、3度の抗争があった。(『天台座主記』)(3度目の大抗争) 1142年、園城寺衆徒は延暦寺東西の両塔を焼く。園城寺金堂を建立する。 1146年、 園城寺僧徒は、延暦寺延命院を焼く。 1148年、金堂の上棟供養が行われる。 1152年、金堂を慶した。 1153年、房覚(覚明?)は、三井新羅社に17日供花する。当社安居の初めになる。 1156年、保元の乱で、平清盛は源為義の探索を行う。 1159年、熊野社を金堂乾角に勧請する。 1161年、延暦寺山徒は、園城寺別院平等院に戒壇建立の事あるを疑い蜂起する。後白河法皇(第77代)が臨幸する。 1162年、延暦寺山徒は覚忠の天台座主補任を拒んで蜂起する。 1163年、旧3月、延暦寺の訴えにより、園城寺僧の天台座主に任じられる者は叡山で受戒するとした。園城寺は従わず、興福寺奏上で園城寺僧侶の南都受戒、延暦寺は興福寺の末寺にすることを請う。旧6月、延暦寺山徒は園城寺、修学院、解脱寺、一乗寺、嵩福寺、梵釈寺も焼く。(4度目の大抗争) 1173年、新羅社頭において歌合が行われ、藤原俊成を判者とした。後白河法皇が覚忠より灌頂を受け「園城寺平等院流阿闍梨行真」と称したともいう。 1178年、後白河法皇の園城寺行幸により潅頂を受けようとし、延暦寺山徒らが反対し強訴する。園城寺焼討ちは朝廷が制した。 1180年、旧5月、平家討伐のため以仁王と源頼政の乱で、王、頼政は、如意越で園城寺に逃れ、園城寺、興福寺、延暦寺に援助を請う。旧11月、朝廷は延暦寺、園城寺で応じる者を糾弾する。旧12月、寺門、山門が源氏方につき、朝廷は、平清房、平宗盛らにより園城寺、延暦寺を焼かせる。園城寺は1万騎の平家の軍により攻められた。800人が殺害され、金堂以外の伽藍637宇に火を放たれ、一切経7000巻、仏像2000体が焼失したという。 1184年、源頼朝は、近江国横山荘、若狭国玉置荘を園城寺に寄進する。 鎌倉時代、1190年、頼朝は上京に際し、青龍院修理料として剣、砂金千両を施入する。 1191年、静恵が無品親王に叙し、寺門法親王の初めになる。 1195年、源頼朝は、初入洛の際に青龍院の修理を施入する。 1196年、四天王寺別当替補に、園城寺衆徒が蜂起する。 1206年、園城寺の堂衆が今津を襲い、官軍との間に衝突があった。 1207年、 後鳥羽上皇(第82代)、園城寺長吏(42代、46代)実慶の房に行幸した。熊野三山検校職はながく三井に付するとの宣下がある。 1208年、 讃岐真庄が寄進される。 1211年、延暦寺山徒が園城寺を焼討ちしようとし幕府が警護した。 1213年、日吉祭に端を発し、寺門僧、山門所司の対立になり、延暦寺山徒は、園城寺を襲った。興福寺衆徒、園城寺の牒に応じ神木を奉じ入京しようにする。道元が長吏公胤に参問する。 1214年、日吉祭での神撰供進を発端に、延暦寺山徒は園城寺を襲い、金堂など129宇を焼くともいう。大津東浦、西浦も焼く。道元は母方の縁者・公胤を頼り延暦寺より園城寺を訪ねる。(5度目の大抗争) 1215年、将軍・源実朝は園城寺を復興する。園城寺衆徒、延暦寺東坂本を焼く。朝廷は張本人12人を処刑する。 1216年、将軍・源実朝は園城寺を復興したともいう。 1238年、北条泰時は政子十三回忌に書写させた一切経を、園城寺唐院に納める。 1257年、長俊、尊賢ら園城寺戒壇建立を訴える。 1258年、延暦寺山徒は園城寺戒壇建立中止を強訴する。園城寺は戒壇建立を幕府に訴える。この頃、南院40、中院74、北院124を数えた。 1259年、戒壇設立の左弁官の宣旨をもって勅許が降りる。だが、山門の抵抗により止む。怒った園城寺衆徒は自ら唐院経蔵を焼く。 1260年、旧1月、園城寺三摩耶戒壇建立を勅許に対し、延暦寺山徒は、日吉・祇園・北野の神輿を奉じて入洛強訴し、勅許は止む。 1264年、園城寺での戒壇建立に対し、延暦寺山徒は園城寺を焼く。山徒は梵鐘を比叡山に持ち帰り、「弁慶の引き摺り鐘」の伝承になる。 1267年、梵鐘が比叡山より還る。 1274年、延暦寺山徒は長吏・円助親王の叙位に日吉神輿を砕く。 1278年、延暦寺山徒は、園城寺金堂供養が勅会に准ずる事に対し、北院を焼いた。神輿を奉じて入京する。 1280年、延暦寺山徒は園城寺を攻め、守護の兵と戦い北院を焼く。 1284年、延暦寺山徒は別当職が園城寺に与えられたことから、神輿振りを行おうとし阻止される。比叡山の堂舎を焼き、園城寺も焼いた。 1285年頃、南院140、中院74、北院124の堂宇があった。 1313年、勧学院が建つ。 1319年、旧3月、延暦寺山徒は、園城寺が戒壇建立を計画したとして焼討ちした。旧4月、戒壇、金堂供養になる。旧4月、山徒は園城寺を焼く。 南北朝時代、1336年、旧1月、足利勢(細川勢)・園城寺と北畠顕家・新田義貞軍、延暦寺山徒は、湖岸、園城寺で対戦した。園城寺に細川定禅の陣が敷かれた。義貞に敗れ、山徒に堂塔を焼かれる。戦は京都にも及んだ。尊氏が入京したため、第96代・後醍醐天皇は比叡山(日吉社大宮彼岸所)へ避難した。旧11月、足利尊氏は、石見、安芸、美作の荘園を園城寺に寄進する。 1337年、足利尊氏は造営料として近江山賀庄を寄進する。 1338年、足利直義は北畠顕家の進攻に対して、園城寺に瀬田(勢多)橋の警固を依頼する。以後、警固が恒例になる。 1339年、淀関(山城)が園城寺の造営料所になる。 1340年、園城寺衆徒は、足利直義の命を受けて勢多橋を警固する。 1343年、園城寺衆徒は幕命により勢多橋を警固する。 1344年、佐渡の数庄が園城寺に寄進される。 1347年、足利尊氏により金堂、新羅善神道などが再建になる。 1350年、 園城寺衆徒に勢多橋を警固させる。 1352年、旧閏2月、足利義詮、寄附地安堵の書状を園城寺へ送る。旧4月、義詮、伊勢丹波の内地を園城寺衆徒に寄進する。旧10月、義詮は石見、安芸、越前、近江の地を園城寺に寄進する。旧12月、尊氏は経蔵を寄進する。 1353年、義詮は美作国青柳庄を園城寺に寄進する。 1354年、足利尊氏は京都・等持院に献じていた一切経を園城寺に移して奉納する。 1365年、園城寺衆徒が山科を焼く。 1367年、南禅寺造営により、園城寺僧徒が強訴する。園城寺衆徒は南禅寺の関二ヶ所を毀ち、禅僧など殺害する。幕府は、南禅寺の訴えにより、園城寺の領する三関を焼く。 1384年、足利義満は、建武以来の寄附の御判を園城寺に与える。 室町時代、1398年、熊野社社殿が上棟になる。 1411年、足利義持は、園城寺旧領の証判を与える。 1419年、幕府は園城寺に関所のことを関わらせる。 1420年、 宝憧寺供養のことで園城寺衆徒が蜂起する。南別所近松、顕証寺が建立される。 1432年、三井如意輪堂が建ち、慶する。 1433年、東坂本の馬借蜂起があり、数百人が京都に乱入した。山門僧が園城寺を攻撃した。旧5月、幕府は園城寺の請により、升米関を復した。旧7月、幕府は園城寺衆徒に命じ勢多橋を警固させる。旧8月、延暦寺山徒は幕府の山門奉行らに不正があったとして弾劾訴訟を行う。山徒は訴訟に同調しなかった園城寺を焼討ちする。足利義教は園城寺僧兵とともに比叡山を包囲した。旧12月、幕府は坂本退治の勲功を賞し、園城寺衆徒に教書を下す。 1443年、園城寺衆徒は金堂に拠り強訴する。 1461年、南都七大寺は三カ条の訴えにより寺門を閉じる。 1468年、足利義視が園城寺に入る。如意寺が焼ける。 1469年、蓮如は、南別所近松寺に顕証寺を建立し、親鸞影像を安置した。 1471年、蓮如は吉崎に移り、近松別院は順如に託した。 1481年、園城寺の正法寺(観音堂)を現在地に移す。 1487年、細川政元の兵が陣を敷く。 1490年、十八明神社を改造する。 1491年、旧9月、足利義材は、六角高頼征伐のため出陣し、園城寺・光浄院に陣する。 1552年、佐々木氏により焼かれた。 1568年、旧9月、足利義昭を奉じて入京を試みた織田信長は、園城寺・極楽院(光浄院とも)に陣する。 1570年、将軍足利義昭は園城寺に移る。 1571年、旧9月、信長は比叡山焼討ちのために園城寺・光浄院に入る。 安土・桃山時代、1582年、旧6月14日、羽柴秀吉は、山崎の戦後、明智光秀の残党狩りに際して園城寺に布陣する。 1592年、園城寺の鐘音が止み、大般若経を転読する。秀吉の命で大津城主・新庄直頼が鐘楼を建立した。 1595年、旧11月、豊臣秀吉は、園城寺に闕所(けっしょ、廃絶)の命を下し、堂塔を破壊し比叡山に移された。本尊など仏像は洛東・大仏照高院に遷された。僧も移る。寺領も没収される。豊臣秀次事件に連座したためともいう。(『園城寺再興略記』) 1596年、旧4月、秀吉の命により園城寺の弥勒堂を比叡山延暦寺の西塔に移し釈迦堂(現、転法輪堂存)にした。園城寺内に釈迦堂(金堂)を移築した。 1598年、旧6月、死の直前に秀吉は園城寺の闕所(廃絶)を解き再興を許す。この陰に、道澄、暹実、道阿弥の多大な尽力があった。北政所は寺領4320石余を復した。旧10月、唐院再興が始まる。 1599年、豊臣秀吉の復興の遺命に従い、正室・北政所により金堂が再建になる。旧5月、北政所が参詣する。講堂立柱、諸堂の復興が行われる。 慶長期(1596-1615)、復興により「三院四十九坊、五別所二十五坊」と称された。 1600年、豊臣秀頼が毛利輝元を奉行として勧学院客殿の建立が始まる。狩野光信は襖絵を描く。毛利輝元は経蔵を再建する。北政所寄進の閼伽井屋が完成する。 1601年、徳川家康は、伏見城内の楼門(仁王門、旧常楽寺楼門)、三重塔(旧比蘇寺三重塔)を移して寄進した。山岡宮内郷法印道阿弥は、光浄院客殿を再建する。 1602年、毛利輝元は周防国の国清寺経蔵を移し、高麗版一切経蔵を寄進し、経蔵に納める。新鐘が完成する。旧12月、照高院を焼失する。 江戸時代、北院・中院・南院の3塔に59院、5別所に25坊があった。 1609年 、徳川秀忠は寺領を寄進する。幕府は、園城寺寺務条規・修験道法度を照高院に下す。 1612年、寺領4484石になる。十八明神社が造営される。 1616年、毘沙門堂が建立になる。 1623年、後水尾天皇は三重塔本尊として禁中御八講本尊・釈迦如来を寄進する。清涼殿の一部を食堂として移築する。 1634年、聖護院道晃、照高院道周は園城寺長吏を争う。 1637年、内裏車寄を移し、閼伽井屋にする。 1641年、聖護院道晃は「寺中諸法度」を出す。 1647年、明正天皇宮殿が移される。 1665年、4代将軍・徳川家綱は4619余の朱印状を寄する。 1673年、長吏聖護院門跡より「寺中法度之覚」として規則発布になり、江戸時代の園城寺寺規の根拠になる。 1686年、観音堂を焼失する。 元禄年間(1688-1703)、南院19、中院14、北院16を数えた。「三谷四十九院五別所二十五坊」と称された。 1689年、観音堂(現在)が再建になる。円空は、関市弥勒寺を園城寺末寺にする。 1690年、観音堂を修復再建ともいう。 1723年、義瑞は北院に法明院を開創し、寺門教学が行われた。 1788年、天明の大火により後桃園上皇(第118代)は照高院に遷幸する。 1850年、旧4月、第121代・孝明天皇は、「万民安楽、宝祚長久」の祈りを、園城寺など七社七寺に命じた。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、早尾社、三尾社、新日吉社(長等社)などが分離する。当寺の聖護院雄仁法親王は還俗した。円満院が大津県に上地され跡地に大津県庁が移転した。 1869年、円満院の殿舎、境内が上地になる。 1870年、寺門、山門、盛門三派が分裂した。 1871年、境内一部が上地になる。 1872年、修験宗を廃し、天台・真言両宗に帰入を命じらる。政所が廃止された。 1873年、9月、大津歩兵第九連隊敷地として、北院境内十町四畝三歩が上地になる。10月、北院境内地3万120坪余を上地する。 1874年、3月、旧修験寺院へ加持祈祷執行に関する布告を発せられる。5月、天台宗寺門派として分立し、末寺など600寺院、講社の総本山になる。天台宗は、寺門、山門、盛門に分かれる。6月、禁厭祈祷により医療妨害を注意布告される。10月、旧修験の無院蹟寺院名の公称を禁ぜられ、その布告を発せられる。 1875年、地租改正に伴い、境内全てが国に没収される。 1876年、園城寺南北中三院を合併し、一院制にする。 1879年、総本山園城寺住職は管長になり聖護院、円満院、実相院三室住職輪次兼帯になる。 1885年、米国人フェノロサ、ビゲローは法明院・敬徳より受戒する。 1887年、旧地が大津県より円満院に返還される。 1894年、園城寺碩室金乗院を焼失する。 1898年、寺門派勧学院が開校になる。 1902年、上地林の一部56町3反余が境内地に編入許可される。 1909年、フェノロサ(諦信)の遺骨を法明院に葬る。 1926年、金堂修復に伴い奈良時代前期(白鳳時代、645-710)の鐙瓦、軒瓦が発掘される。この地に、7世紀半にすでに寺院が存在したとみられている。 1928年、ビゲロー(月心)の遺骨を法明院に葬る。 1930年、唐院に伝法灌頂を開壇する。 1934年、台風により山内多くの倒木があり、新羅社本地堂、拝殿を全壊する。 1940年、円珍1500年大遠忌法要が営まれ、『智證大師全集』などが編纂された。 1941年、宗教団体法により、天台三派(寺門、山門、盛門)は合同し、天台宗として発足する。 現代、1946年、宗教法人令により、三派は分立し、園城寺は天台寺門宗を設立、総本山になる。聖護院が寺門宗より独立する。 1947年、観音堂庫裡、客殿を焼失する。2月、円満院は独立し無宗派単立寺院になる。 1952年、金堂が放火されるが小火にとどまる。10月、伝法灌頂が行われる。12月、国有境内地24万坪(79万3388㎡)が無償譲渡になる。実相院が寺門宗より独立した。 1953年、台風13号により倒木被害が出る。 1954年、東京「三井寺秘宝展」で黄不動尊が初めて山外に出る。 1961年、 第二室戸台風により、金堂、閼伽井屋、三重塔、一切経蔵、食堂などを被災する。 1963年、4月、三井古流煎茶道を復活する。(『煎茶道」)。8月、村雲御所書院の一部を買収し、観音堂客殿として再建する。(寺誌) 1970年、国鉄湖西線敷設のトンネル掘削工事により水源が切れ、閼伽井も断水する。 1975年、熊野大峯順峰七十五靡奥駈修行が復活する。 1978年、西大津バイパス工事に伴い、建設省は土地収用法により境内を侵害したとして園城寺は提訴した。翌年、道路は開通した。 1996年、梵鐘が環境庁「残したい日本の音風景百選」の一つに選定された。 2012年、大津市歴史博物館は三井寺(園城寺)に安置された木造地蔵菩薩坐像頭部より、室町幕府の将軍・足利尊氏か義詮の遺髪が入っているとみられる包みが見つかったと発表した。 2013年、琵琶湖疏の土地の使用権を巡る園城寺と京都市の訴訟は大阪高裁で和解した。境内地下の疏水が通る三井寺に地上部分の使用権があり、京都市は地下部分の使用権と疏水管理の権利を確保した。 ◆大友 皇子 飛鳥時代の皇族・大友 皇子(おおとも-の-おうじ、648-672)。男性。伊賀皇子。父・天智天皇。大友氏は近江国(滋賀県)滋賀郡の渡来系豪族になる。671年、初の太政大臣に任じられた。天智天皇没後、近江朝の政務をとる。天智天皇の弟・大海人皇子(おおあまおうじ、天武天皇)は吉野を脱出し、大友皇子の近江朝廷側と対立した。672年、壬申の乱で両者は皇位継承を争う。大友皇子が敗れ「山前」で自死した。文武に優れ漢詩集『懐風藻』に収められた。25歳。 1870年、天皇号が追贈された。園城寺境内の閼伽井石庭付近は、皇子の邸宅跡ともいわれている。大津市に陵墓、長等山前陵がある。 ◆大友 与多王 飛鳥時代の皇族・大友 与多王(おおとも-の-よたの-おおきみ、?-?)。詳細不明。男性。大友与多王。父・弘文天皇(大友皇子)の皇子。686年、父の菩提を弔うために、自らの田園城邑(田畑屋敷)を投げ打ち、園城寺(三井寺)建立を発願したという。第40代・天武天皇は「園城寺」の勅額を与えたという。 ◆円珍 平安時代前期の僧・円珍(えんちん、814-891)。男性。俗姓は和気、字は遠塵、諡号は智証大師。讃岐国(香川県)の生まれ。母は空海の姪に当たる。景行天皇の15代孫という。829年、15歳で比叡山に登り天台座主・義真に師事し『法華経』『金光明経』を学ぶ。19歳で天台宗年分度者になる。833年、比叡山戒壇院で菩薩戒を受け、12年間籠山行に入り学頭、内供奉に任じられる。838年、十二年籠山中に黄不動尊の示現に遭う。845年、大峯、葛城、熊野三山、那智の滝に参籠し、三井修験道の起源になる。846年、比叡山真言学頭に推される。850年、伝燈大法師位に叙せられる。853年、唐に渡る。福州・開元寺で印度那蘭陀寺の般若多羅三蔵により悉曇 (梵字)を学ぶ。温州の同寺で『法華経』などを授けられた。また、天台山国清寺で最澄の遺跡を訪ね、最澄が建立した禅林寺(天台日本国大徳僧院)を再興した。止観堂とも呼ばれ、日本の留学僧が利用した。各寺で止観(禅)、天台、密教などを学ぶ。6年後の858年、経典類441部1000巻を携え帰国する。859年、園城寺長吏になる。866年、三井寺別当職(長吏)に任じられる。四国金倉寺、比叡山の山王院に住し、868年、第5世座主になる。天台別院・園城寺(三井寺)を再興し、伝法灌頂の道場とした。唐より請来の経籍を唐坊に納める。888年、三カ条の遺誡を描き円仁門徒との親交を諭した。890年、少僧都、891年、比叡山山王院で亡くなる。78歳。 天台寺門宗の宗祖天台宗寺門派の祖。入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)の一人。弟子は500余人、教えを受けた人は3000人といわれる。没後の929年、第60代・醍醐天皇より智証大師の諡号(大師号)を贈られる。 ◆余慶 平安時代中期の天台宗の僧・余慶(よけい、919-991)。男性。俗姓は宇佐、諡号は智弁、観音院僧正。筑前(福岡県)の生まれ。園城寺・明仙(みょうせん)に師事、行誉に密灌を受けた。979 年、同寺長吏になる。981年、法性寺座主になる。円仁流の反対があり停止、山門・寺門派争いの原因になった。989年、天台座主になり、山門・寺門派の争いで3カ月で辞した。権僧正に任じられた。岩倉・観音院(大雲寺)に移る。智証大師流の興隆者。73歳。 ◆定暹 平安時代中期の僧・定暹(じょうせん、930?-?)。男性。父・藤原為時という。紫式部の異母兄弟ともいう。叡山で修行する。1002年、第66代・一条天皇の母、藤原詮子追善八講で、請僧六十口のうち聴衆二十口の一人として奉仕する。1006年以降、教静大阿闍梨より灌頂を受け阿闍梨になる。1011年、一条天皇御大葬に御前僧二十口の一人として参列する。この後、律師に任じられ園城寺林泉坊に居住した。なお、1016年、園城寺で為時は出家している。 ◆慶祚 平安時代中期-後期の僧・慶祚(けいそ、955-1020)。男性。俗姓は中原、号は竜雲坊先徳。園城寺の余慶に師事、四神足の一人になる。993年、比叡山から円珍派の門徒が追放された際、比叡山千手院を守ったが、岩倉大雲寺に移る。その後、園城寺竜雲坊に移り、天台教学興隆となった。994年、五別所の一つ微笑寺を建立した。997年、朝命を受け宋の源清が送った新書五部のうち『竜女成仏義』を批判する書を著した。1017年、円珍忌に法華十講を行う。増賀や源信にも仰がれた。65歳。 ◆明尊 平安時代中期-後期の僧・明尊(みょうそん、971-1063)。男性。円満院僧正、志賀僧正。京都の生まれ。父・兵庫頭・小野挙時。小野道風の孫。余慶、観修、慶祚らに師事した。園城寺長吏を2度勤め、円満院を創建した。1038年、大僧正、1039年、上東門院に授戒した。園城寺に戒壇創建を主張した。1048年、天台座主になるがすぐに辞職した。藤原頼通の帰依を受け、興福寺再建供養会の導師、宇治平等院の検校になる。第66代・一条天皇から園城寺唯一の八宗総博士に任じられた。歌人。志賀僧正と呼ばれた。93歳。 ◆頼豪 平安時代後期の僧・頼豪(らいごう、1002-1084)。詳細不明。男性。父・伊賀守藤原有家。園城寺の心誉に師事、円行から法を受け、実相院に住した。1074年、第72代・白河天皇の皇子誕生を修法祈願し、敦文親王が誕生した。園城寺の戒壇創設を天皇に請うが、延暦寺の反対により実現しなかった。その後、断食により絶命した。82歳。 ◆静円 平安時代後期の僧・歌人・静円( じょうえん、1016-1074)。詳細不明。男性。木幡(こはた)権僧正。父・藤原教通、母・小式部内侍。1070年、権僧正、1071年、法成寺執行。園城寺に入寺した。『後拾遺和歌集』などに収められた。59歳。 ◆隆明 平安時代後期の天台宗の僧・隆明(りょうみょう、1019/1020-1104)。男性。号は羅惹院僧正。父・権中納言・藤原隆家。明尊に師事した。白河天皇、堀河天皇の護持僧、白河上皇に授戒した。園城寺・羅惹院を創建、三室戸寺を再興する。崇福寺、梵釈寺の別当を歴任。1098年、園城寺長吏、法成寺執行職を寺門派僧に固定するよう申請した。1100年、園城寺の大衆に住房を焼かれる。長吏を甥・増誉に譲る。1102年、大僧正。85歳。 ◆増誉 平安時代後期の僧・増誉(ぞうよ、1032-1116)。男性。号は一乗寺僧正。父・権大納言・藤原経輔。6歳で園城寺で出家、大峰、 葛城山で修行した。第72代・白河天皇、第73代・堀河天皇の護持僧になる。1086年、権大僧都、1090年、白河上皇の熊野詣の先達を勤め、熊野三山検校に補され、聖護院を建立した。1100年、園城寺長吏、1105年、第39世天台座主になるが、山門派の反対で翌日辞退した。大僧正になり13カ寺別当も兼ねた。85歳。 ◆覚猷 平安時代後期の僧・覚猷(かくゆう、1053-1140)。男性。俗名は顕智、通称は法輪院僧正、鳥羽僧正。父・公卿・源隆国。園城寺・覚円に師事し、法輪院に住した。鳥羽離宮の証金剛院別当として移り、鳥羽僧正と呼ばれた。鳥羽上皇の護持僧、園城寺長吏、天台座主を歴任した。画僧として京都・勝光明院扉絵を手掛ける。「鳥獣戯画」などの作者ともいう。密教の白描図像を研究し、収集図像は「法輪院本」と呼ばれた。88歳。 ◆覚忠 平安時代後期の僧・覚忠(かくちゅう、1118-1177)。詳細不明。男性。京都の生まれ。父・公卿・ 藤原忠通。園城寺・増智に師事。後白河上皇(第72代)出家の際の戒師をつとめた。1162年、天台座主、1164年、大僧正、園城寺長吏。歌人としても知られた。勅撰集『千載和歌集』に入集。60歳。 ◆行尊 平安時代後期の僧・行尊(ぎょうそん、1055-1135)。男性。通称は平等院大僧正。第67代・三条天皇の曾孫、参議・源基平の子。12歳で出家し、園城寺に入る。大峰山で修行し、25歳で頼豪から阿闍梨灌頂を受けた。第74代・鳥羽天皇の護持僧になり、園城寺長吏、大僧正に任じられた。書、琵琶、和歌に優れ「小倉百人一首」に入集した。81歳。 ◆円暁 平安時代後期-鎌倉時代前期の僧・円暁(?-? )。詳細不明。男性。母・源為義の娘。弟・尊暁。園城寺に入る。1182年、源頼朝は、円暁を招いて鎌倉鶴岡八幡宮の初代別当とした。 ◆公暁 鎌倉時代前期の僧・公暁(くぎょう、1200-1219)。男性。幼名は善哉。父・2代将軍・源頼家。父が将軍職を廃され、鶴岡八幡宮寺別当・尊暁の弟子になる。1206年、将軍源実朝の猶子になる。1211年、落飾し公暁と称した。園城寺で修行し、1217年、鶴岡八幡宮寺の別当になる。1219年、実朝の右大臣拝賀儀式の直後、父の敵として実朝と剣役の源仲章を殺害する。だが、雑賀定景により殺害され源氏は滅んだ。20歳。 ◆道元 鎌倉時代前期-中期の曹洞宗開祖・道元(どうげん、1200-1253)。男性。号は希玄(きげん)、字は仏法房、諡号は仏性伝東国師、承陽大師。父・内大臣源(土御門)通親、母・太政大臣・藤原(松殿)基房(もとふさ)の三女・伊子(いし)の間に生まれた。誕生地は、宇治木幡の松殿家山荘という。その後、久我の地に引き取られたとみられる。1203年、父を亡くす。1207年、母を亡くした。1208年、叔父・師家は、松殿家の養子に迎え入れようにするがそれを断る。1212年、母の弟・比叡山延暦寺の良観法印の庵に入り、横川般若谷、千光谷に住した。1213年、座主・公円のもとで菩薩戒を受ける。1214年、比叡山を下り、園城寺の母方縁者・公胤(こういん、47世長吏)の門を敲く。公胤の勧めにより1217年、臨済宗の建仁寺に移り栄西、その高弟・明全に学ぶ。1223年、師・明全と共に宋に渡る。天童山・景徳寺で無際了派に学ぶ。杭州、台州を遍歴した。1225年、明全が亡くなる。曹洞宗・長翁如浄に師事し曹洞禅を学んだ。1227年、如浄の法統を得て帰国、1228年、建仁寺に入る。建仁寺で日本初の坐禅儀『普勧坐禅儀』を書く。禅は釈迦の正法としたため、比叡山衆徒による迫害を受け、1230年、深草・安養院に閑居する。1233年、深草・極楽寺に修行道場の観音導利院(後の興聖宝林禅寺)を建立する。天台宗の圧力はやまず、1243年、越前に逃れ、1244年、大仏寺(後の永平寺)を開いた。1247年、鎌倉幕府執権・北条時頼に請われ下向、1252年、病になり、翌年、京都の俗弟子・覚念の邸で亡くなったという。54歳。 道元は、無限の修行を成仏の本質にする「修証一如」、坐禅に打ち込むことこそが最高の修行にする「只管打坐」(しかんたざ)などを唱えた。6篇の禅院での修道規則「永平清規」も定めた。仏法の正門は座禅にあるとした『正法眼蔵』95巻(1230-1252)を著した。 ◆心敬 室町時代前期-中期の連歌師・心敬(しんけい、1406-1475)。男性。初名は連海、心恵。紀伊国(和歌山県)の生まれ。京都で仏門に入り、園城寺に入寺、権大僧都、十住心院住持になった。1429年頃から、清巌正徹に師事し和歌を学ぶ。1433年、北野万句に連海法師の名で参加し、連歌師の活動を始める。1463年、紀伊で連歌論『ささめごと』を著した。1467年、伊勢へ下向、その後、武蔵国に移る。1471年より、相模国に隠棲した。70歳。 ◆道阿弥 室町時代後期-江戸時代前期の武将・僧の道阿弥(どうあみ、1540-1604)。男性。法名は暹慶(せんけい)。父・守護六角氏家臣の山岡景之の4男。常陸古渡藩初代藩主。園城寺光浄院の僧侶になり、暹慶(せんけい)と号した。第15代将軍・足利義昭に従い、1571年、幕臣になる。1572年、義昭の命で還俗し山岡景友と名乗り、山城半国の守護に任じられた。信長と義昭の戦いでは義昭に従う。1582年、本能寺の変後、明智光秀軍と戦い、小牧・長久手の戦い、文禄の役、関ヶ原の戦いにも加わる。後に再び剃髪し道阿弥と号した。62歳。 ◆狩野 光信 室町時代後期-江戸時代前期の狩野派の絵師・狩野 光信(かのう-みつのぶ、1565/1561-1608)。男性。幼名は四郎次郎、源四郎、右京進。父・狩野永徳の長男。織田信長に仕え、父・永徳とともに安土城の障壁画を描く。豊臣秀吉にも仕えた。1590年、狩野派の指導者になる。肥前国名護屋城、伏見城などの障壁画を作成した。大和絵の手法を取り入れ、優美繊細な画風を確立し、花鳥画に優れた。長谷川派との親和を図り、風俗画にも取り組む。遺作は少ない。当寺に障壁画がある。44/48歳。 ◆嘉言 親王 江戸時代後期の僧・嘉言 親王(よしこと-しんのう、1821-1868) 。男性。幼称は巍宮、法名は雄仁。父・邦家(くにいえ)親王の王子。1831年、聖護院の盈仁(えいにん)入道親王の弟子になる。第119代・光格天皇の養子になる。1832年、親王になり得度した。園城寺153代長吏になる。後に聖護院門跡になった。1868年、還俗し内国事務総督、海軍総督などを勤めた。48歳。 ◆関わりある僧 円珍が唐から持ち帰った多数の文献があることから、多くの僧が寺を訪れている。平安時代-鎌倉時代の臨済宗の開祖、建仁寺の開山の栄西(1141-1215)。鎌倉時代の臨済宗聖一派派祖、東福寺開山の聖一国師円爾弁円(1202-1280)。日本曹洞宗の開祖、大佛寺(永平寺)開山の道元(1200-1253)。日蓮宗(法華宗)の宗祖、久遠寺開山の日蓮(1222-1282)などがいる。 室町時代中期、1465年、延暦寺衆徒による大谷の本願寺破却後、蓮如は一時近江に逃れた。室町時代後期、1469年、蓮如は、園城寺南別所近松寺内に顕証寺を建立し、親鸞影像を安置した。1471年、北陸吉崎に移り、近松別院は順如に託した。観音堂に蓮如作という「六字名号」がある。 江戸時代の行脚僧・円空(1632?-1695?)は、江戸時代前期、1689年に寺を訪れている。再興した弥勒寺(関市)を園城寺の末寺にするために師・日光院大僧正尊栄を訪れた。この時、8体(1体は付随)の仏像を刻み園城寺経蔵に残した。 ◆本尊・仏像・画像・神像・肖像 ◈秘仏「黄不動尊画像」(国宝)は、円珍が平安時代前期、838年に石龕(せきがん、岩室)中で坐禅して感得した金色の不動明王を描かせたという。(三善清行著『智証大師伝』)。ただ、唐の図像を手本としたともいう。「金色不動明王」ともいい、全身が黄土色で塗られているため、江戸時代より「黄不動」とも呼ばれた。螺髪(らほつ)で、両眼を見開き、火焔頭光、両足で踏ん張り、真正面に虚空上に立つ。全身を肉瘤で盛り上げ、右手に剣、左手に羂索を持つ。「日本三大不動」(ほかに京都・青蓮寺の青不動、高野山・明王院の赤不動)の一つに数えられる。なお、京都・曼殊院などに伝わるのは模写像であり、磐座上に立つ。 ◈本堂(金堂)には、本尊の秘仏「弥勒菩薩」が安置されている。『寺門伝記補録』によると、身丈三寸二分(像高9.7cm)の弥勒菩薩という。第38代・天智天皇の念持仏だったという。「三国伝来の霊仏」といわれ、かつて中国天台宗の高祖慧思禅師が修行中に降臨し、自らの分身として残した。像は常に光を放ち全身が温かく、「生けるがごとし」霊仏であったという。百済より第31代・用明天皇(在位:585-587)の時に渡来したという。今日まで、一度も開扉されていない。 ⋄ほかに、第33代・推古天皇、第45代・聖武天皇、第57代・陽成天皇、藤原鎌足、藤原道長、行基菩薩が奉納した6躯の「弥勒菩薩」が安置されている。金堂安置の木造漆箔「大日如来坐像」は、平安時代後期作で智拳印を結ぶ。像高94.9㎝。 ◈唐院大師堂に安置の木造「金色不動明王立像」(重文)は、「黄不動尊画像」(国宝)を立体的を模した。鎌倉時代(13世紀)作。 ⋄木造「智証大師坐像(中尊大師像)」(国宝)が厨子内に安置されている。10世紀作になる。かつて円珍が住坊、比叡山の山王院に安置していたという。平安時代中期、993年の慈覚大師門徒との抗争の際に比叡山から遷された。卵形の円珍頭、彩色、ヒノキ材、像高84.2cm。 ⋄中尊大師像の左脇に祀られている木造「智証大師坐像(御骨大師)」(国宝)は、胎内に大師の舎利(遺骨)を納める。平安時代前期作になる。 ◈三重塔一層目の須弥壇には、木造「釈迦三尊像」が安置されている。 ◈微妙寺に木造彩色「十一面観音立像」(重文)を安置する。平安時代(9世紀、10世紀とも)作で、園城寺別所の尾蔵寺旧本尊という。また、かつて志賀寺の霊仏で第38代・天智天皇の念持仏という。参拝者が多数押しかけて人々の笠が破れたことから「はずれ笠の観音」「笠ぬげの観音」と呼ばれた。湖国十一面観音霊場第一番札所の本尊として、土・日・祝日のみ開扉されている。 裳は朱彩、截金の花文も残る。ヒノキの一木造、台座の蓮肉も同じ材による。像高81.8cm。 ⋄木造「千手観音立像」(重文)は、平安時代(9世紀、10世紀初頭とも)作になる。唐風を一部に残す。かつて如意ヶ岳の南にあった園城寺別院の如意寺の本尊とされる。「園城寺境内古図」五幅の一幅に描かれている。台座の蓮肉まで一材による一木造。像高180.3cm。 ⋄木造彩色の「不動明王坐像」(重文)は、平安時代後期、1014年作になる。仏師僧・盛忠作になる。像底から内刳りし別材製の底板を当てた。迦陵頻迦の舟形光背の大部分と台座の最上段も当初のものになる。雄曼荼羅様、両手までサクラの一材、像高39.1cm。 ◈護法善神堂の左脇に安置の木造彩色「訶梨帝母倚像(かりていもいぞう)」(重文)は、鎌倉時代(13世紀前半)作になる。円珍に教法守護を約束したという伝承がある。榻座(とうざ)に坐し宋風の衣に右手に柘榴を持ち、左手に幼児を抱く、半跏の鬼子母神、智証大師の護法神。ヒノキの寄木造、玉眼、像高43.9cm。 ⋄護法善神堂の安置の本尊である木造彩色「護法善神立像」(重文)は、平安時代(12世紀)作。智証大師が5歳の頃と入唐後にその姿をあらわしたという訶梨帝母という。円珍自刻ともいう。右手は垂下、左手に柘榴(吉祥果)を持ち、唐風の衣裳を纏う。足元の愛子像は後補。ヒノキの一木造、彩色、像高159.1cm。 ⋄木造彩色「吉祥天立像」(重文)は、鎌倉時代(13世紀前半)になる。宋風衣に右手は垂下、左手には宝珠、ヒノキによる寄木造、玉眼 像高67.6cm。 ◈観音堂に本尊「如意輪観世音菩薩」(重文)を安置する。10世紀末の作とされ、一面六臂、円珍自刻ともいう。西国三十三箇所観音霊場の第14番礼所になる。 ⋄観音堂の脇侍の木造彩色「愛染明王坐像」(重文)は、平安時代(12世紀後半)作になる。ヒノキの寄木造、像高92.1cm。 ⋄観音堂に「毘沙門天像」を安置する。 ⋄観音堂の「智証大師坐像」(重文)は、鎌倉時代作になる。大師を慕う弟子により肖像を模刻して造られた。かつて南院勧学院持仏堂に安置されていた。祇支(袈裟下の衣)、袈裟に禅定印、木造彩色結跏趺坐、ヒノキ材の一木彫り、像高39㎝。 ◈観音堂百体堂に本尊の「如意輪観音像」を安置する。右に坂東三十三箇所、左に秩父三十四箇所の本尊、百体の観音像を安置する。 ◈「円空仏七体」は、一切経蔵の天井から発見された。江戸時代作になる。 火難除けの木造「善女龍王像」がある。 ◈御廟に「円珍像」(国宝)が2体ある。円珍の遺命により造られ、遺骨が納められた。園城寺唐坊と延暦寺の千手院に安置された。その後、円仁、円珍の対立により、唐坊に遷されたという。(『寺門伝記補録』)。ヒノキ材、一木造、彩色、像高85.1cm。 ◈教待堂に、「教待和尚の御像」を安置する。教待和尚は智証大師円珍入山まで当寺を護持していたという。大師をこの地に迎えるとともに、石窟に入り姿を隠したという。のちに大師はこの石窟上に一宇を建てその廟にした。石段は今も和尚像を安置する須弥壇の真下にあるという。昔から当寺の僧が出家の際に、その落髪を窟内に納める伝統があるという。 ◈神変行者堂に、「神変大菩薩(役小角)」、「不動明王」(右)、「智證大師」(左)を安置する。本山採灯大護摩供(7月22日)が行われている。 ◈護法善神堂・千団子社の本尊に「護法善神立像」(重文)を祀る。鬼子母神(訶梨帝母、かりていも)を祀り、「千団子さん」とも呼ばれる。 帝母は王舎城の夜叉神の娘で、結婚し千人の子を産んだ。だが、近隣の幼児をとって喰らい人々に恐れられた。釈迦は、その過ちを改めようと帝母の末の子を隠した。我が子を失った帝母の悲しみは深く、釈迦は、「千人のうちの一子を失うもかくの如し。いわんや人の一子を食らうとき、その父母の嘆きやいかん」と戒めた。以後、帝母は行い改め、釈迦に帰依した。その後、婦女子の守護神になり、安産・子育の神とした崇敬された。 千団子祭(5月16日-18日)では、千人の子らの供養のために千の団子を供え、子どもの無事成長、安産を祈願する。堂前の放生池に霊亀を放する。本尊も開帳される。 ◆建築 ◈「大門(仁王門)」(重文)は室町時代中期、1452年/1451年)に建立された。かつて天台宗の甲賀の常楽寺(西寺、湖南市石部町)の門であり、豊臣秀吉によって伏見に移された。さらに安土・桃山時代、1601年に徳川家康によって現在地に建てられたという。 組物に彩色がある例は少ないという。 蟇股、木鼻、斗栱(ときょう)の三手先などに室町時代の特徴がある。三井寺中院の表門、鎌倉時代の仏師・運慶作という仁王像を安置する。三間一戸楼門、入母屋造、檜皮葺。 ◈「釈迦堂(食堂、じきどう)」(重文)は、室町時代初期に建立されたとみられている。安土・桃山時代、1595年、豊臣秀吉による破却の後、江戸時代前期、1623年に清涼殿を移築したともいわれる。詳細は不明。かつては食堂として使われていた。現在は、清涼寺式釈迦如来像を本尊として安置する釈迦堂になっている。 周囲1間通が廂、化粧屋根裏。正面、脇に縁。正面一間が開方、扉口は両端間のみにある。5間2間が内陣、猿頬天井。須弥壇には精巧な透かし彫りの彫刻がある。唐破風の向拝は江戸時代、文政年間(1818-1829)に後補された。7間4間、一重、入母屋造、檜皮葺。 ◈「金堂(本堂)」(国宝)は、安土・桃山時代、1599年に建立された。豊臣秀吉の正室北政所によって再建された。 密教天台系内陣になっており、外陣(前3間通り)・内陣(5間3間、左右に脇陣)・後陣(背面3間通り)に別れ、内両側に脇陣を設けている。内外陣は格子戸、扉で仕切る。内陣の床は一段下げた四半瓦敷(土間)、それ以外の前後2間両側1間は板敷(床張り)になる。天井は組入れ天井が主。内外陣正面に両開き板扉、菱格子欄間、引違格子戸。本尊の秘仏・弥勒菩薩を安置する。手挟に雲、菊、蓮、迦陵頻迦などの彫刻がある。二手先、軒天井、支輪、尾垂木もないのが特徴という。 7間7間(23.21m、23.17m)、一重、入母屋造、正面に3間の向拝付、檜皮葺。 ◈「閼伽井屋」は、安土・桃山時代、1600年に建立された。三井の霊泉(重文)の覆屋になる。覆屋正面上部に江戸時代の彫り物の名手と謳われた職人・左甚五郎作という龍の彫り物がある。かつて、この龍が夜な夜な琵琶湖に出て暴れたという。左甚五郎は龍の眼に五寸釘を打ち込みこれを鎮めたという。左甚五郎は実在したという説と否定する説がある。個人ではなく集団ともいう。各地に多くの作品と伝承を残している。 両開き格子戸、両側に嵌殺し格子戸、正面と両側面に花狭間欄間。三斗。3間2間、一重、正面に向いた向唐破風造、檜皮葺。 ◈「光浄院客殿」(国宝)は、室町時代に山岡氏によって建立された。秀吉の破却後、山岡道阿弥が、安土・桃山時代、1601年に再興した。 外観は、勧学院客殿とほぼ同じになっている。上代の寝殿造の流れをくむ初期の主殿造といわれる書院造になっており、双方の特徴がみられる。妻度、蔀戸、舞良戸、東に唐破風車寄、東南に中門廊、南に広縁、落縁などが見られる。間取りは南北6列、東西3列の6室になる。角柱、上座の間(主室)に床、違棚、帳台構、彩色の襖、ここにしか見られない一之間の付書院が広縁に張り出している。また、出書院がある。一之間、二之間には狩野派による障壁画ある。(非公開) 7間6間、一重、入母屋造、妻入、正面軒唐破風付(貴賓出入口)、総杮(こけら)葺。 ◈「勧学院客殿」(国宝)は、鎌倉時代、1312年に房海僧正により学問所として創立された。その後、火災や秀吉の破却後、安土・桃山時代、1600年に毛利輝元により再建された。 光浄院に見られた上段の間小室を欠く。南列の一之間と広い二之間には狩野光信の障壁画がある。鎌倉時代の石造宝塔(重美)がある。 7間7間、一重、入母屋造、妻入、正面軒唐破風付、総杮(こけら)葺。室内は3列3行の9室、(非公開)。 ◈「唐院」は、開祖・智證大師円珍の廟所になっている。円珍が唐より持ち帰った経典をここに納めたことから唐院という。平安時代前期、858年、円珍が唐より持ち帰った経典や法具を、868年に内裏の仁寿殿を移築して納めた。以後、伝法潅頂の道場になる。かつて大門南にあり、安土・桃山時代、1598年に現在地に再建された。 四脚門、灌頂堂、唐門、大師堂、長日護摩堂などが建つ。参道の石段の両脇に歴代の探題によって奉納された石造灯篭が並んで立つ。 ◈唐院の「大師堂」(重文)は、灌頂堂の背後に建てられている。安土・桃山時代、1598年に建立された。 面取方柱に舟肘木、疎垂木。二体の智証大師坐像(中尊大師・御骨大師)(国宝)、黄不動尊立像(重文)の三体が安置され御廟になっている。3間2間、一重、宝形造、檜皮葺。 ◈唐院の「唐門」は、安土・桃山時代-江戸時代前期の慶長期(1596-1615)に建立された。1間1戸、向唐門。 ◈唐院の「潅頂堂」(重文)は、江戸時代前期、1629年に建立された。大師堂の東(前)に建ち拝殿になっている。方柱、舟肘木、桟唐戸、半蔀戸。側面背面に腰高障子、舞良戸。内部は前室(5間4間)・折上小組格天井と後室(5間1間)・棹縁天井があり、寺流の密教、唐ノ坊灌頂、伝法潅頂伝承の道場になる。5間5間、一重、入母屋造、檜皮葺、正面に唐破風、縁付き。 ◈唐院の「長日護摩堂」(県指定文化財)は、江戸時代の第108代・後水尾天皇の祈願により建てられたという。本尊は不動明王を安置する。長日護摩供を修する道場になる。 灌頂堂とは渡り廊下でつながる。正面は桟唐戸、両脇を連子窓、側面の正面寄りに舞良戸、ほかは横羽目板壁。3間3間、一重、宝形造、本瓦葺。 ◈唐院の「三重塔」「塔婆」(重文)は、鎌倉時代末-室町時代初期に建立されたと見られている。かつて大和・比蘇(比曾)寺の塔であり東西2塔あったという。安土・桃山時代、1597年、豊臣秀吉によって東塔が伏見城に移築された。1600年/1601年に徳川家康が園城寺に移築寄進した。一層目の須弥壇には、木造・釈迦三尊像が安置されている。 二重、三重、中の間に菱格子。初重天井は折上小組格天井。3間3間、三重塔、本瓦葺。 ◈「一切経蔵」、内部の「八角輪蔵」(重文)は、室町時代に建立された。もとは戦国大名・毛利氏との関わりがある禅宗寺院国清寺(山口市)の経蔵で、室町時代初期に建立されたとみられている。安土・桃山時代、1602年に毛利輝元によって境内に移築された。 四方は明層といわれる明り取りの窓があり、高い位置から蔵内に採光している。鏡天井、極彩色の天井画が描かれている。波形連子の欄間、蟇股、三手先、花灯窓、桟唐戸、大疎垂木などが見られる。3間3間、一重、裳階付の重層宝形造、檜皮葺。禅宗様の堂。身舎は1間1間。 高麗版一切経(大蔵経版木)を納める回転式の巨大な八角輪蔵(回転書架)がある。上部は鏡天井、八角八柱造、八方に三角形の千鳥破風。内部、天井絵は極彩色になる。 ◈「毘沙門堂」(重文)は、江戸時代前期、1616年に、園城寺五別所の一つ尾蔵寺(びぞうじ)の南勝坊境内に建立されたとみられている。近代以降、1909年に三尾社の下に移築された。さらに、現代、1956年の解体修理の際に現在地に移された。 正面に花狭間入桟唐戸、側面に堅板の板壁。三斗、蟇股、木鼻。1間2間、一重、宝形造、檜皮葺。極彩色の唐様式。 ◈「鐘楼」(重文)は、下に腰板上は連子になる。1間2間、一重、切妻造、檜皮葺。 「梵鐘(三井の晩鐘)」(重文)(県文化財)がある。 ◈「観音堂」(県指定文化財)は、高台にある。かつて、観音堂は聖願寺、正法寺とも呼ばれ、長等山(ながらやま)山上近くの華の谷にあった。平安時代後期、1072年に第71代・後三条天皇の病気平癒を祈願し、その命により一宇が建立され、本尊の観音像を安置したという。「聖願寺」の勅額を与えられた。1161年、覚忠は「二二番如意輪堂」と記しており観音堂とみられている。(『寺門高僧記』)。 山上にあるため参詣の道が険しく、女人結界になっていた。室町時代、1477年3月のある夜、寺中の僧たちに夢告があった。一人の老僧が現れ、華の谷に住まう者という。いまの堂の場所では大悲無辺の誓願を達成できない。山を下りて衆生を利益したいと告げた。その後、1481年に現在地に遷されたという。(『寺門伝記補録』)。江戸時代前期、1686年に焼失し、1689年に再建された。 本尊は如意輪観世音坐像(重文)を安置する。円珍が自ら刻んだという。33年に一度開帳される。脇侍は愛染明王像(重文)、毘沙門天像になる。西国三十三箇所観音霊場の第14番礼所になる。絵馬が奉納され、観音堂再建の様子を描いた「石突きの図」、「落慶図」などが掲げられている。 礼堂、合の間、正堂からなる。礼堂は9間5間、二重、合の間、入母屋造、本瓦葺。側廻りに面取角柱に舟肘木をのせ、漆喰の壁。柱、虹梁に極彩色。 正堂、礼堂の間に化粧屋根裏の合の間があり、それらを複合して繋いでいる。正堂は3間2間、一重、入母屋造、檜皮葺。 ◈「観音堂百体堂」(県指定文化財)は、高台にある。江戸時代中期、1753年に創建された。3間2間、宝形造。 ◈「観音堂の観月舞台」(県指定文化財)は、高台にある。江戸時代後期、1849年に建立された。1間1間、一重、入母屋造、檜皮葺、懸造(舞台造)。 ◈「鐘楼」(県指定文化財)は、高台にある。江戸時代後期、1814年に上棟された。南院札所伽藍の一つになる。尾垂木はなく、三手先で中備は蟇股、蓑束で飾る。腰組も三手先、簀縁、高欄付。3間2間、袴腰付、入母屋造、檜皮葺、総ケヤキ造。 ◈「地蔵堂」(市指定文化財)は、江戸時代中期、1819年に建立された。中坂世継地蔵堂とも呼ばれている。 ◈「護法善神堂・千団子社」(市指定文化財)は、江戸時代中期、1727年に建立された。鬼子母神(訶梨帝母、かりていも)を祀り、「千団子さん」とも呼ばれる。 ◆寺院 ◈「宝寿院」には、三井古流煎茶道本部が置かれている。金堂傍の「三井の霊泉」は、天下の名水として知られていた。江戸時代後期、文化文政の頃(1804-1843)、壷井軒という老居士が境内に住していた。霊水を汲み金堂の本尊・弥勒菩薩に献茶することを日課とし、参詣の善男善女に茶を頒っていたことを起源にするという。 ◈「微妙寺」は、平安時代中期、994年に慶祚大阿闍梨(955-1020)により創建された。本堂は江戸時代中期、1776年に建立された。園城寺五別所の一つになる。 ◈「水観寺」(県指定文化財)は、平安時代後期、1040年に明尊大僧正によって創建された園城寺の五別所寺院の一つになる。現代、1988年に現在地に移築された。江戸時代前期、1655年に再建された。4間5間、一重、入母屋造、杮(こけら)葺。 本尊の薬師如来は、西国薬師霊場第四十八番札所。 ◆鎮守社 ◈「早尾社」は、常在寺近くにあり土着神になる。ご神体は千石岩になる。近代、1868年に分離独立した。 ◈「三尾社」は、土着神になる。近代、1868年に分離独立した。 ◈「長等神社」は、新宮大明神、大権現、新山野有王、新日吉と呼ばれた。かつて、長等山の岩座谷に祀られていたという。飛鳥時代、667年の第38代・天智天皇の大津宮遷宮の際に、新都の鎮守社として祀られた。近代、1868年に分離独立した。1882年に長等神社に改められた。 ◈「弁才天社」は、食堂近くにある。江戸時代前期、1683年に建立された。弁財天を祀る。 ◈「熊野権現社」は、金堂の西にある。平安時代前期、845年、円珍が大峯、熊野三山に入り修行を行ったことに因み、平安時代末期、1159年、熊野権現をこの地に勧請した。三井修験の鎮神として祀られている。現在の社殿は江戸時代後期、1837年の再建による。 ◈「ねずみの宮(十八明神)」は、「ねずみの宮さん」と呼ばれる。社は、ねずみの霊を祀り、北の比叡山を向いているという。 平安時代、第72代・白河天皇(在位:1073 -1087)の時、当寺の頼豪阿闍梨に皇子降誕祈誓の勅命があった。その祈祷の験があり敦文親王(1075-1077)が生まれた。その褒美として天皇より、園城寺念願の戒壇道場建立の勅許を得た。だが、比叡山山徒の強訴により勅許が取り消される。また、天皇は山門、寺門の間の対立を危惧して許可しなかった。頼豪は怒り、遣わされた知恵者・大江匡房に、約束を果たさなかった天子の皇子も道連れにするといい、21日間の護摩を焚き壇上で亡くなったという。また、絶食により果てたという。その怨霊は八万四千の鉄鼠と化し比叡山へ押し寄せた。鼠は堂塔や仏像経巻を喰い荒らしたという。さらに、敦文親王は4歳でその祟りにより夭逝したという。(『平家物語』『太平記』、曲亭馬琴『頼豪阿闍梨恠鼠伝』) ◆庭園 ◈閼伽井石庭は、閼伽井の北隣にある。日本最古の石庭という。東海中にある蓬莱山を石組で表したという。仙人棲み不老不死の霊山を、中央に人物、神仏、鶴、亀に見立てた石で組まれている。なおこの地は大友皇子の邸宅跡ともいわれている。 ◈「光浄院庭園」(名勝、史跡)は、安土・桃山時代、1601年頃作庭されたとみられている。池泉観賞式庭園は、客殿南縁の柱が護岸石の上に建ち、建物と庭園が一体化している。池には石橋を架けた亀島、石橋、夜泊石風の浮石、枯滝の石組みがある。ツツジ・サツキ、山腹にはスギ・ヒノキ・マツなどの植栽がある。池庭の作庭は、庭の作庭以前という。 ◈「善法院庭園」(名勝、史跡)は、安土・桃山時代の作庭による。 安土・桃山時代とみられる勧学院庭園は、池を中心に後の改修が行われているという。池に浮石、石造物が据えられている。鎌倉時代末頃の宝塔は、笠石が平面三角形になる。「是より於くへ女人きんせ以」と刻まれた江戸時代の角柱碑は、かつて門前に立てられていたものが移された。スギ・ヒノキの大木やアシビ・ツツジ・サツキなどの植栽がある。 ◈「普賢堂庭園」は、江戸時代の池泉観賞式庭園になる。客殿の南側に、長等山を借景としている。正面に饅頭形の築山、右手奥に枯滝の石組、手前に三日月形の池があり池中に浮石、各所に多数の立石やツツジの植込みなどを配した。 ◆梵鐘 園城寺の鐘は「日本三銘鐘」の一つであり、「音(声)の三井寺」として知られている。園城寺には3口の梵鐘がある。 ◈霊堂の「梵鐘(弁慶鐘、弁慶引摺鐘)」(重文)は、奈良時代作という。初代の梵鐘になる。「日本三銘鐘」(宇治平等院、高雄神護寺)の一つに数えられる。また、「日本の残したい音百選」の一つになる。円珍入山以前の遺品とされ、最上部の龍頭と直角で比較的高い位置に十二葉素弁蓮華文の撞座(つきざ)がある。外に張り出さない最下部の縁の駒の爪がある。突起物の乳の数は5段7列になる。鐘身に傷や欠損があり弁慶引摺鐘と呼ばれている。『寺門伝記補録』中に、鎌倉時代中期、文永年間(1264-1275)/1264年、比叡山衆徒に鐘が持ち去られた際の損傷という。3年後に幕府の命によって返却された。また、俵藤太秀郷が三上山の百足退治の礼に、竜宮から持ち帰り寺に寄進したとの伝承がある。山門により延暦寺に持ち去られた際に、弁慶が鐘を奪い比叡山に引き摺り上げて撞いたところ、「いのー、いのー(帰りたい、帰りたい)」と響いたため、弁慶は怒り鐘を谷に落としたともいう。霊堂の「弁慶の引き摺り鐘」は、当寺の初代の梵鐘で、奈良時代作という。 「さざ浪や三井の古寺鐘はあれどむかしにかへる音はきこへず」と、三井寺法印定円に詠まれた。 東大寺の鐘に匹敵する屈指の大きさという。銅鋳造一口、総高199.0cm、身高156.0cm、口径123.2cmある。 ◈「梵鐘(三井の晩鐘)」(重文)(県指定文化財)は、安土・桃山時代、1602年、長吏・准三宮道澄により、「弁慶の引き摺り鐘」の後継として新鋳造された。近江八景の一つ「三井の晩鐘」で知られている。「日本の三銘鐘」の一つ、「音の三井寺」といわれ、現代、1996年、環境庁の「残したい日本の音風景100選」に選定された。 乳が一区内5段5系列の100個と、上の上帯内部の8個を合わせ煩悩の108個あり、乳のある在銘最古の遺品とされている。銅鋳造一口、総高208.0cm、身高155.2cm、口径124.8cm、重量は225㎏。 ◈高麗時代、1032年の「梵鐘(朝鮮鐘、慶尚北道)」(重文)は、戦前には旧国宝に指定されていた。かつては金堂に置かれた。上部の龍頭は単頭で円筒形の旗挿(はたさし)という円筒がつく。十弁蓮華文の撞座、乳郭、3段3列の乳、上下帯、飛翔する天人像を浮彫りがある。下方の銘区に銘がある。銅鋳造一口、総高77.2cm、身高57.8cm、口径50cm。 ◆鐘の伝承 寺には、鐘にまつわるいくつかの伝承が残されている。 ◈霊堂の「弁慶の引き摺り鐘」についての逸話がある。 平安時代中期、承平年間(931-938)に、武将・田原藤太秀郷が三上山の百足退治の礼として、琵琶湖の龍神より贈られた十種宝器の一つとされる鐘を寄進したという。その後、山門との争いで弁慶が奪い、比叡山へ引き摺り上げたという。撞くと「いのー、いのー(帰りたい)」と響いた。弁慶は怒り、鐘を谷底へ投げ捨ててしまう。鐘にはその時の傷痕や破目などが残ったという。 ただ、実際には鎌倉時代中期、1264年、園城寺での戒壇建立に対し、比叡山山徒が園城寺を焼き、梵鐘を比叡山に持ち帰った。この移動の際に生じた損傷といわれている。(『寺門伝記補録』) ◈寺の変事に、前兆として鐘に不可思議な現象が生じた。鐘が汗をかき撞いても鳴らず、吉事には自然に鳴るとされた。南北朝時代、建武の争乱時(1334-1336)には、梵鐘の略奪を恐れ鐘を地中に埋めたという。だが、自ら鳴り響き、足利尊氏軍が勝利したという。 安土・桃山時代、1592年7月、突然に鐘音が鳴らなくなったことから、僧侶たちは大般若経を転読する。8月になりようやく鳴るようになった。(『園城寺古記』)。なお、この3年後の1595年、豊臣秀吉の命により、園城寺の弥勒堂は比叡山延暦寺の西塔に移された。秀吉は園城寺に闕所(廃絶)の命を下し、堂塔は破却され、寺領も没収されている。 ◈観音堂鐘楼内の現在の梵鐘は朝鮮鐘を写した。鐘にまつわる奇妙な話がある。かつて鐘は、「童子因縁之鐘」と呼ばれ、この鐘楼内に吊られていた。 この鐘の鋳造に際して僧たちは、勧進のために大津の町を托鉢したという。僧は山麓、尾花川のとある富豪の家に立ち寄る。家の主は吝嗇家で知られ、何かと噂のある人だった。家人は金子などないといい放ち、子どもが沢山いるので代わりに子を何人でも寄進しようと悪態をついた。 僧たちはその申し出を受け入れるわけにもいかず、そのまま帰った。後日、梵鐘が完成すると、不思議なことに鐘に3人の子の遊ぶ姿が浮かび上がっていた。その日、家の子ら3人が行方知れずになる。さすがにその家の主も、以後心入れ替え、慈悲深い人になったという。 その鐘は、第二次世界大戦の際の金属供出で失われた。現在の鐘は朝鮮鐘を写したものになる。一枚の写真のみが残されている。その鐘身の草ノ間には、3人の子どもが互いに向き合い花を捧げ、遊ぶ様子が半肉彫りされている。 ◈琵琶湖の畔に一人の貧しい若者が住んでいた。ある時、殺されかけている蛇を見かけ、その命を救い湖に逃がしてやった。その夜、若者の家を訪ねた若い娘がいた。娘はそのまま家に住みつき、やがて2人は夫婦となり妻は子を身ごもった。妻が、産小屋で赤子を産み落とした時、夫は心配のあまり小屋に入る。すると化身した龍(大蛇)が喘いでいた。龍の姿を見られた妻は、乳呑児を残して湖に還っていった。 龍は、残された我が子が無事に育つようにと玉を与えていた。子はこの玉を吸って育つ。ある時、地頭に玉を奪われる。困り果てた夫が乞うと、龍は乳の代わりにと、くり貫いた自らの二つの目玉を差し出した。そのため龍は盲目になり、子の成長する姿を二度と見ることができなかった。 龍は、夫に寺に鐘を寄進し、鐘を毎日撞いて子の無事を知らせてくれるようにと頼んだ。また、除夜の鐘はできるかぎり多く撞くようにと頼んだ。以後、園城寺では除夜の鐘に、龍神を慰めるために龍の眼に因んだ目玉飴を供える。以来、108つに限らず、できるだけ大勢の人々が多くの鐘を撞くようになったという。 ◈室町時代の世阿弥元清の謡曲「三井寺」には、三井寺の鐘楼、梵鐘が登場する。 駿河国清見ヶ関の女が、京の清水観音に参籠した。人買いに連れ去られ、いまも行方知れずの我が子、千満丸との再会を祈願するためだった。母は霊夢を得て三井寺へ向かう。仲秋の名月の夜であり、三井寺の鐘の音に惹かれ、鐘楼に上がる。僧がそれを咎めると、母は鐘の故事を語り、狂じ、鐘尽くしの謡いを歌い舞った。 その様を、寺僧に伴われて月見に寺を訪れていた少年に見出される。少年は女の国里を訊ねる。やがて、二人は母子であることを知り、その再会を喜びともに手をとり故郷へ帰る。 ◆塔頭 塔頭は門跡としてかつて、山内に円満院(1947年独立)、山外に聖護院(1946年独立)、実相院(1952年独立)、照高院(1614年廃絶)があった。 ほかに光浄院、勧学院、妙厳寺、龍泉院、本寿院、万徳院、宝寿院、円宗院、法泉院、上光院、覚勝院、善法院、法明院など。 ◆石造物 ◈「金堂前灯籠(園城寺金堂無名指灯籠)」が立つ。飛鳥時代の第38代・天智天皇が、飛鳥時代、646年の大化の改新にあたり、蘇我氏一族を滅ぼした。その罪障消滅のため、天皇自ら左薬指(「無名指」)を切り落とし、この灯籠の台座下に納めたという。 ◆園城寺 飛鳥時代、667年に第38代・天智天皇により飛鳥から近江に遷都され、近江大津京(大津宮)が開かれた。この時、大津京を中心として四大寺院、園城寺前身寺院、南志賀町寺、崇福寺、穴太(あのう)廃寺が建立配置されたとみられている。寺院は城塞の意味も含んでいたといわれ、園城寺は七堂伽藍を整えていた。 672年に天智天皇没後、長子の大友皇子(第39代・弘文天皇)を擁した近江朝廷に対して、天皇の弟・大海人皇子(第40代・天武天皇)が皇位継承をめぐって反乱・壬申の乱を起こした。大友皇子は敗れ、園城寺境内の長等山崎で自害したという。 大友皇子の大友与多王は父の霊を弔い、乱の犠牲者追悼のために田園城邑(じょうゆう)を寄進して寺を創建した。大友皇子を滅ぼした天武天皇から「田園城邑」のうちの「園城」を採った勅額を贈られ、寺号は「園城寺」にしたという。天智天皇の一族、乱犠牲者を弔うために建立されたという。 その後、近江大津京は5年しか続かず、大海人皇子は再び飛鳥に遷都している。 また、創建伝承がある。平安時代前期、858年に唐から帰国した円珍のもとに、新羅明神が姿を現した。唐より将来した典籍を収める場所として三井寺へ円珍を伴った。教待(きょうたい)という162歳の老僧が迎え、大友与多王の子・都堵牟麿(ととむまろ)が寺を円珍に献じたともいう。 ◆三井・三井寺 現在、境内金堂西側にある「閼伽井屋(あかいや)」岩間より、閼伽井の湧水が続いている。古来より閼伽水として金堂の弥勒供えられてきた。この清水が寺号の三井寺と呼ばれる由来になったという。 飛鳥時代、第38代・天智天皇(626-672)、第40代・天武天皇(631? -686)、第41代・持統天皇(645-703)の三帝誕生の際に、産湯に用いられた。以後、寺号を「御井(みい)の寺」と称した。飛鳥時代、670年条の『古事記』に「山の御井の畔に、諸神の座を敷きて、幣帛を奉げられた」とある。文献初例になる。その後、俗称として「三井寺」と呼ばれるようになる。 平安時代前期、859年、円珍は園城寺長吏になり、その後、井水を厳義・三部潅頂の法儀に用いた。弥勒菩薩がこの世に下り、人々を救済する弥勒三会(さんえ)の暁を待つ意味で、以降は「三井寺」と呼ばれたともいう。 かつて、泉に九頭一身の龍神が棲み、年に十日、丑の刻に姿を現わした。金の御器により花を金堂弥勒に供えたという。その日、霊泉に近づくと罰、咎ありとされ人々は畏れた。 なお、この御井は東大寺お水取りの井、若狭「若狭井」に地下水脈が通じているといわれている。 ◆教学 園城寺の天台寺門宗と延暦寺の天台宗間に教義の差異はないといわれている。ただ、前者は「教相為本」(教相門、経論の解釈・研究を中心とした教理・理論)、後者は「観心為本」(観心門、教相門の教理を体得するための修行)とされる。寺門宗は、後に倶舎論(くしゃろん)、婆沙論(ばしゃろん)が盛んになる。これらは、小乗仏教教理の集大成「大毘(だいび)婆沙論」の綱要を記した法相宗の教学書になる。5世紀、インドの世親が著した。 寺門宗は、菩薩行の実践にあり、自らの悟りを追求し他の「済世利人」、世を済い、人を利することを求める。そのために、すべての存在をありのままに見て、体得し行動する「円頓止観」が説かれる。教理の理解と修の一致、解行一致が重視されている。 天台宗の円・密・禅・戒の四宗兼学に加え、天台寺門宗では修験を加え五法門になる。また、顕教、密教と実践行の修験道(後の本山派)の3つが一つに融合するよう修行する「顕・密・修験の三道鼎立」が特色になっている。 平安時代前期、845年の智証大師流の密教を体得する僧としての基礎の修法「四度加行(十八道、護摩、胎蔵界、金剛界)」と、大峯山系を抖そうする修験道の「奥駈修行(峰入修行)」がある。智証大師が役行者の遺法を慕い、熊野から吉野へと至る峯々で修行したことに因む。山そのものを大日如来の曼荼羅とし、行場を巡ることで自己との一体化(即身成仏)を目指す。 寺流(寺門流)と呼ばれる「声明(しょうみょう)」が伝わる。「山(延暦寺)の泣き節、三井の怒り節」と喩えられる。 ◆新羅明神 円珍が唐の留学より帰国した際に、船中に守護・護法神の新羅明神が顕れた。その霊像は秘仏・新羅明神像(国宝)として北院の新羅善神堂にいまも祀られている。平安時代前期、860年、円珍、円敏、増命、康済らは新羅神社を建立している。明神の姿は、唐服で顎ひげをたくわえた老翁という。束帯姿の火御子、笏を持つ般若菩薩と箱を捧げる宿王菩薩を従える。円珍が唐より持ち帰った経典類はこの新羅明神の夢告により、園城寺唐院に収蔵されたという。 ◆教団分裂 平安時代前期、822年、最澄の没後、延暦寺の初代座主に義真(修禪大師)が就く。2代には円澄(寂光大師)が就いた。このため、円澄と円修が互いに対立し、円修派は室生寺に去った。その後は3代・円仁(慈覚大師)、4代・安慧と円澄派が続く。円珍(智証大師、義真派)は排斥され、円珍と円仁の対立が始まる。 5代に就いた円珍は座主在位23年間に渡り、以後、50年間は円珍派(智証派)が続いた。19年間に及んだ18代・良源座主の逝去に伴い、弟子・円仁派(慈覚派)の尋禅が19代に就き、権門化(門閥)が始まる。 平安時代中期、981年、慣例の円仁派(慈覚派)に代わり、円珍派(智証派)の余慶が法性寺座主になった。円仁派(慈覚派)門徒は改補を奏請強訴した。円珍・円仁門徒間が不和になり確執が深まる。989年、20代天台座主に余慶が就く。だが、両派の対立が表面化し、わずか3カ月で辞した。(永祚宣命事件)。993年、21代の円仁派(慈覚派)、陽生の時、円珍派(智証派)門徒が赤山禅院を襲う。22代に良源門流(円仁派[慈覚派] )の暹賀(せんが)が就くと、比叡山では円仁派(慈覚派)門徒が円珍派(智証派)の寺院を相次いで襲った。このため、円珍派(智証派)門徒千人は、智証大師(円珍)の影像を担いで、天台別院・園城寺に逃れた。 以後、天台教団は、山門派(円仁派、慈覚派、延暦寺)と寺門派(円珍派、智証派、園城寺[三井寺] )に分裂した。その後も座主継承、園城寺での戒壇新設などをめぐり対立した。戦国時代末まで武力抗争が続いた。 ◆三井修験 園城寺は神変大菩薩(役小角)を開基にする天台修験道の本山派修験の根本道場になっている。平安時代末、寺には修験僧がおり、熊野三山、大峰山、金峰山(きんぷせん)、葛城山などに抖擻(とそう)、参籠修行した。 平安時代、園城寺長吏・隆明(りょうみょう、1020-1104)は第72代・白河天皇、第73代・堀河天皇の護持僧になり、1096年に白河上皇に沙弥戒を授けた。その子・行慶(1101-1165)は覚円の室に入る。長吏・増誉(1032-1116)も両天皇の護持僧になる。1087年、増誉は熊野に参詣した白河上皇の先達をつとめ、初代の熊野三山検校に補任された。増誉は洛東に聖護院を建て、熊野権現を勧請した。以後、6代の覚実まで、長吏が任じられた。平安時代後期、1159年、園城寺に熊野権現社が勧請された。行尊(1057-1135)は、北院に常在院を建立し、熊野三所を勧請した。行尊、覚宗、覚讃なども上皇、女院、公卿の熊野詣先達を務め熊野三山検校に補せられ、覚讃以後は洛東・新熊野社の検校を兼ねた。 行尊(120日)、覚忠(1118-1177)(75日)らによる四国観音霊場三十三所巡礼記録が最古の巡礼記録であり、後の巡礼規範になった。さらに、東国三十三所巡礼に拡大する。 ◆源氏 園城寺は源氏との関わり深い。平安時代後期、1180年、以仁王(1151-1180)と源頼政(1104-1180) は平家討伐の挙兵計画が事前に露見し、追手の六波羅から逃れるために園城寺を頼り境内に入った。この際に王は女装し、三条高倉の邸から近衛大路、鴨川を渡り、鹿ヶ谷、如意ヶ岳を越えた。その後、頼政は300騎で園城寺に合流した。延暦寺への応援要請に返事がなく、興福寺は兵を向かわせなかった。仕方なく王は園城寺を出て、宇治の別院・平等院に移る。頼政は平家の軍勢との戦いで敗れ自害、王は奈良・興福寺に向かう途中で討たれた。報復のため、園城寺は平家1万の兵に攻められ、火を放たれ金堂以外は破却された。大津の在家の家々にも火が放たれたという。 鎌倉時代前期、1192年以後、源頼朝(1147-1199)の治世となり、頼朝は、園城寺・青龍院修理料の施入、如意寺に大慈院を建てた。実朝は伽藍を再建し、園城寺は「源氏数代祟重寺」といわれた。1219年、実朝は鶴岡八幡宮で頼家の子・公暁に暗殺された。これにより三代続いた源氏将軍は断絶した。以後、鎌倉幕府3代執権・北条泰時(1183-1242)も寺に関わり、その後の室町幕府の初代将軍・足利尊氏(1305-1358)も、源氏嫡流として深く新羅明神を崇敬し、園城寺に一切経を奉納するなどした。 ◆源氏物語・紫式部 平安時代中期の紫式部(?-?)と園城寺の関わりも深い。内供奉十禅師で園城寺阿闍梨・康延(?-?)は、式部の母方の叔父にあたる。同じく阿闍梨・定暹(980?-?)は異母弟という。1016年、式部と定暹の父・藤原為時(949?-?)は園城寺で出家し法師になっている。 『源氏物語』、第5帖「若紫」巻の「なにがし寺」とは、園城寺別院で寺門派拠点寺の岩倉・大雲寺ともいわれている。 ◆園城寺五別所 平安時代の院政期(1086-1192)に円満院、聖護院、実相院の三門跡が成立した。 中世(鎌倉時代-室町時代)には、寺院経営を担う北院、中院、南院の3つの地区があり、園城寺政所が管轄した。 平安時代以降に、境内周辺に別所と呼ばれる寺院が建立された。これらの別院は、広く衆生救済のためとされた。「園城寺五別所」としては、微妙寺(びみょうじ)、水観寺(すいかんじ)、近松寺(こんしょうじ)、尾蔵寺(びぞうじ)、常在寺(じょうざいじ)がある。それらに加えて如意寺があった。これらは、「三院五別所」、中世後期以降-近世初期は「三院三別所」と呼ばれた。 平安時代に定円(安然大徳とも)が創建した近松寺には、人形浄瑠璃・歌舞伎作者の近松門左衛門(1653-1725)も入り、仏典漢籍を学ぶ。近松の姓はこの寺号に由来するという。近松寺は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1643)、平安時代中期の琵琶法師・歌人の蝉丸(?-?)を祀る蝉丸宮を支配した。 ◆三井寺法師 園城寺(三井寺)の僧兵は、「三井寺法師(みいでら-ほうし/みいでら-ぼうし) 」、「寺法師」ともいわれた。延暦寺の僧兵は「山法師」、興福寺は「奈良法師」といわれ勢力を誇った。 ◆大津京 大津京(大津宮)の詳細は分かっていない。飛鳥時代、663年に飛鳥より遷都になった大津宮は、錦織遺跡(大津市錦織2丁目)を中心として、琵琶湖の西岸に建都されたとみられている。 663年の白村江の戦いにより、日本は、唐・新羅の連合軍に敗れた。中大兄皇子は、国防、国内体制強化をはかるために、大津京を造営したといわれている。旧勢力の影響を避け亡命した、百済系渡来人が多く居住していた近江が選ばれたという。664年、皇子は第38代・天智天皇として即位した。だが、672年の壬申の乱後、第40代・天武天皇は飛鳥浄御原宮に遷都し、大津京はわずか5年で廃都になる。 大津京の四方に、防御的な城郭の意味も含めて、4つの寺院が配置されていたという。大津京の北に南志賀町寺、北東に穴太寺、北西に崇福寺(志賀寺)、南部には、園城寺前身寺(あるいは園城寺)があったとみられている。なお、崇福寺は、668年、天智天皇の勅願により創建されたという。平安時代初期、東大寺・興福寺などと並ぶ十大寺の一つに数えられた。鎌倉時代初期に園城寺の支院とされ、室町時代には廃絶した。これらの位置確定により、大津京の所在地を探る手がかりにもなるとされている。 江戸時代以来、寒川辰清は大津宮の伝承地として錦織の地を紹介した。近代以降、宮跡所在地をめぐる論争が起こる。近代、1895年、この錦織に「志賀宮址碑」が建立された。1901年、木村一郎は、志賀里説を提唱する。1927年、滋賀町廃寺跡を第50代・桓武天皇が創建した梵釈寺とし、大津京内裏跡ともされた。1941年、崇福寺跡が国の史跡に指定される。現代、1979年、錦織遺跡は国の史跡に指定されている。1989年、山尾幸久は、平安時代には宮跡地が「粟津」とみなされていたとした。 ◆文化財 多くの文化財が残されている。国宝10件(64点) ・重要文化財42件(720点) にのぼる。 ◈絹本著色「新羅明神像」(重文)は鎌倉時代(13世紀)作になる。 唐服で顎ひげをたくわえた老翁姿の明神、束帯姿の火御子、笏を持つ般若菩薩と箱を捧げる宿王菩薩を配した。明神の頭上円相内には、本地仏である文殊菩薩を描く垂迹曼荼羅。縦86.7cm 横39.4cm。 ◈絹本著色「不動明王二童子像」(重文)は、鎌倉時代(14世紀)作になる。矜伽羅(こんがら)、制多迦を配した三尊になる。縦105.1cm 横56.5cm。 ◈絹本著色「不動明王八大童子像」(重文)は、鎌倉時代(12世紀)不動明王、三童子し、下方に五人の使者を配した五菩薩五忿怒像になる。縦134.5cm 横124.5cm。 ◈絹本著色「尊勝曼荼羅図」(重文)は、鎌倉時代(13世紀)作になる。大円相内に智拳印を結ぶ大日如来を中心に、八大仏頂をめぐらし、下三角形の中に不動明王、半月形内に降三世明王を配し、上部左右に二組の飛天を描く。縦80.3cm 横42.4cm。 ◈絹本著色「両界曼荼羅図」(重文)は、鎌倉時代(13世紀)作になる。金剛界が九会曼荼羅で、数少ない天台密教系彩色本両界曼荼羅の一つ。各縦234.0cm 横146cm。 ◈絹本著色「多聞天像」(重文)は、鎌倉時代(14世紀)作になる。毘沙門天、吉祥天と善膩子童子の三尊形式、縦105.6cm 横48.2cm。 ◈絹本著色「天台大師像」(重文)は、鎌倉時代(14世紀)作になる。座下の水瓶を蓮華を象った台に載せる。縦93.0cm 横59.2cm。 ◈平安時代後期の「金銅孔雀文磬」(重文)。 唐院には、二つの竹尺「園城寺尺」が伝えられている。室町時代前期、「応永三十一年」(1424年)の銘ある「唐院預竹計」(長35.6cm、幅1.3cm)(重文)、「応永三十三年」(1426年)の銘がある「唐院預尺」(長36.9cm 幅1.0cm)。 ◈「預竹計」は潅頂において下される布帛を計算する際の裁衣尺で、預尺はその写しという。 ◈霊堂の「弁慶汁鍋」は、弁慶や僧兵が使ったという伝説がある。 ◆文献・絵画 平安時代の七種の「智証大師関係文書典籍一括」51巻夾(きょう)2帖(国宝)がある。 ◈「智證大師請来像」のうち、唐代の紙本墨画「五部心観」2巻(国宝)は、金剛界五部諸尊の観法を説いた。平安時代前期、855年に円珍が長安で師・法全より贈られたという。858年に将来した。 ◈平安時代前期、承和年間(834-848)の紙本墨書「円珍俗姓系図(大師系図、和気氏系図)」(国宝)は、第12代・景行天皇から始まり円珍までの系図を記した。円珍の生家は讃岐因支首(後の和気公)になる。全巻にわたって大師自筆の加筆が見られ、竪系図としては最古のものになる。 ◈平安時代(9世紀)の綾本墨書「伝燈大法師位位記(綾本 中務位記)」1巻、(国宝)は、平安時代前期、849年に大法師の位を授かった。850年、入唐求法に際して、証明用として再下付された。薄茶地菱形文の綾裂に書かれ入唐の旅に際して携行した。 ◈南北朝時代の足利尊氏の書写させた「一切経(大蔵経、尊氏願経)」(重文)、室町時代の紙本著色「園城寺境内図」。 平安時代前期、888年、円珍筆、紙本墨書「制誡文」(国宝)。唐時代、854年、円珍筆、紙本墨書「福州温州台州求法目録」。平安時代、863年、円珍自筆、本紙本墨書「円珍請伝法公験奏状案」(国宝)。 平安時代、853年、円珍筆、「感夢記」(国宝)。南北朝時代、1354年、紙本墨書「大蔵経(足利尊氏願経)」592帖(重文)。鎌倉時代(14世紀)、紙本著色「園城寺境内古図」5幅。唐時代、853年、円珍加筆、紙本墨書「開元寺求法目録」1巻(国宝)。唐時代、855年、円珍加筆、法全加筆証明、紙本墨書「青竜寺求法目録」1巻(国宝)。唐時代、858年、円珍加筆、紙本墨書「国清寺外諸寺求法惣目録」1巻(国宝)。 鎌倉時代「不動明王八大童子像」(重文)、いずれも鎌倉時代(重文)の「尊勝曼荼羅図」、「八大仏頂曼荼羅図」「黄色金剛童子像」、「尊星王像」「多聞天像」「閻魔天像」「水天像」「不動明王二童子像」「不動明王像」「天台大師像」「釈迦十六善神像」。南北朝時代「両界曼荼羅図」(重文)、室町時代の「仏涅槃像」(重文)など。 ◆障壁画など 勧学院客殿一之間に安土・桃山時代の狩野光信(1561/1565-1608)筆の襖絵、紙本金地著色「四季花卉図」(重文)(各179.5×116.7㎝)、客殿一之間床に貼付絵「金地著色 滝図」。勧学院客殿二之間に安土・桃山時代の狩野光信筆襖絵「紙本著色 花鳥図」(重文)。 勧学院客殿南の表一之間、二之間の障壁画は狩野光信(1561/1565-1608)による。一之間は部屋四周の襖と戸障子貼付に、金地著色で四季の花卉、梅、桧、桜、杉、滝、雪山が描かれている。二之間は、素地に著色で花鳥図24面が描かれている。 光浄院客殿一之間の床貼付絵は紙本金地著色「松に滝図」(重文)、安土・桃山時代、1601年、狩野山楽(1559-1635)筆による。 一之間の大床壁貼付は金地著色で大松に滝図、南側の付書院の床貼付と障子腰貼付は金地に離に菊図、東側の襖、北側の帳台構貼付は水墨画で列仙図を描く。二之間12面は素地著色で花鳥図を描く。北側と西側の8面には四季花鳥図、東側襖4面には竹林が描かれている。 ◆鬼の寒念仏 観音堂、百体堂に大津絵の「鬼の寒念仏」の絵馬がある。赤鬼が僧衣をまとっている典型的な図柄で、本性を隠した偽善者を諷刺しているという。 民画・大津絵は仏画より始まったとされ、江戸時代前期、寛永年間(1624-1643)に生まれたという。合羽摺り、版木押し、コンパス、定規などの道具を用い早書き早摺りされた。墨、丹(朱)、胡粉(白)、黄土など七色程度を用い簡潔に生き生きと描かれた。 近松門左衛門は園城寺に一時学んだ。「傾城反魂香」には、「吃の又平」という大津絵の絵師が登場する。大津絵は近代以降、一時廃れかけたが、現在も描き続けられている。 ◆三尾明神の影向石 三尾明神の影向石は、勧学院の西にある。 古来よりこの辺りは琴尾谷と呼ばれた。谷を流れる清流に天人が舞い降り、琴や笛を奏で舞い、歌い神を慰めたという。 三尾明神は長等山の地主神として園城寺創建以前から祀られていた。現在、社殿はなく、上三尾社の跡地には、三尾影向石と呼ばれる磐石が井桁の中に祀られている。三尾明神が来臨した際には、この岩に坐したという。このすぐ近くに普賢堂(三尾明神の本地堂)がある。なお、東方には三尾神社がある。 ◆石橋 ◈「村雲橋」は、勧学院の石垣の築地堀の手前にある。志賀衆、見世衆により修復された。 かつて円珍がこの橋を渡ろうとして西の空を見ると、入唐の際に学んだ長安の青竜寺が焼けていると察知した。すぐに真言を唱え橋上から閼伽水を撒いたという。すると、橋の下から一条の雲(黒雲とも)が湧き起り、西の空に飛び去った。青竜寺は実際に火事になっており、その飛雲により雨が降り小火で鎮火することができた。後に園城寺の円珍のもとに礼状が送られてきたという。以後、「むらかりたつ雲の橋」ということにより、村雲橋と呼ぶようになったという。 ◈「石橋」(重要美術館)は、護法善神堂前にある。江戸時代、1725年に架橋され、放生池に架かる。 ◆遺跡 境内で白鳳時代(645-710、飛鳥時代)と平安時代後期の二期の瓦が出土している。白鳳時代の素弁蓮華文鐙瓦は、高句麗要素、百済末期様式、複弁蓮華文鐙瓦は初唐様式で、同時期の大津京四大寺院と同じ形式だった。 その後、円珍が中興した時には山岳伽藍様の檜皮葺に変えられ、11世紀に瓦葺に葺き替えられたとみられている。 ◆碑・石像 ◈「三井寺の 門をたたけばけふの月」という芭蕉(1644-1694)の句碑が金堂脇にある。芭蕉は、江戸時代前期、1689年より2年間を大津に暮らした。1691年の中秋の名月に、木曽塚(義仲寺)無明庵で催された月見の句会に参加し、琵琶湖に漕ぎ出した舟中よりこの句を詠んだという。唐の詩人・賈島(かとう、779-843)が、「僧は推す月下の門」という自作の詩句について、「推す」を「敲(たた)く」と迷い、文人・韓愈に問い「敲」の字に改めたという。この故事により「推敲」の語源になった。碑は御影石、現代、1994年11月に建立された。揮毫は榊莫山(1926-2010)による。 ◈「大津そろばん顕彰碑」が立つ。大津算盤(おおつそろばん)は、日本式算盤の起源とされている。江戸時代前期、1612年、大津一里塚前の片岡庄兵衛は長崎奉行の長谷川左衛藤広に随行し長崎に向かった。片岡は同地で明の渡来人から算盤の見本と使い方を習う。帰郷後に研究を重ね、改良を加えた。 その後、江戸幕府より御本丸勘定方御用調達に任命される。算盤の家元となり、片岡家は代々「庄兵衛」の名を襲名した。だが、近代に入り廃れた。現在も名高い播州算盤は、安土・桃山時代、 天正年間(1573-1592)、三木城落城に際し大津に避難してきた播州の人々が、故郷に技術を持ち帰って普及させたという。 ◈「天台大師像」が立つ。智顗(ちぎ、538-597)は、中国の僧侶であり、天台宗の実質的な開祖、慧文、慧思に次いで第三祖(第四祖とも)とされている。智者大師ともいう。575年より天台山に登り、天台教学を確立した。 ◆天狗杉 金堂の向かいに「天狗杉」と呼ばれる樹齢1000年の大杉、樹高20mが立っている。 伝承が残されている。室町時代初め、僧・相模坊道了(妙覚道了)は勧学院書院で密教の修行をしていた。ある夜、道了は突如として天狗に化身し、書院の窓から飛び出した。大杉の上に止まり、やがて朝を迎えると東の空に向かって飛び去った。天狗は小田原まで飛び大雄山最乗寺の地に降りたという。道了は五百人力と称され、験徳著しく、最乗寺の道了尊堂に祀られた。勧学院には「天狗の間」がある。 室町時代前期の曹洞宗・修験道の僧という妙覚道了の詳細は不明。室町時代前期、1394年、曹洞宗の僧・了庵慧明が最乗寺を開創し、弟子の道了は力により寺の創建に助力したという。師の没後、寺門守護と衆生救済を誓い天狗になったという。最乗寺の守護神として祀られた。神奈川県南足柄市に曹洞宗最乗寺はいまもある。奥の院に、御本地十一面観世音菩薩(守護道了大薩の御本地)が安置されている。 ◆桜楓 境内にソメイヨシノや山桜1000本、楓がある。 ◆孔雀舎 孔雀舎に、孔雀50羽ほどが飼われてている。 密教の尊格に孔雀明王がある。もとはインドの女神マハーマーユーリー「偉大な孔雀」の意という。菩薩形で孔雀に乗り、一面四臂(また三面六臂)の姿をしている。孔雀は害虫や毒蛇を食べることから功徳があるとされた。さらに、祈雨、三毒(貪り・嗔り・痴行)、魔を喰らうとして大護摩に際しての除魔法に用いられた。明王を本尊とした呪法に孔雀経法がある。 ◆長等山 長等山は、長柄山とも記された。境内の西に見える。 平安時代中期の三十六歌仙の一人、平兼盛(?- 991)は「楽浪や長等の山の長らへば久しかるべき君が御代かな」と詠んだ。 平安時代後期-鎌倉時代の鴨長明(1155-1216)に「ためおく人もながらの山にだにさよふけぬればまつ風の声」(『新古今集』)がある。 ◆西国観音霊場三十三所 当寺は、「西国観音霊場三十三所」の第14番札所になっている。第1番の和歌山・青岸渡寺より、第33番の岐阜・華厳寺までを巡る近畿2府4県(1000km)の巡礼になる。 長谷寺を開いた飛鳥時代の徳道(とくどう、656-?)は、病により仮死し、冥途で閻魔に出あった。閻魔は地獄に堕ちる者が多いとして、観音菩薩の慈悲を説き、33の霊場を参ると功徳を得られるとした。 観音菩薩は浄土に往生せず、現世で苦しむ人々を救済するために、聖観音、十一面観音、千手観音など33(無限)の姿に身を変えるとされる。徳道は、閻魔より33の宝印、起請文を授かり現世に戻る。徳道は兵庫・中山寺に宝印を納めたという。 巡礼は、奈良時代に始まる。その後、途絶したともいう。平安時代、花山法皇(第65代、968-1008)は、徳道の納めた宝印を掘り起こし、巡礼を再興したという。また、平安時代後期(12世紀)に再興されともいう。平安時代後期には天皇、公家が巡礼し、鎌倉時代-室町時代には、庶民にも広まった。江戸時代に最も盛んになる。周辺の伊勢神宮参り、熊野詣、善光寺参りとも結びついた。「三十三度行者」と呼ばれるのは、33所を33回も巡礼した人を意味した。御朱印、千社札の始まりにもなった。 ◆仏像開扉 毎日開扉は金堂の円空仏7体、水観寺の薬師如来・二十八部衆、釈迦堂の清涼寺式釈迦如来像。 微妙寺の十一面観音立像(重文)は毎月17日・18日・土日祝日のみ開扉。 唐院・大師堂の智証大師坐像(国宝、中尊大師)の開扉は10月29日のみ。 観音堂の如意輪観音坐像(重文)は、33年に一度のみ開扉。 金堂の弥勒菩薩像は開扉されない。 ◆祭礼 三井寺千団子祭・鬼子母善神開扉(5月中頃の土日曜日)には、神像が開帳される。鬼子母神の子ども1000人への供養として、串刺しの1000個の団子を供える。 ◆修行体験 座禅(止観)、写経・写仏、山伏(長等山修験)、ビーズブレスレット(腕輪念珠)の制作体験。 ◆年間行事 修正会(1月1日)、仁王会・寒中説法(1月8日)、尊星王星祭(2月節分)、涅槃会(3月15日)、彼岸中日法要(彼岸中日)、智証大師誕生会(3月25日)、潅仏会(4月8日)、桜ライトアップ・夜桜コンサート(4月1日-17日、無料開放)、三井古流青山茶会(4月中)、三井寺千団子祭・鬼子母善神開扉(5月中頃の土日曜日)、修禅大師講(7月4日)、三井寺札焼(7月第2土曜日)、本山採灯大護摩供(7月22日)、原爆犠牲者慰霊法要(8月6日)、千日会(観音菩薩)(8月9日)、三井寺鐘供養・盆法要(8月15日)、三井寺納涼祭り(8月第2土曜日)、彼岸中日法要(9月彼岸中日)、智証大師御逮夜(おたいや)法要(10月28日)、智証大師御祥忌法要・智証大師坐像(中尊大師)御開扉・三井古流紅楓茶会(10月29日)、教待会(11月11日)、天台・智証両大師講(11月24日)、三井晩鐘・除夜の鐘(12月31日)。 弥勒講(毎月5日)、十七夜法要(毎月17日)、智証大師講(毎月29日)。 *概ね一般的な拝観の順路に従って案内しています。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *多くの建物の内部は撮影禁止。一部の建物は原則非公開(事前申込み制)になっています。 *参考文献・資料 『比叡山諸堂史の研究』、『闘いと祈りの聖域 比叡山史』、『三井寺』、『近江・若狭・越前 寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『古寺巡礼近江 三井寺』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『近江神宮 天智天皇と大津京』、ウェブサイト「天台寺門宗」、『歴史のなかの宗教 日本の寺院』、『日本の名僧』、週刊日本の合戦-羽柴秀吉と山崎の戦い』、『京都・湖南の芭蕉』、『週刊 日本の美をめぐる 室町5 38 狩野派の流れ 元信 永徳 探幽』、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |