|
|
|
| * | |
| 妙顕寺(妙顯寺) (京都市上京区) Myoken-ji Temple |
|
| 妙顕寺 | 妙顕寺 |
  大門           小門    日像が由井ヶ浜で感得したという独特の「浜ゆり題目」の宝塔  「尾形光琳墓在此寺中」  本堂、右の燈籠が妙顕寺燈籠   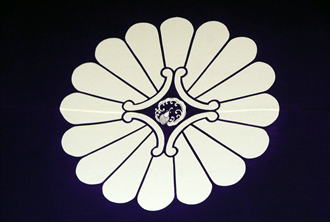 本堂  本堂  本堂  本堂、須弥壇  本堂、格天井、家紋が描かれている。  本堂、金丸  本堂、多宝塔  本堂  本堂、宗祖日蓮大菩薩  本堂     本堂  本堂          妙顕寺型燈籠     三菩薩堂  三菩薩堂、「勅賜三菩薩」の扁額   大玄関  方丈  方丈   方丈  大客殿  大客殿    「龍華飛翔(りゅうげひしょう)の庭(四海唱導の庭)          大客殿中央 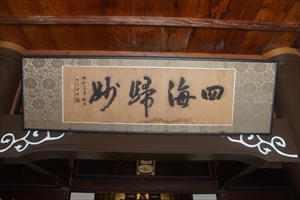  「日像の帝都弘通」  「祇園祭奇瑞」  大客殿東  大客殿東  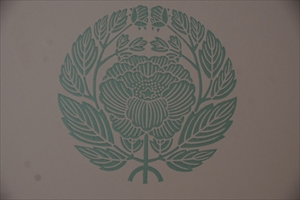  勅使門  勅使門      勅使門   「孟宗竹林の坪庭」        書院  抱一曲水の庭      「光琳曲水の庭」  奥書院  茶室、円窓  茶室    尊神堂(鬼子母神堂)  尊神堂    尊神堂   御真骨堂  御真骨堂  御真骨堂  納骨堂  鐘楼・梵鐘(京都府指定有形文化財)     慶中大菩薩  慶中大菩薩  妙見大菩薩   寿福院寿塔   宗祖開教750年記念宝塔  「四海唱導之霊蹟之霊蹟」の碑、後光厳天皇により2世・大覚の時に贈られた称号。    【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた妙顕寺、鴨川二条大橋の説明板より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた妙顕寺、鴨川二条大橋の説明板より 【参照】「妙顕寺前町」の町名板 |
妙顕寺(みょうけん-じ、妙顯寺)の南面した大門には、「門下唯一勅願寺」の木札が掲げられている。京都初の日蓮宗道場になる。創建以来、数々の弾圧を受け、寺地も各所を転々とした。境内は広大で2万坪(66115.7㎡)、建坪6000坪(19
834.7㎡)ある。 山号は貝足山(ぐそく-ざん)という。龍華院の院号もある。正式には四海唱導(しかいしょうどう)妙顕寺という。通称は「竜華(龍華、りゅうげ)」という。 日蓮宗。本尊は釈迦多宝仏。 日蓮宗四大本山の一つ。日蓮宗京都16本山(かつては21本山)の一つ。末寺263。日蓮の孫弟子・日像(龍華樹[寿]院)により開山された「京都の三具足山(龍華の三具足)」(ほかに妙覚寺、立本寺)の一つ。洛中法華宗の二大勢力の一つ。 御朱印(御朱印、御首題「波揺りのお題目」)が授けられる。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1294年、旧4月28日、日蓮宗の僧・日像は入洛した。師・日蓮の遺命により、日蓮宗最初の京都弘通(ぐつう、布教)を行った。 1311年、綾小路大宮(下京区)付近に、拠点になる法華堂が建立されたとみられている。 1321年、旧12月8日、日像は、第96代・後醍醐天皇より弘通の勅許を得る。天皇により寺領を与えられ、皇居御溝の傍、今小路(上京区)に法華堂を移した。この地は、安居院(あぐいん)の旧地になる。これが妙顕寺の起源ともいう。京都での日蓮宗最初の道場になる。 南北朝時代、1333年、後醍醐天皇皇子・護良(もりよし/もりなが)親王は、隠岐配流の父・後醍醐天皇の京都還幸を祈る令旨(りょうじ、命を伝える文書)を出した。 1334年、後醍醐天皇の綸旨(りんじ、蔵人が天皇の意を受けて発給する命令文書)により、法華宗号が公許され法華経の最初の勅願寺になった。洛中洛外の宗門の第一位と認められ、「四海唱導妙顕寺」といわれる。京都の16本山を総統した。 1336年、室町幕府将軍家、北朝光厳院の祈祷所になる。 1341年/1340年/1326年、2世・大覚妙実の時、北朝初代・光厳院の院宣(いんぜん、院司が院の命を奉じて出す文書)により、四条櫛笥西頬(しじょう-くしげ-にしづら)(中京区)に移転する。寺名も「妙本寺」と改称した。寺は栄え、以後、「四条門流」と呼ばれる。光厳院祈願所になる。 1352年、比叡山延暦寺衆徒との抗争により破却された。 1358年、大覚妙実は、北朝第4代・後光厳天皇の詔により、衆僧300人で桂川で法華経による祈雨祈祷を行い、すぐに効験が顕れたという。また、第97代、南朝第2代・後村上天皇により大覚妙実は、大僧正に任じられ、日蓮に大菩薩号、日朗・日像に菩薩号が与えられた。その後、寺勢は増した。 1387年、比叡山延暦寺衆徒により破却された。だが、叡山は再興を許さなかった。北朝最後の第6代・後小松天皇により、土地(四条以南、綾小路以北、壬生以東、櫛笥以西)を与えられた。 室町時代、1393年、足利義満により三条坊門堀川(押小路堀川西、押小路以南、綾小路以北、壬生以東、櫛笥以西、中京区)を寄進される。移転するとともに、叡山の干渉があり、「妙本寺」と寺名を改めて再興した。 1411年、室町幕府3代将軍・足利義満の祈願寺になる。比叡山延暦寺衆徒との抗争により破却された。 1413年、比叡山宗徒による破却が行われた。 1483年、三条西洞院に移る。 1511年、二条西洞院町に本妙寺(妙顕寺)の名がある。(『宣胤卿記』同年条) 1519年/永正-大永年間(1504-1528)、16世紀(1501-1600)初頭、「妙顕寺」と寺名を戻している。 1521年、室町幕府10代将軍・足利義稙により、二条西洞院南に再建された。 1536年、比叡山衆徒による洛中洛外の日蓮宗21寺を襲った事件、「天文法華の乱」(天文法乱)により破却される。堺・妙法寺に逃れた。 1542年、帰洛し、二条西洞院南(中京区)に再興され、「法華寺」と改める。 安土・桃山時代、1575年、土地(二条以南、三条坊門北、油小路、西洞院間)を与えられる。 1583年/1584年、羽柴秀吉の妙顕寺城建立(中京区古城町、押小路通小川西入北側)に伴い、その命により寺は現在地(小川寺ノ内)に移転させられた。秀吉は跡地に、政庁になる二条新邸を築いた。 1588年より、「妙顕寺」の旧名に復した。 1595年、方広寺大仏殿千僧供養出仕では受派になり、その拠点寺になる。 江戸時代、1628年、寿福院(千代保)は寿塔を立てた。 1633年、末寺193があった。 1745年、末寺329があった。 1788年、天明の大火により焼失している。 1834年、再建された。 近代に入り、法華各宗派が大合同し、身延山を祖山とする日蓮宗が結成され、大本山として全国に300あまりの末寺を統率した。 1941年、制度改革によって、全ての末寺を解放した。 ◆日像 鎌倉時代中期-南北朝時代の日蓮宗の僧・日像(にちぞう、1269-1342)。男性。俗姓は平賀、通称は肥後阿闍梨、号は竜華寿(樹)院。下総国(千葉県・茨城県)の生まれ。7歳で日蓮の六大弟子の一人・日朗に師事した。1275年、身延の日蓮の弟子になり、経一丸と命名され本尊を授与する。1282年、日蓮没後、日朗に再び師事した。1293年、北陸を経て、1294年、入洛し、日蓮の遺命により日蓮宗最初の京都弘通(ぐつう、布教)、宗義天奏(天皇への布教)を行う。松ヶ崎・歓喜寺(妙泉寺)、洛西・真経寺、深草・極楽寺(宝塔寺)を日蓮宗に改宗させた。柳酒屋仲興(やなぎざかや-なかおき)ら町衆に信徒拡大し、一時の京都は「法華題目の巷」と呼ばれた。1307年頃、乙訓山崎付近で布教を行う。比叡山延暦寺などの圧力により、1307年、土佐配流、1308年、紀伊流罪になり、1311年、綾小路大宮(下京区)付近に、拠点の法華堂が建立されたとみられている。妙顕寺を開創し、教団発展の礎を築く。1321年、第96代・後醍醐天皇より弘通の勅許を得る。今小路に法華堂を移し、妙顕寺の起源ともいう。京都での日蓮宗最初の道場になる。同年、洛内追放になる。3度の弾圧と赦免「三黜三赦(さんちつ-さんしゃ)の法難」を受けた。著『秘蔵集』など。74歳。深草・宝塔寺(伏見区)に葬られる。 一門は四条にあったことから四条門流と呼ばれた。1358年、弟子・大覚の祈雨の功により菩薩号が贈られた。 ◆大覚 妙実 鎌倉時代後期-南北朝時代の日蓮宗の僧・大覚 妙実(だいかく/だいがく-みょうじつ、1297-1364)。詳細不明。男性。日像に師事し、妙顕寺2世になる。中国地方での布教に成功した。1358年、桂川鳥羽の畔で雨乞の成功により、北朝第4代・後光厳天皇から大僧正に任じられた。日蓮に大菩薩号、日朗・日像に菩薩号が与えられ、公武接近を果たした。68歳。 大覚妙実により妙顕寺が開かれたともいう。 ◆前田 利家 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・前田 利家(まえだ-としいえ1538-1599)。男性。幼名は犬千代、孫四郎、又左衛門尉、筑前守、加賀大納言、異名は槍(やり)の又左衛門。尾張国(愛知県)の生まれ。父・前田利昌、母・竹野氏の4男。織田信長に近侍し、1551年以後、従軍した。1556年、美濃の斎藤道三征伐に加わる。1558年、まつ(芳春院)と結婚した。1559年、信長の勘気を受け一時蟄居した。1560年、桶狭間の戦いに加わる。1569年、信長に許され、その命で兄・利久に代り家督を継ぎ、赤母衣衆(あかほろしゅう)になる。1570年、姉川の戦い、1575年、長篠の戦いに加わる。信長から越前を与えられた柴田勝家の監視役として、佐々成政・不破光治と府中(武生市)に配され、府中三人衆として施政に当たる。1581年、能登七尾城主になり国持大名になる。1582年、本能寺の変の後、越中の前線から撤退し、石動山天平寺の僧徒、温井・三宅などの反乱を討伐した。1583年、賤ヶ岳の戦で、当初、柴田勝家に加担し、後に豊臣秀吉に降伏した。勝家の自害・柴田氏の滅亡後、加賀金沢城主になり、北陸を制する大大名になった。1584年、小牧の戦いに成政を末守城で破り、加増された。1585年、秀吉の越中征伐後、長男・利勝(利長)が越中3郡を領し、北陸の雄藩としての基礎を固める。秀吉の信頼を得て、1586年、羽柴姓と秀吉の旧官名筑前守を譲られた。1587年、九州征伐で京都・大坂を守護した。1590年、小田原征伐で北関東から進撃し、奥羽征伐にも従い秀吉の全国統一に参加する。参議になる。1592年、文禄の役で、名護屋に駐留し徳川家康とともに漢城(ソウル)陥落後の秀吉渡海を止めた。1593年、秀吉に秀頼誕生後、傅役(守り役)に任じられる。1596年、秀吉・秀頼父子の参内に供奉した。1597年、権大納言になる。1598年、五大老の一員になった。秀吉没後、秀頼とともに大坂城に入り、後見した。1599年、家康を追及する先頭に立ちすぐに和解する。直後、妻・まつに遺書を代筆させる。大坂城内で病没した。62歳。 加賀藩の始祖。かぶき者で知られた。計算上手で民政・理財に優れ、茶の湯・和歌にも長じた。豊臣氏とは織田配下の同輩であり、秀吉の室・北政所(高台院)と利家の室・芳春院とは幼なじみだった。利家の3女・摩阿(加賀殿)は秀吉の側室、4女・豪、6女・菊は秀吉の養女になっている。利家の没後、石田三成の失脚、嫡男・利長の加賀帰国など、1600年、関ヶ原の戦へと展開した。 。 墓は利家の遺言に従い金沢野田山にある。 ◆寿福院 室町時代後期-江戸時代前期の寿福院(じゅふくいん、1570-1631)。女性。本名は千代、千代保(ちよぼ)、東丸殿。越前(福井県)の生まれ。父・朝倉義景の家臣・上木新兵衛、母・朝倉家臣・山崎右京の娘の3女。異母兄に善住院日淳(経王寺再興開基)。妹に八重(大文字屋新十郎の妻)。父の死後、母は千代保を連れて小幡(おばた)九兵衛に再嫁した。前田利家の正室・まつ(芳春院)の侍女として前田家に入り、1592年、文禄の役で名護屋の陣中にあった利家の身の回りの世話を務めた。利家の側室になる。1593年、金沢に帰り利家の4男・利常(猿千代)を産む。利常は生後すぐに千代保から引き離され、越中守山・前田長種で養育された。千代保は熱心な日蓮宗徒であり、1601年、養仙院日護を招き、金沢に経王寺(きょうおうじ)を創建した。1603年、能登の妙成寺(みょうじょうじ)を菩提寺に定め、伽藍を建立した。1605年、子・利常が家督を継ぎ、千代保は藩主の御生母になる。1614年、2代藩主・利長の死後、利常が3代藩主になる。芳春院と入れ替わり、江戸へ下向し徳川氏の人質になった。加賀藩江戸屋敷で亡くなる。62歳。 江戸で徳川家康の側室・養珠院(お万の方)と親交した。熱心な日蓮宗檀信徒であり、1628年、妙顕寺の寿塔のほか、鎌倉妙本寺、甲斐・身延山久遠寺、鎌倉・長興山妙本寺、安房・誕生寺などに堂塔を寄進している。 墓は経王寺(金沢)、分骨され妙成寺(能登)にある。 ◆日筵 江戸時代前期の日蓮宗の僧・日筵(にちえん、1609-1681)。男性。字は春山、号は隆源院。京都の生まれ。下総中村・小西(千葉県)の両檀林で学び、両檀林の化主(けしゅ)、京都・妙顕寺の住持になる。1667年、甲斐(山梨県)身延山久遠寺29世になる。1679年、久遠寺31世の後継者争いに関与し出羽秋田に流された。著『一期行業』『不受不施論記』など。73歳。 日筵を祖に仰ぐ法脈を莚師(えんし)法縁という。 ◆尾形 光琳 江戸時代前期-中期の尾形家6代・画家・尾形 光琳(おがた-こうりん、1658-1716)。男性。名は惟富、惟亮、伊亮(これすけ)、幼名は市之丞、別号は積翠、道祟(どうすう)、寂明、方祝(まさとき)、澗声(かんせい)、青々、道号は日受。京都の生まれ。父・富裕な呉服商「雁金屋 (かりがねや)」の尾形宗謙の次男。弟・陶芸家の尾形乾山、曾祖父・道柏の妻は本阿弥光悦の姉。少年時代から能楽・茶道・書道などに親しんだ。父、山本素軒より狩野派の画法を学ぶ。1687年、父の遺産の半分を譲渡され、数年内に使い果たした。34-35歳頃より光琳と称した。39歳頃より画家になる。1699年、弟・乾山は鳴滝に開窯し、光琳は絵付けを手伝う。1701年、二条綱平の推挙により法橋に叙せられ、「小形」を用いた。1703年、奢侈禁止令の咎により「京市中住居お構い」により京都を追われる。1704年、江戸に一度出る。肖像画「中村内蔵助像」を描く。酒井家・津軽家などの大名屋敷にも出入りした。1709年、京都に戻る。1711年、自ら設計した建物で創作活動に打ち込む。59歳。 初め狩野派の画技を学び、土佐派、俵屋宗達・宗達派、光悦蒔絵、野々村仁清にも影響を受ける。独自の大和絵画風(後の琳派)を大成した。銀座役人・中村内蔵助、材木商・冬木家らが支援した。本格的な画業を始めたのは、晩年の20年ほどだった。作品に繰り返される絵柄で構成された「燕子花(かきつばた)図屏風」(国宝、18世紀前半)、宗達を模写し、宗達の「風神雷神図屏風」を意識した傑作「紅白梅図屏風」(国宝、18世紀前半)などがある。乾山に協力し絵付けを行った「黄山谷観鴎図角皿」、工芸「八橋蒔絵螺鈿硯箱」(国宝)、「白地秋草模様小袖」(重文)などの傑作を遺した。屏風絵のほか、香包、扇面、団扇、小袖、蒔絵、水墨画なども幅広く手がけた。 妙顕寺・興善院(後に泉妙院)(上京区)に葬られた。墓は、妙顕寺の塔頭・善行院の南にもある。 ◆仏像・木像 ◈本堂須弥檀に「一塔両尊(題目宝塔・釈迦如来・多宝如来)」・四士像(安立行菩薩・浄行菩薩・上行菩薩・無辺行菩薩)」合掌印を安置している。 宝塔があり本尊の十界曼荼羅に「南無妙法蓮華経」と書かれている。向かって左に釈迦如来が安置されている。「黄金釈迦如来像」と呼ばれ日蓮の念持仏だった。右に多宝如来、日蓮、日朗、日像、本覚、文殊菩薩、普賢菩薩、四天王などが安置されている。宗祖だけではなく三宝諸尊(日蓮、日朗、日像)の等身大像が祀られるのが当山の特徴になっている。 ◈「日蓮聖人坐像」がある。鎌倉時代-南北朝時代、14世紀(1301-1400)、院與作になる。 ◈尊神堂に「鬼子母神」を祀る。安産子易祈願の信仰を集める。 ◈三菩薩堂に日蓮、日朗、日像を安置する。 ◈御真骨堂に三師の舎利を納めている。 ◆建築 江戸時代後期、1788年、天明の大火後に伽藍が再建された。本堂、客殿、三菩薩堂、表門など7棟が京都府指定有形文化財に指定されている。 ◈「勅使門」は、天皇家のみが通ることを許されていた。南北朝時代、1334年に妙顕寺は、宗門初の勅願寺に認められたため現在も残されているという。 ◈「本堂」は、江戸時代後期、1830年に上棟、1839年頃に完成した。1788年の天明の大火以前の姿に復元された。京都屈指の規模がある。 日蓮宗様式を踏襲している。かつて天井画として「二大龍王図」があり、2匹の龍が描かれていた。現代、1975年に老朽化により天井が崩れ修復ができなかった。そのため、格天井の一つ一つの枡内に、寄進した檀信徒の家紋が描かれている。豪華な天蓋の内側に8人の天女が描かれている。内陣に三宝諸尊(日蓮、日朗、日像)の等身大像が安置されている。扁額「四海唱導」は、北朝第4代・後光厳天皇により大覚に贈られた称号になる。御所紫宸殿に見られる蔀戸がある。 入母屋造、総欅造。15間/16面4面、間口28m、奥行25m、瓦葺。 ◈「三菩薩堂」は、日蓮、日朗、日像を祀る。南北朝時代、1358年、妙顕寺2世・大覚により雨乞いが行われ、宗祖・日蓮に「大菩薩号」、開祖・日像と、その師・日朗に「菩薩号」が与えられた。このため、「三菩薩堂」と呼ばれた。扁額「勅賜三菩薩」が掛かる。 檜材、入母屋造、瓦葺。 ◈「鬼子母神堂」は、入母屋造流向背、瓦葺。 天皇が参詣したという。安産・子どもの守護神、最悪を除き福をもたらす鬼子母神が祀られている。 ◈「御真骨堂」は、総檜、二層造、瓦葺。 ◈「鐘楼」は、江戸時代後期、1788年の天明の大火で焼失後に再建された。現代、1965年、大門の東隅から、五重塔があった現在地に移築された。 「梵鐘」(京都府指定有形文化財)は、江戸時代中期、1713年の鋳造による。 ◈「大客殿」は入母屋造、瓦葺。 ◈「書院」は入母屋造、瓦葺。 ◈「奥書院」は入母屋造、瓦葺。 ◈「御真骨堂」には、日蓮大聖人・日朗聖人・日像聖人の眞舎利を祀った、近代、52世・福田日耀上人の代に再建された。鉄筋コンクリート多宝塔型、瓦葺。 ◈「宝蔵」は、土蔵造、瓦葺。 ◈「庫裏」は、入母屋造、瓦葺。 ◆庭園 ◈大客殿の前庭は、「龍華飛翔(りゅうげ-ひしょう)の庭(四海唱導の庭)」という。枯山水式庭園になる。「四海唱導」とは、世界中のあらゆる人々を法華経の教えに導き、その功徳により人々を救済する意味が込められている。 朝廷・貴人を迎えるための庭だった。南に勅使門があり、本堂の大屋根が借景になっている。白砂に南北に延壇が直線に敷かれ、東に石組みがある。左奥の3石は滝を表し、流れ落ちた水流はやがて白砂の大海に導かれる。サクラ、カエデなどが植えられている。 ◈「光琳曲水の庭」は、書院前庭になる。かつて江戸時代前期-中期の画家・尾形光琳(1658-1716)自ら作庭した庭があったという。尾形家は妙顕寺の檀家であり、光琳とも関係があった。 江戸時代後期、1788年の天明の大火により庭園も失われた。後に、宝物庫に残されていた光琳筆の「松竹梅図」の掛軸を元にして新たに作庭された。 樹齢400年の赤松の大木があり、それを中心にし川の流れを表現している。枝は、釈迦が人々の救済のために多方面に慈悲の手を差し伸べた姿を表すという。樹齢200年の黒松、梅、白砂、苔地、飛石、石橋、植栽などで構成されている。 ◈「孟宗竹林の坪庭」は、書院の南にある。五角形の庭面に、苔地に法華経に因み28本の孟宗竹が植えられている。 ◈「抱一曲水の庭」は、書院の西にある。光琳曲水の庭と対をなしている。尾形光琳百回忌の際に、江戸時代中期-後期の画家・酒井抱一(1761-1828)により奉納された「観世音図」の中に描かれた花が咲き誇る。白砂、石組、苔地、植栽などで構成されている。白砂の川が流れ石橋が架かる。蹲踞、水琴窟がある。 ◈塔頭・本妙院に「本妙院庭園」(京都市指定名勝)、塔頭・教法院に「妙顕寺北之方丈」(御題目庭園)などがある。 ◆文化財 ◈室町時代の紙本墨書「後小松天皇宸翰御消息」(重文)、「後醍醐天皇綸旨」(重文)、「後光厳天皇綸旨」。 ◈鎌倉時代-江戸時代の日像・日像・大覚ら7代の歴代書状などの「妙顕寺文書」(重文)。 ◈鎌倉時代の日蓮筆「神国王書」2巻(重文)、日蓮真筆「玄旨伝法本尊」、日蓮真筆「強仁状御返事」、ほか「八宗違目抄」、「三八経」、「消息断片数軸」など。 ◈日像筆の細字「極細字法華経」。鎌倉時代の「金字法華経巻第五」。 ◈狩野山楽筆の紙本金地墨画「 楼閣山水図 六曲屏風」(京都市指定有形文化財)。 ◈尾形光琳が晩年に描いた現存唯一の絵「寿老松竹梅図 三幅対」。 ◈酒井抱一筆「観世音菩薩像」は、光琳100回忌に描かれた。 ◈歴代の曼荼羅が遺されている。 ◈古文書の多くは竜華文庫に収蔵されている。 ◆妙顕寺型燈籠 本堂前の2基の常明燈は、「妙顕寺型燈籠」と呼ばれている。 家屋型であり、屋根は入母屋造、軒裏に垂木がある。江戸時代前期、1661年作。 ◆寿塔 江戸時代前期、1628年に、寿福院は、巨大な十一重石塔の寿塔(寿福院寿塔)を立てた。客殿前にある。基壇に「加越登三州大守御母堂」「寿福院日栄」と刻まれている。 ◆日像の逸話 日像(1269-1342)に関する逸話がある。 鎌倉時代後期、1294年旧4月28日の早朝、日像(1269-1342)は日蓮(1222-1282)の立教開宗の聖日に京都御所内裏の東御門に立ち、お題目を唱え京都弘通(ぐづう、布教)を宣言した。唱題は夕方まで続き、内裏警護の武士たちはその大音響に圧倒されたという。 旧5月13日・21日にも辻説法を行った。五条西洞院の造り酒屋「柳屋」の仲興氏の老婦人・妙蓮法尼は、日像の教えに深く共感し、町衆最初の檀越になったという。その邸宅は、妙顕寺が創建されるまで日像の京都の拠点になったという。 ◈南北朝時代、1333年に日像(1269-1342)は護良親王(もりなが-しんのう、1308-1335)の令旨により、隠岐の島に流されていた第96代・後醍醐天皇(1288-1339)の還幸を祈願し法華経千部を読経したという。護良親王は天皇の第1皇子になる。 その年に、天皇は京都に戻り、この功績により、尾張・備中3カ所の寺領が寄進された。さらに、宮中参内・法華経上奏を求める天皇の使者が訪れた。 1334年旧4月14日に、日像は参内し天皇に上奏を行い、天皇により勅願寺の綸旨を賜る。法華宗(日蓮宗)は朝廷の公認を受け、日蓮(1222-1282)の遺言である帝都弘通が実現した。 以来、千部会「所願成就会」(4月14日)が執り行われている。 ◈ある時、日像(1269-1342)は京都の四条辻で辻説法を行っていた。祇園御霊会(祇園祭)で、町衆が神輿を牛に曳かせて通りかかる。牛は日像の前で聞き耳を立てまったく動かなくなった。日像がお題目を唱え、曼荼羅をしたため神輿に掲げたところ、牛はたちまち動き出した。喜んだ町衆はともに題目を唱え踊り出したという。以来、町衆が建てた鉾には、大曼荼羅本尊が掲げられるようになったという。 妙顕寺創建時の日記『花園天皇宸記』(1321年旧7月24日)には、鉾を取り巻く「鉾衆」の周りで、「鼓打」が風流の舞を演じたとある。これが山鉾巡行の原型とされる最古の記録という。祇園祭は別名「祇園法華祭」とも呼ばれた。町衆・有力商人がこぞって法華経に帰依し、鉾を建て練ったという。 ◆妙実の逸話 南北朝時代、1358年の夏は京都で旱魃になった。大覚妙実(1297-1364)は、北朝第4代・後光厳天皇(1338-1374)の勅により、桂川鳥羽の畔で読経僧数百人と徒雨乞を行う。法華経一部の読し始め、一巻が終わらないうちに俄に大雨が降り始めた。雨は数日間降り続き、人々は大いに喜んだという。 雨は龍神の御加護であり、妙顕寺の守護神とされ、八房大龍神が当寺に勧請された。天皇はこの功績により、日蓮(1222-1282)に大菩薩号、日像(1269-1342)・日郎(1245-1320)に菩薩号を授与し、妙実は大僧正の僧階を賜った。以来、妙顕寺は朝廷・幕府との関係を深め、足利尊氏(1305-1358)からは寺領を寄進された。 最盛期には宗門随一の栄華を誇り、日像の院号の龍華樹(寿)に因み「龍華」と呼ばれたという。 ◆題目の巷 日像(1269-1342)らの布教活動により、京の町には法華信者が増え、「題目の巷」とまでいわれた。近世の芸術家の中にも多くの信者が現れている。 室町時代後期の画家・狩野元信(1476-1559)、室町時代後期-江戸時代前期の画家・長谷川等伯(1539-1610)、室町時代後期-江戸時代前期の能書家・工芸家・本阿弥光悦(1558-1637)、安土・桃山時代-江戸時代前期の画家・俵屋宗達(?-?)、江戸時代前期-中期の画家・工芸家・尾形光琳(1658-1716)、江戸時代前期-中期の陶工・画家・尾形乾山(1663-1743)などの名がある。 ◆分立・分出 妙顕寺一門としては、妙覚寺、立本寺があり、山号をともに具足山という。その後分立した。また、妙蓮寺、本隆寺も分出した。 ◆支院 久本院、大妙院、十乗院、恵命院、本妙院、実成院、教法院院、善行院、法音院、泉妙院がある。 ◆歴代 江戸時代の16世・僧那院日豊(?-1669)は池上本門寺19世、17世・隆源院日延(?-1681)は身延29世、20世・勝光院日耀(?-1697)は中山法華経寺40世、24世・南無院日妙(?-1710)は法華経寺49世になった。 ◆慶中稲荷 「慶中稲荷」はかつて京都御所に祀られていた。御所鎮護の守護神であり、願い事が必ず叶うといわれた。宮中に仕える女官たちに尊崇されていた。 ◆妙顕寺城 安土・桃山時代、1583年、羽柴秀吉(1537-1598)は、妙顕寺の境内地に妙顕寺城を築造し、寺は小川寺ノ内に移転させた。 跡地には、二条新邸を築造した。平素は前田玄以(1539-1602)が政務を行い、秀吉上洛の際に宿舎になった。1586年の聚楽第の造営まで、京都の政庁として機能した。 現在は、「妙顕寺城址碑」(中京区古城町、押小路通小川西入北側)が立てられている。 ◆遺跡 室町時代後期、1536年に、比叡山衆徒、南近江の守護六角氏らは京都の法華宗二十一本山を焼き討ちした。この天文法華の乱に備えた構え跡の遺跡がある。 ◆墓 ◈塔頭・善行院に江戸時代の絵師で工芸家の尾形光琳(1658-1716)の墓があった。江戸時代後期、1819年に画家・酒井抱一(1761-1828)が建立したという。現在は、墓跡に顕彰碑が立てられている。 塔頭・泉妙院にも尾形光琳の墓がある。 ◈陶工・絵師の尾形乾山(1663-1743)の墓がある。光琳は次兄になる。 ◈安土桃山時代-江戸時代の武将で、加賀藩第3代藩主・前田利光(利常、1594-1658)の墓がある。 ◆樹木 イブキは区民の誇りの木に指定されている。オガタマノキが植えられている。 ◆宿坊 女性専用の宿坊があり、宿泊できる。 ◆年間行事 新年祈祷会(1月1日-3日)、二の午慶中様大祭(2月)、彼岸会(3月)、法華千部会(4月14日)、法華懺法会(後醍醐天皇聖忌会)(6月16日)、盆施餓鬼法要(8月10日)、彼岸会(9月)、宗祖御会式(開山日像菩薩御会式)(11月13日)、冬至除災祈祷会(お焚き上げ)(12月8日)。 鬼子母神大祭(毎月8日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 妙覚寺の案内板・解説板など、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の寺社505を歩く 上』、『事典 日本の名僧』、『日蓮宗寺院大鑑』、『第49回 京の冬の旅 非公開文化財特別公開 ガイドブック』、『京都大事典』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『京都隠れた史跡100選』、『京都 神社と寺院の森』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、『京都の隠れた御朱印ブック』、ウェブサイト「妙覚寺」、ウェブサイト「コトバンク」 |
| |
|
| |
|