|
|
|
| 有栖川宮旧邸・京都地方裁判所所長旧官舎 (京都市上京区) Former Residence of Prince Arisugawa |
|
| 有栖川宮旧邸 | 有栖川宮旧邸 |
 |
 |
 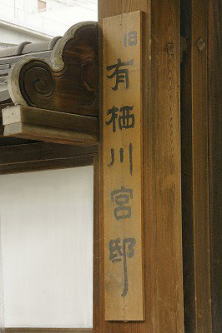 青天門    長屋門  屋敷内から見た長屋門  玄関  客間、左手に南庭、右に中庭がある。  「床の間」と「付書院」(左手)による「上段の間」  「付書院」  引き手金具にも菊花紋があしらわれている。  旧邸が移築されたと見られる「和室」  板の間、矢筈敷(檜垣組)  梁は、贅沢な一本の部材を使ってある。  南庭  中庭  枝垂れ桜  |
京都御所の西に、宮家・有栖川宮(ありすがわのみや)旧邸、かつての京都地方裁判所所長官舎の旧官舎が残されている。 現在は「平安女学院大学有栖館」として利用されている。 ◆歴史年表 有栖川宮邸は、京都御所南にある建礼門の前付近に建てられていた。 近代以降、1873年、9月より一時期、京都裁判所の仮庁舎として使用される。 1891年、3月、現在地に移築された。 現代、1952年、三井下鴨別邸内の顕名霊社中門(平唐門)が現在地に移築されている。 2007年まで、京都地方裁判所所長官舎として使われた。 その後、民有地になる。 2008年、8月、学校法人・平安女学院の所有となる。現在は「伝統文化の教育や文化活動の拠点」として活用されている。 ◆好仁親王 江戸時代前期の皇族・好仁親王(よしひと-しんのう、1603-1638)。幼称は七宮、三宮、通称は永照院宮、花町宮。父・第107代・後陽成天皇、母・中和門院の第7皇子。第108代・後水尾天皇の弟。1612年、親王になる。1625年、高松宮の称号を受け一家を創立した。36歳。 有栖川宮(ありすがわのみや)家の祖。 ◆幸仁親王 江戸時代前期の皇族・幸仁親王(ゆきひと/こうじん-しんのう1656-1699)。幼称は二宮。父・第111代・後西天皇、母・清閑寺共子(ともこ)の第2皇子。1654年、父即位後に3代・高松宮を継ぐ。1669年、親王になる。1672年、有栖川宮(ありすがわのみや)と改称した。後に式部卿になる。44歳。 和歌、文、書、絵、茶に秀でた。第112代・霊元天皇より能書方、書道の入木道(じゅぼくどう)を伝授された。 ◆有栖川宮 宮家の有栖川宮(ありすがわのみや)は、世襲四親王家の一つになる。歌道、書道が家学とされた。 江戸時代前期、1625年に、第107代・後陽成天皇の皇子・好仁(よしひと)親王(1603-1638)が高松宮家を創立した。称は親王の養母・新上東門院(1553-1620)の居所である高松殿に由来する。 好仁親王に嗣子がなく、2代は第108代・後水尾天皇の皇子・良仁(ながひと)親王(1637-1685)で、花町宮と称した。のち皇位を継ぎ、第111代・後西天皇になったため、継嗣を絶ち14年間途絶える。 1667年に後西天皇の皇子・幸仁(ゆきひと)親王(1656-1699)が3代を継ぎ、1672年に後水尾法皇の命により有栖川宮と改称した。墓所が有栖川(北区紫野)にあったことに因む。 4代・正仁(ただひと)親王(1694-1716 )の早世後、5代は第112代・霊元天皇皇子・職仁(よりひと)親王(1713-1769)が継いだ。以来、6代・織仁(おりひと)親王(1754 1820)、7代・韶仁(つなひと)(1784-1845)、8代・幟仁(たかひと)親王(1812-1886)、9代・熾仁(たるひと)親王(1835-1895)、10代・威仁(たけひと)親王(1862-1913)と続く。 近代、1908年に威仁親王の王子・栽仁(たねひと)王(1887-1908)が早世する。1913年の威仁親王の死去に伴い、有栖川宮は300余年で廃絶した。同年に第123代・大正天皇の勅旨により、天皇皇子・宣仁(のぶひと)親王(1905-1987)が、高松宮の称号により有栖川宮の祭祀を継承した。 ◆三井高保 江戸時代後期-近代の実業家・三井高保(みつい-たかやす、1850-1922)。幼名は宸之助、号は華精。京都の生まれ。父・三井総領家8代・三井高福、母・津尾の5男。弟に三井高棟。幕末期、三井京本店で営業見習修業し、1868年、維新後に東京呉服店に移った。三井室町家・三井高良の養子になり、同家10代目当主になる。1876年、三井銀行設立時に発起人に名を連ねた。1884年、高保と改名する。1887年、三井物産社長・益田孝と共に、銀行業務視察のために欧米各国を巡る。1890年、京都博覧会社副頭取、1889年に同頭取になる。1891年-1920年、三井高喜に代り、三井銀行総長(社長)に就いた。副長・中上川彦次郎を登用し経営改善にあたる。1909年、三井合名会社の設立により業務執行社員になった。73歳。 三井室町家10代。三井銀行の発展に努め、総帥・三井高棟を支え、三井11家の指導格の地位にあった。表千家流の茶人だった。 ◆小川治兵衞 近現代の造園家・11代・小川治兵衞(おがわ-うえじ、1942-)。小川雅史。父・9代目・小川治兵衞の次男。 1962年、京都市立日吉ケ丘高校特別美術コース(日本画)を卒業した。1966年、京都市立美術大学 (現・京都市立芸術大学)を卒業する。在学中に新製作日本画本展・京展に入選する。 その後、「造園植治(ぞうえん-うえじ)」(東山区)に勤務した。1970年、11代目・治兵衞を受け継ぐ。 現在は造園植治の代表取締役会長に就任している。著『「植治の庭」を歩いてみませんか』 。 ◆建築 ◈有栖川宮旧邸は、江戸時代、初代・好仁親王(1603-1638 )の時に、京都御所の北東、猿ヶ辻付近にあった。 江戸時代後期、1865年、幟仁親王(1812-1886)の時に、京都御所拡張のために召し上げられる。1866年までに建物・敷地も消滅した。 代替地として、京都御苑内建礼門前の松平容保(1835-1893)の宿舎跡があてられた。凝華洞(御花畑)跡になる。 近代、1869年に新御殿が完成する。東京遷都後の1872年に、幟仁親王(1812-1886)は東京へ移る。土地家屋は京都府、司法省を経て、1873年9月より一時期、京都裁判所の仮庁舎として使用される。1891年3月に、現在地(京都御苑東)に移築された。京都地方裁判所所長官舎裁判所として転用され、2007年まで使用された。 その後、民有地を経て、2008年8月に、学校法人・平安女学院の所有になり、現在は「有栖館」として残されている。 ◈有栖川宮旧邸は大きく分けて、公家屋敷と武家屋敷の2つの様式からなり、さらに後世の増改築が施された、高級官僚官舎の様相が加わる複合的な建築様式になる。 建物内部は、「玄関棟」「住居棟」「客間棟」という3つの棟からなる。 ⋄和室の「客間」は、有栖川宮旧邸がそのまま移築されたと見られる。書院造りの様式を備えた部屋で12畳半ある。「床の間」と「付書院」を備えた2畳の「上段の間」がある。また、中庭を挟んだ北西隅の「和室」も旧邸の様式を残しているとみられている。 幕末-大正期にかけての高級官僚官舎の様相を伝える、15畳のケヤキの部材を使った板張りの「板間」「能舞台の間」がある。板は、「ハの字」に組まれ、床下には、音響効果を高めるための大甕が埋められているという。 ⋄「長屋門」は、南側の下立売通に面している。創建年は不明という。長屋門形式としては最上級の構えといわれ、白漆喰塗になる。門の両側は長屋で、門番部屋として、家臣・使用人の居所などに利用されていた。あるいは、屋敷内から見て右手は、居住に、左手は納屋として使ったともいう。これらの様式は、近世諸大名の武家屋敷門として江戸時代に多く建てられたという。 ⋄「青天門」は、烏丸通に面している。表門として銅板と真鍮板で葺かれた平唐門になっている。塀とともに、大正期の門建築の作例として評価が高いという。 近代、1912年に、三井銀行総長・社長の三井高保(1850-1922)私邸(室町通竹屋町)の表門として新築された。その後、三井家下鴨別邸(左京区)の顕名霊社の中門(平唐門)として移築された。さらに、1952年に下鴨別邸敷地が国有化された際に、現在地に再移築された。 名の由来は、その年の仲秋の名月の夜、当時の所長・石田寿と親交があった歌人・吉井勇(1886-1960)により、李白の詩より「青天門」と名付けられたという。 ◆庭園 庭は南庭と中庭の2庭ある。2009年、「植治(しょくじ)」の第11代・小川治兵衛(1942-)の作庭による。 枯山水の南庭は、石組と飛石、白砂、苔地、植栽を使った、丸、三角、四角と多形で多彩な構成になっている。 中庭は、石の囲いの中に、白砂、刈り込みによる州浜で、現代的な枯山水の庭になる。 ◆しだれ桜 敷地内にある2本の枝垂れ桜は、1952年、現代の画家・堂本印象(1891-1975)の発案により、醍醐寺三宝院内の実生の桜を移植した。 安土・桃山時代、太閤秀吉(1537-1598)の「醍醐の花見」(1592)当時の桜の孫にあたるという。 ◆年間行事 秋の特別公開(10月30日-11月3日)。 *普段は非公開。 *年間行事は日時など変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 駒札、『京都大事典』、『日本の名家・名門人物系譜総覧』、『歴史読本 天皇宮家人物総覧』、ウェブサイト「明治初期における京都御苑の造成について - J-Stage」、ウェブサイト「重要文化財(建造物) 旧三井家下鴨別邸保存活用計画案-京都市文化市民局文化芸術都市推進室 文化財保護課」、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |
| |
|