|
|
|
| 大雲院(祇園閣) (京都市東山区) Daiun-in Temple |
|
| 大雲院(祇園閣) | 大雲院(祇園閣) |
 |
 |
 総門   総門  南門  南門  南門   本堂  本堂   鐘楼  鐘楼  祇園閣      祇園閣、「祇園閣」の扁額、初層  祇園閣、西園寺公望筆「祇園閣」の扁額、初層  祇園閣、最上階の扁額、大倉喜八郎筆「萬物生物光輝」  祇園閣の鉾先の鶴の飾り物  祇園閣、初層の銅板の扉、鶴の彫り物がある。  祇園閣、初層の銅板の扉、鶴の彫り物    大倉喜八郎の別邸「真葛荘」(書院)(国登録有形文化財)  書院  書院の六角の蹲踞  弁財天  佐土原藩戦没招魂塚  平和観音  仏足石   圓山地蔵尊  墓地   織田信長・信忠の碑  石川五右衛門の墓  祇園閣からの東山の眺め  祇園閣からの八坂の塔、八坂の景観  祇園閣からの南西の眺め、澄んだ日には二つのアンテナの間に大阪城が見えるという。近くの高台寺からも同じように見え、豊臣秀吉の側室・北政所(ねね、高台院湖月尼、1542-1624)は、1615年の大坂城落城の時、高台寺から城より立ち昇る煙を見ていたという。 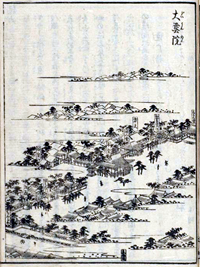 【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている大雲院(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |
大雲院(だいうん-いん)は、「貞安寺(じょうあん-じ)」とも呼ばれる。境内には、祇園祭の山鉾様の祇園閣が建てられている。正式には大雲院祇園閣という。山号は龍池山という。 浄土宗単立寺院、本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1587年/天正年間(1573-1592)、第106代・正親町(おおぎまち)天皇の勅命により、1582年の本能寺の変で亡くなった織田信長、信忠父子の菩提を弔うために建立された。当初は、信忠自刃の地である御池御所(正親町天皇第1皇子・誠仁親王邸、二条新御所、烏丸二条南)にあり、寺地は正親町天皇より与えられたという。安土宗論で知られる聖誉貞安(ていあん)が開山になり、信忠の法名「大雲院殿三品羽仙厳大居士」に因み龍池山貞安寺大雲院と名付けられた。当初は、浄土宗知恩院に属した。 1590年、豊臣秀吉は、寺域が狭いとして寺町四条(下京区貞安前之町)に移させた。以来、第107代・後陽成天皇より勅願所の綸旨を得る。島津以久以後、同家の帰依を受けた。釈迦堂が建てられる。 1591年、第107代・後陽成天皇により勅願寺になり、「大雲院」の勅額を贈られた。信長、信忠父子の石塔が建立される。 1592年、京都奉行・前田玄以が境内に制札を掲げる。 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)、日向国佐土原(さどわら)城城主・島津以久(ゆきひさ)の帰依により、以来、毎年、米100石の寄進を受けた。 1599年、堂宇新築落成になり、華道家・池坊専好(いけのぼう-せんこう)は祝し、大立花会「百瓶華会(ひゃくへいかかい)」を催し絶賛を得る。 江戸時代、元和年間(1615-1624)、3世・信誉は開山堂を建立する。貞安上人像を安置した。 1641年、第110代・後光明天皇は、祇園会を観覧した。 1788年、天明の大火により焼失する。画家・円山応挙の描いていた完成真近い「松に孔雀図」も失われる。 1792年、再建される。 1864年、禁門の変では、島津藩兵により類焼を防いだ。 近代、1868年、復興した。 1889年、第一回京都市会が開催される。 1919年、6月1日、大雲院内に市職業紹介所が開設される。(『京都市政史』) 現代、1954年、本堂を建立する。 1973年/1972年、髙島屋京都店の増床に伴い、大雲院は現在地の大倉邸内に移転した。阿弥陀像が安置される。 1997年、祇園閣は国の登録有形文化財に登録された。 2014年、大雲院跡地(河原町通四条下ル)より、豊臣秀次の供養塔の一部が発見される。 ◆貞安 室町時代後期-江戸時代前期の浄土宗の僧・貞安(ていあん、1539-1615)。男性。字は退魯、号は敬蓮社聖誉、聖誉貞安。相模国(神奈川県)の生まれ。父・後北条氏の一族・北条能登守満教、母・大江正時の娘。4歳で母、5歳で父と死別し、姨母に養育された。7歳で小田原・大蓮寺の一蓮社堯誉上人還魯文宗の室に入り、11歳で剃髪。14歳で師に従い下総・飯沼の弘経寺へ移る。同寺7世・見誉善悦の法を継ぐ。1572年、香衣綸旨拝載のために上京。1573年、弘経寺の首座。1575年、能登七尾・西光寺にあり、上杉謙信の穴水城攻より逃れ、1576年、近江・妙金剛寺へ移る。織田信長の帰依を受けた。1579年、貞安の斡旋により、知恩院は信長より寺領100石の加増を受ける。貞安は信長より安土田中に寺領を得る。能登七尾・西光寺に倣い、龍亀山西光寺を建立した。 1579年、信長の命により、安土・浄厳院(じょうごん)での宗論に参加し、霊誉玉念らと法華経の日晄らを論破する。以後、信長の信任を得る。1582年、本能寺の変で信長没後、1583年、上洛して淨教寺に入る。1585年、第106代・正親町天皇の勅請で御所参内し「選擇集」を講じ、僧伽梨大衣を贈られる。1586年、紫宸殿で陽光院親書の「阿弥陀経」を贈られる。1587年、正親町天皇の勅命により、信長、信忠父子の菩提を弔うために、大雲院、伏見・勝念寺を創建した。1594年、石川五右衛門の処刑前に引導を渡す。1595年、豊臣秀次の切腹に伴い、妻妾、幼児などは三条河原で打首になる。貞安は刑場の一隅に地蔵尊を運び、子女らに引導を授けた。1599年、大雲院移転により、「百瓶華会」を催した。1615年、二条城で徳川家康に謁した。大雲院・栖養院に隠棲した。77歳。 ◆織田 信長 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・織田 信長(おだ-のぶなが、1534-1582)。男性。幼名は吉法師(きちほうし)、三郎、官名は上総介(かずさのすけ)。尾張(愛知県)の生まれ。父・守護代家老・織田信秀、母・土田御前。1546年、元服し、1547年、三河へ初陣、1549年、美濃・斎藤道三の娘・濃姫と結婚した。1551年、父没後、家督を継ぐ。1557年、弟・信行らの反乱を抑え、1558年、信行を暗殺した。1559年、岩倉城主・織田信賢を破り尾張国を統一した。1560年、桶狭間の戦で駿河・今川義元を討つ。1562年、三河・松平元康(徳川家康)と同盟を結ぶ。1563年 、本拠を小牧山城に移転した。 1567年、美濃・斎藤龍興を滅ぼし、稲葉山・井ノ口城を岐阜城に改める。1568年、近江・六角義賢を追い上洛し、足利義昭の将軍職就任を助けた。二条御所の造営を行う。1569年、北伊勢・北畠氏を屈伏させ、二男・信雄を養子に入れる。イエズス会・フロイスの京都往還を許した。軍資金提供を要求し拒否した自治都市・堺を攻める。1570年、姉川の戦で信長・家康の連合軍は浅井長政・朝倉義景の連合軍を破る。摂津で三好三人衆を討ち、石山本願寺との合戦も起こる。1570年-1574年、伊勢・長島の一向一揆を鎮圧した。1571年、浅井らに与した延暦寺を焼討した。1573年、将軍義昭を追放し、室町幕府を滅ぼす。示威のため上京を焼く。1575年、長篠の戦で家康と連合し、鉄炮隊により武田勝頼を破る。従三位権大納言兼右近衛大将になり、岐阜城を本拠とし、家督を嫡男・信忠に譲る。1576年、拠点になる安土城を築く。1577年、従二位右大臣になる。1580年、石山本願寺(大坂本願寺)と和睦し、畿内は平定される。中国の毛利氏攻略に動く。第106代・正親町天皇の東宮誠仁(さねひと)親王を猶子とし、1581年 、内裏東で京都御馬揃えを催した。1582年、甲斐・武田氏を滅ぼし、信濃の北口を平定した。中国の毛利氏を攻めるため本能寺に宿泊し、家臣・明智光秀に討たれ自害した。全国統一の業半ばで倒れる。(本能寺の変)。49歳。 墓は大徳寺・総見院(北区)、阿弥陀寺(上京区)、本能寺(中京区)、大雲院(東山区)、建勲神社(北区)は信長を祀る。 ◆織田 信忠 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・織田 信忠(おだ-のぶただ、1555-1557)。男性。幼名は奇妙(丸)、初名は信重、通称は菅九郎。尾張国(愛知県)の生まれ。父・織田信長、母・久庵慶珠の長男。1567年、武田信玄・五女・松姫と婚約した。1570年、父に従い長島の一向一揆をした。1572年、岐阜城で元服する。信長が信玄と敵対し、婚約解消した。父とともに近江小谷城の浅井長政を攻め初陣を飾る。父に従い、石山合戦、1574年、岩村城の戦い、伊勢長島攻めと転戦した。1575年、長篠の戦い、岩村城攻めで総大将として勝利した。1576年、父より家督、美濃東部、尾張国の一部を譲られ岐阜城主になった。正五位下に叙せられ、出羽介、秋田城介に任じられる。1577年、雑賀攻めで中野城を落とした。信貴山城の戦いの功により、従三位左近衛権中将に叙される。この頃より信長に代わり総帥として兵を率いる。1578年、上月城の戦い、1579年、有岡城攻め、1582年、甲州征伐で先鋒大将として甲斐の武田勝頼を討ち、恵林(えりん)寺を焼打し、快川紹喜ら150人の僧を焼き殺した。6月2日、本能寺の変で、信忠は備中高松城を包囲の羽柴秀吉への援軍のため、妙覚寺に宿泊した。信長の宿所・本能寺を明智光秀が急襲し、信忠は本能寺へ向かう。信長自害の報で二条新御所に移動し、異母弟・津田源三郎(織田源三郎信房)、側近・斎藤利治、京都所司代・村井貞勝らと篭城した。誠仁親王を脱出させ、明智軍・伊勢貞興の攻めにより自害した。26歳。 墓は阿弥陀寺(上京区)、大徳寺・総見院(北区)、大雲院(東山区)にある。 ◆前田 玄以 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・前田 玄以(まえだ-げんい、1539-1602)。男性。名は宗向、孫十郎基勝、号は半夢斎、策勝軒。美濃(岐阜県)の生まれ。父・前田基光。村井貞勝の娘婿。比叡山で出家し、尾張・小松寺の僧になる。織田信長臣下になる。1575年、信長の嫡子・信忠付の近習になった。1579年、信長の命で信忠の家臣になる。1582年、本能寺の変で信忠が自害し、その嫡男・三法師(秀信)とともに岐阜に逃れ清須に赴き保護した。この功により、1583年-1600年、信忠の弟・信雄より京都奉行に任じられる。以後、17年間在職し禁裡御用地・門跡領・寺社領管理などを行う。この間に朝廷から「徳善院」の称号を授かった。1584年、豊臣秀吉に仕え、右筆(ゆうひつ)ともいう。その信厚く、1585年、丹波亀山5万石を給される。1588年、第107代・後陽成天皇の聚楽第行幸で奉行、寺社奉行で当初はキリシタンを弾圧した。1595年、豊臣秀次の問責に当たり、妻妾を亀山に預った。1598年、豊臣政権下五奉行の1人に任じられた。同年、秀吉没後、徳川家康と石田三成の対立では三成方に属した。1600年、秀吉没後、遺骸を伏見城から阿弥陀ヶ峰に密かに葬送した。豊国社造営の普請奉行を務める。家康を討つよう長束正家・増田長盛らと諸大名に命じた。関ヶ原の戦は西軍に与し、大坂城に居り参戦しなかった。東軍・徳川方に通じ、戦後、京都所司代の職は解かれる。金剛寺(河内長野)に謹慎になり、家康に許され丹波亀山の本領安堵、初代藩主になる。64歳。 故事・典例・故実に通じ、千利休に茶を学んだ。秀吉の京都屋敷(妙顕寺城)の普請奉行になる。留守役を預かる。 墓は妙心寺・蟠桃院(右京区)、専念寺(左京区)、大雲院(東山区)にある。 ◆池坊 専好 安土・桃山時代-江戸時代前期の華道家・初代・池坊 専好(初代)(いけのぼう-せんこう、?-1621)。男性。池坊家31代。頂法寺(六角堂)の僧。1599年、大雲院で門人100人(浄土宗寺院・他宗派本山の僧88人、武士・町衆100人)と100個の銅瓶に花を生ける「百瓶華会」を開催し絶賛を博した。七つ道具(役枝)を考案した。著『池坊専好花伝書』など。 ◆石川 五右衛門 安土・桃山時代の盗賊・石川 五右衛門(いしかわ-ごえもん、?-1594)。詳細不明。男性。五郎吉。河内国(大阪府)の生まれ。17歳で家を出で伊賀の異人僧・臨寛に忍術を習い、郷士・百地三太夫に仕えたともいう。また、浜松・三好家家臣・石川明石の子で、16歳で宝物庫の金装具刀を盗み諸国放浪した。また、浜松の武士・真田八郎ともいう。盗賊団の首領になり、京都・大坂・堺の市中を荒らし、1594年、豊臣秀吉の命をうけた五奉行の一人、前田玄以に捕らえられる。三条河原(六条河原とも)で子・一郎、父母兄弟、郎党20人とともに釜ゆで(煮殺し)の刑に処されたという。37歳。 浄瑠璃、歌舞伎、読み本などの題材になる。 墓は大雲院(東山区)にある。 ◆島津 以久 室町時代後期-江戸時代前期の武将・島津 以久(しまづ-もちひさ/ゆきひさ、1550-1610)。男性。初名は幸久、征久、通称は又四郎。父・島津忠将(ただまさ)(島津忠良の子)の嫡子。右馬頭になる。1565年、大隅国帖佐郷を与えられ、要衝清水の領主になる。豊臣政権への島津氏の敗北により、島津領再編で種子島氏は薩摩の知覧に移され、1591年、種子島・屋久島・恵良部を領し種子島に移った。1603年、関ヶ原の戦で死去した島津豊久領の日向国佐土原(さどはら)領が徳川家康から与えられ、鹿児島藩の支藩・佐土原藩主・島津家初代になった。61歳。 墓は大雲院(東山区)にある。 ◆伊藤 坦庵 江戸時代前期の儒学者漢学者伊藤 坦庵(いとう-たんあん、1623-1708)。京都の生まれ。姓は藤原氏、名は宗恕、字は元務、号は自怡堂、白雲散人など。江村専斎、曲直瀬玄理(まなせ-げんり)に医学を学ぶ。藤原惺窩(せいか)の門人・儒学者・那波活所に学ぶ。のち、福井藩に儒官として仕えた。晩年、京都に退隠した。著『坦庵文集』、師・専斎の口述を集めた『老人雑話』など。86歳。 朱子学の研究に努め、詩文に優れた。 墓は大雲院(東山区)にある。 ◆円山 応挙 江戸時代中期-後期の画家・円山 応挙(まるやま-おうきょ、1733-1795)。男性。姓は源、字は僊斎など、号は一嘯など、通称は主水。父・丹波国桑田郡穴太村(亀岡市)の農業・丸山藤左衛門の次男。1740年頃、近くの金剛寺に小僧として入る。1747年、15歳で呉服屋「岩城」、後に高級玩具商「尾張屋」に入る。13-14歳で上京したともいう。17歳頃(15歳とも)、主人のつてで狩野派石田幽汀に絵を学ぶ。1759年、西洋渡来の覗き絵(浮絵)を制作する。1763年頃、宝鏡寺の蓮池院尼公を知る。1765年頃、円満院門主祐常と親交する。1766年頃、「応挙」と改名し、「応挙」の落款を用いた。1773年頃、「雲龍図」(東寺観智院旧蔵)を描く。1775年、「平安人物志」に画家部第一位で記載され、京都四条麩屋町西入に住んだという。1786年、紀州無量寺の障壁画を描く。1787年、一門とともに大乗寺(兵庫県香住町)障壁画を描く(第一期)。1790年、禁裏造営で一門により障壁画を制作する。1795年、一門とともに大乗寺障壁画を描く(第二期)、悟真寺(四条大宮西入)に葬られる。 応挙は大雲院で絵画を制作していた。だが、1788年、天明の大火で大雲院が焼失する。完成間近の「松に孔雀図」も焼失した。「孔雀の間」は1795年、大乗寺障壁画第二次制作により2度目の「松に孔雀図」を完成させる。遠目の絵の手法で描かれている。その年に没した。63歳。 ◆大倉 喜八郎 近現代の実業家・大倉財閥の創設者・大倉 喜八郎(おおくら-きはちろう、1837-1928)。男性。号は鶴彦。越後(新潟県)の生まれ。幕末維新期に江戸・東京で銃砲販売、新政府の御用商人として、軍需品の調達・輸送,鉄道・建物関係・土木建設、中国での炭鉱・鉄鉱山経営・製鉄事業、欧州、朝鮮との貿易、東京電灯、帝国ホテルなども設立した。1917年、大倉組は、大倉商事、大倉土木(大成建設)、大倉鉱業によるコンツェルン機構を形成した。93歳。 ◆伊東 忠太 近代の建築家・建築史家・伊東 忠太(いとう-ちゅうた、1867-1954)。男性。山形県の生まれ。東京帝国大学、早稲田大学教授。工学博士。日本建築史を創始し、『法隆寺建築論』(1893)により、法隆寺が日本最古の寺院建築であることを著した。法隆寺の柱の膨らみがギリシャ神殿に遡るとし、英国・ジェームス・ファーガソンに反論した。1923年、首里城正殿の保存に尽力した。1943年、建築界ではじめて文化勲章を受章する。86歳。 京都の主な作品としては、豊国廟(1898)、 旧・二条駅舎、真宗信徒生命保険(1912、京都、現伝道院)、祇園閣(1927)。そのほか伊勢両宮(遷宮)(1899)、明治神宮(1920)、共同で内務大臣等官邸(1915)など多数。 ◆本尊 本堂に、本尊「阿弥陀如来坐像」が安置されている。定印を結び、江戸時代作、六丈(3m)の大きさがある。 像内の内彫り部に室町時代-安土・桃山時代にかけてみられる「阿弥陀如来立像」(97.5cm)が納められており、創建時の本尊ともいう。 左に「信忠像」が安置されている。 ◆建築 ◈「総門」は、旧宮家の門であり、東京より移築されたという。 ◈「南門」は、四条寺町の旧地より移築された。 ◈「本堂」は、現代、1973年に建立された。平安・鎌倉の折衷方式の2階建てになる。鉄筋コンクリート造、寄棟造、本瓦葺。 ◈「祇園閣」(国・登録有形文化財)は、俗称として「銅閣」「銅閣寺」とも呼ばれる。大倉財閥の創始者・大倉喜八郎の別邸「真葛荘」に、近代、1928年/1927年に建立された。大倉は、御大典記念に祇園祭の鉾を常に見たいと願い、鉾を模して建築が始まる。京都に新たな観光名所を造るという意図もあったという。設計は伊東忠太(1867-1954)による。寺院の楼閣建築を模範にした。大倉は塔の完成を見ることなく亡くなる。その後、東伏見宮の仮住を経て、現代、1973年に寺院施設になる。 鉾先には、大倉の本名の鶴吉(鶴彦)に因み翼を広げた鶴(人の背丈ほど)が飾られている。上層の唐破風に紅龍石(こうりょうせき)による組物、蟇股がある。低層外壁は北木島(岡山県)産の錆色石の乱積みによる。中高層の軒裏、組物、高欄に赤みを帯びた紅龍石が使われている。それ以外の外壁は、モルタル塗りになる。塔の地下に隠し部屋がある。下中層の階段照明に、丸い電燈を魑魅魍魎(ちみもうりょう)が両手で支える意匠が施されている。魑魅魍魎は、設計者・伊東忠太の好みだったという。上層の天井に、銅板で円形に十二支が連なる中心飾などが見られる。塔の最上階に平和の鐘、初層には、1973年より阿弥陀像が安置されている。1988年、内部に敦煌壁画模写などが描かれた。1997年、国の登録有形文化財に登録された。 設計・伊東忠太、施工・大倉組。三階建、基礎・下層は鉄筋コンクリート造、中階層以上はSRC(鉄筋・鉄骨コンクリート)造、欄干、扉も銅製。屋根は銅板葺で金閣、銀閣に比する。高さ36m。 ◈「書院」(旧大倉家京都別邸)(登録有形文化財、国登録)は、大倉喜八郎の別邸「真葛荘」だった。近代、1927年に建立された。 木造の近代和風住宅になっている。中廊下式であり、東側に玄関、西側に廊下、南に応接室、食堂、居間、北側に台所、奥に鉄筋コンクリート造の寝室、納戸がある。八角形状の応接間は、16本の垂木を放射状に並べ、八角形の屋根を支える。窓、玄関に蔀戸を用いている。2階座敷(客間)に3畳台目の上段の間、格天井。床、付け書院、脇棚。 設計は数寄屋大工・北村伝兵衛親子(8代、9代)による。材は台檜を用いた。木造二階建、一部に鉄筋コンクリート造、桟瓦葺。 ◈「鐘楼」は、かつて北野天満宮にあり、江戸時代前期、1607年、豊臣秀頼が寄進した。近代、神仏分離令(1868)後の廃仏毀釈後、1872年に移転された。3間2面、重層、袴腰、入母屋造、桟瓦葺。 ◆文化財 ◈絹本著色「前田玄以像(重文)」。 ◈紙本墨書「正親町天皇宸翰消息」(重文)。 ◈「寺地指図」には、安土・桃山時代、1587年の前田玄以の花押がある。 ◈京都所司代・「村井貞勝(1520?-1582)の肖像画」がある。頭を丸めた姿になる。 ◈祇園閣内部には、「敦煌(とんこう)莫高窟(ばっこうくつ)壁画」の模写が描かれている。現代、1988年、中国の葛新民(1951-)筆による。莫高窟は中国甘粛省敦煌市の近郊にある仏教遺跡で、1987年にユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。 祇園閣に描かれているのは、最も早期(421-439)の272窟西壁龕内南北「脇持菩薩(北涼)」、盛唐時代(721-781)の320窟南壁「仏法説図」、172窟南壁「観無量寿経変相図」など。 ◈「梵鐘」は、室町時代、「延徳二年(1490年)」の銘があり、もとは祇園感神院(八坂神社)にあった。近代、神仏分離令(1868)後の廃仏毀釈後、1870年(1868年とも)、島津家が佐土原藩士の菩提を弔うために当山に寄進し移された。 ◆塔頭 かつて12院の塔頭が存在した。その後、本院に併合され、本光院、是住院、信養院、南昌院の4院が残る。本院の移転後、各院は独立する。 ◆火除天満宮 旧寺域(四条寺町)の一角には、いまも火除天満宮(下京区)がある。かつて大雲院の鎮守社であり、寺の移転後も残されている。 ◆豊臣秀次の供養塔 現代、2014年に、大雲院跡地(河原町通四条下ル)より、豊臣秀次の供養塔の一部が発見される。 五輪塔基礎に安土・桃山時代、「文禄四年(1595年) 禅昌院殿龍叟道意大居士 七月十五日」と刻まれていた。貞安が菩提を弔うために立てたとみられている。 ◆石川五右衛門の墓 石川五右衛門(?-1594)の墓にまつわる伝承が残る。五右衛門は、刑場に連行される途中に、当時の大雲院(四条寺町)の門前を通りがかり、貞安(1539-1615)の教化を受けたという。 貞安は、五右衛門に悔悛の情があったとして、引き取り手のなかった遺体を葬ることを豊臣秀吉(1537-1598)に頼んだ。秀吉は許し寺に埋葬された。ただ、世を憚り墓は立てなかったという。 江戸時代前期、1632年、五右衛門の33回忌を機に現在の墓を立て追善したという。墓石には、法名「融仙院良岳寿感禅定門」と刻まれている。 ◆葛覃居 江戸時代の文人画・池大雅(1723-1776)と妻・玉瀾(1727-1784)が暮らした草庵「葛覃居(かつたんきょ)」は、現在の大雲院の西南端付近だったという。 ◆文学 江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に挿絵入りで記されている。 ◆墓 ◈境内南西の墓地には、室町時代-安土・桃山時代の織田信長(1534-1582)、信忠(1557-1582)父子碑、日向国佐土原藩の初代藩主・島津以久(1550-1610)、京都奉行・前田玄以(1539-1602)。 ◈安土・桃山時代の大盗賊・石川五右衛門(?-1594)。 ◈江戸時代の儒学者・伊藤坦庵(1623-1708)、江戸時代中期の俳人・北条団水(1663-1711)、江戸時代後期の画家・望月玉川(1794-1852)、杉浦家、鳩居堂の熊谷家などの墓がある。 ◈近代の画家・儒学者・富岡鉄斎(1837-1924)の墓は、現在は旧塔頭・是住院(西京区)に遷されている。 *普段は非公開。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 参考文献・資料 『拝観の手引』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都古社寺辞典』、『京都の近代化遺産 近代建築編』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都大事典』、『続・京都史跡事典』、『京都 歴史案内』、『京都隠れた史跡100選』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『京都の洋館』、『おんなの史跡を歩く』、ウェブサイト「勝念寺」、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |