|
|
|
| 今熊野観音寺(観音寺) 〔泉涌寺〕 (京都市東山区) Imakumano-kannon-ji Temple |
|
| 今熊野観音寺 | 今熊野観音寺 |
 |
 |
  鳥居橋、今熊野川に架かる。        本堂     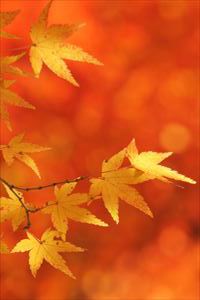     後白河法皇頭痛封じ霊験記を表す画  紋章 「今熊野浪」       大師堂  大師堂   大師堂  大師堂  地蔵堂  医聖堂     鐘楼   茶所     大講堂  大書院  子護弘法大師  ぼけ封じ観音  三重石塔  医心方の碑  「今熊野西国霊場」、西国三十三ヶ所霊場の本尊が石仏として祀られている。  稲荷社  熊野権現社  金龍弁財天  五智の井     市街地の眺望  「藤原三代の墓」  「島津逆修の塔」 |
東山三十六峰の今熊野山麓に今熊野観音寺(いまくまの-かんのん-じ)はある。今熊野の地は古くより貴人の葬所であり、平安時代には観音霊場として、また藤の名所にもなった。熊野権現出現の伝説地としても知られた。 後白河法皇(第77代)ゆかりの頭痛封じの伝承により、「頭の観音さん」と親しまれている。「今(新)熊野」「今(新)熊野観音」ともいう。正式には「観音寺」という。山号は後白河法皇より贈られた「新那智山」という。 泉涌寺の塔頭の一つで真言宗泉涌寺派、本尊は十一面観世音菩薩。 西国三十三所観音霊場の第15番札所、泉山(せんざん)七福神の第3番、恵比寿神は、商売繁盛、海運守護の信仰がある。ぼけ封じ・近畿十楽観音巡礼の第1番札所、京都七福神のえびす神、洛陽三十三所観音霊場の第19番札所、神仏霊場会第122番、京都第42番。弥勒菩薩(六七日)は京都十三仏霊場めぐりの第6番札所。京の通称寺霊場31番。 頭痛封じ・平癒、ぼけ防止、身体健康・健康長寿・病気平癒・無病息災、開運厄除・災難消除、家内安全、良縁成就、安産祈願、諸芸上達、心願成就、智慧授け・学業成就・受験合格、商売繁盛・社業繁栄、子護大師は子ども守護などの信仰がある。御朱印(6種類)が授けられる。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。 平安時代、807年/大同年間(806-810)/天長年間(824-834)、空海が熊野権現の霊示により、この地に庵を結んだことに始まるという。 812年/825年頃/弘仁年間(810-824)、空海は第52代・嵯峨天皇の寄進、勅により諸堂を造営したという。 天長年間(824-834)、伽藍は完成をみたという。 左大臣・藤原緒嗣(774-843)により、その邸に伽藍造営が図られたともいう。 855年、藤原緒嗣の子・春津に受け継がれ完成した。 969年、 左大臣・藤原師尹(もろまさ)を同寺西岡に葬る。 1016年、一条尼上(藤原道長室倫子の母・穆子 [ぼくし] )を無常所に葬る。 1135年、当寺が「二十五番札所」として記されている。(行尊『巡礼手中記』) 1150年、当寺が「十八番札所」として記されている。(長谷僧正『巡拝記』) 1160年、後白河上皇(第77代)がこの地の法住殿に熊野権現を勧請した。当山の本尊を本地仏と定め、「新那智山」の山号を贈り、今熊野観音と称した。 1161年、当寺が「二十六番札所」として記されている。(覚忠『巡礼記』) 平安時代-鎌倉時代、この地で、葬送、追善が行われる。 鎌倉時代、1234年、後堀河上皇(第86代)没後、当寺北の観音寺陵が築かれ埋葬された。観音堂は北面し、末永く本尊を拝するように葬られている。 1244年、第87代・四条天皇の二周忌に法華八講が修された。 鎌倉時代-南北朝時代、永暦年間(1331-1334)、山麓に新熊野神社が建てられた。今熊野は、紀州熊野の観音霊場になぞらえられた。その本地仏安置の寺とされ、社殿が山麓に造営された。神社と寺を結ぶ観音寺大路(現在の泉涌寺道)が通され、熊野御幸のための御潔斎場の御精進屋が観音堂近くに建立される。 室町時代、1468年、兵火により泉涌寺とともに焼失した。 1470年、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失する。北朝、足利将軍の援助により復興された。乱後、泉涌寺塔頭になったという。 1515年頃-1517年、今熊野観音寺別当・雲龍院と今村兄弟との間で、今熊野観音寺巡礼堂領をめぐる相論があった。 安土・桃山時代、1580年頃、現在の地に堂宇が建立されたとみられている。 江戸時代、西国霊場巡拝が盛んになる。 1712年/承徳年間(1711-1716)、宗絮祖元律師により、現在の本堂が建立された。 現代、2005年、「平成洛陽三十三所観音」が復興された。 ◆空海 奈良時代-平安時代前期の真言宗の開祖・空海(くうかい、774-835)。男性。弘法大師。讃岐国(香川県)の生まれ。父・豪族の佐伯田公(義通)、母・阿刀氏。788年、15歳で上京し、母方の叔父・阿刀大足に師事し儒学を学ぶ。791年、18歳で大学明経科に入るが、中途で退学し私渡僧(しどそう)として山岳修行を始め四国の大滝岳や室戸崎などで山林修行した。797年、『聾瞽指帰(ろうこしいき)』を著す。798年、槙尾山寺で沙弥になり、教海と称する。804年、東大寺戒壇院で具足戒を受ける。遣唐使留学僧として唐へ渡り、805年、長安・青竜寺の恵果(けいか)により両界、伝法阿闍梨の灌頂を受ける。806年、当初の20年の義務期間を2年に短縮して帰国、多くの経典、密教法具などを持ち帰る。入京できず太宰府・観音寺に住した。809年、入京を許される。810年、高雄山寺(神護寺)を経て、811年、乙訓寺に移り、約1年間任に当たった。別当になる。812年、乙訓寺を訪れた天台宗開祖・最澄は、空海と会っている。その後、空海は高雄山で最澄らに金剛界結界灌頂を行った。後、二人は決裂し、断絶する。813年、東大寺別当、819年頃/818年、高野山を開く。822年、東大寺に灌頂道場(真言院)を開く。823年、東寺を真言密教の道場にした。824年、高雄山寺を神護寺に改名する。神泉苑で祈雨の修法を行う。827年、大僧都になる。828年、綜芸種智院を創立した。832年、高野山で万灯会、834年、正月、宮中中務省で後七日御修法を営む。830年、『秘密曼荼羅十住心論』を著す。高野山で亡くなり、東峰に葬られた。62歳。 ◆清 少納言 平安時代前期-後期の歌人・清 少納言(せい-しょうなごん、966?-1025?)。女性。父・歌人・清原元輔。曾祖父・清原深養父(ふかやぶ)。981年頃、橘則光と結婚し、982年、則長を産んだ。まもなく離婚した。若くして小白河での上達部(かんだちめ)の法華八講に列席した。990年、父没後、991年頃、少納言・藤原信義/藤原棟世(むねよ)と再婚する。993年、関白・藤原道隆の娘・第66代・一条天皇中宮・定子(ていし)に出仕し、寵愛を受け10年余り女房生活を送った。四納言(藤原公任、源俊賢、藤原斉信、藤原行成)と交友した。996年、中宮一家と対立した左大臣・藤原道長方に内通したとの噂が立ち、私邸に籠居した。1000年、定子の没後、その遺児・脩子内親王に仕える。その後、前摂津守・藤原棟世(むねよ)と三度目の結婚をし、娘・歌人・小馬命婦(こまのみょうぶ)を産んだともいう。後に別居した。晩年、父・元輔の邸宅があった現在の観音寺境内付近に暮らしたという。清少納言が仕えた定子皇后、皇后、女御らは鳥辺野陵(今熊野観音寺北付近)に葬られる。清少納言は尼になり、皇后を偲び月輪近くに庵を結び隠棲し、念仏に明け暮れたという。随筆集『枕草子』、歌集『清少納言集』、『小倉百人一首』に入集。59歳?。 漢詩文の教養があった。中古三十六歌仙のひとり。和泉式部、紫式部とともに平安時代の女性文学を代表した。和泉式部、赤染衛門らと交流した。 ◆藤原 長家 平安時代中期の公卿・歌人・藤原 長家(ふじわら-の-ながいえ、1005-1064 )。男性。父・藤原道長、母・源明子の6男。父の正室源倫子の養子。正二位、権大納言となる。勅撰集には「後拾遺和歌集」以下に44首がはいる。康平7年11月9日死去。60歳。 醍醐天皇の皇子・兼明(かねあきら)親王の邸宅「御子左第」を伝領し、御子左大納言と呼ばれる。後、家系は歌道の御子左(みこひだり)家になる。 ◆藤原 忠通 平安時代後期の公卿・藤原 忠通(ふじわら-の-ただみち、1097-1164)。男性。別称は法性寺 (ほっしょうじ) 殿。父・関白・藤原忠実、母・右大臣・源顕房の娘・師子。1107年、元服、1110年、従三位、1115年、内大臣。1120年、父・忠実が娘・泰子(高陽院)の入内問題で蟄居になる。1121年-1158年、関白・氏長者になる。第74代・鳥羽天皇、第75代・崇徳天皇、第76代・近衛天皇、第77代・後白河天皇に摂政・関白として務めた。左大臣・太政大臣を経て従一位に至る。1129年、白河法皇没後、鳥羽院政により父・忠実が内覧として復帰し対立した。1150年、父より義絶され、氏長者は異母弟の頼長に奪われた。頼長は養女・藤原多子を近衛天皇の後宮に入れ、忠通は対抗し、藤原伊通の娘・呈子(九条院)を養女として後宮に入れた。1155年、近衛天皇没後の後嗣問題で、崇徳上皇と対立した鳥羽上皇(第74代)に後白河天皇の即位を助言した。これらは、1156年、保元の乱の一因になる。崇徳上皇方に付き、敗れた父の所領を相続、父の流罪を防いだ。1158年、乱後、崇徳上皇方に付いた父の所領を相続、父の流罪を防いだ。法性寺西殿に隠退し、御堂(浄光明院)に丈六の阿弥陀坐像(現在、万寿寺の本尊)を安置した。摂関職を子・基実に譲り、1162年、出家した。 法性寺関白と称された。68歳。 和歌、漢詩に優れ、能書家であり法性寺流と称された。『金葉集』以下の勅撰集に入集。子孫は近衛家、九条家に分かれ、五摂家になる。和歌を好み、漢詩優れ、書風は法性寺流と称された。 墓はかつて泉山(せんざん)にあり、1950年に東福寺の九条家墓地に移された。今熊野観音寺(東山区)にもある。 ◆慈円 平安時代後期-鎌倉時代前期の天台宗の僧・慈円(じえん、1155-1225)。男性。法名は道快、通称は吉水僧正、無動寺法印、諡号は慈鎮。父・摂政関白・藤原忠通、母・藤原仲光の娘。九条兼実の弟。1165年、11歳で延暦寺の 青蓮院に入り、1167年、覚快法親王の室に入って出家し、道快と称した。1181年、慈円と改名した。1192年、権僧正、天台座主、護持僧になった。1193年、座主を辞し、東山の吉水の祈祷道場大懺法院に住む。1196年、座主の地位を追われ、1201 年、再び座主になり、都合4度座主になった。1203年、大僧正になり、後鳥羽上皇(第82代)の護持僧になった。1221年、承久の乱後、新たに大懺法院を整備した。無動寺検校、四天王寺別当などを務めた。71歳。墓は比叡山東坂本小島坊、善峰寺(西京区)、今熊野観音寺(東山区)にもある。 公武協調した史書・史論書の『愚管抄』を著した。歌人として知られ、『新古今和歌集』、家集『拾玉集』にも多くの歌が収められている。 慈円は天台座主でありながら、当時の新興宗教だった浄土宗開祖・法然、浄土真宗開祖・親鸞に理解を示し、延暦寺の圧力から庇護した。慈円が法然に与えた院内一坊跡に、法然没後、門弟の源智により勢至堂が建立され、知恩院の起こりになった。9歳の親鸞の得度に際して、剃髪の師になった。 ◆島津 義久 室町時代後期-江戸時代前期の武将・島津 義久(しまづ-よしひさ、1533-1611)。男性。父・貴久の嫡子。1566年、家督を相続し島津氏第16代当主になる。1570年、薩摩統一、1572年、木崎原の戦いに勝利し、1573年、大隅統一を果たした。1577年、伊東氏を日向国から追放し、1578年、豊後大友氏を日向耳川に下し南九州3国を領する。1584年、沖田畷の戦いでは肥前国の龍造寺氏を撃ち破った。1587年、豊臣秀吉の九州平定には降伏した。だが、弟の義弘・歳久らは抗戦を続けた。義久は降伏を命じたが歳久は応じなかった。秀吉は歳久の首を要求し、義久は歳久に自害を命じている。弟は自刃、義久はその後、出家して竜伯と号した。1592年、朝鮮出兵には義弘らを派遣した。隠居後も家中に強い政治力を持ち続けた。79歳。 島津逆修の塔は、今熊野観音寺(東山区)にある。歳久ゆかりの寺として浄福寺(上京区)がある。 ◆象海 江戸時代後期の僧・象海(ぞうかい、?-1865)。詳細不明。今熊野観音住持になる。1856年、泉涌寺長老時に新待賢門院(第121代・孝明天皇の母)の葬儀導師を務めた。1863年、将軍・徳川家茂の泉涌寺歴代天皇陵の参詣に対応した。 幕末期の泉涌寺を支えた。 ◆仏像など ◈本尊の秘仏「十一面観世音菩薩」(丈1尺8寸、54.5㎝)は空海(774-835)作ともいう。一刀三礼して自刻し、胎内仏として熊野権現より授かった天照大神作という「十一面観世音菩薩」(身丈・1寸8分、5.45㎝)が納められている。頭の観音様として知られ、その霊験により後白河法皇(第77代、1127-1192)も病平癒したという。頭痛・脳卒中平癒、知恵授かりの信仰がある。 本尊御前立の「十一面観世音菩薩」がある。 脇仏は、智証大師円珍(814-891)作ともいう「不動明王」、運慶(?-1224)作ともいう「毘沙門天」がある。 ◈ほかに、本堂に「大聖歓喜天(聖天)」、「薬師如来」、「准胝観音」、「三面大黒天」、京都七福神の「恵比須神」を安置する。 ◈画像の「刀八(とうはち)毘沙門天像」は、室町時代作になる。兜跋(とばつ)毘沙門天の兜跋の当て字という。3面の毘沙門天が獅子に乗り8本の刀を掲げ持つ。 ◈大師堂には「弘法大師空海」を祀る。「不動明王」、「愛染明王」、伽藍を寄進建立した「左大臣藤原緒嗣」の像も祀られている。 ◈地蔵堂には、本尊「地蔵菩薩」、「十一面観音」、「弘法大師空海」も祀られている。 ◈「ぼけ封じ観音」は大師堂前に立つ。「ぼけ封じ近畿十楽観音霊場」第1番札所になる。心身の惚けを取り除くとされ、身代わりの石仏に願いを込めて奉納する。 ◈「子護弘法大師」は子ども守護の信仰がある。子・孫の心身健康・学業成就・諸芸上達・交通安全などを祈願する。 ◆建築 ◈「本堂」は、かつて奥の院巡礼堂の地に建つ。弘法大師が熊野権現と出会った場所という。江戸時代中期、1712年に宗絮祖元律師によって建立された。 ◈「大師堂」は、護摩の修法、修行僧の修行道場にも使われる。 ◈「医聖堂」は、平安様式の多宝塔であり、医界関係者などが祭祀されている。 ◈「鐘楼」の梵鐘は、近代、太平洋戦争(1941-1945)時に金属供出になる。ただ、元のままの姿で残されていたという。現代、1946年に修理された。 ◈「大講堂」は法要、行事、法事などに使用される。 ◆茶室 茶室「福海寮」は、 第121代・孝明天皇の皇后・英照(えいしょう)皇太后(1835-1897)の意向による。 ◆鎮守社 ◈「熊野権現社」が祀られている。空海が唐から帰国後、山中の光明にひかれてこの地に来て熊野権現と遭ったという。 ◈「稲荷社」がある。 ◈「金龍弁財天」は、池の近くで金色の巳(蛇の神)が現われたことから祀られたという。 ◆文化財 ◈絹本墨書「伝俊芿(しゅんじょう)筆断簡」1葉は、鎌倉時代作になる。『摩訶止観』の経文を註釈したとみられている。縦27.7×横5.9㎝。 ◈絹本墨書「渡唐天神像」1幅は、室町時代-安土・桃山時代、16世紀作になる。伝承として、円爾(えんに、1202-1280)の助言により、天神(菅原道真、845-903)が宋に渡り、無準師範(1177-1249)に参禅した物語を描いている。天神は中国文官風で梅枝を持ち、巾・衣服が風でたなびく。縦73.4×横27.5㎝。 ◈絹本著色「象海宗師(ぞうかい-すうす)像」1幅は、今熊野観音住持・象海(?-1865)であり、法被を掛けた椅子に坐している。縦115×横41.5㎝。 ◈絹本著色「三宝荒神像」1幅は、室町時代後期作とみられる。江戸時代後期、1843年に象海が修復した。 八面三目十臂の肉身朱色の忿怒相になる。本面は開口し、左右脇面は上歯牙で下唇を噛む肉身緑青になる。本面頭上の五面が載る。十臂例は少なく、左右第一手に筆・経冊、左右第二手-五手に弓矢・宝剣・三弁火焔宝珠、輪宝・三叉戟などを持つ。台座に踵を合わせて坐している。 肉身朱色の鬼神は左手掌に男女一対の小人を載せる。肉身朱具の鬼神は両手で戟を執り立つ。縦88.2×横38.4㎝。 ◈紙本墨書「今村藤左衛門尉幷源左衛門言上状(ごんじょうじょう)案」1通は、室町時代後期、1515年作になる。縦25×横40㎝。 ◈紙本墨書「室町幕府奉行人連署奉書」1通は、室町時代後期、1516年作になる。縦27.4×横44.3㎝。 ◈紙本墨書「室町幕府奉行人連署奉書案」1通は、室町時代後期、1516年、1517年作になる。縦25.2×横41.7㎝。 ◈紙本墨書「室町幕府奉行人連署奉書案(紙背・山城国守護奉行人連署状)」通は、室町時代後期、1516年になる。縦24.5×横41.5㎝。 ◈紙本墨書「山城国守護奉行人杉興重打渡状(うちわたしじょう)」1通は、室町時代後期、1516年作になる。縦25.7×横41.5㎝。 ◈紙本墨書「山城国守護奉行人連署奉書案」1通は、室町時代後期、1516年作になる。縦25.8×横41㎝。 ◈紙本墨書「山城国守護奉行人連署奉書案」1通は、室町時代後期、1516年作になる。縦24.8×横41.3㎝。 ◈紙本墨書「室町幕府奉行人連署奉書案」1通は、室町時代後期、1517年作になる。縦28.5×横43.6㎝。 ◆空海の伝承 空海にまつわる伝承がある。平安時代前期、806年、空海が唐の国から帰国後に、東寺で真言密教の秘法を修法した際に、東山の山中に光明がさし、瑞雲棚引いているのが見えた。 そこへ赴くと、山中に白髪の老翁が姿を現わし、「この山に一寸八分の観世音がましますが、これは天照大神の御作で、衆生済度のためにこの地に来現されたのである。ここに一宇を構えて観世音を祀り、末世の衆生を利益し救済されよ。」という。また、一寸八分の十一面観世音菩薩像と、一夥の宝印を大師に与えた。 老翁に何者か尋ねると、「熊野の権現で、永くこの地の守護神になるであろう」と告げて姿を消したという。現在の本堂の位置が空海が老翁に出会った場所という。 空海はこの地に一堂を建立し、自ら一尺八寸(54.5㎝)の十一面観世音菩薩像を刻み、授かった一寸八分(5.45㎝)の像を胎内仏として納め、奉安したという。 ◆熊野信仰・今熊野修験 古くから熊野は、観音の補陀落浄土としての信仰の中心になっていた。平安時代後期に熊野詣が盛んになる。天皇や貴族が度々熊野を訪れた。後白河上皇も本宮に34回、新宮那智には15回も訪れている。 当時、今熊野は熊野修験の中心地として、今熊野権現と本地仏への信仰があった。また、宇佐信仰の習合した山岳仏教、平安時代後期に、豊後国東半島一帯に起きた今熊野権現・本地仏を信仰する修験にも影響を及ぼした。 ◆鳥戸野 東山七条の東の峰を阿弥陀が峰という。峰の南西一帯の今熊野の地は、鳥戸野(とりべの)ともいわれた。皇室の葬地であり、観音寺はそれらの管掌寺院になっていた。 寺域には鳥戸野陵があり、平安時代、第66代・一条天皇の皇后・藤原定子(977-1001)をはじめ皇族、藤原道長(996-1027)などの貴族の火葬塚があり、葬儀や法要は観音寺が執り行っていた。 ◆後白河法皇の頭痛封じ 後白河法皇( ◆寺紋 寺紋の 「今熊野浪」は、立浪の紋章の中に環が描かれている。 ◆医聖堂 「医聖堂」は、現代、1981年に建立された。医道顕彰会は、奈良時代-幕末の日本の医家122人を選定し祭祀した。その後、医療関係者も合祀されている。大祭(10月吉日)が行われている。 その傍らに「医心方一千年記念碑」が立てられている。平安時代中期、984年に、鍼博士・丹波康頼(たんば-やすのり、912-995)が著した日本最古の医学書『医心方』を記念した。 ◆西国観音霊場三十三所 当寺は、「西国観音霊場三十三所」の第15番札所になっている。第1番の和歌山・青岸渡寺より、第33番の岐阜・華厳寺までを巡る近畿2府4県(1000km)の巡礼になる。 長谷寺を開いた飛鳥時代の徳道(とくどう、656-? )は、病により仮死し、冥途で閻魔に出あった。閻魔は地獄に堕ちる者が多いとして、観音菩薩の慈悲を説き、33の霊場を参ると功徳を得られるとした。 観音菩薩は浄土に往生せず、現世で苦しむ人々を救済するために、聖観音、十一面観音、千手観音など33(無限)の姿に身を変えるとされる。徳道は、閻魔より33の宝印、起請文を授かり現世に戻る。徳道は兵庫・中山寺に宝印を納めたという。 巡礼は、奈良時代に始まる。その後、途絶したともいう。平安時代、花山法皇(第65代、968-1008)は、徳道の納めた宝印を掘り起こし、巡礼を再興したという。また、平安時代後期(12世紀)に再興されともいう。平安時代後期には天皇、公家が巡礼し、鎌倉時代-室町時代には、庶民にも広まった。江戸時代に最も盛んになる。周辺の伊勢神宮参り、熊野詣、善光寺参りとも結びついた。「三十三度行者」と呼ばれるのは、33所を33回も巡礼した人を意味した。御朱印、千社札の始まりにもなった。 ◆京都十三仏霊場めぐり 弥勒菩薩(六七日)は「京都十三仏霊場めぐり」の第6番札所になっている。室町時代、8代将軍・足利義政(1436-1490)が、歴代将軍の供養を十三仏に祈願したことから始まったという。また、貴族にはそれ以前よりの信仰があったともいう。 十三仏とは中陰法要、年忌法要の際の十三体の仏・菩薩をいう。中陰法要は、葬儀後、初七日の不動明王、二十七日の釈迦如来、三十七日の文殊菩薩、四十七日の普賢菩薩、五十七日の地蔵菩薩、六十七日の弥勒菩薩、七十七日の薬師如来とあり、これらを終えた満中陰により新たな生を受け、続いて百日の観音菩薩、一周忌の勢至菩薩、三回忌の阿弥陀如来、七回忌の阿閦(あしゅく)如来、十三回忌の大日如来、三十三回忌の虚空蔵菩薩と追善法要が続く。 ◆七福神巡り 泉涌寺山内の「七福神めぐり」(成人の日)は、泉涌寺(泉山)七福神巡りとして塔頭9カ寺を巡る。現代、1951年以来続けられている。これらを福笹を持ちお参りしていく。 第1番は福禄寿・即成院、第2番は弁財天・戒光寺、番外の愛染明王・新善光寺、第3番は恵比寿神・今熊野観音寺、第4番は布袋尊・来迎院、第5番は大黒天・雲龍院、番外の楊貴妃観音・泉涌寺本坊、第6番は毘沙門天・悲田院、第7番は寿老人・法音院になる。 ◆五智水 五智の井は、空海が当山を開いた際に、錫杖で岩根を穿つと湧き出したという。「五智水」とも呼ばれいまも湧き出している。 ◆石造物 「三重石塔」は、平安時代作という ◆墓 ◈墓地に「石造宝塔」3基が立つ。「藤原三代の墓」と呼ばれ、 右より慈円、藤原忠通、藤原長家という。宝塔であり、左端は基礎がない。基礎に格狭間、円筒形の塔身、首部は二段、笠石軒下に二段の垂木型、隅木がある。相輪はなく、風輪、空輪がのる。花崗岩製、2m。 ⋄平安時代末期の貴族・藤原忠通(1097-1164)は、忠実の子に生まれた。鳥羽、崇徳、近衛、後白河の四帝に仕え、摂政関白・太政大臣、関白太政大臣になる。法性寺で出家し、法性寺入道前と称した。詩歌、書の法性寺流を創始した。 ⋄平安時代末期-鎌倉初期の公家・九条兼実(1149-1207)は、忠通の子になる。九条家の祖。源頼朝の後援により議奏公卿の上首、摂政になり、記録所を再興した。後に関白となる。明経の術、和歌、書道にも通じた。 ⋄平安時代末期-鎌倉時代初期の僧・慈円(1155-1225、慈鎮和尚)は、忠通の子になる。兼実の弟。4度天台座主になる。天王寺別当にも就く。和歌にすぐれ、史論「愚管抄」を著した。 ◈「島津逆修の塔」には、安土・桃山時代の大名・島津家第16代当主・島津義久(1533-1611)が眠る。逆修(ぎゃくしゅ)とは、生前の墓、位牌の建立をいう。 「慶長五年(1600年)逆修、藤原氏島津義久」と刻まれている。石は薩摩より運んだという。五輪塔。 ◆年間行事 修正会(元旦-1月3日)、新年厄除開運大祈願祭(1月15日)、京都七福神巡り(昆布茶接待)(成人の日)、初観音会(1月18日)、節分星供大祈願会(2月3日)、春季彼岸会(3月彼岸中日)、弘法大師正御影供(4月21日)、青葉祭・弘法大師の御誕生法会(6月15日)、盂蘭盆会施餓鬼法要(8月16日)、四国八十八ヶ所お砂踏法要(9月21日-23日)、秋季彼岸会(9月彼岸中日)、医聖堂例大祭(10月吉日)、紅葉まつり(11月下旬)、お終い参り・除夜の鐘(大晦日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』、『京都・山城寺院神社大事典』、パンフレット「今熊野観音寺」、『京都の寺社505を歩く 上』、『日本の名僧』、『京都古社寺辞典』、『増補版 京都の医史跡探訪』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京都のご利益手帖』、『京の福神めぐり』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 古社名刹巡拝の旅 32 東山』 、『山科事典』 、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |
| |
|