|
|
|
| 旧第一勧業銀行京都支店(みずほ銀行京都中央支店)・三条南殿跡 (京都市中京区) Former Dai-Ichi Kangyo Bank Kyoto Branch |
|
| 旧第一勧業銀行京都支店 | 旧第一勧業銀行京都支店 |
 |
 |
 東側 東側 東側、正面  東側、「みずほ銀行」の銘鈑 東側、「みずほ銀行」の銘鈑 東側、正面  東側 東側 東側 東側 東側  東側 東側 東側 東側 東側  東側  東側、ドーマー窓  東側  東側、小塔 東側、小塔 東側  東側 東側 西側  西側、小塔  西側 西側 西側 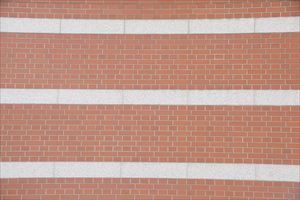 西側、白い帯石 西側、白い帯石 西側、ドーマー窓 西側、ドーマー窓 東側、「三條南殿の遺址」の銘鈑 |
烏丸通三条南西角に、赤煉瓦造の旧第一勧業銀行京都支店(きゅう-だいいち-かんぎょう-ぎんこう-きょうとしてん)が再建されている。 現在はみずほ銀行京都中央支店に名を変えた。設計は近代の辰野葛西建築事務所による。 なお、付近の三条通には、近代の歴史的建造物がまだ複数残されている。 ◆歴史年表 近代、1904年、3月、「第一勧業銀行京都支店」の建物は起工した。 1906年、5月、支店は竣工する。 1919年、南側、西側が増築される。 現代、1997年、三条通周辺は京都市の「界わい景観整備地区」に指定される。同支店は最も重要な景観構成要素の一つになる。 1999年、支店は取り壊される。 2003年、旧支店がレプリカ再建された。 2005年、2月、店舗名は「みずほ銀行京都中央支店」に変更になった。 ◆辰野金吾 江戸時代後期-近代の建築家・教育者・辰野金吾(たつの-きんご、1854-1919) 。男性。旧姓は松倉。唐津(佐賀県)の生まれ。父・唐津藩藩士・姫松倉右衛門の次男。1868年、辰野宗安の養嗣子になる。1873年、工部省工学寮に入学した。イギリス人・建築技師・ジョサイア・コンドル(Josiah Conder,1852-1920)の指導を受ける。1879年、工部大学校(工学寮)造家学科の第1回卒業生として卒業した。1880年、留学のため、ロンドンのコンドルの師・バージェス(William Burges,1827-1881)建築事務所などで建築を研修した。フランス、イタリアにも行く。1883年、帰国し工部省に入る。設計の処女作になった銀行集会所(1885)の設計を行う。1884年、コンドルの後任として、工部大学校教授に就任し、日本建築講座を担当する。1886年、「辰野建築事務所」を設立した。造家学会(現・日本建築学会)創立に参加した。1887年、日本銀行の設計者に決定し渡欧する。1888年、帰国する。1898年、建築学会会長、工科大学長に就任する。1902年、工科大学を退官した。1903年、教え子・葛西萬司と東京・「辰野葛西事務所」を開設した。1905年、片岡安と大阪・「辰野片岡事務所」を開設する。議院建築調査会委員を歴任する。工学博士。66歳。 「日本近代建築の父」といわれた。日本人で洋風建築技術を最初に学ぶ。創成期の日本近代建築を主導した。門弟に伊東忠太、関野貞、大熊喜邦らがいる。主な作品は、工科大学本館(1888) 、日本銀行本店(1896) 、両国国技館(1909)、東京中央停車場(東京駅、1914) などがある。 ◆葛西萬司 江戸時代後期-近代の建築家・葛西萬司(かさい-まんじ、1863-1942)。 男性。盛岡(宮城県)の生まれ。南部藩家老・鴨澤舍の次男、後に南部藩士葛西重雄の養子になる。1890年、 東京帝国大学工科大学造家学科を卒業し、日本銀行技師になる。1903年、 辰野金吾と東京・「辰野葛西設計事務所」を開設する。1915年、 工学博士になった。1919年、 辰野金吾の没後、葛西設計事務所を経営する。1927年、 田中實と「葛西田中建築事務所」を開く。1937年、単独経営になり「葛西建築事務所」に改称する。工手学校(現・工学院大学)造家学科教員を務めた。79歳。 辰野葛西設計事務所の現存作品として、旧盛岡銀行本店本館(現・岩手銀行中ノ橋支店赤レンガ館 )(1911、重文)、 旧中央停車場(現・東京駅)(1914、重文) 、岩手病院診療棟(現・岩手医科大学1号館) (1926)、葛西建築事務所として旧盛岡貯蓄銀行本店(現・盛岡信用金庫本店) (1927 などがある。 ◆建築 第一勧業銀行京都支店は、近代、1904年3月に着工し、1906年5月に竣工した。設計は辰野葛西建築事務所(辰野金吾・葛西萬司)による。1919年に清水組により、南側、西側の増築が行われた。その後、1999年に取り壊される。2003年に、旧支店のほぼ同様の外観でレプリカ再建(イメージ復元)されている。 第一勧業銀行京都支店は、東京海上火災本社屋と並び、辰野葛西建築事務所の第1作だった。辰野の現存作品中で、日本銀行本店(1896)、日本銀行大阪支店(1903)に次ぎ3番目に古い作品になる。 東面して建つ。外観は、英国のヴィクトリア様式による赤煉瓦を露出させた。フリー・クラシック(辰野式)と呼ばれている。辰野は、旧日本銀行京都支店(現・京都府京都文化博物館、1906)で、この様式を試みている。フリー・クラシックは、19世紀後半に英国で流行している。細部は古典系様式、骨格はゴシック的になる。赤煉瓦を露出させ、白い石材を帯石・隅石として用い、屋根には高屋根、小塔を載せた。明治30年代(1897-1906)後半-大正期(1912-1926)半まで、辰野により百数十件が建てられた。近代建築史上の最も代表的意匠であり、その起点の一つに位置付けられる。 外壁は煉瓦3枚積で、壁面は化粧煉瓦積、丹波産花崗岩を随所に用いる。屋根はマンサード屋根(腰折れ屋根、切妻屋根の変形で、屋根の勾配が上部が緩く下部が急な2段もの)で、かつては上部は銅板葺、下部はスレート葺だった。屋根にドーマー窓(垂直面の採光窓)がある。2階窓はアーチ形になる。 1919年に清水組技師長・田辺淳吉(1879-1926)の設計、清水組施工により、南側に3ベイ(柱間・梁間)分、西側に4ベイ分の増築、内部改造を行なった。さらに戦後にも、西側の増築部分は改築された。増築の際に烏丸通側玄関上部の窓形状が変更される。これらの増改築はすべて部分的なものに限られている。 施工は清水組、煉瓦造2階建、当初の建築面積は127坪(420㎡)。現在は全面銅板葺。 ◆三条南殿の遺跡 建物の東側に「三條南殿の遺址」という金属プレートが掲げられている。現代、1975年に平安博物館により設置された。 この地には、平安時代後期に左大臣・藤原実能(ふじわら-の-さねよし、1096-1157)の邸宅があった。三条南殿と呼ばれた。邸宅は三条通、烏丸通、六角通、室町通の4通りに面し、方121mを占めた。 平安時代後期、1133年頃に、邸宅は鳥羽上皇(第74代、1103-1156)に献上されその御所になる。その後、1151年頃に上皇の第2皇女・上西門院(1126-1189)の御所になった。1158年-1159年には、武将・源頼朝(1147-1199)が上西門院の官人として仕えている。鎌倉時代の1197年には第82代・後鳥羽天皇(1180-1239)の生母・七条院(1157-1228)の御所になった。 平安時代後期-鎌倉時代中期まで、この地は女院御所になり、歴代天皇がしばしば行幸している。また、女院の女房達により和歌文化の中心地の一つになった。 *内部は通常非公開 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「第一勧業銀行・東京三菱銀行京都支店 - 日本建築学会」、『京都の洋館』、『京都のモダニズム建築』、平安博物館の案内板、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |