|
|
|
| 龍翔寺・天瑞寺 〔大徳寺〕 (京都市北区) Ryusho-ji Temple,Tenzui-ji Temple |
|
| 龍翔寺・天瑞寺 | 龍翔寺・天瑞寺 |
 |
 |
 門前の石畳参道  龍翔寺 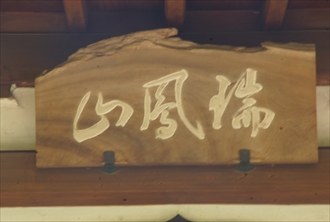 龍翔寺山号扁額「瑞鳳山」  龍翔寺  龍翔寺、「本派専門道場」 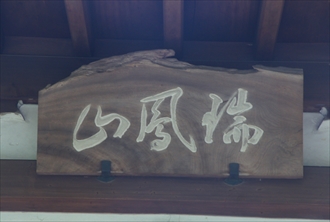   龍翔寺延段     【参照】柳殿御所跡(右京区太秦安井、現在の後宇多天皇御髪塔)  【参照】柳殿御所跡(右京区太秦安井、現在の賀陽門門院墓)  |
大徳寺境外塔頭である龍翔寺(りゅうしょう-じ)は、境内3000坪(1万㎡)を有している。 正式には萬歳龍翔禅寺という。「本派専門道場」とも呼ばれている。山号は瑞鳳山という。 大徳寺派の修行専門道場になる。 ◆龍翔寺の歴史年表 鎌倉時代、1309年、第91代・後宇多天皇により寄進された柳殿御所跡(右京区太秦安井、現在の後宇多天皇御髪塔、賀陽門門院墓付近一帯)に、南浦紹明(なんぽ-しょうみょう)の塔所(祥雲庵)として創建された。以後、絶崖宗卓(ぜつがい-そうたく、?-1334)ら、紹明門徒・横岳派が護持する。 南北朝時代、1378年、焼失する。 1386年、五山制度改定に伴い、官刹として大徳寺と並び十刹第9位になる。 室町時代、1431年以降/文明年間(1469-1487)、林下(りんか/りんげ、在野寺院)になる。以後、徐々に衰微した。 1458年/1461年、一休が寺を訪れた。荒廃していたため、修理料を寄せたという。また、「感龍翔寺廃」を作詩している。(『臥雲日件録』『狂雲抄』) 応仁・文明の乱(1467-1477)以前、寺運隆盛を迎え、寺地(3町歩)は大徳寺に匹敵した。(『太秦村誌』)。寺領寄進も相次ぐ。 応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失する。 文明年間(1469-1486)、春浦宗煕(しゅんぽ-そうき)により再興される。 1527年、柳本賢治の丹波・三好勝長ら阿波国人衆と細川高国・細川忠賢の桂川原での戦により、開山塔、昭堂、方丈、庫裏、開山木像、本尊、寺宝などを焼失する。 1540年、室町幕府は龍翔寺の大徳寺山内移転、再興を認める。 1541年/天文年間(1532-1555)、天啓宗歅(てんけい-そういん)が、大徳寺山内の白毫寺の地(現在の大徳寺塔頭・三玄院の地)に移転する。以後、大徳寺塔頭になる。太秦安井の跡地には、大応国師の塔所(国師塔)、後宇多法皇の御髪塔が残された。龍翔寺輪住の僧は、毎年旧7月に廟参諷経を続けたという。(『雍州府志』) 1558年、大徳寺の外護・三好長慶は、禁制下付する。 同1558年、豊臣秀吉・羽柴秀長は、母・大政所の病気平癒を祈願し、大徳寺塔頭・総見院の西(現在の龍翔寺の地)に天瑞寺を創建する。開祖は黄梅院の玉仲宗琇(ぎょくちゅう-そうしゅう)による。 1592年、旧7月、大政所が亡くなる。 1595年、大政所の病気平癒と長寿を祝い、天瑞寺に石造の寿塔を建立し、覆堂に納める。 江戸時代、1607年、第一回回答兼刷還使(朝鮮通信使)の正使らが大瑞寺に定宿する。 1816年、龍翔寺は焼失した。 1817年、客殿(現在の三玄院客殿)が再建された。 江戸時代末、別山になり、大徳寺長老が隔年で輪住した。(『龍宝摘撮』) 近代、明治期(1868-1912)/1874年、天瑞寺は廃仏毀釈により廃絶する。 1878年、4月、天瑞寺は売却される。 1891年、大政所の300回忌に、天瑞寺の大政所廟堂が売却された。 明治期(1868-1912)中期、大応国師の塔所(国師塔)が大徳寺に遷された。 1925年/大正期(1911-1926)、現在地の大徳寺塔頭・天瑞寺跡に、実業家・山口玄洞の寄進により龍翔寺は再建された。以後、大徳寺派の専門道場になる。 ◆南浦 紹明 鎌倉時代中期-後期の臨済宗の僧・南浦 紹明(なんぽ-じょうみょう、1235-1308)。男性。駿河(静岡県)の生まれ。建穂寺の浄辨に天台宗を学ぶ。1249年、15歳で剃髪受戒、鎌倉・建長寺の蘭渓道隆(らんけい-どうりゅう)に師事した。1259年、入宋、杭州・浄慈寺の虚堂智愚(きどう-ちぐ)に学び、後に法嗣になる。1265年、虚堂に従い径山・万寿寺に移る。1267年、帰国し、建長寺の蘭溪道隆(らんけい-どうりゅう)に参じ蔵主になる。1270年、筑前・興徳寺、1272年、太宰府・崇福寺、1304年、後宇多法皇(第91代)の詔により上洛、洛西安井・韜光庵(とうこうあん)に住した。宗峰妙超(しゅうほう- みょうちょう)が弟子になる。1305年、東山・万寿寺に入る。法皇による東山・嘉元寺の開山は成らなかった。1307年、北条時貞の帰依により建長寺に入る。塔所は鎌倉・天源塔、筑前・崇福寺の瑞雲塔、京都安井・龍翔寺にあった。門弟多く、臨済禅大応派の祖になる。74歳。 没後、1309年、後宇多法皇に贈られた国師号「円通大応国師」は日本初例になる。「応灯関(大応国師[南浦紹明] 、大灯国師[宗峰妙超] 、関山慧玄)」の一人。 ◆後宇多 天皇 鎌倉時代中期-後期の第91代・後宇多 天皇(ごうだ-てんのう、1267-1324)。男性。父・第90代・亀山天皇、母・皇后・藤原佶子(京極院)の第2皇子。亀山上皇による院政下、8歳で即位した。治世中、モンゴルの来襲(1274年、1281年、元寇、文永・弘安の両役)が起こる。1287年、譲位後、自らも94代・後二条天皇、 96代・後醍醐天皇時に院政を敷いた。1307年、仁和寺で落飾し、金剛性と称し、大覚寺に入寺、門跡になった。1308年、東寺灌頂院で伝法灌頂を受法した。大覚寺御所で亡くなる。58歳。 南浦紹明(なんぽ-じょうみょう)に深く帰依した。 ◆嘉陽門院 鎌倉時代前期-中期の皇族・嘉陽門院(かよう-もんいん、1200-1273)。女性。礼子内親王。父・後鳥羽天皇、母・坊門局(内大臣坊門信清の娘)の第2皇女。1204年、5歳で内親王宣下、准三宮、賀茂斎院に卜定された。1205年、左近衛府へ初斎院になる。1206年、紫野院へ入る。1212年、病により退いた。その後、祖母・七条院と同居した。1214年、院号宣下。1220年、同母兄弟・道助入道親王により出家し、法名は真如性と号した。1221年、承久の乱後、賀茂斎院は廃絶し、歴代最後の斎院になる。74歳。 龍翔寺旧地(柳殿御所跡)に葬られたのは、かつて斎院がこの地にあったからともいう。 ◆絶崖 宗卓 南北朝時代の臨済宗の僧・絶崖 宗卓(ぜつがい-そうたく、?-1334)。男性。南浦紹明(なんぽ-しょうみょう)に師事し、法を嗣ぐ。筑前・崇福寺、京都・万寿寺、南禅寺住持。鎌倉・浄智寺、豊後・円福寺を開き、紹明を開山とし、自らは2世になる。諡号は広智禅師。 ◆春浦 宗煕 室町時代前期-後期の臨済宗の僧・春浦 宗煕(しゅんぽ-そうき、1409/1416-1496)。男性。播磨(兵庫県)の生まれ。6歳で建仁寺・乾心和尚に師事、18歳で出家、得度した。蔵主になる。大徳寺に移り、養叟宗頤(ようそう-そうい)の法を嗣ぐ。東山・大蔭庵、大徳寺・大用庵に住した。1461年、大徳寺40世。1464年、大徳寺・養徳院の住持。応仁・文明の乱(1467-1477)を避け摂津・城福寺、堺・陽春庵に移る。1473年、大徳寺再住、復興を行う。1481年、伏見・清泉寺の開祖になる。1492年、大徳寺に松源院を開く。諡号は1490年に「正続大宗(しょうぞくだいしゅう)禅師」。松源院に塔された。81/88歳。 ◆天啓 宗歅 室町時代後期の臨済宗の僧・天啓 宗歅(てんけい-そういん、?-1551)。男性。能登(石川県)の生まれ。小渓紹怤(しょうけい-じょうふ)の法嗣。1533年、興臨院納所、1538年、大徳寺94世。1541年、龍翔寺住持、1545年、大徳寺。越前・福原寺の玉雲庵を開く。大徳寺・玉雲軒を創建した。大智仏勝禅師。龍源門下玉雲派の祖。弟子に雲叔宗慶(うんしゅく-そうきょう)がある。 ◆玉仲 宗琇 室町時代後期-江戸時代前期の僧・玉仲 宗琇(ぎょくちゅう-そうしゅう、1531-1614)。男性。日向(宮崎県)の生まれ。春林宗俶(しゅんりん-そうしゅく)の法を嗣ぐ。1558年、豊臣秀吉の信により、大徳寺山内に秀吉の母・大政所のために天瑞院を開いた。1570年、大徳寺112世。小早川隆景、今井宗久らと親交をむすぶ。第106代・正親町天皇から仏機大雄禅師の号を贈られる。83歳。 ◆大政所 室町時代後期-安土・桃山時代の大政所(おおまんどころ、1513-1592)。女性。仲(なか)。法名は天瑞院春岩。尾張国(愛知県)の生まれ。織田家足軽、雑兵・木下弥右衛門に嫁ぎ、1534年、とも(日秀)、1537年、秀吉を産む。夫病没後、織田信秀に仕えた同朋衆・竹阿弥(ちくあみ)に再嫁した。1540年、小竹(秀長)、1543年、旭(朝日姫)を産む。1574年、秀吉は長浜城に仲を引き取る。1583年、大坂城に移る。1585年、秀吉の関白任官に伴い、従一位に叙された。以後、大政所と呼ばれた。1586年、秀吉は徳川家康の正室に送った妹・朝日姫に続き、母・大政所も岡崎城に人質として送り、家康の上洛、秀吉との拝謁を促した。1588年、病になる。1590年、朝日姫、1591年、秀長に先立たれる。聚楽第で亡くなった。80歳。 城内でも畑地を設け、野良仕事をやめなかったという。墓所は大徳寺の龍翔寺、天瑞寺の寿塔覆堂は後に横浜に移された。本国寺に、弥右衛門、婿・三好吉房、孫・豊臣秀保と合祀された供養塔がある。 ◆豊臣 秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀吉(とよとみ-ひでよし、1537-1598)。男性。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎。小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の百姓、織田信秀の足軽・木下弥右衛門、母・百姓の娘・なか(天瑞院)。1551年、家出し、後に今川氏の家臣・松下之綱、1554年、織田信長に仕える。1561年、浅野長勝の養女・ねねと結婚し、木下藤吉郎秀吉と名乗った。戦功を重ね、1573年、小谷城主、羽柴姓と筑前守、信長の天下統一にともない西国転戦した。1582年、備中高松城の毛利軍と戦いの最中に本能寺の変が起こり和睦した。軍を返し山崎で明智光秀を討つ。1584年、小牧・長久手で織田信雄、徳川家康の連合軍に敗れる。1585年、紀州根来と雑賀、四国・長宗我部元親を服した。関白に進む。1586年、聚楽第、広寺大仏造営に着手し、太政大臣に昇り豊臣の姓を賜わる。1587年、九州征討、聚楽第が完成する。旧10月、北野天満宮で北野大茶湯を催した。1588年、第107代・後陽成天皇が聚楽第を行幸する。検地、刀狩を行う。1590年、小田原の北条氏直らの征討、朝鮮使を聚楽第に引見した。1591年、利休を自刃させる。1592年、文禄の役を始めた。甥の養子・秀次に関白職を譲り、太閤と称した。1593年、側室淀殿に秀頼が生まれると、1595年、秀次を謀反人として切腹させ、妻妾子女らも処刑した。1597年-1598年、朝鮮を攻めた慶長の役に敗れた。1598年、旧3月、醍醐寺で「醍醐の花見」を行う。旧8月、伏見城で没した。62歳。 ◆羽柴 秀長 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・羽柴 秀長(はしば-ひでなが、1541-1591)。豊臣秀長、幼名は小竹、通称は小一郎、名は長秀、大和大納言。尾張(愛知県)の生まれ。父・百姓・弥右衛門/竹阿弥?、母・なか(大政所)。秀吉の弟/異父弟。1564年以降、秀吉に仕える。1573年、長浜城城代になる。藤堂高虎が仕官した。1574年、伊勢長島一向一揆攻めで、丹羽長秀・前田利家らと先陣を務めた。1575年、羽柴の名字を与えられる。秀吉の中国攻めで、1577年、第1次但馬攻め、1578年、但馬攻め、黒井城の戦いに加わる。1579年、丹生山を襲撃し、淡河城を攻め撤退した。(三木合戦)。1580年、第2次但馬攻めで総大将を務め、但馬の竹田・出石城の城代になる。1581年、鳥取城の戦い、1582年、備中高松城の戦い、本能寺の変後、山崎の戦い、1583年、賤ヶ岳の戦いに参戦した。美濃守に任官し、姫路城を居城にした。1584年より、秀長と名乗る。小牧・長久手の戦いに参戦し、講和交渉で秀吉の名代として赴く。1585年、紀州征伐で秀吉の副将に任命される。功として紀伊・和泉に所領を得る。四国攻めで、病の秀吉に代わり総大将になった。その後、紀伊・和泉に大和一国が加増される。居城を紀伊若山から大和郡山に移した。豊臣の本姓を与えられる。1586年、北山一揆出陣、従三位、参議になる。1587年、九州攻めで日向方面の総大将になる。島津攻めの先鋒になった。戦後、従二位・権大納言に叙任され、大和大納言と呼ばれる。大和郡山城で病没した。52/51歳。 常に秀吉の補佐役として奮闘した。 戒名は古溪宗陳が「大光院殿前亜相春岳紹栄大居士」と付した。墓は大徳寺・大光院(北区)、1777年に大和郡山に町衆により供養塔(大納言塚)が立てられた。 ◆羽柴 秀保 安土・桃山時代の武将・羽柴 秀保(はしば-ひでやす、1579-1595) 。男性。父・三好吉房、母・日秀尼の3男。豊臣秀次・秀勝の弟。1588年、叔父・羽柴秀長の養子になる。1592年、従三位、権中納言になり、大和中納言と呼ばれた。1592年、文禄の役で肥前名護屋で普請役を務めた。17歳。 ◆狩野 永徳 室町時代後期-安土・桃山時代の画家・狩野 永徳(かのう-えいとく、1543-1590)。男性。源四郎。狩野松栄の長男。1552年、祖父・元信とともに室町幕府将軍・足利義輝へ正月参賀に赴く。1566年、創建の大徳寺・聚光院の障壁画を父と制作する。1576年、織田信長の安土城、1583年、総見院、1585年、豊臣秀吉の大坂城、 1586年、正親町院御所、1587年、秀吉の聚楽第、1588年、大徳寺・天瑞寺、1589年、後陽成天皇の内裏、1590年、京都御所などの障壁画を一門とともに手掛ける。東福寺法堂天井の龍図制作中に急逝した。龍図は弟子・山楽が引き継ぐ。48歳。 1574年、足利義輝の注文により23歳で描いた「上杉本洛中洛外図屏風」は、織田信長から上杉謙信に贈られたといわれている。大徳寺・聚光院には障壁画があり、現存するもので当時のままに鑑賞できる唯一の作品になる。 ◆山口 玄洞 江戸時代後期-近代の実業家・山口 玄洞(やまぐち-げんどう、1863-1937)。男性。広島県の生まれ。医業と副業の醤油販売業・山口寿安の長男。1871年、9歳で愛媛の漢学塾「知新館」に学ぶ。1877年、父急死により、尾道で行商を始める。1878年、大阪の洋反物店「土居善」に丁稚奉公に出る。1881年、倒産により鳥取で商う。1882年、大阪で洋反物仲買「山口商店」を開業し、輸入織物のモスリンを扱い成功する。1896年、山口家4代目として玄洞を襲名した。1904年-1906年、高額納税者のため貴族院勅任議員に互選される。三十四銀行取締役、大阪織物同業組合初代組長、泉尾土地会社・尼崎紡績、大日本紡績(現ユニチカ)・毛斯倫紡績・大阪商事などの役職を兼ねる。1917年、引退し、京都の本邸で隠居、仏教を篤く信仰する。資産の多くを公共・慈善事業、寺社に寄付し、表千家も後援した。75歳。 墓は大徳寺・龍翔寺、尾道の西國寺にある。 ◆普光塔 鎌倉時代後期、1309年、第91代・後宇多天皇は、南浦紹明(なんぽ-しょうみょう、1235-1309)に「円通大応国師」の勅諡号と塔頭敷地として太秦安井(右京区)の柳殿御所跡を寄進した。 この地に、絶崖宗卓(ぜつがい-そうたく、?-1334)らが塔所として龍翔寺(祥雲庵)を創建し、普光塔と称された。以後、紹明門徒・横岳派が護持する。寺は南北朝時代、1378年、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)、1527年に焼失し、1541年に大徳寺山内に移された。 旧地には現在、後宇多天皇御髪塔、賀陽門門院墓付などが遺されている。 ◆天瑞寺 安土・桃山時代、1558年旧8月に天瑞寺(てんずい-じ、天瑞院とも)は、豊臣秀吉(1537-1598は、弟・秀長(1541-1591)により建立された。母・大政所(1513-1592)の病気平癒を祈願し、寺号は大政所の法号「天瑞寺殿春岩宗桂大禅定尼」による。山号は金鳳山(きんぽう-ざん)といった。境内は、主君・織田信長(1534-1582)の菩提所で大徳寺の塔頭・総見院の西隣(現在の龍翔寺の地)だった。開祖は黄梅院の玉仲宗琇(ぎょくちゅう-そうしゅう、1522-1605)による。 秀吉の命により、秀長は本寺の普請奉行に、その子・秀保(1579-1595)は、庫裡の造営奉行になった。客殿(方丈、桁行18間、梁行20間)・庫裏・鐘楼が建てられた。狩野永徳( 宗琇は1589年に「天瑞寺之規縄」を定めている。1592年旧2月に、大政所の病気平癒と長寿を祝い、石造の寿塔(墓塔)を建立し覆堂に納める。旧7月22日に大政所は亡くなった。秀吉は名護屋に居り、臨終に間に合わなかった。旧8月6日に大徳寺で葬儀が営まれる。旧8月7日、蓮台野で火葬に付され、天瑞寺の寿塔下に埋納された。 近代、1874年に衰退し廃寺になる。1878年4月に、大徳寺は困窮のため寺を売却している。境内(3500坪)には廟堂(2間四方)が建てられ大政所の寿塔が納められていた。1891年に、廟堂も売却されている。 元廟堂は、大徳寺塔頭・瑞光院、黄梅院の所有を経て、近代、1902年に三渓園(横浜市)に移された。現在は、「旧天瑞寺寿塔覆堂」(重文)として公開されている。 現在、大徳寺・龍翔寺(北区)境内の西北隅には、大政所の寿塔のみが残されている。 ◆三玄院 大徳寺・塔頭の三玄院は、安土・桃山時代、1589年、武将・石田三成(1560-1600)、浅野幸長(1576-1613)、森忠政(1570-1634)らが、大徳寺111世・春屋宗園(しゅんおく-そうえん、1529-1611)を開山として創建した。当初は、当地の西隣にあった。 近代に入り、現在地に移る。この地にあった龍翔寺の部材により再興された。 ◆建築 ◈龍翔寺の現在の「禅道場」は、大徳寺塔頭・総見院より移築された。 ◈龍翔寺の「旧客殿」は、江戸時代後期、1817年に再建された。現在は、大徳寺塔頭・三玄院の客殿として使われている。 ◆茶室 龍翔寺の現在の茶室「韜光庵(とうこうあん)」は、実業家・山口玄洞(1863-1937)好みの五畳で中柱を立てる。 ◆障壁画 かつて、天瑞寺客殿(方丈)は8室あり、安土・桃山時代、1588年、狩野永徳は総金張りの7室に極彩色の松の間(朝日を表す金の円板、名月を表す銀の円板)、竹、梅、菊、水墨の山水、三笑、富士の図を描いた。その後、これらはすべて失われた。 ◆文化財 龍翔寺に「大応国師(南浦紹明)木像」がある。 ◆朝鮮通信使 安土・桃山時代、1592年-1598年、豊臣秀吉(1537-1598)による文禄・慶長の役(壬辰・丁酉倭乱)後、初めての使節団として、江戸時代前期、1607年に、第一回回答兼刷還使(朝鮮通信使)の500人が大徳寺に定宿する。徳川家康(1543-1616)の国書に対し朝鮮国王の回答国書を携帯し、文禄・慶長の役の際の朝鮮人の民間被虜人を連れ帰る目的があった。 通信使の正使らは天瑞寺、随員は総見院・真珠庵・聚光院、大仙院などに宿泊した。京都所司代は、蹴鞠・猿回しなどを呼び一行を歓待した。 ◆墓 龍翔寺境内の西北隅に大政所の墓(寿塔)が残されている。かつて、廟堂に覆われていた。寿塔覆堂は、横浜の三渓園に移され保存されている。 ▣龍翔寺 柳殿御所跡(右京区太秦安井)→白毫寺旧地(現在の大徳寺・三玄院の地、龍翔寺旧地)→天瑞寺旧地(現在の龍翔寺の地) ▣天瑞寺 現在の龍翔寺の地→廃寺 ▣三玄院 現在の三玄院(龍翔寺旧地)の西→現在地(龍翔寺旧地) *非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『雍州府志』、『別冊愛蔵版 淡交 大徳寺と茶道 その歴史と大徳寺僧の書』、『紫野大徳寺の歴史と文化』、『京都・紫野大徳寺僧の略歴』、『事典 日本の名僧』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『秀吉の京をゆく』 、『京都戦国武将の寺をゆく』、朝鮮通信使ゆかりの地の駒札、ウェブサイト「文化史17 朝鮮通信使 -京都市」ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |
| |
|