|
|
|
| 熊野神社・聖護院の森 (京都市左京区) Kumano-jinja Shrine |
|
| 熊野神社・聖護院の森 | 熊野神社・聖護院の森 |
 |
 |
      本殿    本殿  本殿       豊臣稲荷大神、金比羅大神   豊臣稲荷大神、金比羅大神  神倉神、須賀大神、春日大神  神倉神、須賀大神、春日大神  神倉神、須賀大神、春日大神
神倉神、須賀大神、春日大神 祖霊殿  地下70mからの湧水  八ッ橋発祥の地の碑 八ッ橋発祥の地の碑 西尾為冶の銅像  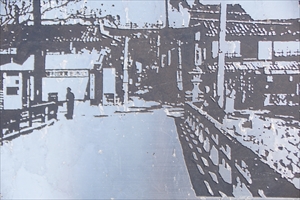 【参照】丸太町橋、熊野時神社一の鳥居、石燈籠、丸太町橋西詰北の説明板より |
熊野神社(くまの-じんじゃ)は、「京都熊野神社」、「白川熊野社」、「熊野権現社」、「権現さん」とも呼ばれている。 平安時代、院政期(1086-1186)に創祀された「京都三熊野(みくまの)」の一つに数えられた。ほかに新熊野(いまくまの)神社、若王子(にゃくおうじ)神社がある。 熊野三山別当職を務めた聖護院の鎮守社でもあり、天台宗本山派修験道の守護神として崇敬されていた。旧郷社。 祭神は伊弉冉尊(いざなみのみこと)、伊弉諸尊(いざなぎのみこと)、天照大神(あまてらすおおみかみ)、速玉男命(はやたまのをのみこと)、事解男命(ことさかのをのみこと)を祀る。 京都十六社朱印めぐりの一つ。京の三熊野神社(ほかに、熊野若王子神社、新熊野神社)の一つ。 縁結び、建礼門院が祈願し安徳天皇を出産したとして安産祈願、病気平癒、健康長寿、鎮火、災い除け・厄除、道中安全・守護などの信仰もある。 授与品は、火の用心お札、熊野牛王宝印、なぎ守り(災厄除)、加楽寿守り、烏絵馬、牛王絵馬、サッカー守りなどが授与される。 ◆歴史年表 平安時代、811年、阿闍梨・日円(圓)上人が、この地に紀州の熊野権現を勧請したのが始まりという。(社伝) また、1103年、園城寺僧・増誉が、白河上皇(第72代)の意により、白川付近に熊野新宮の御霊を勧請したともいう。(『中右記』)。以後、増誉が建立した聖護院の鎮守社になり、天台宗本山派修験道の鎮護の社になる。聖護院は別当職を置いて管理した。 1112年、熊野新宮祭が行われた。 室町時代、1396年、3代将軍・足利義満(1358-1408)により、広大な社域を寄進される。(社伝) 1468年、応仁・文明の乱(1467-1477)に際して社殿は焼失し、その後荒廃する。(『碧山日録』) 江戸時代、1666年、聖護院宮道寛法親王により再興された。(『坊目誌』) 1835年、下鴨神社旧本殿が移され、大修造が行なわれた。 近代、1893年、道路拡張により社地が縮小になる。 1913年、市電丸太町線開通に伴い、境内は縮小した。 ◆日円 平安時代前期の天台宗の僧・日円(にちえん、?-?)。詳細不明。男性。円(圓)上人。阿闍梨だった。811年、紀州の熊野権現を勧請し、京都に熊野神社を創建したという。 ◆増誉 平安時代後期の天台宗の僧・増誉(ぞうよ、1032-1116)。男性。通称は一乗寺僧正。父・権大納言・藤原経輔。6歳の時、園城寺の乗延に師事、行円の下で得度で出家した。大峰山、 葛城山で修業を積む。1074年、権少僧都、第72代・白河天皇の護持僧、 第73代・堀河天皇の護持僧、1090年、白河上皇の熊野詣の先達を勤め、熊野三山検校となる。1094年、四天王寺の別当職、1096年、権僧正、1098年、広隆寺別当職、1100年、園城寺の長吏、1102年、正僧正、法成寺執印に補任されている。1105年、天台座主となるものの山門派の反対で翌日辞退した。大僧正。尊勝寺などの13寺の別当も兼ねた。85歳。 聖護院開基の増誉は、修験道を開いた役行者の法灯を継いだとされる。墓は、長谷の御所谷の林の中にあった。 ◆後白河 天皇 平安時代後期の第77代・後白河 天皇(ごしらかわ-てんのう、1127-1192)。男性。雅仁(まさひと)、法名は行真。父・第74代・鳥羽天皇、母・中宮待賢門院璋子(権大納言藤原公実の娘) の第4皇子。1155年、異母弟の第76代・近衛天皇の死により践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)し、29歳で即位する。即位は鳥羽法皇の意向により、崇徳上皇、その子の皇位継承を阻止するためだった。乳父・藤原信西が重用された。1156年、鳥羽上皇没後、皇位継承を巡り、保元の乱が起こる。崇徳上皇方と後白河天皇方で戦い、天皇方が源義朝(よしとも)、平清盛(きよもり)らの活躍で勝利した。崇徳上皇を配流させる。乱後、新制七か条を制定し、記録所を設置して荘園整理を行い、寺社勢力の削減を図ろうとした。1158年、3年の在位の後、第78代・二条天皇に譲位した。1159年、信西に反感を抱く人々による平治の乱で、清盛の攻勢で仁和寺に逃れた。乱後、清盛が実権を握り、平家と連携する。1161年、法住寺殿に移る。1168年、清盛と謀り六条天皇を退位させ、憲仁親王(高倉天皇)を即位させる。1169年、園城寺前大僧正・正覚を戒師として出家する。園城寺長吏・覚忠により受戒し、法名は行眞と称した。院近臣の強化、延暦寺や東大寺の僧兵の利用で清盛を除こうとした。1170年、東大寺で改めて受戒した。1171年、清盛の娘・徳子が法皇の猶子になり、高倉天皇に入内になる。1177年、近臣による平氏打倒の謀議が発覚する鹿ケ谷の事件が起こる。以後、清盛との関係が悪化する。1179年、清盛の謀反により、院政を止め鳥羽殿に幽閉の身になる。1181年、高倉上皇没後、院政を再開する。法皇は頼朝と結び義仲を排しようとした。法皇は比叡山に身を隠した。1183年、法住寺合戦で、木曾義仲が法住寺殿を襲撃し、後白河法皇と後鳥羽天皇は六条西洞院の御所に幽閉され院政を止められる。法皇は頼朝に救援を依頼した。1184年、義仲が討たれる。平氏は京都を追われ、1185年、源義経の軍に壇ノ浦で滅ぼされた。1192年、室町殿(六条殿)で亡くなる。66歳。没後、法住寺法華堂に葬られる。 二条天皇、六条、高倉、安徳、後鳥羽天皇の5代30余年にわたって院政を行い、治天の君(院と天皇の二重権力の競合併存)として王朝権力の復興・強化に専念した。台頭した武士勢力を対抗させて巧みに抑え、源頼朝は「日本一の大天狗」と評した。大内裏造営を行い、法皇になり清盛の尽力し蓮華王院(三十三間堂)、長講堂などを造営し、造寺、造仏、高野山、比叡山東大寺などの参詣を盛んに行なった。熊野参詣は34回に及んだという。歌謡を分類集成した『梁塵秘抄』『梁塵秘抄口伝集』10巻を撰した。遊女・乙前に今様を学ぶ。今様は、法住寺の広御所で披露され、さまざまな階層が参加した。 ◆建築 旧拝殿、拝殿、本殿、社務所などがある。 ◈「本殿」は、江戸時代後期、1835年に下鴨神社旧本殿が移されて大修造が行なわれた。 ◈「社務所」は、現代、1973年に改築された。 ◆文化財 剣鉾「烏鉾」の茎銘は、江戸時代後期、1805年になる。「熊野皇太神」の額があり、地の金色の剣・錺に左右に3匹のずつの黒烏が全体で円形にあしらわれている。 身139㎝、茎40.2㎝、全長179.2㎝になる。 ◆熊野信仰 熊野神在祭は古くから行なわれており、「人まねの熊野詣」「蟻の熊野詣」と称された。 歴代天皇の信仰を集めた。平安時代末期、後白河法皇(1127-1192)は、熊野詣(往復500km、3週間の行程)を度々行い、当社殿を修造し、境内を寄進した。当社は、京の熊野三山(ほかに新熊野社、若王子・熊野権現)の一つとして庶民の信仰も篤かった。 ◆牛王法院 当社での祈祷に際して、熊野の「牛王法印(ごおうほういん/ごずほういん)」の誓紙を用いる。願い事の文を「起請文(きしょうもん)」という。神にかけて誓う厳しいものであり、背くと罰を受けるとされた。 法印には「烏天(うてん)」が用いられており、初代・神武天皇の東征に際して、道案内したという八咫烏(やたがらす)48羽を文字にして星図とした。盗難除け、災除、病気平癒の護符とされた。縁結び、安産、夫婦和合のご利益もある。 ◆文学 中河興一作『天の夕顔』に界隈の描写がある。 ◆八ッ橋 京都銘菓の一つ「八ッ橋」について、詳細は分かっていない。 ◈境内に、「八ッ橋発祥の地」として西尾家12代目・西尾為冶(1879-1962)の銅像が立つ。八ッ橋を京の銘菓に育て「中興の祖」といわれた。碑は、その功績を顕彰するために、現代、1994年に平安建都1200年記念に立てられた。 「本家西尾八ッ橋」の歴史は、江戸時代前期、1687年にまで遡るという。聖護院の森にあった「八ッ橋屋梅林茶店」では、米粉を使った素朴な「白餅」が売られていた。東海道を往来する旅人の携帯食としても重宝されていた。1689年に、八ッ橋の原型になる橋の形をした米粉の煎餅が生まれ、「八ッ橋」と名づけられたという。江戸時代後期、1824年に熊野神社に奉納された絵馬には「八ッ橋屋為治郎」の名前が残る。 近代に入り、為冶は八ッ橋を世界の博覧会に出品する。1889年のパリ万博では銀賞を受賞する。1902年のフランス博覧会(ハノイ)では金賞を受賞した。1905年には、携帯食として八ッ橋が割れにくくするために丸みを帯びた形になる。1910年の日英博覧会では銀賞、1905年の米国オレゴン州ポートランド大博覧会で銀賞、1909年のアラスカ・ユニコーン太平洋博覧会ではグランプリ受賞した。 ◈八ッ橋の名の由来は、『伊勢物語』、謡曲「かきつばた」の中の故事「三河国八ッ橋」にあるという。夫を失った若い母と2人の幼子が暮らしていた。働きに出た母を追い、子どもたちは橋のない途中の川を渡り溺死した。1人残され悲しんだ母は仏門に入る。ある日、夢枕に僧が現れ、川の入り江に材木があるから、橋を造るようにと告げる。それが子どもたちへの供養にもなるという。翌朝、川に行くと、材木が川に浮いていた。母はそれらを互い違いに並べて、八つの橋が生まれたという。 この話に因み、本家西尾八ッ橋では「八ッ橋」と名づけたという。 ◈八ッ橋の形は、八橋流箏曲の始祖・八橋検校の琴の形に因み、検校を偲んで作られたともいう。検校の葬られている金戒光明寺(黒谷)の参道にあった茶店では、江戸時代前期、1689年以来、干し菓子を出しており、その菓子に由来するともいう。 八橋検校の命日(6月12日)に、金戒光明寺・常光院(左京区)で八橋忌、法然院(左京区)で八橋祭がそれぞれ行われている。 ◆聖護院の森 かつて、社域は広大で、境内南西に鬱蒼とした森が広がり、「聖護院の森」といわれていた。(『山城名跡巡行志』)。1町四方の境内があったともいう。丸太町通の南北に付近には、多くの梅の木が植えられていた。花期には遊宴が催された。現在は、600坪(1983㎡)ほどの境内が残る。 近代以降、1926年、1943年の市電丸太町線の軌道敷設にともない、境内は大幅に狭められた。それでも境内には、いまもムクノキ、モミなどの巨木が残る。ナギが植えられている。 なお、錦林小学校にも聖護院森の名残のケヤキ、ムクノキなどがある。 ◆京都十六社朱印めぐり 京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)は、現代、1976年に始まり当初は14社だった。古社16社を巡拝し、各社より朱印を授かる。すべての神社を参拝すると一年間のあらゆるご利益が得られるという。専用の朱印帳で期間中に全てのご朱印を受けると干支置物が授けられる。 ◆市電 付近に京都市電の停留場「熊野神社前」があった。 近代、 1912年6月11日に京都市電の丸太町線・円町-熊野神社前 、1913年4月16日に丸太町線・烏丸丸太町-熊野神社前、東山線・ 熊野神社前-竹屋町通(仮)が開業する。1928年1月13日に、東山線・熊野神社前-百万遍 、1930年3月2日に、丸太町線・熊野神社前-岡崎天王町(後・天王町) の開業により全線開業した。 現代、1976年4月1日に丸太町線・円町-熊野神社前は廃止された。 ◆祭礼 神幸祭(氏子大祭)(4月29日)では、1週間前に神輿・剣鉾の鉾頭が拝殿に飾られる。神幸祭当日に、現在は剣鉾は巡幸列には加わらない。 ◆年間行事 初詣(神酒授与)(1月1日-3日)、京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)、節分祭(星祭り)(吉田神社への参詣の折に、当社で台所に貼る「火の用心」のお札を授与してもらうという風習がある。福引、福豆授与、茶菓接待。)(2月2-3日)、神幸祭(氏子大祭)(4月29日)、出輿祭(5月15日)、例祭(神幸祭)(5月16日)、夏越祭(6月30日)、祖霊祭(8月15日)、七五三祭(11月15日)、火焚祭(湯神楽神事)(11月20日)、除夜祭(12月31日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『続・京都史跡事典』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『剣鉾まつり』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京のご利益めぐり』、『京都のご利益手帖』、『京の福神めぐり』、『京都 神社と寺院の森』 、ウェブサイト「西尾八ッ橋の歴史 - 本家西尾八ッ橋」、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |