|
|
|
| 極楽寺 (京都市東山区) Gokuraku-ji Temple |
|
| 極楽寺 | 極楽寺 |
 |
 |
   本堂  本堂 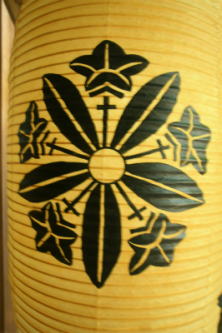  本尊阿弥陀仏   宝篋印塔 |
伏見街道(本町通)の東に面して極楽寺(ごくらく-じ)はある。 寺号は平安時代の公卿・藤原基経(836-891)、その子・時平(871-909)が建立した深草・極楽寺の旧号を継いだという。山号は金龍(竜)山という。 浄土宗禅林寺派。本尊は阿弥陀仏を安置する。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、925年、公卿・藤原忠平が創建したという藤原氏氏寺・法性寺(ほっしょうじ)の、十王堂(じゅうおうどう)の故地だったという。 江戸時代、その地名は残っていたという。 その後(創建年不明)、僧・岷空、僧・鳳山の二僧が開基したという。(『京都府地誌』) ◆藤原時平 平安時代前期-中期の公卿・藤原時平(ふじわら-の-ときひら/しへい、871-909)。男性。通称は本院大臣、中御門左大臣。父・太政大臣・藤原基経、母・人康親王(第54代・仁明皇子)の娘の長男。父の威光により、第58代・光孝天皇に重用された。886年、元服に際し光孝天皇自ら加冠役を務めた。正五位下。887年、従四位下、左近衛中将、蔵人頭になる。890年、従三位、891年、基経が没し参議になる。第59代・宇多天皇は、藤原氏の専権抑制のために菅原道真を抜擢した。892年、権中納言、897年、大納言、左大将、氏長者になる。第60代・醍醐天皇下で、899年、左大臣になり、「延喜の治」を推進した。右大臣に任じられた道真を排斥し、901年、道真を讒言(ざんげん、告げ口)により大宰権帥(だざいのごんのそち)に左遷する。902年、最初の荘園整理令など、律令制の再編強化のために諸法令を出し「延喜の治」を推進した。その後、政治的に失墜し、急逝した。著『時平草子』『外記蕃記(げきばんき)』など。39歳。 没後、正一位、太政大臣を追贈された。国史の編纂として『日本三代実録』『延喜式(えんぎしき)』の撰修に関与した。その死は道真怨霊の祟りとされ、子孫も転落し消滅した。 墓は宇治陵(宇治市)に包括されている。宇治陵35号陵は「時平塚」ともいう。 ◆本尊 本堂安置の本尊、丈六の阿弥陀仏坐像は、奈良時代の唐よりの渡来僧・鑑真(688-763)作ともいう。 ◆十王堂 十王堂は法性寺の門外、南にあり、本尊は閻魔王を安置した。冥界における十人の裁判官である十大王を安置していたという。(『拾遺都名所図会』)。 ◆井戸 境内の古井戸は弘法大師空海(774-835)の杖の跡という。十王堂の閻魔像はこの土で作られたといい、伏見人形との関わりもあるという。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』  |
 |
 |
| |
|