|
|
||
| 五条(條)天神社 (京都市下京区) Gosho-tenjinsha Shrine |
||
| 五条(條)天神社 | 五条(條)天神社 | |
 |
 |
|
     「皇国医祖神 五条天神宮」の石柱   本殿  本殿  本殿    右より、白太夫神社、大国主神社、金刀比良神社、福部神社  右より、辨財天社・辨財天、猿田彦神社・猿田彦大神、稲荷神社・倉稻魂命  筑紫天満宮・菅原道真   医家の祖神の碑、少彦名命は薬の神で、医薬・禁厭(おまじない)・農耕の神   【参照】祗園祭の橋弁慶山、説明板より。牛若丸と弁慶の五条大橋の上の戦い「橋弁慶」を題材にしている。弁慶は鎧姿に大長刀を斜めにかまえ、牛若丸は橋の欄干の擬宝珠の上に足駄で立ち片足を曲げ右手に太刀を持っている。橋は黒漆塗で、牛若丸の人形は足駄金具一本でこれを支えている。  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた五条天神社、鴨川二条大橋の説明板より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた五条天神社、鴨川二条大橋の説明板より  【参照】「天使突抜」の住所表示 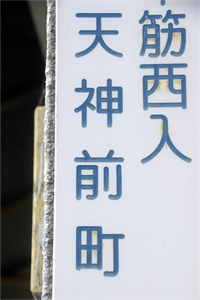 【参照】「天神前町」の町名  【参照】松原通りの表示板 |
五条天神社(ごしょう-てんじん-しゃ)は、鴨川にかかる松原橋の西にある。この地は、鴨川の氾濫原であり、水神、雷神を鎮め疫病を防ぐ御霊社だった。「てんしん」「天使社」「天使の宮」「五条天神宮」ともいわれた。 祭神は、大自己貴命(おおなむちのみこと)、少彦名命(すくなひこなのみこと)、天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀る。 農耕、病気退散の神、疫神、厄除け、医道の祖神、医薬、禁厭(きんえん、まじないの意)の神として崇敬される。ガガイモ(蘿藦/鏡芋)の皮でできた宝船の絵の御札が授与される。 ◆歴史年表 平安時代、794年、平安京遷都にともない、この地(旧五条西洞院大路)に、奈良北東部の大和宇陀郡(うだ-ぐん)より天神(あまつかみ)を勧請したといわれる。空海(774-835)の勧請によるともいう。当初は、「天使の宮」「天使社」ともいわれた。 804年、渡唐にあたり、最澄(767-822)、空海は、当社に安全祈願したという。 1156年、保元の乱により焼失したという。 第82代・後鳥羽天皇(在位:1183-1198)の時、五條天神宮と改められる。 平安時代末、祇園社末社だったともいう。 室町時代、1421年、五条天神は流罪宣下を被る。(『看聞御記』) 応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失したという。 1528年、焼失している。 江戸時代、1788年、天明の大火により焼失している。 1864年、蛤御門の変によって焼失し、その後再興された。 ◆空海 奈良時代-平安時代前期の真言宗の開祖・空海(くうかい、774-835)。男性。俗姓は佐伯氏、幼名は真魚(まお) 、灌頂名は遍照金剛、弘法大師。讃岐国(香川県)の生まれ。父・豪族の佐伯田公(義通)、母・阿刀氏。788年、15歳で上京し、母方の叔父・阿刀大足に師事し儒学を学ぶ。791年、18歳で大学明経科に入るが、中途で退学し私渡僧(しどそう)として山岳修行を始め、四国の大滝岳、室戸崎などで山林修行した。797年、『聾瞽指帰(ろうこしいき)』を著す。798年、槙尾山寺で沙弥になり、教海と称する。804年、東大寺戒壇院で具足戒を受ける。遣唐使留学僧として唐へ渡り、805年、長安・青竜寺の恵果(けいか)により両界、伝法阿闍梨の灌頂を受ける。806年、当初の20年の義務期間を2年に短縮して帰国、多くの経典、密教法具などを持ち帰る。入京できず太宰府・観音寺に住した。809年、入京を許される。810年、高雄山寺(神護寺)を経て、811年、乙訓寺に移り、約1年間任に当たった。別当になる。812年、乙訓寺を訪れた天台宗開祖・最澄は、空海と会っている。その後、空海は高雄山で最澄らに金剛界結界灌頂を行った。後、二人は決裂し、断絶する。813年、東大寺別当、819年頃/818年、高野山を開く。822年、東大寺に灌頂道場(真言院)を開く。823年、東寺を真言密教の道場にした。824年、高雄山寺を神護寺と改名する。神泉苑で祈雨の修法を行う。827年、大僧都になる。828年、綜芸種智院を創立した。832年、高野山で万灯会、834年、正月、宮中中務省で後七日御修法を営む。830年、『秘密曼荼羅十住心論』を著す。高野山で亡くなり東峰に葬られた。62歳。 空海は、中国から真言密教をもたらし、日本天台宗の開祖・最澄(伝教大師)とともに、奈良仏教から平安仏教への礎を築いた。空海による真言密教の拠点は、東寺のほかに高野山、宮中の真言院の三寺ある。空海の真言密教の神髄は、大日如来の教えに従い、あらゆる存在、性質、思考は、宇宙の絶対者である毘盧遮那仏が姿を変えたものであるとした。第52代・嵯峨天皇、橘逸勢と共に「三筆」の一人として数えられている。東寺境内に日本最初の私立学校「綜芸種智院」も創立した。唐で学んだ土木技術により、各所で灌漑、土木工事などを行い、祈雨の伝承も残っている。 ◆源 義経 平安時代後期-鎌倉時代前期の武士・源 義経(みなもと-の-よしつね、1159-1189)。男性。幼名は牛若丸、遮那王。父・義朝。1159年、父が平治の乱で敗死、平氏より逃れる。母・常盤御前は捕えられ、三人の子が寺に入ることを条件に命を許される。義経は、公卿の藤原長成の援助により鞍馬寺・東光坊阿闍梨蓮忍に預けられる。後、禅林坊の覚日のもとへ移る。金商人・吉次にとともに奥州に移る。1180年、兄・ 頼朝の挙兵し呼応、1183年、頼朝の代官として畿内近国に派遣される。1185年、壇の浦で平氏を滅ぼした。だが、三種の神器の宝剣を回収できず兄・頼朝との対立、畿内近国の支配権を奪われる。後白河法皇による頼朝追討宣旨を得て挙兵するが失敗し、愛妾・静御前と共に吉野に、さらに奥州藤原秀衡を頼り逃れた。だが、その没後、藤原泰衡により衣川の館で討たれ自刃した。31歳。 ◆弁慶 平安時代後期-鎌倉時代前期の伝説的僧・弁慶(べんけい、?-1189?)。詳細不明。男性。幼名は鬼若、武蔵坊とも呼ばれる。熊野の生まれ。父・熊野別当。幼時に比叡山西塔桜本僧正に預けられる。乱行により放逐、自ら剃髪し弁慶と名乗る。播磨書写山放逐後、京都で1000本の太刀を奪う悲願を立て五条天神に参詣して祈願する。義経に出会い、清水観音境内で義経と闘う。敗れて以後従う。義経の平家討伐に加わる。1189年、衣川の合戦では立ったまま死んだという。 ◆祇園社 祇園社と関わりがある。平安時代後期、久寿年間(1154-1156)にはその末社だったという。 その後、一度支配から離れ、少なくとも南北朝時代、1390年に再び戻ったという。 ◆ゆき 「靱(ゆき)」は、矢を納める武具の靱(ゆき)を意味する。靱(うつぼ)、空穂(うつぼ)とも記される。矢を入れ、腰に下げ持ち歩く筒形の容器をいう。長い竹籠(たけかご)で作り、外側を動物の毛皮や鳥の羽などで覆った。 靱に矢を入れる際には鏃(やじり、ぞく)を上にした。かつては、靱負(ゆげい、ゆきえ)という武人がいたという。 『諸社根源記』、また、鎌倉時代末期の吉田兼好『徒然草 』第203段に靱の名がみえる。元来は疫神であり、天皇の病を平癒、世の安泰を祈願し、社前に靱を掲げ祈念したという。五条天神社にも祀られ、同様の疫神は今宮神社の韓神、鞍馬の由岐神社にもみられる。 ◆宝船 神社が配する宝船図は、日本最古のものという。船に、稲穂が乗った図案になっている。 宝船に、厄除け、病除けの祈願をすると、つつがなく世上の波渡りができるという信仰がある。室町時代には、宮中、親王、公家にのみ献上されていた。近代、大正期(1912-1926)以降は一般にも配布された。節分の日には、おけら餅、勝餅とともに授けられる。 ◆松原 松原橋、松原通は、豊臣秀吉の現在の五条大橋架け替え以前は、それぞれ五条大橋、五条通といわれていた。 ◆西洞院川 かつて社の東に西洞院川が流れていた。牛若丸と弁慶の立合いがあったのは、五条大橋(現松原橋)ではなく、この川に架かっていた橋という伝承もある。 ◆天使の杜 一帯には、かつて「天使の杜」という広大な森があった。この「天使」とは、当社の祭神・少彦名命の異名「天子(天皇)」を言い換えたともいう。 西隣には真言宗天使山一音寺一音院(下京区岩上通五条上ル柿本町)があり、かつては当社と関係があったという。 社の一筋西の通りには、「天使突抜(てんし-つきぬけ)」という町名も残され、4丁目まである。これらは、「天使の宮」、「天使社」に由来するとの説が一般的になっている。 「突抜」については、もともとこの地には広い社域があった。安土・桃山時代、1590年に、豊臣秀吉の都市改造が行われた。社の鎮守の森を削り、突き抜けて町が拓かれたことに由来するともいう。当初の通り名は、「天使突抜通」(現在の東中辻通)と名づけられた。異説もある。 「突抜」とは、単に路地の呼び名であり、建物を通り抜けるの意味があったともいう。市内には25以上の「突抜」の地名があったという。 ◆文化財 ◈宝船の版木は、舟の中央に稲束が置かれている。2本の稲穂はたわわに実り、舟の上部からも稲穂がはみ出し、豊年を象徴している。 ◈剣鉾2基ある。永養寺町が護持する1基には額「五條天神宮」があり、菊の意匠の錺(かざり)が付く。 高辻西洞院町が護持する1基には、額「五條天神宮」に、左右に日の扇・月の扇の錺がある。 ◆伝承 平安時代末期の『今昔物語』、鎌倉時代末期の『徒然草 203段』にも当社が取り上げられている。天皇の病、世情不安な時に、五条天神に武具の靫(ゆぎ)を捧げて祈ったという。病疫退散の神として知られていた。 社の近くで、牛若丸(源義経、1159-1189)と弁慶が出遭ったともいわれている。(『義経記』、謡曲・歌舞伎の『橋弁慶』)。また、義経は、陰陽師・鬼一法眼の謀略により、印地大将湛海と闘う場所として当社が設定されている。 平安時代の第60代・醍醐天皇(在位897-930)の頃、境内の柿の木に偽の仏が現れたという。庶民が群衆した。(『宇治拾遺物語』巻2) 文覚(1139-1203)は流罪の時、当社鳥居の下に黄金を埋めたとして船頭を欺いたという。(『源平盛衰記』巻18) 室町時代、1421年 疫病が流行し、五条天神が流罪とする宣下が祇園社に下ったという。(『看聞御記』) ◆印地の大将 源義経に兵法を伝授したとされる鬼一法眼(きいちほうげん)は陰陽師だった。「一条堀河」の西に住み、屋形を構えて天下の御祈祷をした。この法眼の娘婿に、北白川天神社に奉仕した印地(いんじ)の大将・湛海(赤山の東海坊)がいたという。彼ら下級の宗教武装集団は、石投げを得意とした。湛海は義経殺害を託されたにもかかわらず、鬼一の謀りにより、義経と五条天神社境内で闘い、殺害される。(『義経記』) 弁慶の出生に関しても五条天神社が関り、義経と弁慶が出会いも当社にあると記されている。(『義経記』) ◆アニメ ◈劇場版アニメーション『名探偵コナン 迷宮の十字路』(原作・青山剛昌、監督・こだま兼嗣、制作・トムス・エンタテインメント、2003年4月)の舞台になった。社前、境内などのシーンがある。 ◆祭礼 「氏子祭」(10月10日)では、前日の午前に、神社の蔵から剣鉾2基が各鉾町飾り場で組立てられ、祭壇が作られる。 当日午前に、各飾り場より供え物を入れた唐櫃(からびつ)を奉ずる列が神社に向かう。本殿に御供え後、夜に本殿での祭典が行われる。各飾り場を神職が訪れ、神事が行われる。現在は、神輿渡御・剣鉾巡行も行われない。 ◆年間行事 歳旦祭(1月1日)、節分祭(白朮、勝餅、宝船の古図が授与される)(2月節分)例祭(5月10日)、氏子祭(10月10日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『増補版 京都の医史跡探訪』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都・美のこころ』、『京の寺 不思議見聞録』、『京都大事典』、『京の医学』、『剣鉾まつり』、ウェブサイト「コトバンク」  |
|
 |
 |
|
| |
||