|
|
|
| 京都府立医科大学旧附属図書館・療病院碑 (京都市上京区) Former Attachment library,Kyoto Prefectural University of Medicine |
|
| 京都府立医科大学旧附属図書館 | 京都府立医科大学旧附属図書館 |
 |
 |
 北側   北側、正面玄関、尖頭アーチ  北側、正面玄関 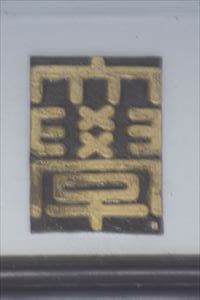 北側、正面玄関  北側、パットレス(控壁)上部の装飾  北東角、パットレス  北側、パットレス  北側、スクラッチタイル貼り  北側  北側、パラペット 北側、パラペット 北側、窓の尖頭アーチ  北側、バルコニー 北側、バルコニー 北側、窓、バルコニー  北側、窓の尖頭アーチ  北側 北側 療病院碑  療病院碑  明治期の府立療病院正門(徳力富吉朗作「白い門」)、療病院説明板より 明治期の府立療病院正門(徳力富吉朗作「白い門」)、療病院説明板より |
京都府立医科大学構内に、旧附属図書館(きゅう-ふぞくとしょかん)が残されている。ネオ・ゴチック建築としては京都府内随一になる。現在は大学本部棟として使用されている。 設計は京都府土木部監理課/京都府営繕係の十河安雄が主任として関わった。 ◆歴史年表 近代、1921年、大学令に基づき京都府立医科大学になった。 1929年、5月、旧附属図書館棟が竣工した。 現代、2008年、3月、京都府の指定文化財になる。その後、修復工事が行われた。 ◆明石 博高 江戸時代後期-近代の医師・化学者・衛生学者・殖産家・明石 博高(あかし-ひろあきら、1839-1910)。男性。名は博人、号は静瀾。京都の生まれ。父・代々の医薬舗「浩然堂」を営む弥三郎、母・浅子。5歳で父が亡くなる。外祖父・蘭方医・松本松翁に育てられ、西洋医術・化学製薬術を学ぶ。14歳頃、桂文郁に古典医学を学んだ。宮本阮甫・武市文造にオランダ語、柏原学介に物理学、錦小路頼徳に解体術、主に新宮凉閣に解剖・生理・薬物・臨床医学、新宮凉民にも学ぶ。田中探山に本草学、辻礼甫に化学・製薬術・測量術を学んだ。1865年、京都医学研究会を創設した。1866年、公家・錦小路頼言(にしきこうじ-よりあき)に入門し、医道免許を受けた。自宅で理科学研究会「煉眞舎(れんししゃ)」を主宰し、理化学・薬学を研究した。1868年、博高は頼言に建議し御所内病院(烏丸一条下ル、施薬院三雲宗順宅)を開設し、医務を担当した。戊辰戦争の死傷者救済を行う。1869年、煉眞舎を三条通室町に移す。大阪・浪華仮病院を創設し、薬局主管・看頭になる。オランダ人・ハラタマ、ボードインらを招く。大阪舎密局のハラタマの助手も務める。1870年、煉眞舎は三井別邸に移る。京都府参事・槇村正直の誘いで京都府に出仕した。京都舎密局を創設し、局長になった。1871年、勧業掛になり、主吏に就く。1874年、京都で日本初の医師免許試験の実施を提言した。1877年、コレラの流行に際して、再流行を予言し検疫制度の採用を提案する。1881年、府知事・北垣国道に代わったため府を辞している。京都舎密局の廃止に際し、払下げを受けた。伏見製作所も払い下げられた。私財を尽くして支援する。1983年、私邸(河原町蛸薬師東入ル)に厚生病院を開き院長を務めた。明石と2人の医師は無給で、診療費も貧富を考慮し「適宜」とした。1884年、京都舎密局は多額の負債で困難をきたし閉鎖している。1887年、厚生病院も廃止され、その後は市井の医師として活動を続けた。著『日本薬泉考』『化学撮要』など。72歳。 槇村正直、山本覚馬、三井源右衛門らと親交があった。博高は数多くの政策・事業に関与している。養蚕場(1871)、鴨東牧畜場(1872)、鉄具製工場(伏見製作所)(1873)、製靴場(1873)、織殿(1874)、染殿(1875)、梅津製紙場(1876)、日本初の小学校、英学校、農学校、女紅場(にょこうば)、博物館、観象台、勧業場(1871)、授産所、療病館(1870)、京都療病院(1872)、避病院(1872)、医学校(1872)、粟田口解剖所(1872)、医務取締制(1872)、医師試験制度(1874)、合薬会社アポテーキ(1874)、京都癲狂院(とんきょういん)(1875)、官立司薬場(1875)、円山吉水温泉などを創設した。京都博覧会開催にも関わる。1873年に、円山の枝垂桜を伐採から守った。 墓は京都市営清水山墓地(東山区)にある。神道のために当初は墓は立てられず、松の木が植えられていた。1959年、明石家、明石博高翁顕彰会により墓が立てられている。 ◆十河 安雄 近代の建築家・十河 安雄(とかわ-やすお、?-?)。詳細不明。男性。京都府営繕課に所属した。 関わった主な作品は、京都府立医科大学旧附属図書館(1929)、紫明会館(1932)、京都府警本部(1933)、鴨沂会館 (1936)、 京都教育大学附属京都小中学校(1938)など。 ◆建築 ◈近代、1929年5月に中央図書館(後に旧附属図書館に改称)は、15万2145円の工費で建設された。設計は京都府土木部監理課/京都府営繕係の十河安雄が主任として関わった。現代、2008年3月、府立医科大学旧附属図書館・階段机・椅子は、京都府指定有形文化財になる。 北面している。平面は東西に長い十字形になる。外観はネオ・ゴシック様式(18-19世紀前半に興きたゴシックの様式を踏襲した新古典主義)になる。正面開口部上部、3階部分の縦長窓に尖頭アーチが開いている。バルコニー、パラペット(屋上、バルコニーの外周部の先端に設けられた低い立ち上がり部分の壁)が見られる。垂直線を強調するパットレス(控壁)が見られる。 外壁全体は人造石洗い出し(セメントモルタルに色石などの骨材を入れて塗り、仕上げ面は天然石のように見せる手法)にしている。中央部のみスクラッチタイル貼り(タイルの表面を櫛引きし、平行の溝をつくる焼成した粘土タイル)、モルタル仕上げになる。 内部にはアール・デコ意匠(1910年代-1930年代にフランス中心に流行した美術工芸様式で、単純・直線的な意匠に特徴がある)が施さている。当初は地階に学生控室、柔剣道場、1階入口ホールにステンドグラスが飾られていた。1階中央階段ステップに階段すべり止め(アメリカ合衆国マサチューセッツ・ローウェルのアメリカン・メイソン・セーフティ・トレッド社製)が用いられている。1階に普通教室2室、2階に図書館、3階に階段教室(階段状講義室)2室があった。階段教室にはステンドグラスが見られる。 施工者は不明。鉄筋コンクリート3階建、地下1階、陸屋根。東西29.9m、南北最大20.4m、建築面積488㎡、延べ床面積580坪(1917㎡)/1952㎡。 ◈現代、2008年以降に修復工事が行われた。外壁は一部落下していたため、補修と洗浄された。屋上からの漏水の修復が優先され、窓の鉄製建具は建築当初と同じ鉄製建具で改修された。3階の東西にある階段教室は、壁が剥落していたため、内装壁は漆喰壁で仕上げた。廊下天井の電気も修復した。東西階段教室の間にあった準備室は、欧風応接室に改修され、上の窓に旧鴨川病棟(1916年建築)のステンドグラス4個が使用された。3階トイレは大理石調に修復された。 ◆京都府立医科大学 ◈京都府立医科大学附属病院の前身は療病院になる。蘭学医・明石博高(1839-1910)らが中心になり資金を募り創設した。近代、1871年に、岡崎願成寺住職・与謝野礼厳、禅林寺(永観堂)前住職・東山天華、慈照寺(銀閣)住職・佐々間雲巌、鹿苑寺(金閣寺)住職・伊藤貫宗らが発起人になり、病院建設を府に出願している。僧らの尽力により、多くの寺院からの出資、広範な府市民の協力得ることに繋がった。京都府は、彼らも含むほか21人(後に67人)と共に療病院勧論方として任命した。寄付金は、一般府民・市民、医師、薬舗からの助資金、花街祇園に課した冥加金などによる資金にで総額5万円に達した。同年に設立許可を受ける。 1872年10月17日(新暦)、木屋町療病院は、仮屋の公舎(木屋町二条下ル19番地)に開院された。当初は、ドイツ人医師・ヨンケル(ユンケル,Junker von Langegg)が診療した。医師の新宮凉閣、新宮凉民、百々一郎、大村達斎、江馬権之助らが日勤、宿直に当った。学生への教育も行われ、寄宿生、通学生がいた。11月24日までの39日間にわたり、仮屋で診療が行われている。 1872年12月1日に、粟田口青蓮院宮旧邸(東山区)を修築し、青蓮院の宸殿大玄関付近に、「京都府立療病院(粟田口療病院)」が開かれる。資金は、寄付金と芸娼妓への冥加金が充てられた。療病院の語源は、飛鳥時代、593年に聖徳太子(厩戸皇子、574-622)が四天王に開設した施設(悲田院、施薬院、療病院、敬田院)の一つに因んでいる。設立基金の発起人の、東山天華、与謝野礼巖、佐々間雲巖らによって名付けられた。ヨンケルは、粟田口青蓮院内の仮療病院で、解剖学の講義を開始した。1872年-1876年に、療病院にオランダ人・マンスフェルト(C.G van Mansvelt)が赴任する。医学教育の系統化を進め、療病院長設置の必要性を勧告した。 1873年に病室が設けられる。粟田口の日ノ岡刑場の裏に建てられた解剖所(山科区)は、療病院所轄になっている。 1874年10月に現在地に土地を選定する。4年制の「医学予備校」・「医学校(校長・萩原三圭)」が開設された。学生はヨンケルが講義した解剖学のほか、生理学、病理学、薬物学、内外科、産科、眼科、整骨科、口中科を学ぶ。通弁(通訳)には山田文友、大井玄洞があたった。同年に梶井町に移転している。 1877年-1881年、ドイツ人・ショイベ(Heinrich Botho Scheube)が赴任した。診療研究に取組み、脚気病、寄生虫学に業績を残した。1879年に医学校(初代校長・萩原三圭)も併設される。1880年、療病院が閉じられている。 ◈近代、1880年7月、療病院は広小路病院(河原町広小路梶井町、元日光宮里坊・二条旧邸・正親町旧邸跡)に6年の歳月を費やし新築移転した。経費は59311円にのぼり、第122代・明治天皇も西日本巡幸時に2500円と宮中建物を寄せた。療病院8451坪(27937.1㎡)、医学校693坪(2290.9㎡)あり、当時としては最新の施設だった。建物は、ライプチッヒ大学病院に倣い、ヨンケルが設計している。講義室3、病室29、手術室、診療所、製薬局、教師館、学生寮も完備していた。 1882年に、医学校は文部省達第4号医学校通則に準拠し、甲種医学校と認定された。1903年に、京都府立医学校が専門医学令による「京都府立医学専門学校」に改編される。療病院はその附属病院になる。 1921年に大学令に基づき「京都府立医科大学」へと昇格し、予科を開設した。現代、戦後の1952年に、学制改革で新制の大学になる。1957年に大学院(医学研究科・博士課程)を開設する。1971年に医療センター、1982年に附属小児疾患研究施設(愛称は京都府こども病院)、1990年に附属脳・血管系老化研究センターなどの附属施設を開設し発展を続けている。 ◈看護学科は、近代、1889年に設置された附属産婆教習所の開設に始まる。現代、1976年、専修学校制度による京都府立医科大学附属看護専門学校、1993年に、本学への医療技術短期大学部併設などの変遷を経て、2002年4月に、京都府立医科大学医学部の学科として設置された。 ◆附属図書館・保存の経緯 近代、1890年に療病院内に京都医学校の書籍室が設けられている。1905年に図書館・学生控所・学生食堂の2階建1棟が竣工している。1926年に学友会の京都医学図書館が大学に移管され、「中央図書館」になる。本館2階に開設され、中央図書館規則が制定された。 1929年に中央図書館が竣工している。現代、1954年に中央図書館が「附属図書館」に改称される。1992年に新たに「図書館・合同講義棟」が竣工した。 2005年-2014年に大学は外来診療棟整備工事基本計画を立てた。2006年からは、新外来棟・臨床研究棟・小児医療センター合同棟の建設が進められた。この時点で、旧附属図書館は新棟竣工の際に、2011年9月末までに解体される予定になっていた。敷地が容積率超過しており、建築基本法に抵触するためだった。 2006年時点で、病院北玄関北側に東西に走る京都市道があり、その北側の第2駐車場(3400㎡)との間に存在していた。この駐車場が大学本体敷地と連続していなかった。市道を駐車場北側に移設させることで、本体の敷地面積を増加させ容積率を下げることができた。大学側(学長・山岸久一)は旧附属図書館保存のために、京都市に対して市道の付け替えを依頼し、京都府には建物保存の承諾を得た。 2007年11月に、荻野文子(1947年卒業)の遺志による寄附の一部を旧附属図書館の改修工事にあてることで、旧附属図書館は遺されることになった。2008年に、旧附属図書館は京都府の指定文化財になった。同年に修復工事が行われている。 ◆療病院碑 療病院碑は、旧附属図書館の東に立てられている。 近代、1880年12月に療病院開院を記念して立てられた。当初は、広小路の正門を入ってすぐ左側に立てられていた。その後、旧臨床行動南側、記念講堂跡地の中庭を経て、現代、2001年2月に現在地に移されている。 建立者は京都府、撰文は京都府知事・ 槙村正直(1834-1896)、篆額は皇族・熾仁親王(1835-1895)、書は中村勤敬による。 瀬田真黒石製、高さ250cm、幅143cm、奥行64cm。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都府立医科大学」、『京都市の近代化遺産 近代建築編』、ウェブサイト「京都府立医科大学図書館メールNews 第177号2011年3月」、『京都の洋館』、『京の医学』、『増補版 京都の医史跡探訪』、説明文「京都府立医科大学附属図書館-京都府立医科大学」、説明文「療病院碑-京都府立医科大学」、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「療病院碑銅版について- 京都府立医科大学」、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |