|
|
|
| 桂宮西ノ墓地 (京都市上京区) Cemetery of Katsuranomiya-nishi-no-bochi |
|
| 桂宮西ノ墓地 | 桂宮西ノ墓地 |
 |
 |
     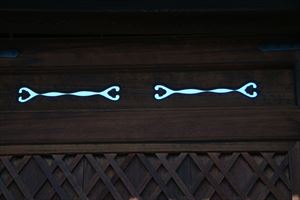  宝篋印塔 |
相国寺の塔頭・慈照院の南東に近接して、桂宮西ノ墓地(かつらのみや-にしのぼち)がある。江戸時代の桂宮家(京極宮)歴代(7代-11代)、その妃など8人の宮墓地がある。 ◆歴史年表 江戸時代、1711年、桂宮家6代(京極宮初代)・文仁親王が亡くなり、この地に葬られた。 1756年、桂宮家8代(京極宮3代)・公仁親王妃・室子女王が亡くなり葬られた。 1768年、桂宮家7代(京極宮2代)・家仁親王が亡くなり葬られた。 1770年、桂宮家8代(京極宮3代)・公仁親王が亡くなり葬られる。 1789年、桂宮家8代(京極宮3代)・公仁親王妃・寿子が亡くなり葬られた。 1811年、桂宮家9代(桂宮初代)・盛仁親王が亡くなり葬られる。 1836年、桂宮家10代(桂宮2代)・節仁親王が亡くなり葬られた。 ◆文仁親王 江戸時代前期-中期の桂宮家6代・文仁親王(あやひと-しんのう、1680-1711)。幼称は富貴宮。京極宮。父・第112代・霊元天皇、母・敬法門院藤原宗子の第8皇子。幸仁(ゆきひと)親王(有栖川宮)の養子になる。尚仁(なおひと)親王の後継に予定されていた弟・作宮(さくのみや、常磐井宮)が死去し、1695年、跡を継ぐ。1696年、京極宮と改称した。1697年、親王になる。京極宮初代。32歳。 墓は桂宮西ノ墓地(上京区)にある。 ◆家仁親王 江戸時代中期の桂宮家7代・家仁親王(やかひと-しんのう、1703-1768) 。京極宮。父・文仁(あやひと)親王の第1王子。第113代・東山天皇の猶子になる。1709年、親王になった。京極宮2代。 墓は桂宮西ノ墓地(上京区)にある。 ◆基子 江戸時代中期の女性・鷹司基子(?-?)。尚君。父・関白・鷹司兼熙(たかつかさ かねひろ)。1720年、家仁親王の正室になる。 墓は桂宮西ノ墓地(上京区)にある。 ◆公仁親王 江戸時代中期の桂宮家8代・公仁親王(きんひと-しんのう、1733-1770)。幼称は胡佐宮(こさのみや)。号は京極宮。父・家仁(やかひと)親王の第1王子。第115代・桜町天皇の猶子になる。1745年、親王になり、上総(かずさの)太守に任じられた。京極宮3代。38歳。 墓は桂宮西ノ墓地(上京区)にある。 ◆室子女王 江戸時代中期の公仁親王妃・室子女王(しつこ-じょおう、1736-1756)。幼称は格宮(ただのみや)。父・直仁(なおひと)親王の第4王女。第113代・東山天皇の孫。1754年、公仁(きんひと)親王と結婚した。1756年、寿賀宮(すがのみや)を産む。2日後に亡くなる。21歳。 墓は桂宮西ノ墓地(上京区)にある。 ◆寿子 江戸時代中期-後期の公仁親王妃・寿子(じゅし、1743-1789)。詳細不明。権大納言・徳川宗直の娘。 墓は桂宮西ノ墓地(上京区)にある。 ◆盛仁親王 江戸時代後期の桂宮家9代・盛仁親王(たけひと-しんのう、1810-1811) 。幼称は磐宮。父・第119代・光格天皇、母・菅原和子の第4皇子(第5皇子とも)。1811年、親王になる。翌日、没した。2歳。 墓は桂宮西ノ墓地(上京区)にある。 ◆節仁親王 江戸時代後期の桂宮家10代・節仁親王(みさひと-しんのう、1833-1836)。幼称は幹宮(もとのみや)。父・第120代・仁孝天皇、母・新待賢門院の第6皇子。4歳。 墓は桂宮西ノ墓地(上京区)にある。 ◆桂宮 安土・桃山時代-近代の宮家、桂宮(かつらのみや)は、世襲の四親王家(ししんのうけ)の一つになる。称号は当初の八条宮の後に、常盤井宮、京極宮、桂宮と変遷する。 安土・桃山時代-江戸時代の誠仁親王(陽光院)の、第6皇子・智仁(としひと)親王(1579-1629)を初代にする。第106代・正親町天皇の皇孫にあたる。智仁親王は幼少で、豊臣秀吉の猶子になった。安土・桃山時代、1589年、秀吉に鶴松が誕生し、猶子は解消される。親王は親王家の取り立てを申請し、秀吉は所領(丹波山城、宇治)を献じた。1590年、八条宮が創立された。江戸時代、2代将軍・徳川秀忠は、山城国下桂川村に知行を贈る。親王は桂川の畔に別邸「桂山荘」を営んだ。継承した2代・智忠(としただ)親王(1619-1662)の時に完成した。現在の桂離宮になる。 その後、第108代・後水尾天皇皇子の3代・穏仁(やすひと)親王(1643-1665)、第111代・後西天皇皇子の第4代・長仁(おさひと)(1655-1675)親王が継ぐ。 第112代・霊元天皇皇子の第5代・尚仁(ひさひと)親王(1671-1689)には継嗣がなく、継嗣に予定されていた霊元天皇皇子・作宮(さくのみや、常磐井宮)も夭折した。このため、同元天皇皇子の6代・文仁(あやひと)親王(1680-1711)が継承し、京極宮(きょうごくのみや)に改めた。作宮の兄になる。 その後、文仁親王の王子の第7代・家仁親王(1704-1768)、孫の第8代・公仁親王(1733-1770)にも継嗣になく、第119代・光格天皇皇子の第9代・盛仁(たけひと)親王(1810-1811)が引き継ぎ、1810年に桂宮と改称した。第120代・仁孝天皇皇子の第10代・節仁(みさひと)親王(1833-1836)、続いて同皇女の第11代・淑子(すみこ)内親王(1829-1881)が継承する。近代、1881年、内親王が没したため、桂宮家は断絶した。 桂宮家屋敷は京都御苑内の今出川門付近にあった。菩提寺は相国寺塔頭・慈照院(上京区)になる。内閣文庫に歌集『桂宮本万葉集(かつらぼん-まんようしゅう)』がある。「五大万葉集」の一つで、現存最古の万葉集写本という。 ◆陵墓 築地塀、門に閉ざされ墓地内を窺うことはできない。域内には桂宮家八方の宝篋印塔などが立つ。 被葬者は、桂宮家6代(京極宮初代)・文仁親王、桂宮家7代(京極宮2代)・家仁親王、家仁親王妃・基子、桂宮家8代(京極宮3代)・公仁親王、公仁親王妃・室子女王、公仁親王妃・寿子、桂宮家9代(桂宮初代)・盛仁親王、桂宮家10代(桂宮2代)・節仁親王になる。 なお、参拝道の東にある東ノ墓地には、初代・智仁(としひと)親王-5代・尚仁(ひさひと)親王、作宮(さくのみや)などが葬られている。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都大事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |