|
|
|
| 住吉大伴神社 (京都市右京区) Sumiyoshi-otomo-jinja Shrine |
|
| 住吉大伴神社 | 住吉大伴神社 |
 |
 |
 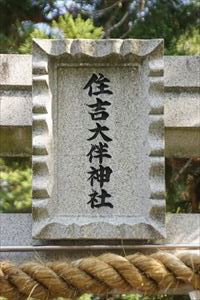   拝殿  拝殿・本殿  本殿  本殿  本殿  小松尾神社、斉明社  十禅師社、天照皇大神、大己貴命を祀る。  十禅師社、「小松尾大明神」の額が掛る。   【参照】大伴家持の「海行かば」の碑  【参照】きぬかけの路の石碑 |
住吉大伴神社(すみよし-おおとも-じんじゃ)は、周山街道(しゅうざん-かいどう、きぬかけの路)に面し、龍安寺の南西に位置している。竜安寺地区、谷口地区の産土神として信仰を集めてきた。かつては、「伴氏(ともうちの)神社」ともいわれ、周辺には大伴氏が住んでいた。 祭神は、古代豪族の大伴氏祖神・天忍日命(あまのおしひのみこと)、道臣命(みちのおみのみこと)、住吉三神の上筒男命(うわつつおのみこと)、中筒男命(なかつつおのみこと)、底筒男命(そこつつおのみこと)。 『延喜式』神名帳には、葛野郡に「伴氏神社(大、月次・新嘗)」と記されている。ご朱印が授けられる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、823年、第53代・淳和天皇の即位に伴い、天皇の諱(いみな)が大伴親王であったことから、避諱(ひき)のため大伴氏は伴氏と改称し、以後、「伴氏(とものうじ)神社」と称された。 834年/834年以前、葛野郡上林郷に、伴氏(伴宿禰[ばんのすくね])の氏神二座を祀り建立されたとみられる。(社伝、『続日本後紀』)。現在地に方1町の土地を得て氏神を祀ったという。 866年、伴善男は応天門の変により失脚した。以後、伴氏の勢力も衰微、次第に祭祀も途絶、廃絶した。 平安時代末期、この地に、藤原氏が勢力を持つ。左大臣・藤原(徳大寺)実能(1096-1157)により山荘「徳大寺殿」が営まれ、堂上(どうじょう)歌人が集った。徳大寺家により、和歌の神・住吉、玉津島の二座が勧請され、「住吉神社(住吉社)」と改称された。(『山城志』)。なお、古代より住吉神と大伴氏との関わりは深かったという。 江戸時代、伴氏神社は、龍安寺村にあり、「日吉」「今日吉」と呼ばれていた。(『山城志』『神名帳考証』)。龍安寺の鎮守社であり、「十禅寺社」と称したともいう。 近代、1942年、天忍日命、道臣命が合祀され、「住吉大伴神社」と改称されている。 ◆伴善男 平安時代前期の公卿・伴善男 (とも-の-よしお、811-868)。佐渡(新潟県)の生まれ。父・参議・大伴国道(おおとも-の-くにみち)の5男。830年、校書殿の官人、第54代・仁明天皇の信任を受け、841年、大内記、蔵人、式部大丞を経て、844年、右少弁になる。846年、法隆寺僧の善愷訴訟事件で弾劾した。847年、蔵人頭、右中弁、848年、参議、849年、検非違使別当、864年、大納言になる。886年、応天門炎上の際に、政敵の左大臣・源信の放火と告発し陥れた。藤原良房に妨げられ、善男と子・中庸(なかつね)が犯人とされ、伊豆へ配流されその地で没した。中庸は隠岐国に流され、伴氏・紀氏の多くが流罪に処せられた。藤原氏の他氏排斥の犠牲になった。(応天門の変) 。58歳。 右大臣・藤原良房らと『続日本後紀』の編纂にも携わった。絵巻物「伴大納言絵詞」の主人公になる。 ◆徳大寺実能 平安時代後期の公卿・徳大寺 実能(とくだいじ-さねよし、1096-1157)。藤原実能。父・権大納言・藤原公実(きんざね)、母・但馬守・藤原隆方の娘・光子。9歳で叙爵、少将、中将を経て、1121年、従三位、1122年、権中納言になる。1133年、長女・幸子が摂関家・藤原頼長と結婚し、1136年、正二位権大納言になる。近衛大将、内大臣に昇る。1147年、徳大寺を建立し、徳大寺左大臣と称された。1156年、保元の乱で頼長に敵対し、第77代・後白河天皇方に付き左大臣になる。1157年、出家し、真理と称した。仁和寺の小堂(徳大寺)で亡くなる。『金葉集』以下勅撰集に入集、日記『実能記』。62歳。 従一位。清華家の一つ徳大寺家の祖になる。歌人としても知られ、僧・歌人・西行(1118-1190)とも親交深かった。衣笠山の西南に別荘があり、徳大寺を建て家名になり、徳大寺左大臣と号した。大炊御門高倉にも邸宅があり、大炊御門左大臣とも称した。 ◆建築 本殿、拝殿、神饌所、神輿倉などが建つ。 ◈「拝殿」は、現代、1978年に新築された。 ◈「本殿」は、昭和期(1926-1989)初めに建立された。それ以前は一間社流造だった。現在は間口1間、奥行1間半の縮小型住吉造と呼ばれ全国唯一という。現代、1978年、茅葺より銅葺になる。 ◆末社 末社の斉明社・小松尾神社、十禅師社がある。 ◆大伴氏 大伴氏は、かつては大和国にあり、遷都に伴いこの地に移住した。上代(飛鳥時代-奈良時代)においては武門の家であり、物部氏と共に皇居を警護、乱を平定して功を立てたという。 平安時代、823年、第53代・淳和天皇の即位に伴い、天皇の諱が大伴親王であったことから、避諱(ひき)のため大伴氏は伴氏と改称している。 一族の中では、奈良時代の政治家・歌人・大伴家持(おおとも-の-やかもち、718-785)が知られている。 ◆文化財 剣鉾の茎銘は、近代、1899年であり、身131.1㎝、茎50.6㎝、全長181.7㎝になる。 ◆氷室 歌枕にもなっている宇多の氷室は、龍安寺から原谷に至る山中付近にあったという。また、住吉山の山麓、住吉大伴神社の地には、徳岡氷室があったという。 ◆碑 きぬかけの路を隔てて、伴家持の当「海行かば 水漬く屍 山行かば 草生す屍 大君の 辺にこそ死なめ かへりみはせじ」の碑が立つ。 ◆祭礼 例祭(秋祭り)(10月第3日曜)の2日前には、鉾宿で剣鉾の組み立てが行われる。夜、神職により神事がある。当日午前に、鉾頭に棹を取り付け台車(鉾車)に載せ吹散を付ける。正午に鉾宿を発し神社へ向かう。巡行後、鉾宿に戻り鉾頭を飾りつけ翌日に片付ける。 剣鉾1基は氏子地域の谷口地区が護持している。額には「住吉大伴神社」とあり、蝶・草花の意匠の錺が付く。 近代、昭和期(1926-1989)初期まで、梅ヶ畑から招いた剣鉾差しがあり、巡行に供奉していた。 ◆年間行事 春の安全祈願祭(4月)、例祭(秋祭り)(10月第3日曜)、神符並びに大祓人形頒布式(12月7日)、歳旦祭(12月31日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の古代社寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『洛西探訪』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都の寺社505を歩く 下』 、『剣鉾まつり』、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |
| |
|