|
|
|
| 明覺寺 (京都市下京区) Мeikaku-ji |
|
| 明覺寺 | 明覺寺 |
 |
 |
 山門   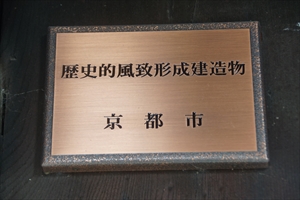 「歴史的風致形成建造物 京都市」のプレート  本堂  本堂内陣、案内写真より     京都タワー |
明覺寺(めいかく-じ、明覚寺)は、新町通に面している。当寺は檀家制ではなく、門徒会・護寺会により運営されている。山号は桃源山という。 浄土真宗本願寺派(西本願寺)、本尊は阿弥陀如来を安置している。 ◆歴史年表 室町時代、1490年、教宗が本願寺8代・蓮如の教化を受け仏門に入り、当初は摂津国島下郡柱本郷(現・高槻市柱本)に一寺を建立したことに始まるという。(寺伝)。当時の柱本は淀川舟運の中心地になっていた。 江戸時代、本願寺の命により、本願寺境内地(下京区門前町)に寺基を移し、塔頭の一つになる。 阿弥陀堂前にあったという。 1607年、旧6月、門前町(下京区)に移ったともいう。 1788年、天明の大火で類焼する。 1864年、元治の大火(どんどん焼け)でも類焼した。 その後、再建される。 近代、1896年/1897年/1898年、現在地(下京区平野町)に移る。 昭和期(1926-1989)初期、茶室「杏梁庵(きょうりょう-あん)」が、明如の別荘「三夜荘」(伏見区)より現在地に移されたという。 現代、2022年、10月、本堂・山門・土蔵・茶室は、国の登録有形文化財に指定された。 ◆教宗 室町時代後期の武士・僧侶・教宗(?-?)。詳細不明。男性。楠木某。楠木正成の末孫という。本願寺8世・蓮如の教化を受け、仏門に入ったという。摂津国島下郡柱本郷(現・高槻市柱本)に一寺を建立し、明覺寺の前身になる。 ◆教誓 安土・桃山時代の浄土真宗の僧・教誓(?-?)。詳細不明。男性。明覺寺5世。1570年-1580年、石山合戦後、1593年、准如の門主就任に際し、幕府の知己を得て円満解決に貢献した。 ◆瑞雲 江戸時代後期-近代の浄土真宗の僧・瑞雲(1858-1912)。詳細不明。男性。明覺寺16世。『声明集』の刊行に尽力した。 ◆大谷 光尊 江戸時代後期-近代の浄土真宗の僧・大谷 光尊(おおたに-こうそん、1850-1903)。男性。法名は明如(みょうにょ)、字は子馨、号は六華、楳窓、信知院(しんちいん)。京都の生まれ。父・西本願寺20世・広如(こうにょ、大谷光沢)の5男。子に長男・大谷光瑞、4男・尊由、次女・九条武子など。1868年、法嗣になる。1871年/1872年、真宗本願寺派本願寺第21世宗主(法主)を継職した。神仏分離令の公布後に、僧・島地黙雷(しまじ-もくらい)、赤松連城(あかまつ-れんじょう)らに諮り、1871年、明治新政府に建言し神祇官を廃し、1872年、教部省の設立を図る。神仏合併の教導職道場「大教院」の大教正になった。1875年、岩倉使節団の一員として島地・赤松をヨーロッパに派遣し、宗門の近代化を行う。島地の提案で大教院から真宗を分離した。1876年、別荘「三夜荘」(伏見区)を建築している。1881年、日本初の選挙制による宗門運営議会制度「集会(しゅうえ、宗会)」を開設した。53歳。 宗門財政改革を進め、本願寺護持財団などを設立して財政改革を行う。宗制寺法を制定した。学林(後の龍谷大学)改革する。北海道・沖縄・アジア・欧米への布教活動、軍隊慰問・軍隊布教、刑務教誨(きょうかい)、救恤(きゅうじゅつ)運動なども進めた。北畠道龍(きたばたけ-どうりゅう)を用いた急進的な宗門改革運動は挫折し、本願寺事務所の築地本願寺御坊への移転計画も中止になる。 ◆柱本 瑞俊 江戸時代後期-現代の僧・柱本 瑞俊(はしらもと-ずいしゅん、1888-1958)。鹿児島県の生まれ。本名は安満星(あま-あきら)。父・性応寺の住持・安満願慧、母・くに(国子)(紀州和歌山・松原有積の次女)。大谷光瑞の従兄弟。1901年、鹿児島師範学校附属小学校高等科第1学年(現・鹿児島大学附属小学校)を修了した 。京都府京都市第三高等小学校 (東山区六波羅)の第2学年へ編入する。1902年、開設された京都府立第二中学校 (南区、現・京都府立鳥羽高等)に入学し、5年の課程を経て、1907年、卒業した。西本願寺の執行所用係になり、室内部に配属になる。同年、得度した。1907年12月-1909年5月、インド調査に赴く。1908年、明覺寺16世・柱本瑞雲とその妻・千代の養子になり柱本に改姓した。1909年、名も改め柱本瑞俊になる。1909年8月-1910年2月、第二次大谷隊インド隊に参加した。1912年、明覺寺17世住職を継承し、1913年、神戸・大谷光瑞の別邸「二楽荘」に併設の武庫仏教中学教員になる。1914年、中学の閉鎖とともに解任され、残務委員として処理に当たった 。1917年、益子(旧姓・若原)と結婚した。1923年、西本願寺に復帰し、枢密部長・室内部長・法務部長、津村別院輪番、審事局長・会計検査局長などを歴任した。退任後、自坊の茶室「杏林庵」で療養生活に入る。70歳。 ◆仏像 本堂内陣に本尊「阿弥陀如来」を安置する。 ◆建築 近代、1897年以降に、建物は現在地に建立された。書院を取り込む寺院建築であり、京町屋の建築様式も内包させている。さらに、茶室・土蔵も加えて一体化させている。明治期京都の特異な寺院建築とされている。2022年10月に、本堂・山門・土蔵・茶室は、国の登録有形文化財に指定された。 ◈「山門」(国・登録有形文化財)は、新町通に面して東側に開く。近代、1897年/明治30年代(1897-1906)に建てられた。五平(長方形断面)の本柱と控柱を貫2段で繋ぐ。両妻は梁上にある板蟇股(いた-かえるまた)が棟木を受ける。軒は一軒疎垂木、破風拝みに懸魚(けぎょ、装飾板)を付ける。 板戸両開、間口2.6m。薬医門、切妻造、桟瓦葺。 ◈「本堂」(国・登録有形文化財)は、近代、1897年/明治30年代(1897-1906)に建てられた。浄土真宗の典型的な建築様式であり、客殿と合体している。外陣(げじん)(12畳2室)と、極楽浄土を表現する黄金に飾られ豪華絢爛な内陣に分かれる。内陣に須弥壇を置く。内陣脇、左右の余間の内、左の余間は書院であり上段の間にもなる。床の間・襖絵が飾られる。 桁行5間、梁間7間、切妻造、桟瓦葺、玄関は入母屋造。 ◈「土蔵」(国・登録有形文化財)は、茶室の南側に建つ。近代、1897年/明治30年代(1897-1906)に建てられた。茶室露地の背景になっている。 腰板は堅板張、上部は漆喰塗で鉢巻まで塗込めている。西に庇を付け、掛子塗(観音扉の重なる部分に段を付けた漆喰塗)の、土戸両開きの戸口を設ける。内部は1・2階に各1室がある。小屋は和小屋で両妻梁が中引梁を受けている。 土蔵造2階建、切妻造、本瓦葺。 ◈「集会所」は、山門に隣接してある。 ◆茶室 茶室「杏梁庵(きょうりょう-あん)」(国・登録有形文化財)は、本堂裏にある。近代、1920年に建てられた。 かつて、本願寺第21世門主・明如の別荘「三夜荘」(伏見区)にあり、昭和期(1926-1989)初期に現在地(下京区)に移されたという。大谷光瑞(1876-1948)ゆかりの茶室になる。「杏梁庵」は瑞俊が命名した。なお、瑞俊は、西本願寺の営繕委員時に、「三夜荘」の修復を担当している。 茶室(4畳半)、水屋(4畳)からなる。半間床、網代天井は北半分を一段落としている。南に躙口、西に貴人口を開ける。切妻造、桟瓦葺。 ◆障壁画など 本堂内陣左余間に襖絵4枚、次の間に杉戸絵がある。 ◆文化財 「明覺寺資料」(主に安満星・柱本瑞俊、九条武子関連など)。 ◆門前町 西本願寺の東に門前町(東西300m、南北700m)はあり、現在は20カ寺ほどが点在する。安土・桃山時代、豊臣秀吉による京都改造に伴い、西本願寺が移され形成された。江戸時代には、広大な境内に80カ寺以上の寺院があり寺内町を形成した。幕府の影響力も及ばない自治を守っていた。江戸時代後期、1864年の蛤御門の変で一帯は焼失し、その後、再建された。 ◆年間行事 元旦会(1月1日)、定例法座(2 月25日)、春季彼岸会(3月11日)、定例法座(4月23日)、定例法 座(6月25日)、盂蘭盆会(8月15日)、秋季彼岸会(9月17日)、定例法座(10月22日)、おみがき(11月12 日)、報恩講法要(11月19日)、定例法座(12月10 ) 。 明歌会(毎月8・18・28日) 、コワーキングスペース(毎週月曜日)、夕方市(過疎地域の野菜の販売)(隔月第2水曜日)、子ども会(日曜学校)(毎月最終日曜日)、落語会(不定期)。 ❊普段は非公開。 ❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『京都市の地名』、ウェブサイト「明覺寺」、「明覺寺の案内」、『拝観之手引-第59回京都非公開文化財特別公開京都』、『京都大事典』、ウェブサイト「大谷探検隊員・柱本瑞俊資料と明覺寺資料-京都,桃源山明覺寺資料調査の現状報告」、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |