|
|
|
| 信行寺 (京都市左京区) Shingyo-ji Temple |
|
| 信行寺 | 信行寺 |
 |
 |
    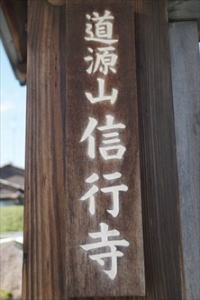  本堂  本堂  本堂  庫裏    |
北門前町、東山通の西側に信行寺(しんぎょう-じ)がある。江戸時代の画家・伊藤若冲が最晩年に描いた天井画で知られている。山号は道源山(どうげん-ざん)という。
浄土宗知恩院末、本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 年代不詳、かつて、摂津・西宮にあった。 年代不詳、その後、開山・順公の時、京都三条東洞院に移り、各所へ移転する。 安土・桃山時代、1589年、豊臣秀吉の命により、寺町丸太町(現在の新島襄旧邸付近)に移る。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、浄土宗寺院の別格寺院の一つに数えられた。 江戸時代、1708年、宝永の大火後、寺町通より現在地(東山仁王門)に移転した9寺院の一つであり、この地に寺院を集めて開かれた。 1716年、現在の本堂が建てられた。 近代、1868年、廃仏毀釈により石峰寺・観音堂(伏見区)の伊藤若冲が描いた天井画が破却される。その後、天井画は当寺に寄贈され、本堂に飾られた。 ◆伊藤 若冲 江戸時代中期-後期の画家・伊藤 若冲(いとう-じゃくちゅう、1716-1800)。男性。名は汝釣、字は景和、別号に斗米庵・米斗翁等。京都・錦小路の青物問屋「桝屋(ますや)」の生まれ。1738年、父没後、4代当主・桝屋(伊藤)源左衛門を襲名した。1751年頃、宝蔵寺に父母の墓を立てる。1752年頃、相国寺の僧・大典顕常より、若冲の居士号を与えられる。大典は若冲を支援した。萬福寺の中国僧・伯珣照浩とも交流した。1755年、40歳で家督を弟・宗巌に譲り、隠居し作画に入る。1758年頃、「動植綵絵」連作着手。1759年、鹿苑寺大書院障壁画を制作する。1764年、金比羅宮奥書院上段の間に描く。1765年、「動植綵絵」「釈迦三尊像」を相国寺に寄進(1770年完了)。宝蔵寺に亡弟の墓を立てた。1773年、萬福寺で道号「革叟」を授かる。1766年、相国寺に寿蔵を建てた。1767年、拓版画「乗輿舟」制作。1768年、『平安人物誌』に3番目に名が載る。1774年、若冲らが奔走し、錦市場の再開が許される。1776年頃、石峰寺五百羅漢の石像を制作を開始する。1788年、天明の大火で家を焼かれた。1790年、大坂・西福寺に襖絵「群鶏図」を描く。1791年(1790年とも)頃より、石峰寺の門前に草庵「斗米(とべい/とまい)庵」を結び、妹・真寂尼と住んだ。斗米翁とも号した。名の由来は、米一斗(14kg)の謝礼で、墨画を描いたためという。一時、相国寺・林光院に住した黄檗宗・売茶翁(月海元昭)が、茶を売り一日の糧を得ていた逸話に倣ったものという。1798年、石峰寺の観音堂に天井画「花卉図」を遺す。1800年、石峰寺に土葬され、相国寺で法要が行われた。84歳。 商いに興味を抱かず、妻帯肉食を拒み、狩野派、中国宋元画、清国・南蘋派に学ぶ。障壁画、画巻、水墨画、木版、拓版画に及び、花鳥、特に鷄の写生に専念する。その画風により「奇想の画家」といわれた。 石峰寺(伏見区)境内に墓がある。相国寺(上京区)には生前墓の寿蔵がある。 ◆仏像 本尊の「阿弥陀如来像」、平安時代作とされる「観音菩薩像」を左脇檀に安置する。一茎二花の蓮を手に持つ。円仁(794-864)ともいう。 ◆文化財 近代、1890年の模写版画集「若冲画譜」、版本。 ◆天井画 本堂の外陣の格天井(ごうてんじょう)に、板絵「花卉図(かきず)」167面(加えて1面は落款)が描かれている。花卉とは観賞用の植物を意味する。伊藤若冲の最晩年の傑作とされる。 近代、1868年、廃仏毀釈により石峰寺の観音堂が破却された。堂の天井に描かれていた若冲の天井画も散逸した。明治期(1868-1912)初期に古美術商の手に渡る。19世紀後半、有力な檀家総代・井上家5代清六が購入し、その後、当寺に寄贈された。その後、本堂の天井画として飾られた。 天井格間は、南北4.8m、東西11.5mになる。南北8段、東西21列の168面ある。東北隅の1面には、若冲の落款と印「斗米翁八十八歳」「若冲居士」(朱文円形)が入る。84歳で亡くなった若冲が88歳としたのは、「四」の数字を忌み、末広がりの「八」としたためという。 正方形の格子面(38cm四方)に、後に加彩されたとみられる群青色の円形型式(円相直径33.6cm)があり、中の板面に色彩で1種の花が精緻に描かれている。円内の斬新な構図は大胆な曲線、折線を用い、独特の配色により描かれている。本来、植物を円内に描く構図は難しいという。若冲は、蕊、葯なども丹念に描き、「草木国土皆悉成仏(そうもく-こくど-しっかい-じょうぶつ、草木・国土のような非情なものも仏性を有して成仏するの意)」の仏教思想に基づき、植物も「いきもの」としてとらえた。本堂内に差し込む自然光の変化に伴い、作品の色合いが微妙に変化する。他方、作品の退色が進む。一部の板地に亀裂もみられる。 花は全体で60種ほどあり、最も多い牡丹(30図)は、当時は「花王」とも呼ばれた。色の違い、一重、千重、「裏牡丹」などと描き分けている。ほかに、菊(家紋)15枚、梅10枚、朝顔6枚、百合6枚、杜若4枚、水仙4枚、蓮4枚、藤4枚なども複数枚描かれている。 入口右手(東)を1列目として、内陣側(北)より入口側(南)に紹介する。東北隅に落款、南へ牡丹、華鬘草(ケマンソウ)、花鳥兜(ハナトリカブト)、日本水仙、牡丹、皐月(サツキ)? 、芭蕉。 2列目、北より、姫芭蕉(ヒメバショウ)、梅、家菊(イエギク)、梅、芙蓉、団扇仙人掌(ウチワサボテン、大型宝剣)、梅、蓮。 3列目、万年青(オモト)、野花菖蒲、牡丹、南天、椿、桐?、立擬宝珠(タチギボウシ)?、肥後椿。 4列目、藤?、牡丹、藤豆(フジマメ)、花鳥兜、日本水仙、鉄砲百合、牡丹、大山蓮華。 5列目、梨、梅、蓮、牡丹、家菊、皐月、梅、山吹八重咲。 6列目、牡丹罌粟(ボタンゲシ)、杜若?、木瓜(ボケ)?、銭葵、桃、沢潟(オモダカ)、石蕗(ツワブキ)、鶏頭(ケイトウ)。 7列目、紫陽花、家菊、藤?、鳳仙花(ホウセンカ)、日本水仙、向日葵、秋海棠(シュウカイドウ)、小手毬(コデマリ)。 8列目、天南星(テンナンショウ)、山百合?、牡丹、檀特(タンドク)、宮城野萩、小手毬?、梅、牡丹。 9列目、瑠璃起こし(ルリオコシ)、牡丹、芙蓉、ぎょ柳梅(ギョリュウバイ)、仙翁花(センノウゲ)、梅、牡丹?、家菊。 10列目、家菊、黄蜀葵(トロロアオイ)、蓮、秋海棠?、牡丹、牡丹、野田藤、杜若?。 11列目、芙蓉、鉄砲百合、美容柳、家菊?、山吹、檀特、大手毬?、朝顔。 12列目、蓮、朝顔、向日葵、総(フサ)アカシア?、家菊、芍薬(シャクヤク)、花海棠(ハナカイドウ)?、立葵(タチアオイ)。 13列目、檜扇(ヒオウギ)?、家菊、家菊、駿河蘭、牡丹、梅、蘇鉄(ソテツ)、牡丹。 14列目、日本水仙、牡丹、鉄線、家菊、河骨(コウホネ)、牡丹、家菊、姫芭蕉。 15列目、牡丹、朝顔?、朝顔、牡丹、鉄線、朝顔、牡丹、鉄砲百合?。 16列目、松本仙翁、牡丹、梅、幣辛夷(シデコブシ)、秋海棠、牡丹、梅、紫苑(シオン)。 17列目、野田藤、下野(シモツケ)?、同定不可、牡丹、仏桑花(ブッソウゲ、ハイビスカス)、牡丹罌粟、家菊、同定不可。 18列目、牡丹、杜若、野萓草(ノカンゾウ)?、牡丹、紫苑、牡丹、家菊、同定不可。 19列目、夾竹桃(キョウチクトウ)、牡丹、芍薬、家菊、大島桜、寒蘭、庚申薔薇、黄蜀葵、 20列目、朝顔、家菊、華鬘草(ケマンソウ)、牡丹、芍薬、徳玉?、薊(アザミ)?、南天。 21列目、牡丹、肥後椿、牡丹、幣辛夷、山百合、杜若、牡丹、鹿子百合(カノコユリ)。(同定は『若冲への招待』参照) 若冲が天井画を描いた例は、ほかに義仲寺(ぎちゅうじ)・翁堂(おきなどう)(大津市)しかない。ここにも「花卉図」15面(12種)が残されている。ただ、この天井画の円外に彩色はない。江戸時代、1856年に翁堂は焼失し、1859年の再建時に天井画が飾られたとみられている。天井画は、石峰寺の観音堂から移されたともいう。翁堂の天井図は信行寺の天井図と関わりがあり、若冲は当初、観音堂に182面(167面+15面)の花卉図を描いたともいう。 *普段は非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、『日本地名大辞典 26 京都府 下巻』、『若冲画譜』、『若冲の花』、『若冲への招待』、『拝観の手引』、『伏見学ことはじめ』 、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |
| |
|