|
|
|
| 城興寺・薬師社 (京都市南区) Joko-ji Temple,Yakushi-sha Shrine |
|
| 城興寺・薬師社 | 城興寺・薬師社 |
 |
 |
   観音堂、右より弘法大師、不動明王、薬師如来、大日如来を安置する。 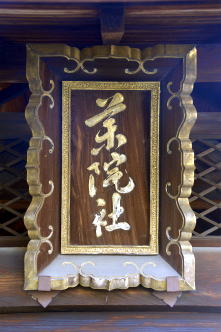 観音堂  「成興寺」とある香炉台  賓頭盧尊者  宝篋印塔  宝篋印塔、梵字  薬院社  薬院社  薬院社   摂社、次郎吉稲荷、唯一の願を叶えるという  イチョウの大木 |
九条烏丸交差点北西に城興寺(じょうこう-じ)はある。かつてこの付近は、平安京の南端にあたる九条大路に面していた。 成興寺ともいう。山号は瑞寶山(ずいほう-ざん)という。 宗派は真言宗泉涌寺派、本尊は千手観音菩薩を安置する。 洛陽三十三所観音巡礼第22番札所。 ◆歴史年表 平安時代後期、1085年、この地には藤原信長の邸宅の一つ九条邸(平安京左京の九条)があった。(『拾芥抄』)。邸内に一堂(九条堂)を建立し丈六の仏像を安置した。また、関白・藤原忠実が伝領し、九条堂(九条院)を営む。堂内に丈六仏を安置し城興院と名づけた。 1113年、忠実の開基により鎮護国家の道場として城興院が創建された。当初は広大な寺域を誇っていた。 1123年、白河法皇(第72代)の院宣により盛大な伽藍供養が行われる。鎮護国家の道場になる。 49世天台座主・最雲親王法親王(1156-1158)が寺領を得た。 1162年、法親王没後、以仁王が寺領を引き継ぐ。(『山槐記』) 1179年、寺領は平氏政権(平清盛)により知行権没収になり、以仁王の乱の遠因の一つとされる。 1185年、平家滅亡後、寺は以仁王の子・真性に受け継がれた。 中世(鎌倉時代-室町時代)、周辺は京外になり、城興寺も次第に衰退する。 室町時代、1399年、室町幕府3代将軍・足利義満は、東は東の洞院大路、西は室町小路、南は九条大路、北は信濃小路に囲まれた土地を僧・良誉に安堵した。(『華頂要略』) 応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失する。一時、衰退した。 15世紀末-16世紀前半、相国寺慶雲院と比叡山不動院の寺域を巡る相論がある。 16世紀(中世末とも)、寺領は比叡山延暦寺不動院の管理下になり、四宗(顕・密・禅・律)兼学の道場になる。 永正年間(1504-1520)、土豪・石井氏、坊城俊名などにより寺領が度々侵される「違乱」があり、幕府はその停止を命じる。不動院に知行が安堵された。 江戸時代、洛陽三十三所観音霊場めぐりが盛んになり、札所として賑わう。「成興寺」の名が記されている。(『都名所図会』) 文久年間(1861-1864)、薬院社はこの地に移転してきたともいう。 1877年、施薬院稲荷は陀枳尼天堂に合祀された。 現代、1983年/1984年、発掘調査により、室町時代後期の城興寺城の掘跡が発見される。 2005年、「平成洛陽三十三所観音」が復興された。 ◆藤原信長 平安時代後期の公卿・藤原信長(ふじわら-の-のぶなが、1022-1094)。男性。九条殿、城興寺殿、九条太政大臣。父・関白・藤原教通(のりみち)、母・藤原公任(きんとう)の娘の3男。1041年、従三位。22歳で参議になり、大納言、内大臣を歴任した。1080年/1088年、従一位太政大臣になった。父から関白職を継ごうとし、父は兄・頼通の子・師実(もろざね)に譲った。73歳。 平安京左京の九条に邸宅があり、邸内に一堂(九条堂、後の城興寺)を建立し丈六の仏像を安置した。 ◆藤原忠実 平安時代後期の公卿・藤原忠実(ふじわら-の-ただざね、1078/1079-1162)。男性。通称は知足院殿、富家(ふけ)殿、法名は円理。京都の生まれ。父・関白・藤原師通、母・藤原全子(右大臣藤原俊家の娘)の嫡男。祖父・藤原師実の養子。1088年、元服、1091年、非参議従三位で公卿に列し、1092年、権中納言、1097年、権大納言になる。1099年、父の死後、祖父・師実の養子になり内覧・藤原氏長者になる。1100年、右大臣、1105年、第73代・堀河天皇の関白に就く。1107年、第74代・鳥羽天皇の即位により摂政、1112年、太政大臣に任じられる。1113年、鳥羽天皇元服により関白になる。娘・泰子(高陽院)の鳥羽天皇入内問題で白河法皇(第72代)と確執があり、1120年、内覧を停められ、1121年、関白を辞し嫡子・忠通が代り、宇治に隠遁した。1129年、法皇の死、鳥羽院政開始により復した。その後、次子・頼長を内覧・氏長者とし忠通と対立した。1133年、泰子を鳥羽上皇妃として入内させた。1140年、准三宮になる。出家した。1156年、保元の乱で頼長の敗死後、忠通の計らいで流罪を免れ知足院に籠居した。京都に没した。日記『殿暦 (でんりゃく) 』、談話筆記『中外抄』など。85歳。 長子・忠通よりも次子・頼長を愛し、兄弟対立が保元の乱の一因になった。有職故実に通じた。 ◆最雲法親王 平安時代後期の皇族、僧・最雲法親王(さいうん-ほっしんのう、1104-1162)。男性。父・第73代・堀河天皇。比叡山に上り、天台座主仁豪に師事し出家・受戒、仁実僧正から顕教・密教を学んだ。1156年、天台寺座主、1158年、僧正、親王宣下を受け法親王となる。同年座主を辞し山房に閑居した。59歳。 ◆以仁王 平安時代後期の皇族・以仁王(もちひとおう、1151-1180)。男性。通称は高倉宮、三条宮。京都の生まれ。父・第77代・後白河天皇、母・藤原成子の第3(第2とも)皇子。天台座主・最雲法親王の弟子になるが、1162年、師没後還俗する。1165年、八条院暲子内親王の猶子となる。皇位継承争いで、異母弟憲仁親王(第80代・高倉天皇)生母・平滋子により阻まれた。父と確執もあり親王になれなかった。1179年、平氏の後白河法皇幽閉に伴い、王の寺領は没収された。1180年、源頼政の勧めにより平清盛・平家追討の令旨(りょうじ)を発した。だが、最勝親王と称した挙兵計画が漏れ、皇族籍剥奪、土佐配流と決まる。検非違使の王の館襲撃から脱し、園城寺から興福寺を頼り奈良へ向かう。途中、綺田付近で追手の藤原景高・藤原忠綱らにより討たれたという。30歳。 ◆真性 平安時代後期-鎌倉時代前期の僧・真性(しんしょう、1167-1230)。男性。父・第77代・後白河天皇。1183年、出家、比叡山慈円僧正につく。第82代・後鳥羽天皇、第83代・土御門天皇、第84代・順徳天皇3代の護持僧となる。1203年、67世・天台座主、1204年、大僧正。四天王寺別当。64歳。 ◆藤原冬嗣 奈良時代-平安時代前期の公卿・藤原冬嗣(ふじわら-の-ふゆつぐ、775-826)。男性。通称は閑院大臣。北家・右大臣・藤原内麻呂の2男、母は飛鳥部奈止麻呂の娘/百済永継(くだら-の-えいけい)。806年、従五位下、第52代・嵯峨天皇の信任篤く、810年、平城太上天皇の変(薬子の変)を契機として、四位下で新設の初代・蔵人頭(くろうどのとう)に任じられる。式部大輔を経て、811年、参議になった。814年、従三位、自邸の閑院(平安左京三条二坊)に嵯峨天皇を迎え詩宴を催している。816年、権中納言、819年、正三位、大納言、821年、右大臣、825年、正二位で左大臣になった。「弘仁格式(きゃくしき)」「内裏式」を撰進し、漢詩は『文華秀麗集』、詩は『凌雲集』などに入る。52歳。 没後に正一位、太政大臣を追贈された。嵯峨天皇、第53代・淳和天皇の信を得た。娘・順子は第54代・仁明天皇の妃になり、道康親王(第55代・文徳天皇)を産む。次男・良房は嵯峨天皇皇女・潔姫(きよひめ)を妻に迎え、皇室との関係を深めた。藤原氏による摂関政治、北家繁栄の基礎を築く。一族子弟のための勧学院、施薬院、氏寺・興福寺に南円堂を建てた。 墓は宇治陵(宇治市)に包括されている。同域内の夫婦塚(赤塚)は冬嗣、妻・藤原美都子の夫婦墓ともいう。 ◆仏像 ◈本尊の秘仏「千手観世音菩薩」は平安時代の円仁(794-864)作という。平安時代前期、838年、円仁が遣唐使の一員として入唐した際に、無事の帰朝を念じ、船中で造作した観音ともいう。 江戸時代から観音霊場として有名で、「成興寺は九条烏丸にあり、本尊観音は慈光大師の作なり」と記載されている。(『都名所図会』、1780) ◈「薬師如来」は、弘法大師空海(774-835)作という。平安時代前期、829年、全国に大疫病流行した。第53代・淳和天皇が祈祷を命じ、大師勅を受け尊像を刻んだ。祈祷し疫病が止んだことに因むともいう。 ◈ほかに、平安時代末期の「不動明王」、「大日如来」がある。 ◆建築 本堂の観音堂、庫裏、寺内社として薬院社(稲荷社)がある。 ◆文化財 ◈紙本墨書「城興寺古伽藍図」1幅は、江戸時代(17世紀)作になる。108.5×54㎝。 ◈「薬院社神鏡」1面は、室町時代前期、1408年作になる。施薬院稲荷に寄進された。直径29.8㎝。 ◆城興寺 かつての城興寺境内は、東は烏丸通東、西は室町小路の東、北は信濃小路南、南は九条大路北で囲まれた方形だった。現在の東寺(南区)に匹敵するほどの寺域を有した。 南門が正門であり、方生池、楼門の仁王門、金堂に薬師如来、講堂に本尊・千手観音を安置し、これらは直線状に建てられていた。ほか、祖師堂(御影堂)、土地堂(薬院社)、庫裡、書院、多宝塔、鐘楼、僧坊などが建てられていた。(「城興寺古伽藍図」) いずれも基壇があり、詰組、弓欄間、裳階など禅宗の特色があった。 ◆薬院社 境内に祀られている薬院社は、祭神に茶吉尼天を祀る。かつて施薬院(せやくいん/やくいん)稲荷と呼ばれた。東九条の鎮守神・産土神であり、町内鎮守、元寺鎮守、祟り示現稲荷であり、蛇伝承も残る。家内安全、病気平癒の信仰がある。 平安時代、境内北西200m(東久九条中殿田町)に施薬院があり、北100m(上殿田町)に施薬院御倉(みくら)が置かれていた。 施薬院は、奈良時代、730年に、光明皇后の発願により、悲田院とともに当初は大和に創設された。病人、孤児の保護・治療・施薬を行ったという。平安京遷都後、平安時代初期に、左大臣・藤原冬嗣が私財を投じ、自らの土地に施薬院を開設した。以後、摂関家藤原氏が維持管理を行う。 鎌倉時代初期、施薬院は他所へ移転し、御倉跡の薬院の森には、施薬院稲荷の祠のみが残ったという。以後、周辺の東九条の鎮守社になる。 また、薬院社は、江戸時代後期、文久年間(1861-1864)、この地に移転してきたという。かつては薬師院の鎮守社だったという。 近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈、また、1872年の辻堂廃止令により、1877年に稲荷が廃絶になる。1878年に地域の農民により、城興寺境内の陀枳尼天堂に合祀されたという。夫婦円満の信仰がある。 ◆城興寺・城興寺城遺跡 現代、1983年、1984年に、旧地境内の発掘調査により、室町時代後期の城興寺城の掘跡が発見される。堀は、現在の境内の東、烏丸通に南北に確認されている。堀の幅は5.8mから7m以上、二段掘りで深さは1.5mあった。堀跡からは漆器、椀、土器、下駄などの生活用品も見つかっている。 ◆おみくじ 人生や恋愛についての「小指みくじ」がある。 ◆修行体験 写仏会(予約により毎日9:00-16:30・19:30-21:00)、写経会(毎月第2日曜日、10:00-12:00、本堂)。 ◆年間行事 修正会 (1月1日-3日)、どんと祭(1月15日) 、彼岸会(3月21日) 、施餓鬼法要(8月17日) 、彼岸会(9月25日) 、お火焚祭(11月3日)。 写仏(毎日9:30-16:30)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』、『京都・山城寺院神社大事典』、『増補版 京都の医史跡探訪』、『秘密の京都』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』 、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |
| |
|