|
|
|
| 松林院〔本圀寺〕 (京都市下京区) Shorin-in Temple |
|
| 松林院〔本圀寺〕 | 松林院〔本圀寺〕 |
 |
 |
   題目碑    宇賀徳正神  宇賀徳正神  宇賀徳正神  淘洗閣  淘洗閣       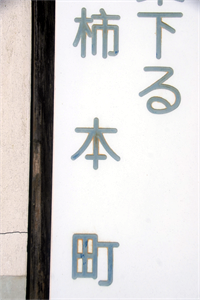 【参照】「柿本町」の町名 |
猪熊通五条下ルに松林院(しょうりん-いん)はある。山号は天霊山(てんれい-ざん)という。 日蓮宗、本尊形態は「一塔両尊四士」になる。3種の御首題(しゅだい)、文庫本様のBUNKOおまもり が授与される。 ◆歴史年表 年代不詳、日行により、当初は鎌倉浮田に天霊寺と号して創建された。 南北朝時代、1345年、日行の兄弟子・日静により、大本山・本国寺が京都六条堀川に移転する際に、法性寺、勧持院(西大坊)、持珠院(北大坊)、戒善院(南大坊)の4カ寺と共に随行した。 以後、開山の院号に因み「天霊山松林院」と改称する。開基は日慶であり、本山塔頭の筆頭とし、「東大坊」と称された。 その後、度々兵火に焼かれる。 近代、大正期(1912-1926)末、現在の本堂が建てられた。 現代、1971年、大本山本圀寺が京都山科に移転後も現在地に残る。 ◆日行 鎌倉時代?の日蓮宗の僧・日行(にちぎょう、?-?)。詳細不明。男性。妙音阿闍梨松林院日行、妙音坊日行。日朗(1245-1320)高弟、九老僧の一人に数えられた。鎌倉浮田に、天霊寺(松林院の前身)を創建した。 ◆日静 鎌倉時代後期-南北朝時代の日蓮宗の僧・日静(にちじょう、1298-1369)。男性。俗姓は上杉、諱は日乗、字は豊龍、号は妙竜院。駿河国(静岡県)の生まれ。父・上杉頼重、母・足利氏の娘。将軍・足利尊氏の叔父にあたるともいう。駿河国・本覚寺の治部公日位、鎌倉・本勝寺の摩訶一房日印に師事した。日印は死に臨み本勝寺を日陣に譲る。1328年、日印の没後、越後国・三条本成寺を継ぐ。1338年、日印弟子・日祐に招かれて上洛する。1345年、足利家の外護を受け本勝寺を六条に移し、本国寺(後の本圀寺)に改称し6世に就く。尊氏の帰依、公武の外護により寺運隆盛になる。1348年、北朝第2代・光明天皇より三位僧都に任命された。天皇から日蓮正嫡の綸旨を受ける。著『六条要文』。72歳。 日蓮宗の2大門流・六条門流の祖。弟子に日伝、日陣がいる。 墓は法華寺(東山区)にある。 ◆日慶 室町時代前期-後期の日蓮宗の僧・日慶(にちけい、1397-1478)。男性。下総国(千葉県・茨城県)の生れ。日像の流れを汲む妙顕寺・月明の門下になる。月明(妙顕寺5世)と対立した日存・日道・日隆と共に妙顕寺を退出した。綾小路五条に草庵を結ぶ。三師につき八品勝劣義の布教に加わる。後、妙蓮寺を建立した。日応を招請し後見役になる。「本山再興本願主」と称された。81歳。 ◆品川亮 現代の日本画家・品川亮(しながわ-りょう、1987-)。男性。大阪府の生まれ。2014年、京都造形芸術大学美術工芸学科日本画コースを卒業する。2015年、同大学大学院芸術表現専攻ペインティング領域在籍中に、翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都の客室を飾る襖絵の制作で注目を集める。同年、「京展」館長奨励賞を受賞した。2016年、同大学大学院を修了する。その後、日本画を学びながら、イタリア滞在、スイス留学などした。 岩絵具・箔などの伝統的な日本画の素材を用い、やまと絵・琳派・狩野派などの様式も取り入れる。日本、ソウル、台北、スイス・バーゼル、ニューヨークなどで作品発表してきた。主な個展に、「SHINAGAWA RYO solo exhibition」(京都芸術的中心、2015)など。 ◆本尊・仏像 ◈本堂の本尊の形態を「一塔両尊四士」といい、釈迦如来が法華経を説く様を現している。 向かって中央左に「釈迦如来」、右に宝塔に「多宝如来」、釈迦如来の左に「浄行菩薩」、「安立行菩薩」、多宝如来の右に「上行菩薩」、「無辺行菩薩」、下に「日蓮聖人」が安置されている。 ◈左右端に、四天王の「持国天」、「広目天」、「増長天」、「多聞天(毘沙門天)」を祀る。 ◈現代、2017年より、「慈母観音」を祀る。 ◆鎮守社 「宇賀徳正神」は境内の鎮守社であり、白蛇の神が祀られている。幸福・利益・智慧・財力、当院では、子育ての神として伝わる。 祀られた経緯がある。 近代、明治期(1868-1912)に、寺の周辺で原因不明の病・不慮の事故で多くの子どもらが亡くなったという。地域全体が悲しみに暮れた。 第47世行学院日隆上人は、この地を守る神を宇賀徳正神とし、境内に祀った。その後、亡くなる子はいなくなったという。 ◆庭園 石庭(3.5m×2m)は、白砂に砂紋が引かれ、苔地、石組で構成されている。 ◆障壁画 本堂障壁画「蓮池図」8面(3.5畳)は、現代の日本画家・品川亮の筆による。 現代、2022年の宗祖日蓮聖人御降誕800年慶讃事業として制作が始められた。天袋の「松林図(仮)」とともに、2023年に完成予定になっている。非公開。 ◆年間行事 新年の挨拶参り(1月3日-16日 )、星祭り(2月3日)、春季彼岸会(3月春分の日 )、棚行(8月1日-16日)、 盂蘭盆施餓鬼会(8月上旬の日曜日)、 お会式(日蓮の報恩法要)(10月13日に近い日曜日か祝日)。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「松林院」、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |