|
|
|
| 勝円寺 (勝圓寺) (京都市下京区) Shoen-ji Temple |
|
| 勝円寺 | 勝円寺 |
 |
 |
 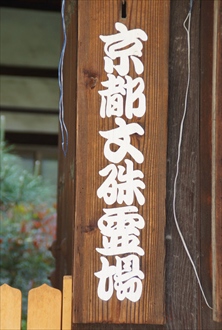    本堂  本堂扁額  本堂内陣  本堂、阿弥陀如来坐像   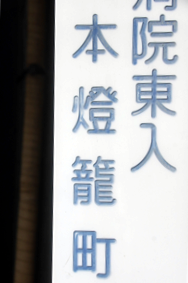 【参照】「本燈籠町」(下京区)の町名 |
富永町の勝円寺(しょうえん-じ、勝圓寺)は山号を大悲山という。 浄土宗。本尊は阿弥陀如来。 京都文殊霊場(知恵の寺)めぐりの第9番。 ◆歴史年表 室町時代、1504年、安誉が開山になる。当初は現在地の南西、東洞院五条北(下京区燈籠町)にあった。(寺伝)。円派仏師・勝円の作という阿弥陀如来を本尊とし、寺号も勝円の名に因むという。 第105代・後奈良醐天皇(1497-1557)の帰依により、勅額が与えられたという。(寺伝) 安土・桃山時代、1587年/1584年、豊臣秀吉の命により現在地に移った。空誉は塔頭・隆彦院(りゅうげん-いん)を創建する。達誉は塔頭・普恩院(ふおんいん)を創建した。 江戸時代、1621年、信誉が塔頭・良松庵(りょうしょうあん)を創建した。最盛期には塔頭・4院、境内3000坪(9917㎡)を有した。 1788年、天明の大火により焼失する。塔頭・隆彦院、普恩院、良松庵が類焼した。 1789年、隆彦院、普恩院、良松庵が再建される。 1796年、勝円寺は再建された。 1850年、勝円寺は類焼した。その後、再建される。 近代、1869年、普恩院の地を借地として下京十二番組小学校(永松小学校)が開校した。 1909年、隆彦院が東山に移転する。 ◆安誉 室町時代後期の浄土宗の僧・安誉(?-? )。詳細不明。1504年、勝円寺の開山になる。 ◆勝円 室町時代の仏師・勝円(しょうえん、?-?)。詳細不明。円派8代・長俊の弟子。勝円寺の寺号は勝円により名付けられた。 ◆武川 幸順 江戸時代中期の医師・武川 幸順(たけかわ -こうじゅん、1725-1780)。男性。字は建徳(けんとく)、号は南山。京都の生まれ。父・小児科医・幸哲(元順)。小児科の名医として知られる。堀景山に入門した。1754年、宣長は武川幸順(室町通綾小路北上ル)に入門し、堀景山宅より移る。京都遊学中の本居宣長(もとおり-のりなが)に医学を教えた。明和年間(1764-1772)、英仁親王(第118代・後桃園天皇)の御殿医になり、法橋、後に法眼になった。56歳。 宣長が『馭戎慨言』を執筆した際に、摂政・九条尚実に献上を試み、半ばで死去した。その子が遺志を継いだ。 墓は勝円寺(下京区)にある。 ◆仏像 ◈ 「阿弥陀如来坐像」(2m)を安置している。室町時代後期、1504年頃、鎌倉時代の円派仏師・勝円?の作という。第二次世界大戦の強制疎開に伴い、本山の知恩院に人力で遷したという。 ◈ 「文殊菩薩」は、かつて掛軸を祀っていた。その後、檀家・村田九郎兵衛が家に祀っていたものを寺に寄進している。文殊菩薩は象に乗らず、ほかに安置されている。象(1m)には人が坐ることができる。 ◆塔頭 塔頭は良寿院が創建早くに廃寺になり、本寺に合併になった。近代、1909年、隆彦院は東山に移転している。現在は、普恩院、良松庵が残る。 ◆墓 墓苑「无玄来苑」に、医師・武川幸順、幸順の父・武川幸哲(1689-1757)夫妻、ほかに武川南海、武川南汀などの墓がある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 勝円寺縁起、『京都市の地名』『京都大事典』『京の福神めぐり』 、ウェブサイト「本居宣長記念館」、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |
| |
|