|
|
|
| 実光院 (京都市左京区) Jikko-in Temple |
|
| 実光院 | 実光院 |
 |
 |
 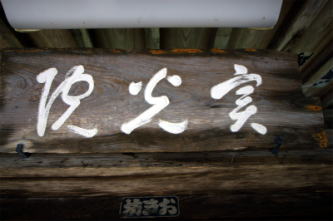           庭園  契心園       不断桜   不断桜と紅葉  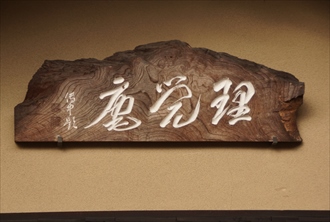 茶室理覚庵  理覚庵  編鐘    シャクナゲ   イカリソウ  ヒカゲツツジ  カンアオイ   ユキモチソウ    スミレ  エイザンスミレ  【参照】借景になっている金毘羅山、小塩山  【参照】穴太積の石垣    【参照】寺の旧地、大原稜  【参照】近くを流れる律川  【参照】律川に架かる未明橋 |
大原の地、律川の流れ近くにある実光院(じっこう-いん)は、天台宗魚山大原寺(ぎょざん-だいげん-じ)下院の本堂、勝林院の子院になっている。魚山の山号名は、声明(しょうみょう)の聖地・中国山東省魚山の地名に因む。
天台宗、本尊は地蔵菩薩坐像を安置する。 京都洛北・森と水の会。 ◆歴史年表 平安時代中期、1013年、円仁9代目の弟子・寂源(?-1024)が建立し、円仁(794-864)を開祖とした。勝林院の子院として学僧が住み、円仁が伝えた声明を継承するために開かれた。当初、現在の大原稜(後鳥羽天皇、順徳天皇陵)の地にあった。 後、良忍(1073?-1132)の開いた来迎院とともに、天台声明(魚山声明)の中心地となり、二院を本堂として魚山大原寺といわれた。 近代、1919年、勝林寺の僧院だった子院・普賢院(ふげんいん)、理覚院(りかくいん)を併合し、現在地の普賢院跡地に移転している。 1921年、客殿が建てられた。 ◆円仁 平安時代前期の天台宗の僧・円仁(えんにん、794-864)。男性。姓は壬生、名は円仁、諡号は慈覚大師。下野国(栃木県)の生まれ。9歳で大慈寺の広智に学び、808年、15歳で唐より帰国した比叡山の最澄に師事、その最期まで14年間仕えた。815年、東大寺で具足戒を受ける。比叡山で12年の籠山行に入る。5年後、法隆寺、四天王寺での夏安吾(げあんご)講師、東北への教化を行う。一時心身衰え、829年、横川に隠棲した。苦修練行を続け、夢中に霊薬を得て回復し、『法華経』書写を始め、小塔(如法堂)を建て写経を納めたという。838年、最後の遣唐使として渡り、9年間学ぶ。847年、帰国、仏典、金剛界曼荼羅など多数を持ち帰った。新羅声明を天台声明として取り入れ、その祖になる。848年、比叡山に戻り、円珍に密教を教えた。854年、第3世・天台座主に就く。862年、東塔に天台密教の根本道場・総持院を建立した。東京・瀧泉寺、山形・立石寺(円仁の遺体納葬の入定窟がある)、松島・瑞巌寺など多くの寺を開いた。『顕揚大戒論』ほか、唐滞在記である『入唐求法巡礼行記』(全4巻)を著す。没後、日本初の大師号(慈覚大師)を贈られた。入唐八家(最澄・空海など)の一人。70歳。 円仁は、法華経と密教は同等であり、円密は一致するとし、天台密教(三部密教、胎蔵部、金剛部、蘇悉地部)を確立した。また、浄土教を一乗思想として天台宗に取り入れた。 ◆寂源 平安時代中期-後期の天台宗の僧・寂源(じゃくげん、965/960-1024)。男性。俗名は時叙。大原入道少将。父・左大臣・源雅信、母・源穆子。986年、右少将の時に出家し大原入道少将と呼ばれた。比叡山に登り覚忍に師事した。990年、両部灌頂を受ける。皇慶の弟子になり、1012年、伝燈大法師位の時、胎蔵界、金剛界の両部灌頂を受ける。常行三昧を修した。1013年、大原に勝林院を創設した。藤原道長、頼通、赤染衛門らの信仰を集めた。 臨終に際し、正念し往生したという。55歳?。 ◆仏像 本尊は彩色の地蔵菩薩坐像、脇侍は不動明王、毘沙門天像を安置する。 ◆建築 客殿は、近代、1921年に建てられた。庫裏の一部は、江戸時代後期のものを移築している。 ◆茶室 茶室「理覚庵」は、現代、1975年に建てられた。ほとんどの資材は実光院領の山林から調達された。 ◆庭園 ◈ 客殿南の庭「契心園(けいしん-えん)」(旧普賢院庭園)は、江戸時代後期に作庭された。池泉観賞式の庭園であり、自然の傾斜地を背にしている。 心字の池には、左手に律川より引かれた水が滝を作る。滝口近くに蓬莱石組があり、築山の五葉松は枝を広げ舞い降りた鶴を表す。池中の岩島は亀を表し、鶴と亀で神仙思想を意味する。かつて亀島には橋が架けられ、現在は飛び石がある。築山には石段が石造の五重塔に導いている。池の手前を俗世・現世(此岸)とし、対岸は極楽浄土・蓬莱山の浄土(彼岸)に見立てている。 築山にあるシャクナゲ、紅葉の庭でも知られている。 ◈ 客殿西には、池泉回遊式庭園「理覚院(りがく-いん)」がある。理覚院の廃寺後、荒廃していた寺地を歴代の住職により作庭した。 中央には「ひょうたん池」が造られ、金毘羅山・小塩山を借景に取り入れている。露地には飛び石、蹲踞なども配されている。 ◆文化財 ◈客殿欄間には、江戸時代中期の狩野派による「三十六歌仙画像」がある。 ◈楽器「石琴」は声明に関する。 ◈「編鐘」は十六音階を奏でる。中国の雅楽で用いられていた。周の時代(前11世紀)にはすでに作られていたという。音律の基準音を定める楽器としても使われ、戦国時代(前5-3世紀)には、16の鐘を列ねた現在の形になった。現代、1983年、南条一雄により復元され、寄贈された。 ◆声明 声明(しょうみょう)は、寺院の法要儀式の中で行われる仏教の儀式音楽で、経典などに独特の節をつけて僧侶により唱和される。その内容は、仏、菩薩、神々を賛美するもので、後に、声明を唱えることが修業となり、また、声明成仏として行われるようになった。 声明は、仏教の起こりとともにインドで始まり、梵唄といわれ、中国に伝えられた。さらに、奈良時代から平安時代に日本にも伝えられた。 大原の天台声明(魚山声明)は、平安時代、慈覚大師円仁により、中国よりもたらされた。後の平安時代後期、円仁の9代目の弟子・寂源により建立された勝林院は、円仁が伝えた声明を継承するために開かれている。さらに、聖応大師良忍が来迎院を建立した。声明は統一され、ニ院を本堂として魚山大原寺と総称され、声明の根本道場として今日まで継承されている。現在でも、天台声明、真言声明が伝えられている。 声明の基本になる音階は5つある。節回しは「塩梅(えんばい)」といわれ、音階間を連続して上下する。この塩梅は小節の源流という。声明は、仏教にとどまらず、今様、平家琵琶、謡曲、浄瑠璃、小唄、長唄、浪花節、民謡、演歌などにも影響を与えた。 ◆不断桜 境内の「不断桜(ふだん-ざくら)」は、初秋より春(11月-4月)まで花を咲かせる珍しい品種として知られる。秋(11月)には紅葉と桜の2つを同時に愛でることができる。 ◆修正会 修正会(1月2日)では、ササラと棒を持った独特の「三十三度法要」とも呼ばれ、無病息災を祈り「三十三度」と声を上げ、跳ねる。 ◆花暦 四季折々の多くの草木花が植えられている。 春(シャクナゲ、ヒカゲツツジ、ホンキリシマツツジ、モクレン、ニワザクラ、、ハナズオウ、アケビ、ハナカイドウ、ワサビシジミバナ、リキュウバイ、バイモ、ホウチャクソウ、エイザンスミレ、イカリソウ、カタクリ)、夏(コウホネ、ヤマアジサイ、キョウカノコ)、秋(ホトトギス、シュウカイドウ)、冬(ツバキ、バイカオウレン)、ほかカンアオイなどがある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都 四季の庭園』、『古都歩きの愉しみ』、『日本の名僧』、『週刊 日本の仏像 第14号 三千院 国宝阿弥陀三尊と大原』、『京のみどり №102』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |