|
|
|
| 退耕庵 〔東福寺〕 (京都市東山区) Taiko-an Temple |
|
| 退耕庵 | 退耕庵 |
 |
 |
   戊辰役殉難士菩提所の碑が門前にある。  地蔵堂 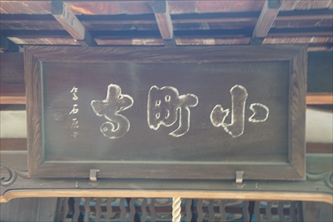 地蔵堂   客殿  小野小町百歳井  「小野小町百歳井」の碑  第56、57代内閣総理大臣・岸信介(1896- 1987)の手植えという槙。 |
東福寺塔頭の一つ退耕庵(たいこう-あん)の門脇には、「戊辰役殉難士菩提所」の碑が立つ。絶世の美女と謳われた平安時代の女性歌人で六歌仙・三十六歌仙の一人、小野小町のゆかりの寺とされ小町寺とも呼ばれる。 臨済宗東福寺派、本尊は千手観音。 洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第42番札所、札所本尊は玉章(たまずさ)地蔵。 玉章地蔵は悪縁断ち、良縁結びの信仰がある。 ◆歴史年表 南北朝時代、1346年、東福寺43世・性海霊見(しょうかい-れいけん)により、その退隠所として創建された。当初は現在地の東(現在の海蔵院の東)にあった。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により罹災し、その後、衰微する。 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)/1599年、当庵11世・安国寺恵瓊(あんこくじ-えけい)が再興した。 江戸時代、寛文年間(1661-1673)、玉章地蔵は第112代・霊元天皇の命により、僧・宝山が洛外・六地蔵以外の48か寺の地蔵尊を選んだ洛陽四十八願所の霊場のひとつになる。 1868年、鳥羽・伏見の戦いで長州藩本陣になる。 近代、1875年、小野寺の廃寺にともない玉章地蔵、扁額、井筒などが当寺に遷された。 ◆性海 霊見 南北朝時代の臨済宗の僧・性海 霊見(しょうかい-れいけん、?-1396)。男性。俗姓は橘、号は不還子、昨夢。信濃(長野県)の生まれ。1343年、元に渡り、帰国後、南禅寺・虎関師錬に師事、その法を嗣ぐ。足利義満、義持の帰依を受ける。京都・三聖寺、東福寺43世、天竜寺、南禅寺住持を歴任。1346年、東福寺・退耕庵に退隠した。著『性海霊見遺稿』。 ◆安国寺 恵瓊 安土・桃山時代の僧・安国寺 恵瓊(あんこくじ-えけい、?-1600)。男性。恵瓊は法諱、道号は瑶甫(ようほ)、号は一任斎・正慶、俗姓は武田、幼名は竹若丸。安芸国(広島県)の生まれ。父・守護武田伸重。4歳の時、一族が毛利一族により滅亡し、竹若丸は銀山城より脱出し、安芸国・安国寺に逃げた。1553年、安国寺で東福寺塔頭・退耕庵主・竺雲恵心(じくうん-えしん)に師事した。京都に上り退耕庵などに住した。1569年、安国寺の住持になる。使僧(外交顧問)として毛利氏と京都の調停に当たる。1573年、足利義昭と織田信長の争いでは、毛利輝元の依頼で調停のため上洛した。1582年、信長と毛利の争いで、豊臣秀吉の備中高松城攻めで双方の講和を結ぶ。その後、秀吉の使僧として四国平定により、1585年、伊予国に所領を与えられ僧でありながら大名になる。文禄・慶長の役(1592-1593・1597-1598)にも加わる。石田三成に与し、毛利家内の吉川広家と対立した。1598年、東福寺224世・住持、1599年、東福寺退耕庵主になる。1600年、南禅寺住持、建仁寺再興に際して、住持をしていた安国寺方丈、東福寺仏殿を移し、それぞれ方丈と仏殿にあてた。関ヶ原の戦では毛利家に与し、小早川秀秋の寝返りという内部分裂もあり西軍が敗北した。京都で捕えられ六条河原で斬首、三条大橋に晒された。五条橋上の腰輿の中で切腹したともいう。 多くの塔堂伽藍の修築を行った。安芸・安国寺、備後・安国寺、厳島・大経堂、東福寺、退耕庵、建仁寺の方丈再建などに尽力した。 首は、建仁寺の僧が持ち帰り、建仁寺に葬ったという。墓は建仁寺の方丈裏にある。 ◆小野 小町 平安時代前期の歌人・小野 小町(おのの-こまち、?-?)。詳細不明。女性。小野氏の出という。出羽国(山形県・秋田県)の郡司良真(よしざね)・当澄(まさずみ)・常澄・篁(たかむら)・小野滝雄・藤原常嗣(つねつぐ)・洛北・市原の小野良実の娘、美材(よしき)・好古(よしふる)らの従妹、篁の孫娘などともいう。小町とは禁中局の名称とされ、本名は小野比右姫ともいう。采女(うねめ)とも、第54代・仁明天皇、第55代・文徳天皇の更衣(こうい)、氏女(うじめ)、中(ちゅうろう)女房ともいう。文徳・清和・陽成年間(850-884)、承和・貞観年間中頃 (834-868頃) に活動した。文屋康秀、凡河内躬恒、在原業平、安倍清行、小野貞樹、僧遍昭らとの歌の贈答がある。恋の歌に特徴あり、漢詩の表現に通じた。『古今集』以下の勅撰集に 60首余入集、『三十六人集』の一つ後人撰家集『小町集』がある。絶世の美女として歌舞伎、義太夫、謡曲など「小町物」の題材になった。六歌仙・三十六歌仙の一人。 ◆地蔵 地蔵堂の地蔵菩薩像は「玉章(たまずさ)地蔵」、「ふみはり地蔵」ともいわれている。 かつて、東山の渋谷峠の小町寺にあった。近代、1875年、当寺に遷された。右手に錫状、左手に宝珠を載せる。石造蓮華座に結跏趺坐する。小野小町作ともいう。良縁を結び、悪縁を絶つとの信仰を集める。像高2m。塑像。 美貌の誉れ高かったという小町には、数多くの艶書(恋文)が送られてきた。老いた小町は自ら像を立て、これらを像内に納めたという。また、恋文を張り像を造ったとされ、地蔵は、除災与楽の信仰を集めた。 後世、像の後ろを破り艶書を取り出した者があったという。腹内には石の五輪が納められ、「慈眼大姉」の銘があったという。北政所の文官・右筆(祐筆)だった小野於津宇(小通)(おの-の-おつう)は、小町の苗孫にあたり、この破損したところを自らの手で張り直し、彩色したという。(『花洛名勝図会』巻3) ◆木像・仏像 地蔵堂堂内には、小野小町作という乾漆の「小町百歳像」も安置されている。世の無常を悟り、自ら作ったといわれている。 脇壇に平安時代作の「薬師瑠璃光如来坐像」、「十一面観音立像」を安置している。 ◆小野寺 江戸時代、東山・渋谷街道(しぶたにかいどう、渋谷越、苦集滅道[くずめち] )に、小町寺という小野小町ゆかりの寺があった。平安時代からあったともいう。 江戸時代には、洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第42番札所になり、札所本尊は玉章地蔵とされた。 近代、1875年、廃寺になり、本尊の玉章地蔵、烏石葛辰(うせき かつしん)筆の扁額「小野寺」、小町像、井筒などが当庵に遷されたという。 ◆建築 ◈「客殿」(京都府指定文化財)は、安土・桃山時代、1599年に建てられている。 ◈現在の「書院」は旧本堂という。 ◆茶室 書院の茶室「作夢軒(さくむ-けん)」は、恵瓊によって建てられた。茶室には、上に「忍び天井」、隣に「伏侍(ふせざむらい)の間」などが隠されている。 豊臣秀吉の没後、茶室では、恵瓊、豊臣政権の五奉行の一人・石田三成(1560-1600)、五大老の一人・宇喜多秀家(1572-1655)らが、関ヶ原の戦い、徳川討伐の謀議を行ったという。 ◆鳥羽・伏見の戦い 江戸時代末、1868年の鳥羽・伏見の戦いで、東福寺に長州藩の陣が置かれた。当庵にも長州藩の屯所が置かれた。 引き続く、戊辰戦争の犠牲者48人が境内に葬られた。戊辰勤皇殿には位牌が祀られ、門前脇に「戊辰役殉難士菩提所」の碑が立つ。防長殉難者の菩提所になっている。 ◆庭園 庭園は、枯山水庭園の南庭と、池泉式庭園睡蓮(6、7月)が咲く北庭、坪庭がある。 南庭の「真隠庭」は、性海霊見の作庭という。スギゴケの苔庭になる。樹齢300年という霧島ツツジの巨木は、4月末に真紅の花をつける。 北庭は、泉観賞式庭園であり、慶長年間(1596-1615)の作庭という。その後、荒廃し、1965年、1972年に修復が行われている。 坪庭は、四方の縁が竹を敷き詰めている。小石を敷いた長方形の庭面に、長方形、円形、景石、蹲踞が置かれている。 ◆文化財 ◈絹本著色「性海和尚像 自賛」1幅(重文)、南北朝時代、1379年作。 ◈紙本墨書「永明智覚寿禅師垂誠」2幅(重文)、性海筆、南北朝時代作、東京国立博物館。 ◈紙本墨書「聖一国師忌斎幹縁流」1幅(重文)、性海筆、南北朝時代、1379年作作。 ◆井戸 境内には「小野小町百歳井」がある。小町は、井戸に映ったという自らの姿を見て、「おもかげの かわらでとしの つもれかし たとえいのちに かぎりあるとも」と詠んだという。 ただ、歌は後世、江戸時代の作ともいわれている。 *普段は非公開、内部、庭園などは写真撮影禁止。 *年間行事・は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼京都 18 東福寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『洛東探訪』、『京都の寺社505を歩く 上』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『新選組と幕末の京都』、『旧版 京のお地蔵さん』、『新版 京のお地蔵さん』、 『山科事典』 、ウェブサイト「東福寺」、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |
| |
|