|
|
|
| 乗願寺 (京都市下京区) Jogan-ji Temple |
|
| 乗願寺 | 乗願寺 |
 |
 |
       森本儀太夫の墓 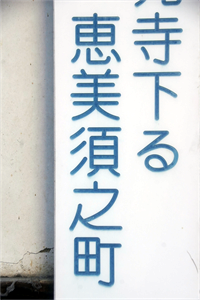 【参照】「恵美須之町」の町名(下京区) |
寺町通仏光寺下ルに乗願寺(じょうがん-じ)はある。 武将・森本儀太夫の墓がある。 浄土宗捨世派。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1576年、僧・信窮が、当初は五条坊門芝山町(現・仏光寺西町)に開創した。 1585年、現在地(現・下京区寺町通仏光寺下ル)に移転した。本堂8間4面・地蔵堂・開山堂・方丈などを有していた。 1591年、豊臣秀吉の命により、現在地に移ったともいう。(『坊目誌』) 江戸時代、1788年、天明の大火により焼失した。(『坊目誌』)。その後、再建された。 近代、1872年、上知令により、境内の3分の1を政府に献上した。 1888年、火災により境内地・伽藍などは大幅に縮小される。 1894年、本堂が再建される。 1926年、書院が新築された。 現代、1993年、森本儀太夫親子の位牌が発見された。 ◆信窮 安土・桃山時代の浄土宗の僧・信窮(?-?)。詳細不明。1576年、乗願寺を開創した。 ◆森本 儀太夫 室町時代後期-江戸時代前期の武士・森本 儀太夫(もりもと-ぎだゆう、1560-1651)。詳細不明。男性。名は一久。京都山崎の生まれ。子に右近太夫。加藤清正に仕えた。1589年、本渡城攻撃で、清正の三傑の一人と称され、500石を加増された。1593年、文禄の役の晋州城攻撃で「亀甲車」を考案した。石垣を撥ね崩し、一番乗りして名声を挙げる。この功績により、豊臣秀吉から「正宗」の刀と「儀」の一字を賜った。肥後国熊本へ入国後、5200石を与えられ、先手三備の二番備の武者奉行になる。津奈木城の城代になった。1632年、加藤家の改易前に浪人になり京都に移る。89歳。 城郭普請に優れ、熊本城築城に際し二の丸北西隅に三階櫓を築き「森本櫓」・「儀太夫櫓」の名が残った。なお、城は1770年に焼失している。江戸城では、加藤家の普請奉行として、桜田・日比谷一帯の石垣築造を行ったという。 ◆森本 右近太夫 江戸時代前期の武士・森本 右近太夫(もりもと-うこんだゆう、?-1674?)。詳細不明。男性。肥州(肥前・肥後国)の生まれ。名は一房(かずふさ)。父・加藤清正の重臣・森本儀太夫(一久)、母・明信の次男。清正に仕えた。1611年、清正の没後以降、肥前・松浦藩に仕えた。1632年、旧正月、カンボジア(南天竺)に、父の現世利益・亡母の後生のためにアンコール・ワット(当時は仏教の聖地・祇園精舎とされた)に少なくとも10日間滞在し、御堂に参詣し4体の仏像を奉納したという。その際に、回廊の柱に墨書(落書き)を残した。帰国後に松浦藩を辞し、山崎に転居した。京都で没したという。 ◆位牌 現代、1993年に乗願寺で森本儀太夫親子とみられる位牌が発見された。 森本家関連の位牌には、法名「月窓院殿光譽道悦居士 森本儀太夫」(没年は慶安4年[1651年]6月11日)とあった。もう一つの儀太夫の子とみられる位牌には、法名「月桂院殿應譽道感一信居士 森本佐太夫(さだゆう)」(没年は延宝2年[1674年]3月28日)とあった。右近太夫の名はなかった。 後年の江戸時代後期、1849年旧4月25日に森本儀十郎が乗願寺に墓参し、この位牌を造った。儀十郎は細川森本家(初代は森本儀太夫の子・四郎兵衛)の7代目に当たる。儀太夫の末孫になり、細川家の家臣だった。 森本佐太夫について、森本右近太夫と同一人物との説がある。江戸時代前期、1632年旧正月に右近太夫はアンコールワットを訪ねている。翌1633年には、幕府により鎖国令二月令が出された。切支丹弾圧のためであり、以後、海外渡航の禁止、密出国者は死刑、帰国者も極刑に処された。このため、右近太夫は佐太夫に名を変え、帰国後は潜んだともいう。 ◆墨書 アンコール・ワットはカンボジアの北西部、シエムレアプ郊外のトンレサップ湖北西にある。クメール王国での大寺院であり、12世紀(1101-1200)前半にスールヤヴァルマン2世により創建された。ヒンズー教寺院であり、ヒンズー教三大神の中のヴィシュヌ神に捧げられた。アンコール・ワットは「大きな寺」という意味を持ち、環濠を含み、東西1.5km、南北1.3kmの広さがある。三重の回廊の上に5つの祠堂が建てられている。 アンコール・ワットの十字回廊などに残された墨書(落書き)は14個所ある。日本人のものは、17世紀前半、江戸時代前期、1612年・1632年などに見られた。肥州(肥前[佐賀・長崎]・肥後[熊本])・堺州・城州(京都)・大坂の武士・商人が、単独・集団・夫婦などで寺院を訪ねたことが分かっている。 当時、多くの日本人は朱印船貿易を通じ、東南アジア各地に渡航していた。現地プノンペン郊外のピニャールーには、日本人町も形成されていた。当時の日本人は、アンコール・ワットを仏教の聖地「祇園精舎」の遺跡とも考えていた。 1632年正月20日に、森本右近太夫は、アンコール・ワットに参詣しており、十字回廊の南廊石柱に墨書した。さらに、10日後の正月30日にも、前半と同一内容の落書きを第一回廊内の北経蔵入口に再び墨書している。右近太夫は、少なくとも10日間はアンコール・ワットに滞在していた。 ◆墓 ◈墓地に森本儀太夫の墓碑があり、院号「月窓院殿光譽道悦」と刻まれている。江戸時代後期、1778年、近代、1888年の2度の火災により一部が損傷している。 ◈池内の手水鉢後方には、森本儀太夫の墓石が転用されている。 ◈位牌に記された森本左太夫の墓碑は、書院庭の池の石組に転用されていた。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『京都市の地名』、『京都戦国武将の寺をゆく』、ウェブサイト「京都府埋蔵文化財論集 第6集」、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |