|
|
|
| 神牛石神社(神牛石社) (京都府久御山町) Jingyuseki-jinja Shrine |
|
| 神牛石神社 | 神牛石神社 |
 |
 |
     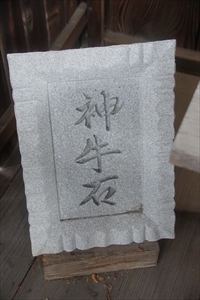  奉納絵馬   十三重石塔   地蔵尊  地蔵尊 |
久御山町佐山の曹洞宗・大松寺(だいしょう-じ)山門脇に神牛石神社(じんぎゅうせき-じんじゃ)がある。神牛石社とも呼ばれている。 御神体は、神牛石という黒い霊石を祀る。石は世に何か異変の起こる前に、しっとりと濡れて予言するという。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、1053年、仁海の感得により神牛石は出現したという。 鎌倉時代、1243年、興正菩薩叡尊により堂宇が建てられた。また、叡尊は三福寺(山福寺)にこの石を安置したという。 その後、石は椏本(あてもと)八幡宮(雙栗[さぐり]神社)の神宮寺・三福寺の蓮池に沈んだという。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、中良元が夢告により池中より石を掘り出して祀ったという。 江戸時代、1676年、石について記されている。(『椏本八幡宮縁起』) 1742年、8月23日、三福寺境内の蓮池跡から石を見つけて堀出し、この日を例祭日にしたという。 1802年、神牛石について記されている。(「記録古書改」) 1812年、石について記されている。(『神牛石縁起』) 近代、1868年、三福寺は廃寺になり、石を御神体にする神牛石神社が創建された。 ◆仁海 平安時代後期の僧・仁海(にんがい、?-?)。詳細不明。1053年、久御山佐山に浄福寺(浄安寺の前身)を創建した。 ◆叡尊 鎌倉時代前期-後期の律宗の僧・叡尊(えいそん/えいぞん、1201-1290)。男性。睿尊、字は思円、諡号は興正菩薩(こうしようぼさつ) 。大和国(奈良県)の生まれ。父・興福寺の学侶・慶玄、母・藤原氏。1207年、母を亡くし、醍醐寺門前の家の養子になり、醍醐寺に入り真言を学ぶ。1217年、叡賢を師として出家した。1234年、戒律の復興を志す。1235年、円晴(えんせい)が東大寺で『四分律行事鈔』講じたのを聞く。大和国西大寺に移る。1236年、東大寺で円晴、覚盛(かくじょう)、有厳らと自誓受戒し比丘になる。その後、大和・海竜王寺に移る。1238年、西大寺に住み、再興した。1262年、鎌倉幕府の北条時頼・実時に招かれて鎌倉に下り、北条一族・御家人などに授戒した。1269年、般若寺で非人供養する。1281年、蒙古来襲時に、伊勢神宮・石清水八幡宮で異国降伏の祈祷も行う。1285年、叡尊の申請による網代破却が行われた。1286年、宇治川の網代破却による殺生禁断を実行し、勧進により宇治橋、浮島の十三石塔を再興した。著『梵網古迹文集』 (10巻) 、自叙伝『感身学正(かんじょうがくしょう)記』 (3巻) など。90歳。 西大寺の中興開山。戒律の復興に努め、律宗中興の祖になる。後嵯峨上皇(第88代)・後深草3上皇(第89代)・亀山上皇(第90代)の帰依を受けた。殺生禁断・慈善救済・土木事業などを行い、非人・貧民・病人救済を行った。 ◆神牛石 神牛石についていくつかの伝承がある。 平安時代後期、1053年に、仁海(?-?)の感得により神牛石は出現したという。鎌倉時代中期、1243年に、興正菩薩叡尊(1201-1290)により堂宇が建てられた。また、叡尊は三福寺(山福寺)に石を安置したともいう。寺は、椏本(あてもと)八幡宮(雙栗[さぐり]神社)の神宮寺だった。 また、その後、三福寺の蓮池に石は沈んだという。安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)に、中良元という人が夢告に従い、池中より石を掘り出して祀ったともいう。 江戸時代前期、1676年に石について記されている。昔より三福寺の門内に大石があり、神牛石と呼ばれていた。(『椏本八幡宮縁起』) また、江戸時代中期、1741年8月24日八ツ時に石は出現し、前日九ツ時には塔石が出たという。(「記録古書改」、1802)。『山州名跡志』(1711)、『山城名勝志』(1711)にも記されている。 その後、石の所在は不明になった。江戸時代中期、1742年8月23日に、三福寺境内の蓮池跡から石を見つけて堀り出した。以来、この日を例祭日にしたともいう。(『神牛石縁起』、1812) 近代、1868年に三福寺は廃寺になる。石を御神体に神牛石神社が創建された。 神牛石は色黒く、形は牛の様な形をしていた。天下に騒ぎ(凶事)があると、必ず石から(水が)滴り落ちて汗のようだったという。神異をあらわす奇石だったという。(『椏本八幡宮縁起』) 以来、石は牛の守護神として崇敬されてきた。なお、神牛石には3種あり、上野国(群馬県)の赤石、近江国(滋賀県)琵琶湖底にあるという白石、神牛石神社の黒石だったという。神牛石は普段は開帳されていない。 ◆文化財 「十三重石塔」は、神牛石神社の右に立つ。鎌倉時代に興正菩薩叡尊が建立したという。三福寺の荒廃後に散乱し、その後、現在地に復元したという。 初重軸部に金剛界四仏の梵字を刻んでいる。高さ3m、花崗岩製。 ◆祭礼 かつて、春秋の例祭(3月23日・9月23日)は、牛を飼育している農家による神牛講が司っていた。 近代、昭和期(1926-1989)初期の例祭日には、近郊・河内からも牛馬が集められた。境内では品評会なども催され、露店も出て賑わっていたという。現代、昭和30年代(1955-1964)に入り、農耕の機械化により牛馬使役は廃れ講も解散した。 現在は、祭祀(9月23日)が大松寺により執り行われている。 ◆年間行事 例祭(9月23日)。 ❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 久御山町郷土史会の説明板、『京都府の地名』、『昭和京都名所図会 7 南山城』、「くみやま文化・歴史ガイド 久御山」、「広報くみやま2005年10月1日」、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |