|
|
|
| 旧三高物理学実験室 (京都市左京区) Former Third High School Physics Laboratory |
|
| 旧三高物理学実験室 | 旧三高物理学実験室 |
 |
 |
 南西角  南側  南側  南側 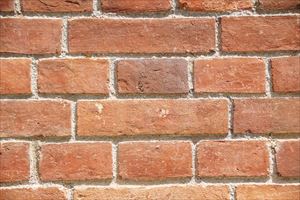 南側、煉瓦積  南側  東側、渡廊下、左手は旧物理学・数学教室  東側、渡廊下  東側  西側  西側  西側  西側、ドーマ  北側 |
京都大学吉田キャンパス本部構内の南西に、赤煉瓦造の旧三高物理学実験室(きゅう-さんこう-ぶつりがく-じっけんしつ)はある。 京都大学構内に現存最古の建物になる。設計は、近代の建築家・山口半六、久留正道による。 ◆歴史年表 近代、1889年、3月、旧三高物理学実験室は起工した。11月、竣工する。 1898年、実験室の東側に京都帝国大学の物理学・数学教室棟が建てられる。建物は一体化した。 ◆山口半六 近代の建築家・山口半六(やまぐち-はんろく、1858-1900)。出雲国(現・島根県)生まれ。松江藩士山口軍兵衛・礼行の次男。1873年、大学南校(開成学校・東京大学の前身)を中退した。1876年、文部省派遣留学生としてフランスに留学する。パリ工業中央専門学校(École Centrale Paris)で建築を学ぶ。1879年、学校を卒業し、1881年、帰国する。郵便汽船三菱会社(現・日本郵船)を経て、1885年/1884年、文部省営繕課の技師になる。同僚・久留正道と多くの学校建築を設計した。1891年、建築家として2人目の工学博士号を授与される。1892年、肺病のため文部省を辞職した。1894年、大阪・桑原工業事務所建築部に移り、以後は関西で活躍した。1897年、大阪市から都市計画を委嘱される。1899年、独立し「山口建築事務所」を開設した。43歳。 山口のフランス作風の意匠は当時の日本建築界では異色だった。工手学校(現・工学院大学)造家学科教員も務めた。主な作品は、東京高等師範学校(1887)、東京帝国大学理科大学(1888)、熊本・第五高等中学校(1889)、京都・第三高等中学校寄宿舎 (現・京都大学吉田寮、1889) 、旧東京音楽学校奏楽堂(1890)、 金沢・第四高等中学校本館(現・四高記念文化交流館、1891)、大阪・日本火災保険(1900)、代表作は没後竣工の兵庫県庁舎(現・兵庫県公館、1902)、大阪・日本貯金銀行(1902)などがある。日本での近代都市計画家の先駆者としても知られ、大阪都市計画(1897)、長崎都市計画(1900)にも参画した。 ◆久留正道 近代の建築家・久留正道(くる-まさみち、1855-1914)。江戸(東京都)生まれ。工部大学校造家学科(現・東京大学)でコンドルに学ぶ。1881年、卒業し、工部省技手などを経て、1886年、文部属になる。1887年、文部省営繕技師になり、第一-第五高等中学校の設計に関わる。1891年、東京工業学校(現・東京工業大学)、東京美術学校(現・東京芸術大学)専修科で嘱託として教鞭をとる。1892年、文部省技師に復帰し、会計課建築掛長に就く。以後、初等・中等教育施設の行政指導、直轄学校の創立工事などに関わる。1905年、シカゴ万国博覧会に日本館「鳳凰殿」を出品した。学校建築の基本型になった『学校建築図説明及設計大要』(1895)を著したといわれている。60歳。 ◆建築 旧三高物理学実験室は、旧石油化学教室の内側の1階建部分になる。三高が大阪から京都に移転した際に、物理学実験室として建てられた。 近代、1889年3月に起工した。同年11月に竣工している。1898年に、東側に京都帝国大学物理学・数学教室棟が建てられ建物が一体化した。旧三高の遺構であり、京都大学構内に現存する建物の中で最も古い。 1549年に日本人初のノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹(1907-1981)、1565年にノーベル物理学賞を受賞した朝永振一郎(1906-1979)、1981年にノーベル化学賞を受賞した福井謙一(1918-1998)も研究に利用した棟のため、「ノーベル賞の館」とも呼ばれている。 平面は「L」字型であり、西側棟(南北方向)と北側棟(東西方向)になる。外観は簡潔で壁体に煉瓦を露出させる。煉瓦は長手積みだけの段、小口積みの段だけの段と一段おきに積む。白いまぐさ石(楣石、窓・出入り口の上部に架け渡した横材)で窓上部を支え、煉瓦色と対比されている。内部は片廊下に沿い、5室の教室が配されていた。南端に階段がある。 施工は日本土木会社(担当・田中豊輔)による。煉瓦造平屋建、寄棟造桟瓦葺。当初は182坪(602㎡)。 なお、文部省営繕課は、これらの建物の設計を通して、近代的な学校施設の設計に関する『学校建築設計大要』(1893)をまとめた。 ◆第三高等中学校・高等学校 「第三高等中学校」は、近代、1869年に大坂舎密(せいみ)局に始まる。洋学校など変転を重ね、1889年8月に大阪から京都上京区(現・左京区)吉田に移転した。大学予科、専門教育の医・法・工学部があった。 1894年6月の高等学校令により、専門教育のみの「第三高等学校」に改称した。1897年に「京都帝国大学」が創設され、法・医・文・理工の4分科大学になる。高等学校は学生募集を停止する。1898年4月に高等学校に大学予科が復活する。9月に吉田二本松町(旧京都大学教養部)に移転し予備教育機関になった。 1949年5月の学制改革により新制の「京都大学」に昇格した。 *内部は通常非公開 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都大学」、『京都市の近代化遺産 近代建築編』、『京都大事典』、ウェブサイト「コトバンク」 |
 |
 |