|
|
|
| 島原住吉神社・弁財天社 (京都市下京区) Shimabara-sumiyosh-jinja Shrine |
|
| 島原住吉神社・弁財天社 | 島原住吉神社・弁財天社 |
 |
 |
 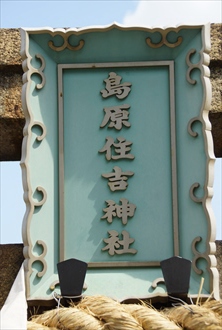   拝殿 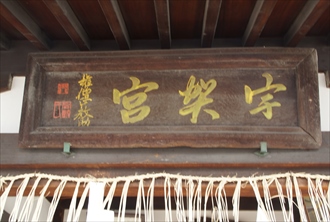 拝殿  拝殿  本殿  本殿  本殿  本殿  末社、幸天満社  末社、幸天満社 |
島原の一角に島原住吉神社(しまばら すみよし-じんじゃ)が南面して建つ。 祭神は本社に宇迦之魂命(うかのみたまのみこと)、表筒男命(おもてつつおのみこと)、中筒男命(なかつつおのみこと)、底筒男命(そこつつおのみこと)、息長足姫命(おきながたらしひめのみこと)を祀る。 末社、幸天満社に菅原道真公(すがわらみちざねこう)を祀る。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 かつて、住吉屋太兵衛(島原中堂寺町)の自宅に住吉大明神として祀られていた。 江戸時代、1732年、霊験あり、良縁のご利益があるとして参詣者で賑わう。島原の西北に遷座し、島原住吉神社として建立された。境内は広大で、南は道筋(島原中央東西道)、北は島原の北端までを有していた。以後、島原の鎮守神として崇敬され、例祭には島原太夫、芸妓らの練りものが行われた。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により廃社になる。祭神は歌舞練場内に遷された。 1903年、船井郡本梅村から無格稲荷社の社格株を譲り受け、現在地に再興される。境内は狭まり、稲荷神社とされた。 現代、1999年、社殿、拝殿が改修され、社務所も新築しされる。 2001年、社名を念願の島原住吉神社に改めた。 ◆弁才天社・大イチョウ 境内の北隣に、旧境内地があり、境内北端に植えられていた大イチョウがいまもある。近代、1868年、島原住吉神社の廃社後もご神木として残された。 1903年に神社は再興される。1930年に大樹の根元に弁財天社が祀られた際に、大イチョウはご神木になる。樹高20m、幹回り3.5m、樹齢300年。 ◆幸天満宮 境内にある幸天満宮は、かつて揚屋町会所に天神の祠として祀られていた。江戸時代中期、1734年に現在地に遷された。 筑紫の太宰府天満宮に倣った、江戸時代中期、1748年創建の鷽替(うそかえ)神)も、近代、明治期(1868-1912)以降に廃れたという。 ◆年間行事 元旦祭(1月1日)、幸天満社祭(梅花祭白梅・御茶献供)(1月25日)、初午祭(2月28日)、節分祭・豆撒き神事(2月節分)、夏越大祓式・人形祓い(6月30日)、例大祭(9月28日か前の日曜日)、火焚祭・火焚神事(11月28日)、大祓式・人形祓い(12月31日)。 月次祭(毎月28日) *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考資料・資料 島原伝統保存会の石碑より  |
 |
 |
| 弁財天社 | |
 弁財天社 |
 弁財天社 |
 弁財天社 |
 弁財天女、歳白龍王、美須龍王 |
 不明 |
 ご神木の大イチョウ |
 |
 |
| |
|