|
|
|
| 松尾大社西七条御旅所・武御前社 (京都市下京区) Matsunoo-taisy Otabisyo |
|
| 松尾大社西七条御旅所・武御前社 | 松尾大社西七条御旅所・武御前社 |
 |
 |
     拝所  拝所 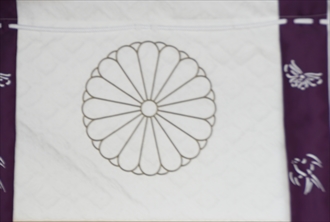 拝所  本殿  手水舎  神輿庫  武御前社  武御前社  武御前社 |
西七条、西蓮寺の南に松尾大社西七条御旅所(まつのおたいしゃ-にししちじょう-おたびしょ)がある。なお、境内の北東隅に武御前社(たけの-ごぜんしゃ)が祀られている。 松尾大社の御旅所の一つであり、4月の松尾祭の神幸祭には、大宮社、櫟谷社、宗像社、四之社の神輿、月読社の唐櫃の渡御があり、5月の還幸まで22日間駐輦(滞在)する。 祭神は、松尾大神。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、貞観年間(859-877)、松尾祭が始まったという。(『江家次第』) 1109年、「松尾稲荷共御旅所」などと記され、この頃、すでに御旅所が存在したと見られる。(『年中行事秘抄』) 1152年、「櫟谷社旅所」と記されている。(『槐山記』) 安土・桃山時代、1585年、豊臣秀吉により145石の朱印社領石高があった。 江戸時代、西七条村に大宮・月読相殿御旅所・谷御旅所、宗像御旅所・衣手御旅所・四太神、川勝寺村に三宮御旅所、朱雀村に惣神社・神供場が祀られていると記されている。(『松尾略注全冊』)。江戸時代、徳川幕府より同じく145石の朱印社領石高があった。(「京都役所向大概覚書」) 近代、明治期(1868-1912)、分散していた東四社の御旅所が、大宮社御旅所(現在地)にまとめられ、「官幣大社 松尾大社西七条御旅所」となる。近代初頭まで、神仏混淆期に、北隣の西蓮寺と松尾大社西七条御旅所は同じ境内地にあったという。 現代、1984年-1985年、松尾大社西七条御旅所造営整備事業により、現在の本殿、神輿庫、社務所が完成する。 ◆武御前社 境内の北東隅に武御前社(たけの-ごぜんしゃ)が祀られている。祭神は、武甕槌神(たけみかつちのかみ)になる。旧西七条村の産土の神として崇敬されてきた。子どもが生まれると当社に宮参りし、男児の額に「大」、女児に「小」という朱文字を書き、鼻を摘んでもらう慣わしがあった。 祭礼では、かつて、お還りの際に、武御前の神輿と称される白木の神輿を新造した。子どもが神輿を桂川まで担いだ。翌日、再び担ぎ叩き壊した。その木切れを持ち帰り、家の厠に挿し、疫病封じの呪いにした。また、後には、神輿は川に捨て、再び御旅所に担いで還ったという。 近代、1886年に神輿は新造になる。現代、1970年まで還幸祭の翌日に、神輿が還った跡を追い、御旅所周辺を巡行した。まだ人々が居眠っている時だったため、「居眠り神輿」と呼ばれた。その後、中断し、1978年に復活する。 現在は、親神輿が御旅所にある日曜日に、延命息災を祈願し、奉納された金柑を神主が子どもたちに撒き、御旅所周辺を神輿巡行している。 ◆年間行事 奉射祭(1月5日以降の日曜日)、神幸祭(おいで)(4月20日以降の第1日曜日)、七日開祭(神幸祭より7日目の土曜日)、還幸祭(おかえり)(神幸祭より21日目の日曜日)、献灯会安全祈願祭・武御前社神輿巡幸(5月3日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 説明板、『京都歴史案内』 、ウェブサイト「歴史的景観の保全に関する検証事業 京都市歴史的景観の保全に関する検討会 第5回 資料3-1 景観重要建造物等の指定候補の事例(神社)」、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |
| |
|