|
|
|
| 俊成社 (京都市下京区) Shunzei-sha Shrine |
|
| 俊成社 | 俊成社 |
 |
 |
   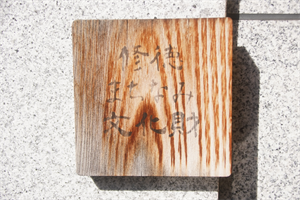 「修徳まちなみ文化財」の木札 |
俊成町に俊成社(しゅんぜい-しゃ)が祀られている。現在は、烏丸通沿いの建物の一角に組み込まれる形で鎮座する。 付近は、平安時代末期の歌人・藤原俊成の邸宅跡といわれ、社は「俊成さん」とも呼ばれている。ただ、邸宅の場所については五条京極にあったともされ、現在地は後世の誤認ともいう。 祭神は歌人・藤原俊成を祀る。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 室町時代中期、藤原俊成の邸が、五条室町(現在の烏丸五条付近? )にあると記されている。(『正徹(しょうてつ)物語』) 鎌倉時代、1204年、俊成の没後、町民が民家の裏に祀ったともいう。 江戸時代、俊成社は現在地近くに祀られていたという。 1758年、町民が奉行所へ願い出て、烏丸通松原から東の一帯(因幡堂前町)を俊成町の異称より正式な町名にした。以来、俊成町に改められる。 現代、2012年、祠はそれまでの屋外より建物の一角に納められ祀られた。 ◆藤原 俊成 平安時代後期-鎌倉時代前期の歌人・公卿・藤原 俊成(ふじわら-の-としなり/しゅんぜい、1114-1204)。男性。初名は顕広、法名は釈阿。父・権中納言・藤原俊忠、母・伊予守・藤原敦家の娘の3男。子・定家。10歳で父に死別、葉室顕頼の養子になる。藤原為忠の催しに参加した。25歳で、藤原基俊の門弟になる。九条兼実の歌道師範になる。54歳で、本家・御子左家(みこひだり)に戻り、俊成と改名した。63歳で、病により出家した。1150年、崇徳上皇主催の「久安百首」の作者、1166年、「中宮亮重家朝臣家歌合」などの歌合判者を務めた。『千載和歌集』(1188)選者、歌論書『古来風躰抄』(1197)などを著す。邸宅「五条第」が五条通にあったとされ、五条三位とも呼ばれた。正3位皇太后宮大夫。西行とも親交があった。91歳。 東福寺塔頭・永明院(東山区)に墓所がある。 ◆平 忠度 平安時代後期の武将・歌人・平 忠度(たいら-の-ただのり、1144-1184)。男性。京都の生まれ。父・忠盛、母・藤原為忠の娘とも。清盛の末弟。正四位下薩摩守。幼少より藤原俊成に和歌を学ぶ。源平合戦で、1180年、富士川の戦、1181年、墨俣川の戦、1183年、礪波山の戦などに参戦した。1183年、平氏都落ちに際し、師・藤原俊成に詠草1巻を託し、後に『千載和歌集』に詠み人知らずで入集する。1184年、一の谷の戦で岡部六弥太忠澄に討たれる。『新勅撰和歌集』『玉葉集』などに 11首選ばれている。自撰集『平忠度朝臣集』。 41歳。 討死後、箙(えびら)に身に付けた和歌が発見されたという。「行きくれて木の下かげを宿とせば花やこよひの主ならまし」。能に「忠度」がある。 ◆藤原 俊成 女 鎌倉時代前期の歌人・藤原 俊成 女(ふじわら-の-としなり/しゅんぜい/-の-むすめ、1171頃 -1251∼)。女性。父・尾張守・藤原盛頼、母・藤原俊成の娘・八条院三条。1177年、父は鹿ケ谷事件首謀者の一人・藤原成親の弟として責を問われ失脚した。俊成女はその歌才を見込まれ、母方祖父・藤原俊成の養女になる。1190年、20歳頃に源通具(みちとも)の妻になり、一男一女を産む。だが、夫は新妻・従三位按察局を迎えた。1201年、後鳥羽院の女房として出仕、『新古今和歌集』以降の勅撰集、定数歌、歌合などに多数の作品を残した。1213年、出家し、嵯峨に住み嵯峨禅尼、越部(こしのべ)禅尼と呼ばれた。1241年、藤原定家没後、播磨国越部庄に隠棲した。『越部禅尼消息』を著し、定家の選んだ『新勅撰集』を非難した。新三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。 ◆忠度 『平家物語』では、咎により西国へ都落ちする薩摩守忠度が俊成邸を訪れる。「千載和歌集」に入集を依頼し、かなえば、あの世から守護するとして、百余りの自作の和歌を差し出す。俊成は詠み人知らずとして、「さざなみや 志賀の都は あれにしを むかしながらの 山ざくらかな」を選ぶ。 世阿弥作の能「忠度」は、俊成に仕えた僧が、須磨の浦で老人と出会う。やがてその翁は、自らが源氏との戦で命を落とした忠度の亡霊であることを暗示する。僧の夢に甲冑姿の忠度の霊が現れる。霊は、朝敵になり、詠み人知らずとされたことを嘆く。霊は、自らの名を書き入れるように、俊成の子・定家へ伝えることを依頼する。霊は身の上のことなども語り、回向を願い消え去る。物語は謡曲の題材にもなっている。 ◆五条第 藤原俊成の邸宅「五条第」は、新玉津嶋神社の一画(玉津島町南部)とされる。(『新玉津島記』)。また、当社の東、俊成社(俊成町)ともいう。 実際には、左京五条四坊十六町の南部(五条大路北、京極大路西の町、現在の下京区京極町西、桝屋町南、石不動町北)付近にあったともいう。俊成はここに生まれ育ったという。 平安時代後期、1183年、俊成は後白河院の院宣により撰集の命を受けた。武将・平忠度(1144-1184)は、歌人としても優れ、俊成に師事していた。同年旧7月、平家一門の都落ちの際に、忠度は従者6人を引き連れ淀から都に引き返し、俊成の五条第を訪れた。歌百余首が記された巻物を俊成に託し、いつか平穏な世に戻った際には、自作の歌を勅撰集に採るように懇願したという。その後、忠度は西国へと落ちて行き、翌1184年旧3月に、一ノ谷の戦いで討死した。 俊成は、1188年に『千載和歌集』を成立させた。朝敵になった忠度の名を憚り、忠度の詠んだ一首「故郷の花」を「詠み人知らず」として選んだ。「さざ波や志賀の都はあれにしを昔ながらの山さくらかな」(『千載和歌集』)。(覚一本『平家物語』巻第七「 忠度都落」) 俊成は、鎌倉時代前期、1196年頃に五条第より三条に移る。俊成の子・定家、定家の同腹姉・八条院権中納言、八条院按察(あぜち)、建春門院中納言らも五条第に育った。(『山塊記』『明月記』『玉葉』) ◆年間行事 祭礼(当日は俊成の命日とされ、俊成の画像、稲荷大明神の軸が掲げられ、お火焚祭が行われる。)(11月28日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都歴史案内』、『京都事典』、『京都市の地名』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の地名検証 2』、『平安京散策』、『京に燃えた女』、『京都大事典』 、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |