|
|
|
| 鏡石 (京都市北区) Kagami-ishi |
|
| 鏡石 | 鏡石 |
 |
 |
 鏡石  わずかに残る平面に近い岩の部分  「衣笠鏡石町」の表示板 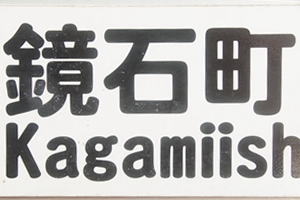 「鏡石町」の町名板  【参照】鏡石町(上京区)の町名板 |
衣笠の金閣寺に近い地に、鏡石町(かがみいし-ちょう)という地名が残る。細い道筋(鏡石通)の山側の崖地に、「鏡石(かがみ-いし)」といわれる大岩が残されている。石面は、断層の滑り面という。 「岩陰の鏡石」として金閣寺の不思議の一つに数えられた。鏡石はかつて鏡のようにものを映したという。名所の一つになり、地名の由来になった。 ◆歴史年表 平安時代前期、歌人・紀貫之(866/872?-945?)が石を詠んだという。 平安時代末期、武将・源義経(1159-1189)は姿見に用いたという。 江戸時代、1780年、紙屋川上流に鏡石があり、石面は水晶のように顔を映すと記されている。(『都名所図会』六巻) 1787年、鏡石の記述があり、岩面に女性の立ち姿が鏡のように映る挿し絵がある。(俳諧師・秋里籬島著の『拾遺都名所図会』) その後、 道を通る際に牛が驚くというので、石面を松葉でいぶし、光りを失わせたという。また、道路拡張工事の際に、岩の一部が削られたともいう。 ◆うばたまの 平安時代前期の歌人・紀貫之(871?-946)の歌に「うば玉の我が黒髪やかはるらん 鏡の影に 降れる白雪」(『古今和歌集』、460番)とある。 「うばたま(烏羽玉)の」は、「黒(髪)」にかかる枕詞であり、「私の黒髪が変ったのだろうか、鏡に映るこの白雪(白髪)は」という意味になる。老いさらばえた自らの白髪について、また、老いの予感を詠んだという。 枕詞の「うばたま(烏羽玉)の」は、黒、闇、夜、夢などにかかる。「ぬばたまの」「むばたまの」ともいう。植物の「うばたま」とはヒオウギの実であり丸くて黒い。「ぬばたま」ともいう。和菓子にも「うばたま」があり、求肥(ぎゅうひ)で餡を包み、白砂糖をまぶす。これも黒く丸い。 ◆鏡石 京都での鏡石の伝承は、ほかにもいくつかある。 ◈貴船神社(左京区)の禁足地の山林内には、貴船大神が降臨した石がある。従者子孫の一人が、多弁として大神により大和に追放される。後に赦されて貴船に戻った。きまり悪く小さく屈んだので鏡石と呼ばれたという。 ◈勝持寺(西京区)の鏡石は、境内の池の近くに置かれ、西行が剃髪の際に姿を映したという。 ◈ほかにも上京区鏡石町がある。同町には聚楽第の北ノ丸北掘の石垣跡になり、石垣に使われたとみられる石材に由来しているという。 左京区大原古知谷の屏風岩という石、西京区嵐山の檪谷神社にも鏡石があったという。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都の地名検証』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『洛中洛外』、『京都大事典』、『京の怪談と七不思議』、「京都歴史散策マップ20 聚楽第」  |
 |
 |
| |
|