|
|
|
| 金毛院 (京都市左京区) Kimmo-in Temple |
|
| 金毛院 | 金毛院 |
 |
 |
 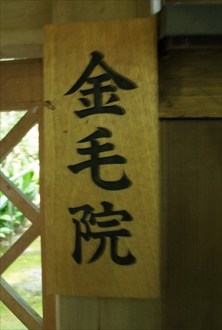         山楓の大木   織部燈籠  石段  ホトトギス   玄関     書院  庭園   山楓   本堂  本堂、扁額「金毛院」  本尊・阿弥陀如来坐像  本堂、箪笥    待合  蹲踞、燈籠  茶室  茶室、床  茶室、躙口  茶室、吉野窓  茶室東の露地庭   飛石 |
法然院境内の南西一角、傾斜地に石垣を築き金毛院(きんもう-いん)は建つ。山号を獅子山という。法然院の別行道場(塔頭)になる。 浄土宗、本尊は阿弥陀如来坐像。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 江戸時代中期、1693年?、法然院の忍澂(1645-1711)の退隠所として開かれたという。 ◆忍澂 江戸時代前期-中期の浄土宗の僧・忍澂(にんちょう、1645-1711)。男性。俗姓は二見、号は白蓮社宣誉信阿、葵翁、金毛老人。江戸の生まれ。幼くして両親を失い、姉に育てられた。父の遺言に従い、江戸・増上寺・最勝院の直伝(じきでん)により11歳で出家、師没後、浄国寺・萬無(まんむ)、増上寺・林冏(りんげい)に学ぶ。各所で修行を重ね、1676年、安孫子・浄福寺で自誓受戒する。萬無は忍澂に命じ、1681年、鹿ヶ谷に法然院を建立し念仏道場とした。萬無没後、規則「白蓮小清規」を定めた。一切経『大蔵経』(1706-1710)の校訂を行う。1693年、金毛院に退隠する。黄檗宗の独湛性瑩と親交した。『勧修作福念仏図説』を開版し、21万8000枚を庶民に配った。1693年、法然院山内の庵に隠居した。67歳。 墓所は法然院(左京区)に金毛塔が立つ。 ◆浄阿 江戸時代後期の浄土宗の僧・浄阿(じょうあ、?-1800)。詳細不明。金毛院の学僧。第105代・後奈良天皇の勅請により宮中に阿弥陀経を講じた。 ◆山号 寺名の金毛院とは、開山・忍澂の号、「金毛老人」に因む。陽光に照らし出され、獅子の毛が黄金色に輝く様をいう。 ◆仏像・木像 ◈本堂に、「阿弥陀仏坐像」が安置されている。平安時代作とされ、恵心僧都(源信、942-1017)が刻んだともいう。開山の忍澂の念持仏だったとされ、法然院より遷されたものという。衲衣は左肩を覆い、転法輪印(てんぽうりんいん)という珍しい印を結ぶ。両手を胸高に上げ、右手の人差指と親指で輪を作る。左手の人差指と薬指は立てられ、左手の薬指と右手の人差し指は交差する寸前で止められているという。右手の掌は前に向けられ、聴衆への法を説く。左手は自分へ向けられており、自らへの法を説く。 転法輪とは法輪を転ずる、真理を説くこと意味し、法を相手に説く様を表し、説法印とも呼ばれる。印にはさまざまな形があるという。本来は、釈迦仏にみられ、阿弥陀仏では平安時代後期以降に多くみられるという。 ◈本堂に、「白衣観音」、「利休の木像」も安置されている。 ◆建築 現在は、玄関、書院、本堂、茶室が鈎型に一棟に建てられている。 本堂は、かつて修学院離宮より移されたという。現代、1959年の伊勢湾台風により被害を受け、現在は一室だけが残り、本堂となっている。 ◆茶室 茶室「凌雲亭」は、四畳半上座床になる。庭の腰掛より飛石があり、躙口、貴人口は東に開く。天井は竿縁の平天井、掛込天井(一畳半)になる。南に吉野窓が開く。 ◆文化財 ◈第108代・後水尾天皇(1596-1680)と関わりがあるという。その皇女筆という「金毛院」の扁額が本堂に掲げられている。額に菊花紋が入る。 ◈修学院離宮より移されたという箪笥があり、螺鈿が施されている。 ◈「宵の白衣観音」は、室町時代の画僧・明兆(1352-1431)筆という。絹地に墨で黒く裏打ちされ、表に観音像が描かれている。このため、地に像が隠され、目が次第に慣れると像が浮かび上がってくるように見える。 ◈徳川家より贈られたという椿の棗、3代将軍・徳川家光(1604-1651)の茶杓、筒、茶人・千宗旦(1578-1658)作という茶杓などがある。 ◈江戸時代前期の俵屋宗達筆という衝立には、竹垣に白い牡丹が描かれている。 ◆庭園 境内、庭は、高台にある。山門より苔に置かれた飛石の石段を上って入る。建物は鉤方の棟続きになっており、書院の南、本堂・茶室の東に露地庭がある。 庭面は狭いが、よく手入れされている。樹高の高い山楓の古木が聳えている。書院より苔の覆う庭に下り、腰掛、茶室に続く飛石が配されている。燈籠、蹲踞、石仏、四季折々の山野草、茶花の植栽が随所に見られる。垂直方向に広がる庭でもある。 茶室の吉野窓の外には、白い花弁を付ける野生種のナツフジがあり、花期は7-8月になる。 ◆年間行事 茶会(8月を除く毎月第2日曜日)。 *普段は非公開、茶会(裏千家)に一般参加も可。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『法然院』、『獅子ヶ谷法然院』 、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |
| |
|