|
|
|
| 専念寺 (京都府久御山町) Sennen-ji Temple |
|
| 専念寺 | 専念寺 |
 |
 |
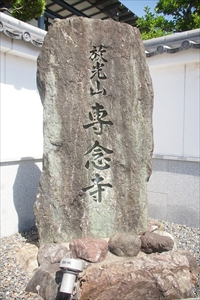    本堂  本堂 |
久御山町田井に専念寺(せんねん-じ)はある。山号は放光山(ほうこう-ざん)という。かつて「樫寺(かし-でら)」とも呼ばれていた。観音堂は城南近在三十三所観音霊場16番札所だった。 浄土宗元一心院派、本尊は阿弥陀如来を安置している。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 室町時代、1549年、武将・御牧益景(みまき-ますかげ、浄念)が、僧・称念に帰依し、専修念仏の道場として堂宇を創建したという。(寺伝) また、1587年、称念が開基になり、檀越・益景が伏見城中にあった聚楽殿舎の古材により築造したともいう。(『京都府地誌』)。同年、豊臣秀吉の命により、益景の子・勘兵衛尉尚秀(御牧勘兵衛)が引き移して再建したともいう。(『佐山村郷土誌』) 江戸時代、1672年、重誉により、旧本堂を庫裡とし、新本堂が建立された。(『佐山村郷土誌』) 1747年、8月17日・23日、木津川の大洪水により被災し、庫裡・観音堂・宝蔵などを流失した。(『佐山村郷土誌』)。御牧勘兵衛由緒・一族の巻物なども失われたという。 ◆称念 室町時代後期の浄土宗の僧・称念(しょうねん、1513-1554)。男性。俗姓は藤田、字は吟応(翁)、号は三蓮社縁誉。江戸/武蔵国(埼玉県・神奈川県)の生まれ。8歳で江戸・増上寺の親誉により剃髪、宗戒両脈を受けた。下総国(茨城県)飯沼・弘経寺の鎮誉に師事し浄土教学を学ぶ。江戸・天智庵を開創した。京都・黒谷に移り、1548年、青蓮院尊鎮親王の帰依により知恩院祖廟の南隣に草庵を結び、六時念仏を行う。信徒により堂舎が建てられ、念仏三昧の道場、本寺・一心院になる。掟「念仏道場七箇条」「別時念仏十一箇条」などを定めた。一心院で専修念仏に努め亡くなる。著『安心鈔』『要義鈔』42歳。 浄土宗捨世派(一心院流)の祖。47ほどの寺院を創立したという。京都では一心院ほかに、市原の専称庵、上嵯峨の称念寺、下嵯峨の正定院、桂の極楽寺などがある。 ◆御牧益景 室町時代中期の武将・御牧益景(みまき-ますかげ、?-?)。詳細不明。男性。浄念。子に景重、景則(勘兵衛)。摂津守。僧・称念に帰依した。1549年、専修念仏の道場として久御山に堂宇を創建し、専念寺の前身になる。1570年、三好三人衆に御牧城を攻められ城は陥落した。直後、羽柴(豊臣)秀吉の助力を得て奪還した。 ◆御牧勘兵衛 安土・桃山時代の武将・御牧勘兵衛(みまき-かんべえ、?-1600?)。男性。景則(かげのり)、御牧勘兵衛尉尚秀。父・御牧益景の次男。兄・景重(かげしげ)。兄とともに明智光秀に仕えた。1582年、山崎の戦いで光秀軍で戦い、兄・景重は戦死した。景則は豊臣秀吉の馬廻になる。1592年、朝鮮出兵の文禄の役で、肥前国名護屋に駐留し、城普請、裏門の警固を担う。後、山城国久世郡市田村に1000石を与えられ、検地奉行として山城国などの検地を行った。 久御山の社寺興隆に尽力した。久御山・専念寺門前の向藪(城薮)に屋敷があったという。 位牌・墓は専念寺(久御山町)にある。 ◆源満仲 平安時代中期の武将・源満仲(みなもと-の-みつなか、912-997)。男性。法名は満慶、多田新発意(しんぼち)、多田満仲。父・清和源氏六孫王経基。子に頼光、頼親、頼信。第56代・清和天皇の曾孫。969年、安和の変の発端になった為平(ためひら)親王を擁し、皇太子・守平親王(第64代・円融天皇)の廃位を狙う謀反で、藤原千晴らを密告し正五位下に叙せられた。左大臣・源高明を失脚させた。以後、第62代・村上天皇、第63代・冷泉天皇、円融天皇、第65代・花山天皇のもと摂関藤原家に仕え、摂津、越前、武蔵、伊予、美濃、下野、陸奥などの国守を歴任した。左馬権頭、治部大輔、鎮守府将軍に就く。朝廷警備も担当した。多田盆地(兵庫県川西市)に所領を得て武士団を形成する。986年、花山天皇退位事件では、山科・元慶寺まで警固にあたった。987年、出家し満慶と称した。994年、大規模な盗賊追捕を一族とともに行う。86歳。 多田源氏の祖。後代の清和源氏発展への礎を作る。左京一条に邸宅を構えた。 遺骸は、宗廟の多田神社に葬られた。 ◆仏像 「阿弥陀如来立像」(79.2㎝)は、鎌倉時代作であり、快慶門流の手によるとみられる。「三尺阿弥陀如来立像」と呼ばれ、安阿弥様になる。 相好・流麗な衣文表現が施されている。両手とも第一指・第二指を捻じる来迎院を結ぶ。頭体の耳後ろで前後に割り矧いでいる。両肩・両手首・両足先を矧ぐ。光背・台座は後補になる。 木造、寄木造、金泥仕上げ、玉眼嵌入。 ◆建築 近年、本堂などが再建されている。 ◈「旧本堂」についての詳細は不明。 安土・桃山時代、1587年に、檀越・御牧益景が伏見城中にあった聚楽殿舎の古材により築造したともいう。(『京都府地誌』)。同年、豊臣秀吉の命により、益景の子・勘兵衛尉尚秀が引き移して再建したともいう。(『佐山村郷土誌』)。また、本山・一心院の記録では、聚楽第の「樫木(かしのき)御殿」を譲り受け移築したとされた。すべて樫材で造られており、専念寺もかつて「樫寺」とも呼ばれていたという。 秀吉による伏見城築城は、後年の安土・桃山時代、1592年に始まっている。旧本堂の材質、聚楽第遺構と伏見城築城の関連から誤記ともいう。また、移転は伏見城廃城後の、江戸時代前期、1623年以降だったともいう。 寄棟造。 ◈「山門」は総ケヤキ造。 ◆文化財 絹本署色「阿弥陀三尊来迎図」(久御山町指定有形文化財)は、室町時代作とみられている。掛軸装になっている。 図の裏面には、江戸時代前期、1655年の専阿による裏書があった。かつて一心院(左京区)により寄付されたという。源信(恵心僧都、942-1017)に深く帰依した武士・源満仲(913-997)が描いたともいう。画に描かれた武士姿の往生者とは、満仲自身と記されていた。 画面中央に、右を向いた阿弥陀如来の立像を大きく描く。雲上の踏割蓮華座に立つ。阿弥陀の額(白亳)から放たれた二条の光明は、右下の往生者にすでに届いている。観音菩薩は、阿弥陀の右下前方にあり、やや腰をかがめ両手で金の蓮台を捧げ持つ。勢至菩薩は、阿弥陀の左下前方で合掌している。 三尊は薄墨線で描かれ、肉身は金泥、衣は金泥、切金で金色に表現されている。面面の右端下方、屋形内に坐し来迎を待つ烏帽子姿の往生者(源満仲)がある。武士姿のある来迎図の例は少なく、貴重とされている。 縦83.0㎝、横36㎝、掛軸装。 ◆墓 御牧勘兵衛尉尚秀の位牌が祀られている。墓とされる五輪塔が立つ。 ◆御牧城・向薮 御牧城についての詳細不明。西一口(にし-いもあらい)の古城地にあり、巨椋池水軍の根拠地だったという。室町時代後期、1570年に御牧益景(?-?)は、三好三人衆に御牧城を攻められ城は陥落した。すぐに、羽柴(豊臣)秀吉の助力を得て奪還に成功する。益景の没後、子・勘兵衛(?-1600?)が城主になった。 後に勘兵衛は、御牧城より専念寺の門前の向薮(むかい-やぶ)/城薮(しろ-やぶ)に移った。この地に、勘兵衛の屋敷があり、勘兵衛はこの地で亡くなったという。 勘兵衛の子・助三郎信景(?-?)は、後に御牧田井村を離れている。一族の故郷である山科厨子村奥村に移ったという。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『京都府の地名』、『昭和京都名所図会 7 南山城』、久御山町教育委員会の説明板、『久御山町誌 第1巻』、ウェブサイト「久御山町」、『久御山町の今昔』、『戦国人名事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |
 |
 |