|
|
|
| 一燈園 (京都市山科区) Itto-en |
|
| 一燈園 | 一燈園 |
 |
 |
  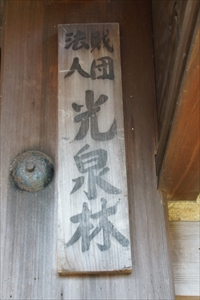        香倉院  香倉院  【参照】山科疏水  【参照】山科疏水 |
一燈園(いっとうえん)は、琵琶湖疏水の山科疏水に沿いに建つ。正しくは財団法人「懺悔奉仕光泉林(ざんげ-ほうし-こうせんりん)」という。 近代の宗教家・西田天香(にしだ-てんこう)が創始した修養団体をいう。 ◆歴史年表 近代、1905年、4月、西田天香が京都で「一燈園」を創始する。 1913年、9月、京都市左京区鹿ヶ谷に宗教道場「一燈園」を創設した。 1928年、山科の現在地に移転した。 1929年、8月、山科に財団法人「懺悔奉仕光泉林」が開設される。 現代、1954年、「一燈園生活研究所」が開設される。 1955年、4月、「一燈園大学林」が開設された。 1988年、4月 、資料館の「香倉院(こうそういん)」が開館になる。 ◆西田天香 近現代の宗教家・西田天香(にしだ -てんこう、1872-1968)。本名は市太郎。滋賀県長浜市の紙問屋に生まれた。小学校卒業後、1889年、18歳の時、滋賀県知事・大越亨に面談し二宮尊徳の報徳思想に共感した。1891年、兵役を逃れ、北海道開拓民として移住し、開墾事業(500ha)の監督になる。小作農民と資本家の対立に苦悩し、3年余で求道の放浪生活を始める。1903年、トルストイ著『わが宗教』に啓発され、無一物の禁欲、奉仕、内省の信仰生活に入る。1905年、長浜・愛染堂(あいぜん)で参籠断食中に、乳児の泣声に、争わなくても恵まれる食があるとして無心の境を悟る。1913年、宗教道場「一燈園」(左京区鹿ヶ谷)を創設し、托鉢、奉仕、懺悔の共同生活を行なう。1919年、六万行願(他家の便所掃除)を発願する。1921年、教話集『懴悔の生活』がベストセラーになる。1923年、関東大地震の被災地で救援活動した。1926年、ハワイ・カリフォルニアで托鉢した。1930年、「光卍十字運動(ひかりまんじゅうじ-うんどう)」を発願した。1931年、俳優・倉橋仙太郎と「すわらじ劇団」を設立した。第二次大戦(1939-1945)中、国策を支持し、海外布教する。戦後、1947年、国民総懺悔を唱え参議院議員になり、「緑風会」結成に参加する。著『西田天香選集』(全5巻)。96歳。 おひかり(大自然、神、仏)による内面的救済を求め、我執を離れ、一燈園信者は絶対平等、無所有、無一物の共同生活を営み、奉仕の托鉢行を行った。ガンジー(1869-1948)の非暴力主義、世界連邦思想に共感した。マキシミリアノ・コルベ神父(1189-1941)、ヘレン・ケラー(1880-1968)らと交流した。 ◆一燈園 一燈園は、近代、1904年に西田天香によって創始された。「一燈園」の名は、親交があった哲学者・評論家・綱島梁川(つなしま-りょうせん、1873-1907)の著書に因む。 自然にかなった生活により、人は何物も所有せず、働きを金に換えなくても許されて生かされるとし、懺悔の心を持ち無所有奉仕の生活を行った。信者は共同体を形成し、奉仕(托鉢行)生活をした。「おひかり(神・仏・大自然)」から預かり託された他の財物を運用経営する宣光社を営む。本部的機能の財団法人懺悔奉仕光泉林(現・一般財団法人懺悔奉仕光泉林)のほか、出版・印刷・農業・建築・劇園、学校法人などを運用する。 日露戦争(1904-1905)後-第一次世界大戦(1914-1918)中に信者が急増する。劇作家・評論家・倉田百三(1891-1943)、俳人・尾崎放哉(1885-1926)、歌舞伎役者・4代目・市川新升(1885-1935)、俳優・山田隆也(1890-1978)、哲学者・塩尻公明(1901-1969)、詩人・三石勝五郎(1888-1976)らも一時入園、関与した。小説家・徳富蘆花(1868-1927)、哲学者・評論家・阿部次郎(1883-1959)、哲学者・教育家・安部能成(1883-1966)、哲学者・倫理学者・和辻哲郎(1889-1960)、社会学者・経済学者・高田保馬(1883-1972)、宗教家・谷口雅春(1893-1985)らに影響を与えた。 第二次世界大戦後は、日本国際連合協会、ユネスコ運動、国際宗教同志会、世界宗教者平和会議(WCRP)、国際自由宗教連盟(IARF)の活動にも協力・参加した。 ◆年間行事 年頭行願(1月6日-9日)、東京光友会夏会(8月22日)、光友世話人会(総路頭預かり)(11月6日)、一燈園総路頭(11月7日)、霜月接心(11月24日-30日)、霜月行願(11月28日)。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊年間行事は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「一燈園」、『京都大事典』、ウェブサイト「コトバンク」 |
 |
 |