
西側、東大路高野第3住宅集会所
 西側、集会所 西側、集会所


 西側、集会所、「東大路高野第3住宅集会所・管理事務所」の銘鈑 西側、集会所、「東大路高野第3住宅集会所・管理事務所」の銘鈑
 西側、集会所、「市民が選ぶ文化財」の銘鈑 西側、集会所、「市民が選ぶ文化財」の銘鈑
 西側、集会所、入口 西側、集会所、入口
 西側、集会所 西側、集会所
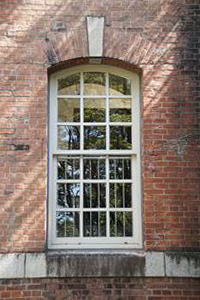
西側、集会所
 西側、集会所 西側、集会所
 西側、集会所 西側、集会所
 西側、集会所 西側、集会所
 東側、集会所 東側、集会所

北側、集会所

南側、南の門

北側、南の門

北側、南の門

西側

 西側、煉瓦壁 西側、煉瓦壁
 西側、煉瓦壁 西側、煉瓦壁
 西側、煉瓦壁 西側、煉瓦壁
 西側、煉瓦壁 西側、煉瓦壁

西側、煉瓦壁

西側、煉瓦壁
 西側、煉瓦壁 西側、煉瓦壁


東側、煉瓦壁

東側、煉瓦壁


西側、高野第3住宅れんが広場



「東大路高野」の石標、高野第3住宅れんが広場 |
高野第3住宅れんが広場の南側に、日本都市整備公団東大路高野住宅団地がある。公園の南東に、東大路高野第3住宅集会所が建つ。建物は、旧鐘紡株式会社京都工場の汽罐室(きかんしつ、ボイラー室)だった。
旧紡績工場の設計は、近代の建築家・横河民輔による。工場跡地・公団住宅の設計は、近現代の建築家・川崎清が手掛けた。
◆歴史年表 近代、1906年、10月、鐘紡株式会社は、現在地の旧田中村に工場建設を開始した。
1907年/1908年、鐘紡株式会社京都工場が竣工する。
1908年5月、工場は操業開始した。
現代、1975年、4月、京都工場は全面封鎖される。
1976年、4月、工場建物の解体が終了し、跡地は日本住宅公団に引き渡される。
1978年、工場跡地は公団東大路高野住宅として再生された。
2005年、集会所は、京都の近代建築を考える会の「市民が選ぶ文化財」に選定される。
2016年、6月、銘鈑「元鐘紡株式会社京都工場」が、鐘紡京都工場OB鐘京会・東大路高野第3住宅管理組合により設置された。
◆横河 民輔 近代の建築家・実業家・横河 民輔(よこがわ-たみすけ、1864-1945)。男性。播磨国(兵庫県)の生まれ。蘭方医・横河安鼎の4男。帝国大学工科大学造家学科(現・東京大学工学部建築学科)で学ぶ。1889年、大学卒業後、建築設計事務所を開設する。1892年、三井財閥の三井元方嘱託・東京工業学校講師になる。1895年、技師長格で三井元方に入社し、三井系企業の建築物設計を行なう。1903年、独立し、「横河工務所(現・横河建築設計事務所)」を開設した。東京帝国大学工科大学講師になり、日本初の「鉄骨構造」を講義した。1906年、「横河工務所大阪支店」を開設する。1907年、「横河橋梁製作所(現・横河ブリッジ)」を分離独立する。
1908年、帝国劇場設計に際し、欧米諸国を視察した。 1911年-1928年、建築業協会理事長に就任する。1915年、工学博士を授与される。「電気計器研究所(現・
横河電機株式会社)」を創立した。1916年、「東亜鉄工所(現 ・横河東亜工業株式会社)」を創立する。 1917年、大蔵省議院建築調査委員になり、国会議事堂建設に関与した。1918年、大蔵省臨時議院建築局常務顧問になる。1925年-1927年、社団法人「日本建築学会」会長を務めた。
1928-1945年、「建築業協会」会長、1930年-1945年、「建築資料協会」会長になる。1935年、合資会社「建築施工研究所」を設立した。
1938年、「両全社(横河コンツェルン本社)」を設立する。 1939年、文部省国宝保存会委員に任命された。1943年、横河工務所所長を辞任する。1944年、財団法人「尚徳学園」理事長になる。1964年、第1回日本建築祭で、日本建築界先覚者遺徳顕彰の1人に選ばれた。80歳。
主な作品は先代・三井本館(1902)、第一生命保険相互会社(1906)、有楽座(1908)、帝国劇場(1911)、三越呉服店(三越日本橋本店)(1914)、東京銀行集会所(1916)、日本工業倶楽部(1920)、猿江小学校(1922)、千代田生命本店(1924)、平和不動産日証館(1928)、交詢ビルディング(1929)、日本電報通信社(電通)社屋(現・電通銀座ビル)(1934)など。
◆川崎 清 近現代の建築家・川崎 清(かわさき-きよし、1932-2018)。男性。新潟県の生まれ。1951年、新潟県立三条高等学校を経て、1955年、京都大学工学部建築学科卒業した。1957年、京都大学大学院研究科建築学専攻修士課程を修了した。1958年、京都大学大学院研究科建築学専攻博士課程を退学する。1958年、京都大学工学部建築学科講師、1964年、京都大学工学部建築学科助教授、1970年、大阪大学工学部環境工学科助教授になる。日本建築学会万国博特別賞を受賞する。1971年、京都大学工学博士を学位取得した。1972年、大阪大学工学部環境工学科教授になる。1973年
、芸術選奨文部大臣賞を受賞した。1974年-1983年、大阪市立大学非常勤講師になる。1983年、京都大学工学部建築学科教授、1988年、建築業協会賞を受賞した。1991年、京都駅コンペ審査員長になる。1995年
、同済大学終身顧問教授(中国上海)、1995年-1998年、 精華大学客員教授(中国北京)、1996年、京都大学名誉教授になる。京都デザイン賞を受賞した。1996年、立命館大学理工学部環境システム学科教授になる。2011年、瑞宝中綬章を受賞する。86歳。
主な作品は、万国博美術館(現・国立国際美術館)(1970)、栃木県立美術館(1972)、京都市美術館収蔵庫(1972)、公団東大路高野住宅(1978)、相国寺承天閣美術館(1984)、みやこめっせ(1996)、京都大学文学部博物館(2000)、京都大学百周年時計台記念館(2003)、石川県こまつ芸術劇場うらら(2003)、新潟県立三条高等学校(2005)など。
◆建築 ◈ 鐘紡株式会社京都工場は、近代、1907年/1908年に竣工した。設計は横河工務所(横河民輔)による。
施工は竹中工務店による。煉瓦造、スレートの鋸屋根。
◈ 現代、1978年に、工場跡地は東大路高野第3住宅集会所として改築される。改築設計は川崎清による。建物は、集会所であり、東大路高野第3住宅管理組合事務所も入る。
旧工場の汽罐室(きかんしつ、ボイラー室)、旧工場の外壁部分の鋸状煉瓦壁のみが保存・改修された。汽罐室は集会所として改装される。鉄筋コンクリートで補強され、屋根のトラスは一部陸屋根に変更された。
煉瓦・鉄筋コンクリート造2階建、スレート・陸屋根。
◆鐘紡株式会社京都工場 近代、1906年10月に、鐘紡株式会社は田中村に工場を建設開始した。1907年/1908年に工場が竣工する。1908年5月に、工場は絹紡5100鐘、油糸1260鐘で操業開始する。
1913年4月に、機械1000台で織布工場を増設する。従業員数は3410人だった。1922年11月に、第4期増設が行われ、機械570台で東洋一の絹紡工場として生産規模、品質を誇った。第二次世界大戦までその地位にあった。1922年-1928年には、第123代・大正天皇皇后、皇太子など皇室関係者が相次いで工場視察している。1941年12月-1945年に、太平洋戦争開戦に伴い戦闘機製作などの軍需工場に転換された。
戦後、1947年7月に、梳毛(そもう、羊毛の繊維より分け、梳いて縮れを延ばした作業)工場として操業再開する。1951年1月に、工場敷地52900坪(17万4876㎡)、建坪24100坪(7万9669㎡)、従業員数1820人(男子320人、女子1500人)を有していた。1953年12月に梳毛紡績7セットを増設する。工場敷地は55786坪(18万4417㎡)あった。
1971年12月に、全工場を手編毛糸に専紡化し再出発する。だが、1975年4月に、京都工場は全面封鎖される。従業員689人は各工場へ分散再雇用された。
1976年4月に、工場建物の解体は終了し、日本住宅公団に引き渡される。旧建物の一部、工作物、樹木なども保全され住宅団地、集会所、公園として再活用された。
❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。
❊参考文献・資料 銘鈑「元鐘紡株式会社京都工場-鐘紡京都工場OB鐘京会」、『京都の赤レンガ』、『京都モダン建築の発見』、ウェブサイト「横河建築設計事務所」、ウェブサイト「川崎
清 + 環境・建築研究所」、ウェブサイト「京都の近代建築を考える会」、ウェブサイト「コトバンク」
     |